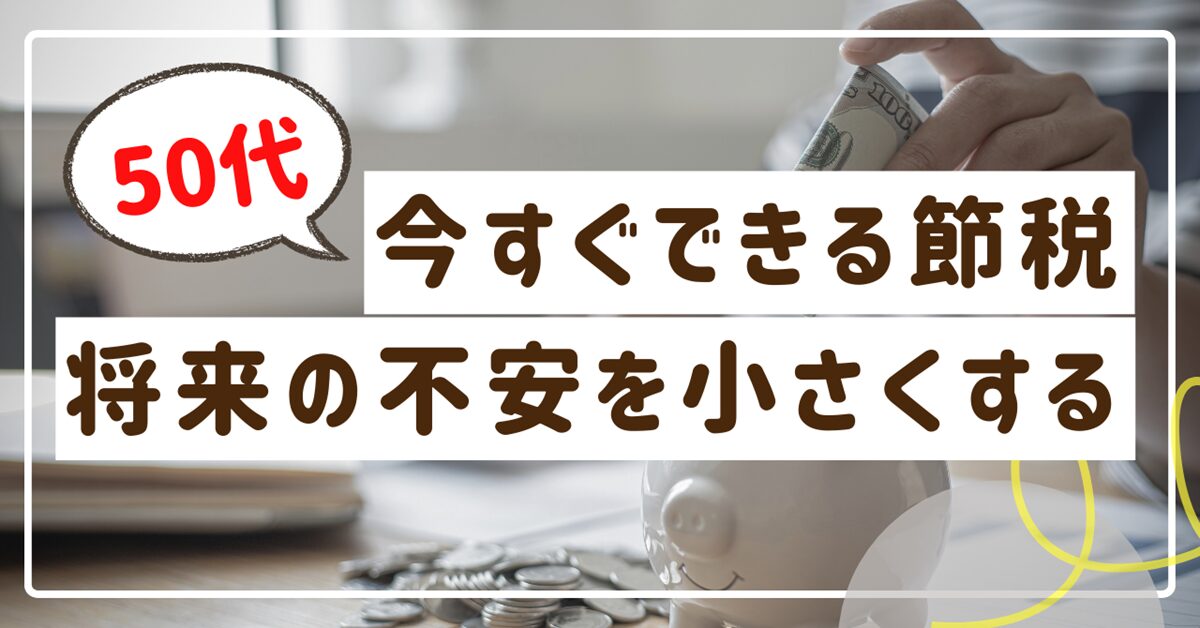あなたは漠然とした将来への不安をお持ちですか?
特に、50代という人生の節目を迎えると「不安」は、多くの人が心に抱く感情です。
健康や老後のお金、仕事のことなど、その不安の形はさまざまです。
身体的な機能が徐々に低下し始め、生活習慣病のリスクが高まるなど、自身の健康に関心が高まる時期でもあります。
また、女性であれば更年期障害など、心身の不調を訴える人も少なくありません。
しかし、その漠然とした不安を和らげる方法があります。
それは不安を「具体的な行動」に変えることで、未来は少しずつ、確実に見通せるようになります。
例えば、経済的な自立は、将来の不安や他者への依存から解放され、人生を豊かにする第一歩となり得ます。他者への依存を少しづつ軽くしていけば、自分の選択肢が広がり、自己決定が容易になり、精神的な自立に近づきます。
ここでは、この漠然とした不安を解消するため、まずは「今すぐ簡単にできる節税対策」から始め、その先に続く「賢い資産形成」まで、ゆっくりと解説していきます。
節税なんてちょっとしか変わらないし意味ないんじゃないの?
と思う方もいらっしゃるかと思いますが、日々の小さな「節約」より「節税」の方がより簡単に長期に渡って費用を押さえられます。
ちょっと難しく考えがちな税金の話ですが、あなたの人生の選択肢を広げるための前向きな行動として捉え、一緒に未来への第一歩を踏み出していきませんか?

まずは「お金の健康診断」から始めましょう
まず節税の話を始める前に、自分の家計の現状を正確に把握しましょう。
そんなことわかっている、という方は飛ばしていただいで大丈夫です。
これは、健康診断で自分の身体の状態を知るのと同じように、今後の計画を立てる上で不可欠な「お金の健康診断」みたいなものです。漠然とした不安の多くは、「何がどれくらい不足しているのか分からない」という状態から生まれます。この「分からない」を「見える化」することで、不安の正体を知り、具体的な対策が見えてきます。
まずは、家計簿アプリ(家計簿アプリ Zaim・シンプル家計簿 MoneyNote(マネーノート))やお気に入りの紙のノートなどを使って、毎月の収入、支出、そして貯蓄額を見える化してみましょう。
「なんだか小学生みたい・・・」
なんて思いましたか?
でも、こんなシンプルな作業が、以外にも家計全体を俯瞰するためにもとっても大切なんです。
自分が何をどのくらい使ったのか分かるようになったら、ご自身の資金を「お金の使い道」や「お金を使うまでの期間」によって分けて見ましょう。
例えばこんなふうに・・・・
- 使うお金
日々の生活費や、病気やケガといった不測の事態に備えるお金です。
すぐに引き出せるよう、預貯金で準備しておくのが賢明です。 - 安定的に増やすお金
5年~10年後の車の買い替えや自宅のリフォームなど、使い道が決まっているお金です。
定期預金や個人向け国債などで、確実に増やせる方法を検討できます。 - 積極的に増やすお金
10年、20年先を見据えた老後資金など、当面使う予定のないお金です。
株式や投資信託といった金融商品を活用し、長期的な資産運用を目指しましょう。
いかがでしたか?
もし「自分の使っているお金のイメージがわかない・・・」という方には 金融経済推進機構のWEB、ライフプランシミュレーション 生活設計診断|知るぽると がお勧めです。チェック項目がたくさんあって大変ですが、どのようにお金を整理したら良いのかが分かってきます。時間のある時にゆっくり挑戦してみてください。
まずは今自分はどうなっているのか分かったら、次の章でご紹介する節税対策で支払わなくてもいいお金を探しましょう!
ところで、節約というとなんだかむなしく感じますよね? でも 節税 ならどうでしょうか?
なんだか試してみたくありませんか?

見逃しがち?年末調整でできる「今すぐ簡単」な節税
節約はちょっと貧乏っぽい感じがして、むなしい・・・・
と感じる方も「節税」ならなんか知的な感じがしませんか?
まず皆さんもよくご存じ「年末調整」から見ていきましょう。
会社にお勤めの給与所得者にとって、最も手軽で身近な節税対策が年末調整です。
毎年秋頃に勤務先から配布される申告書に必要事項を記入して提出するだけで、税負担を軽減できる可能性があります。
ここでは、見落としがちな控除を中心に、すぐに実践できる対策をご紹介します。
生命保険料控除・地震保険料控除
生命保険料控除は、生命保険、介護医療保険、個人年金保険の保険料に応じて、所得から最大12万円を控除できる制度です。また、自宅や家財にかける地震保険料についても、最大5万円を控除できます。
手続きは非常に簡単です。保険会社から送付される「生命保険料控除証明書」または「地震保険料控除証明書」を、勤務先から提供される年末調整の申告書に添付して提出するだけです。多分多くの方が忘れず申告されているかと思います。
通常、これらの証明書は毎年10月頃に郵送で届きます。もし紛失してしまっても、保険会社に連絡すれば再発行が可能で、多くの場合、過去5年分の再発行にも対応しています。また、マイナポータル連携を利用すれば、書面での提出が不要になるケースもあります。
社会保険料控除
社会保険料控除は、国民年金保険料や国民健康保険料など、あなたが支払った社会保険料を全額所得から控除できる制度です。給与から天引きされている社会保険料は会社が手続きを行いますが、自分で支払っている国民年金保険料や国民健康保険料は、自分で申告しなければ控除の適用を受けられません。
ここで重要なのは、「実際に保険料を支払った人」が控除を受けられるという原則です。
例えば、生計を一つにする親の国民年金保険料を代わりに支払っている場合、その支払い分はあなたの社会保険料控除の対象となります。しかし、親自身の年金から国民年金保険料が天引き(特別徴収)されている場合は、たとえあなたが扶養していても、親が支払ったと見なされるため、あなたが控除を受けることはできません。
国民年金保険料の控除に必要な「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」は、毎年日本年金機構から送付されます。もしも、この証明書を紛失した場合は、「ねんきんネット」やマイナポータルを通じて再交付を申請できます。
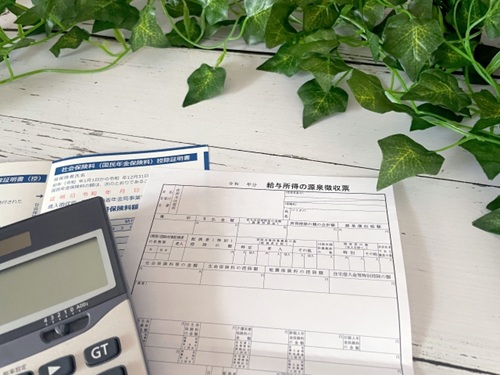
扶養控除・ひとり親控除・寡婦控除
家族構成に変化があった場合、年末調整の申告書を見直すことで、大きな節税につながることがあります。特に、配偶者の合計所得が年間48万円以下の場合、納税者本人の所得が1,000万円以下であれば配偶者控除が受けられます。
また、特定の条件を満たす場合は「ひとり親控除」や「寡婦控除」を利用できます。例えば、夫と離婚後、婚姻しておらず、合計所得金額が500万円以下で子どもがいる場合、ひとり親控除として所得から35万円が控除されます。これらの控除は、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に記入することで適用されます。
結婚や離婚、子どもの自立など、家族状況に変化があった際には、必ず申告書の内容を確認しましょう。

以下の表に、年末調整でできる主な控除をまとめました。
| 控除の種類 | 概要 | 控除額の目安 | 主な必要書類 |
| 生命保険料控除 | 生命保険、個人年金保険などの保険料を支払った場合に適用される控除。 | 最大12万円(新制度) | 生命保険料控除証明書 |
| 地震保険料控除 | 自宅や家財にかける地震保険料を支払った場合に適用される控除。 | 最大5万円 | 地震保険料控除証明書 |
| 社会保険料控除 | 国民年金保険料などを自分で支払った場合に適用される控除。 | 全額 | 社会保険料(国民年金保険料)控除証明書 |
| 扶養控除・ひとり親控除 | 扶養している家族や、ひとり親である場合に適用される控除。 | 扶養控除:38〜63万円ひとり親控除:35万円寡婦控除:27万円9 | 「扶養控除等(異動)申告書」への記入 |
つまり、だまっていては節税はできません。
「自分が申告すること」が大切なのです。
「ふるさと納税」は節税になる?
皆さんもご存じ「ふるさと納税」は、「税金を納める自治体を自分で選ぶ」というユニークな制度です。この制度を活用することで、実質2,000円の自己負担で、寄付額から「住民税と所得税」が控除され、返礼品として地域の特産品などを受け取ることができます。
でもちょっと誤解されやすいのは、ふるさと納税をしても支払う税金が減るわけではありません。もともと住んでいる自治体に支払うべき税金を、寄付という形で自分の好きなの自治体に前払いする制度です。
詳しく見ていきましょう。

控除限度額の計算と注意点
まず、ふるさと納税を始める際に最も大切なのは、ご自身の「控除限度額」を正確に把握しましょう。この限度額を超えて寄付をすると、超過分は税金控除の対象とならず、全額自己負担となるので注意してください。多くのポータルサイトでは、年収と家族構成を入力するだけで簡単に限度額の目安を算出できるシミュレーターが提供されているので利用してみましょう。
より正確な金額を知りたい場合は、源泉徴収票を用意し、以下の項目をシミュレーターに入力しましょう。
- 総収入金額
- 給与所得控除後の金額
- 所得控除額の合計額
- 住宅借入金等特別控除の額
また、ふるさと納税を行う際には、以下の点に注意が必要です。
- 名義の一致: 寄付を行う名義人と、税金の控除を受ける名義人は必ず一致させる必要があります。共働きのご家庭では、夫婦で異なる名義で寄付をすると控除が受けられない可能性があるため、事前に確認しておきましょう。
- キャッシュフロー: ふるさと納税は、寄付金を先に支払う「先払い」の仕組みです。税金控除が適用されるのは翌年のため、寄付する時点では一時的に手元の現金が減ります。家計に余裕がある時に計画的に行うことが大切です。
手続きの注意点:ワンストップ特例制度のメリットと落とし穴
ふるさと納税の控除を受けるには、原則として確定申告が必要です。
けれど、給与所得者で確定申告をする必要がない方は、「ワンストップ特例制度」を利用すれば、確定申告が不要になります。
ワンストップ特例制度の利用条件
- 給与の収入金額が2,000万円以下で、他に確定申告の必要がない方
- 1年間の寄付先が5自治体以内であること
この2つを満たしていれば「ワンストップ特例制度」を使うことができます。
「ワンストップ特例制度」の申請方法は、ふるさと納税を申し込む時に「ワンストップ特例制度を希望する」にチェックをしておくと、寄附先の自治体から「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」(ワンストップ特例申請書)が送付されるのを待つだけです。
寄付先の自治体から送付された「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」に必要事項を記入し、本人確認書類のコピーを添付して、寄付をした翌年の1月10日までに郵送するだけです。
年末ぎりぎりだと書類が間に合わなかったり、万が一書類を紛失してしまった場合は、ご自身で申請書をダウンロードして印刷することができます。多くのふるさと納税サイトや、総務省のウェブサイトから入手可能です。
ただし、この制度には重要な落とし穴があります。
もし医療費控除などの理由で確定申告をすると、ワンストップ特例制度はすべて無効になってしまいます。この場合、改めてふるさと納税分も確定申告書に記入し直す必要があるので注意してください。
節税にはならないけどお得
ふるさと納税は支払うべき税金を前払いをして、所得税なら還付、また住民税なら控除することができる制度です。つまり、税金を安くすることはできません。
ふるさと納税の一番のメリットは負担額2000円でもらえる返礼品です。
負担額が2000円とはいっても、寄付金額の2,000円をはるかに超える価値のものが多数あります。
この負担額より大きい返礼品が大きな魅力になっています。
いったいなぜ、負担額より大きな品物がもらえるのでしょうか?
3割ルールの基準は「仕入れ値」
それは、返礼品が仕入れ値で計算されているからです。
総務省は、ふるさと納税の返礼品の調達費用について、「寄付金額の3割以下」とするよう各自治体に要請しています。この「3割」の基準は、市場価格(小売価格)ではなく、仕入れ値(自治体が業者から購入する価格)です。
多くの返礼品は、地元事業者が生産・販売している特産品です。この場合、店頭価格には生産コストに加えて、流通コストや事業者の利益が含まれています。そのため、自治体が仕入れ値で購入した場合、市場価格よりも安く購入できることがほとんどです。
例えば、
- 寄付金額:10,000円
- 自治体の仕入れ値の上限:10,000円 × 30% = 3,000円
この場合、自治体は3,000円以内の仕入れ値で返礼品を調達します。
しかし、その商品の市場価格は、例えば5,000円かもしれません。
その結果、私たちは10,000円の寄付に対して、市場価格5,000円の返礼品を受け取ることができている、という状況になっているのです。
このようなしくみによって、私たちは実質2,000円の自己負担で、寄付金額の約3割程度の市場価値がある返礼品を受け取ることができるので、ふるさと納税は大きな「お得感」が生まれとても人気のある制度になっているのです。
人気のふるさと納税サイト
【楽天市場】楽天ふるさと納税|
ふるさと納税サイト【さとふる】
【ふるさとチョイス】お礼の品掲載数No.1

50代だからこそ知っておきたい「医療費」の節税術
50代は健康への意識が高まる時期であり、病気や不調により医療費がかさむことも少なくありません。しかし、かかった医療費は「医療費控除」として、税金を取り戻すチャンスでもあります。
医療費控除の基本
医療費控除は、自分や生計を一にする配偶者、その他の親族のために支払った医療費の合計額が、年間10万円(または年間所得の5%の少ない方)を超えた場合に適用される所得控除です。
対象となる費用は、診察代や治療費、薬代だけではありません。通院のための交通費(電車代やバス代など)、出産にかかる費用なども含まれます。50代女性に多い更年期障害の治療にかかった費用も、医師が必要と判断した治療であれば、原則として医療費控除の対象となります。
セルフメディケーション税制というもう一つの選択肢
医療費控除の特例として、「セルフメディケーション税制」という制度もあります。これは、健康診断などを受けている人が、特定の市販薬(スイッチOTC医薬品)を年間1万2,000円を超えて購入した場合に適用できる控除です。ただし、この制度は通常の医療費控除とは
併用できません。どちらか一方を選択する必要があります。
申請方法:確定申告の手続きとe-Taxの活用
医療費控除を受けるためには、ご自身で確定申告を行う必要があります。以前は医療費の領収書をすべて提出する必要がありましたが、現在は「医療費控除の明細書」を作成し、添付することで申請できます。領収書自体は自宅で5年間保管する必要があります。
確定申告は、税務署に直接持参したり、郵送したりするほか、e-Tax(電子申告システム)を利用すれば、スマートフォンやパソコンからオンラインで手続きが可能です。e-Taxでは、マイナポータル連携機能を使って医療費通知のデータを自動で取得できるため、明細書の作成が格段に楽になります。
また、医療費控除による還付申告は、対象年の翌年1月1日から5年間さかのぼって行うことができます。数年分の医療費を合算することはできませんが、年ごとに分けて申告できるため、過去に申告し忘れた医療費がある場合は、この機会にぜひ見直してみましょう。

医療費控除とふるさと納税の併用に関する重要な注意点
医療費控除とふるさと納税は併用できますが、前述の通り、医療費控除のために確定申告を行うと、ふるさと納税のワンストップ特例制度は無効になります。
さらに、医療費控除は所得控除であるため、控除額が大きいと課税所得金額が減り、その結果、ふるさと納税の控除限度額も少なくなります。医療費がかさんだ年に、安易に医療費控除前の限度額でふるさと納税をすると、自己負担額が増えてしまう可能性があります。
このような状況を避けるためには、1年間の終盤に、医療費控除の概算を計算してから、ふるさと納税の限度額を再計算し、寄付を行うことが賢明です。
老後資金の不安を解消!「攻め」と「守り」の資産形成
将来の不安の多くは、老後資金に対する漠然とした懸念から生まれます。
節税対策で手元に残ったお金を、ただ貯金するだけでなく、賢く増やすことも重要な選択肢です。50代からでも決して遅くはありません。人生100年時代と言われる現代では、50代からでも30年以上の資産運用期間を確保できます。ここでは、強力な税制優遇制度を持つ「新NISA」と「iDeCo」を解説します。
新NISA:50代からでも遅くない「生涯非課税」のメリット
2024年から始まった新NISAは、非課税保有期間が無期限になったことで、50代からでも長期的な資産形成を始めやすい制度となりました。NISAは、投資で得た利益(運用益や配当金)が非課税になる制度です。
新NISAには、主に以下の2つの投資枠があります。
- つみたて投資枠: 年間120万円まで。金融庁が定めた、長期の積立・分散投資に適した投資信託などが対象です。
- 成長投資枠: 年間240万円まで。上場株式や幅広い投資信託などが対象です。
特におすすめなのは、初心者でも始めやすい「つみたて投資枠」です。毎月小さな金額を自動で投資する方法です。価格変動のリスクを抑えながら、長期的に安定した運用が期待できます。
例えば、50歳から毎月5万円を20年間積み立て、年利5%で運用できた場合、元本1,200万円が約2,037万円になるというシミュレーションもあります。
NISAを始めるには証券口座を開設する必要があります。
口座開設は、ネット証券がおすすめです。
取扱商品が多く、手数料も安いため、長期的な運用に適しているからです。
手続きはオンラインで簡単にでき、マイナンバーカードや本人確認書類を準備すれば20分程度で完了できます。
お金を育てる研究所 | あなたの資産運用をサポートするサイト
iDeCo:最強の節税効果を賢く利用する
iDeCo(個人型確定拠出年金)は、掛け金が全額所得控除の対象となる、非常に強力な節税メリットを持つ制度です。運用益も非課税となるため、老後資金を準備する上で非常に有利です。
しかし、50代からiDeCoを始める場合は、以下の3つの注意点を理解しておくことが不可欠です。
50代ならではの注意点
- 資金の流動性
DeCoの資金は、原則として60歳まで引き出すことができません。掛け金を拠出できる期間は最長で65歳未満までですが、通算加入期間が10年未満の場合、受け取れる年齢が61歳以降に遅れるというルールがあります。50代は、教育費や住宅ローン、親の介護などで支出がかさむ時期でもあり、手元資金が拘束されることによる家計への影響を慎重に検討する必要があります。 - 運用商品の選び方
運用期間が短くなるため、価格変動リスクの高い商品(個別株など)は避けるのが賢明です。定期預金などの元本確保型商品や、債券型、バランス型といったリスクが比較的低い商品を中心に運用を検討しましょう。 - 退職金との併用
iDeCoは、退職金と同時に一時金として受け取る場合、税金の計算方法に注意が必要です。退職所得控除は、退職金とiDeCoの一時金を合計した額に適用されますが、控除額には限りがあります。2026年1月以降は、職場からの退職金とiDeCoの一時金を5年ではなく10年以上の期間を空けて受け取らないと、控除額が減ってしまう「10年ルール」が適用されます。退職金が高額になることが予想される場合は、iDeCoの受け取り方を「一時金」ではなく、「年金」形式にするなど、出口戦略をあらかじめ考えておくことが大切です。
以下の表は、新NISAとiDeCoの主な違いをまとめたものです。
| 項目 | 新NISA | iDeCo |
| 年齢制限 | 18歳以上であれば年齢上限なし | 原則65歳未満まで拠出可 |
| 資金の引き出し | いつでも可能 | 原則60歳以降 |
| 主な税制優遇 | 運用益が非課税 | 拠出金が全額所得控除運用益が非課税受取時も控除あり |
| 退職金との併用 | 無関係 | 受取時期に注意が必要 |

今日から一つ行動を起こしてみませんか?
将来への漠然とした不安を抱える50代のあなたへ。
ここでご紹介した節税対策は、どれも「知っているか知らないか」で、手元に残るお金が大きく変わるものです。そして、それは単に金銭的なメリットだけでなく、「自分の未来は自分でコントロールできる」という自信につながる、パワフルな行動です。
全てを一度に完璧にこなそうとする必要はありません。
まずは、この中のたった一つ、一番簡単にできそうなことから始めてみましょう。
年末調整の申告書に記入漏れがないか確認してみるだけでも、立派な第一歩です。
もし、ご自身の状況が複雑で判断に迷うことがあれば、一人で抱え込まずに専門家の力を借りることも良いですね。ファイナンシャルプランナー(FP)の無料相談窓口も多く存在します。
節税と聞くと難しく感じてしまうかもしれませんが、大切なのは「自分のお金について考える時間を持つこと」です。この記事が、あなたがご自身のお金と向き合うきっかけになれば幸いです。
一歩ずつ、無理のない範囲で始めていきませんか?
参考文献
日本銀行時系列統計データ検索サイト (boj.or.jp)
経済学入門 ティモシー・テイラー
めちゃくちゃわかるよ経済学 坪井賢一