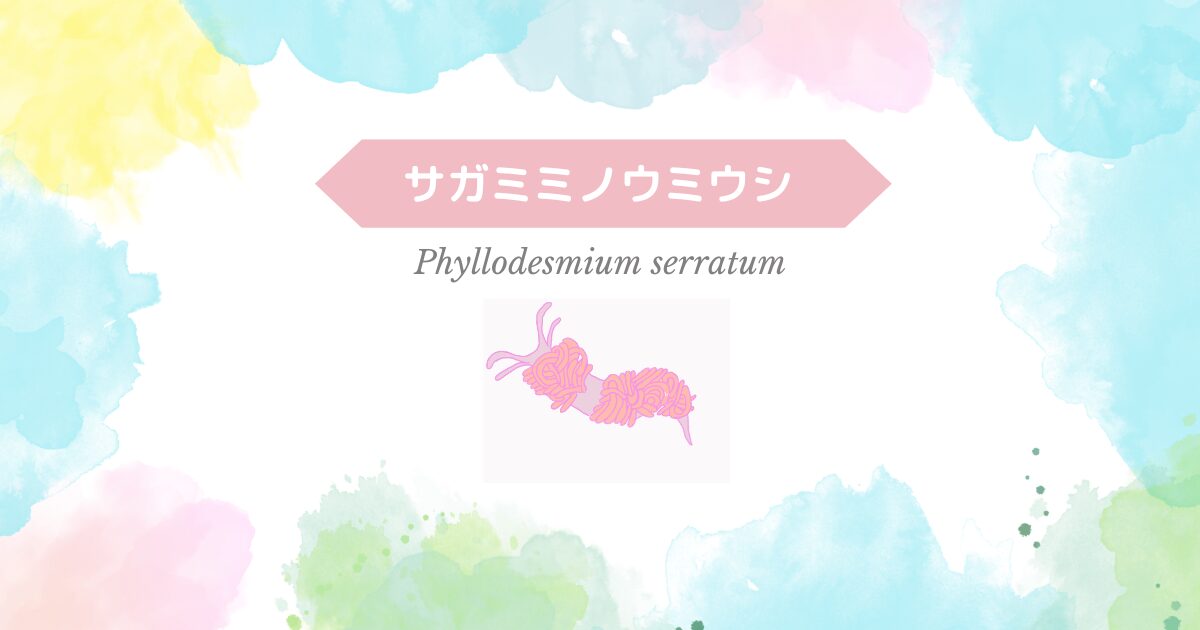あなたは海に生きる小さな生き物「ウミウシ」をご存じですか?
カラフルでかわいらしい種類が多いのでダイバーにとても人気があります。
ダイビングを始めるのはちょっと・・・と言う方でも、ウミウシなら海岸から見ることができるので、ちょっとした観察にもってこいの海の生き物です。
あなたもぜひ、かわいらしいウミウシに出会って、海と仲良くなってください!
ここでは、そんなウミウシの中でも、観察しやすい「サガミミノウミウシ」というピンクのウミウシを徹底解説します。
ウミウシの観察のヒントも載せていますので、ぜひご覧ください。

サガミミノウミウシ
まだ吹く風が冷たく寒い2月から3月の海岸へ行くと、いろいろな海藻が芽吹き始めています。
岩の上にはアオサが岩を緑色に染め、隣の石の上にはハバノリが伸びてきています。
海藻が芽吹き始めるとそれを食べる小さな貝や生き物たちが活動を初め、海岸は賑やかになります。
生き物が活発になるとサガミミノウミウシというウミウシも活動し始めます。
サガミミノウミウシの特徴と生態
サガミミノウミウシは、相模湾で最初に発見されたことから名付けられました。
ピンク色の伸びた鰓がひらひらと波に揺られ、愛らしく人気の高いウミウシです。
サガミミノウミウシは「ウミウシ」と言う仲間の一種です。
ウミウシは、世界に約3000種類以上存在する軟体動物(貝の仲間)の一種です。
ウミウシは貝の仲間ですが、進化が進むにつれ貝殻が退化していきました。
貝殻で体を守らなくなった代わりに、背中に突起状のミノをもっています。
突起の先には、食事で食べた刺胞動物の刺細胞を活用して配置して、自分の身を守るために使っています。
つまり、他の動物が武器として持っている細胞を食べて、消化しないでそれを利用しているのです。
サガミミノウミウシの特徴
- 体長 : 最大4cm
- 体色 : ピンク、オレンジ、白など鮮やか
- 背中の突起 : ミノのようにたくさんの突起がついています。突起は鰓として使われ、突起の先には棘細胞が集まっています。
- 生息地 : 日本の太平洋岸、インド洋、西太平洋
- 食性 : 肉食、イソバナやウミトサカなどを食べる
サガミミノウシの観察のヒント
カラフルなウミウシを観察するのは、とっても楽しい遊びです!
ここでは、ウミウシにもっと出会えるいくつかのヒントをご紹介します。
観察場所と時期
- 干潮時間に気を付けよう
満潮時よりも干潮時の方が観察しやすいのでしおみエールなどで干潮時間を調べていきましょう。 - 岩の上や周辺
ミノウミウシは、海藻生えている岩場の上やその周辺で見つかることが多いです。 - 観察の時期
ミノウミウシは、活動が活発になる3月から6月までの期間に探すのがお勧めです。
観察方法と道具
- 注意深く探そう!
ミノウミウシは4㎝くらいと小さいので、注意深くゆっくりと探すことが大切です。 - マクロレンズ
小さなウミウシの細部を観察したり、写真に撮ったりするのに便利です。 - 水中カメラ
ウミウシの美しい姿を記録に残すことができます。 - 図鑑やガイドブック
他のウミウシや生き物を特定するのに役立ちます。 - 安全に注意しましょう
岩場は滑りやすいので、足元に注意して観察しましょう。
観察のポイント
- 根気よく探す
最初は見つからなくても、諦めずに探してみましょう。 - 同じ場所に留まらない
少しずつ場所を移動しながら探すことで、より多くのウミウシに出会える可能性があります。 - ウミウシの行動を観察する
捕食している様子や移動している様子など、生き生きとした姿を観察できるかもしれません。
水中には、息をのむような美しさを持つ生き物たちがたくさんいます。
さあ、あなたも身近な海へ飛び込んで、小さな冒険を始めてみませんか?
きっと、今まで知らなかった海の魅力に気づくはずです。

参考文献
ウミウシを観察しよう 千葉県立中央博物館分館 海の博物館
磯の生き物図鑑 トンボ出版
日本動物大百科 平凡社
ウミウシ - Wikipedia
日本産サガミミノウミウシの解剖学的研究 (jst.go.jp)
バリ島ダイビング・MAX DIVE バリ (xn--eckya9b7cr9ksc.com)