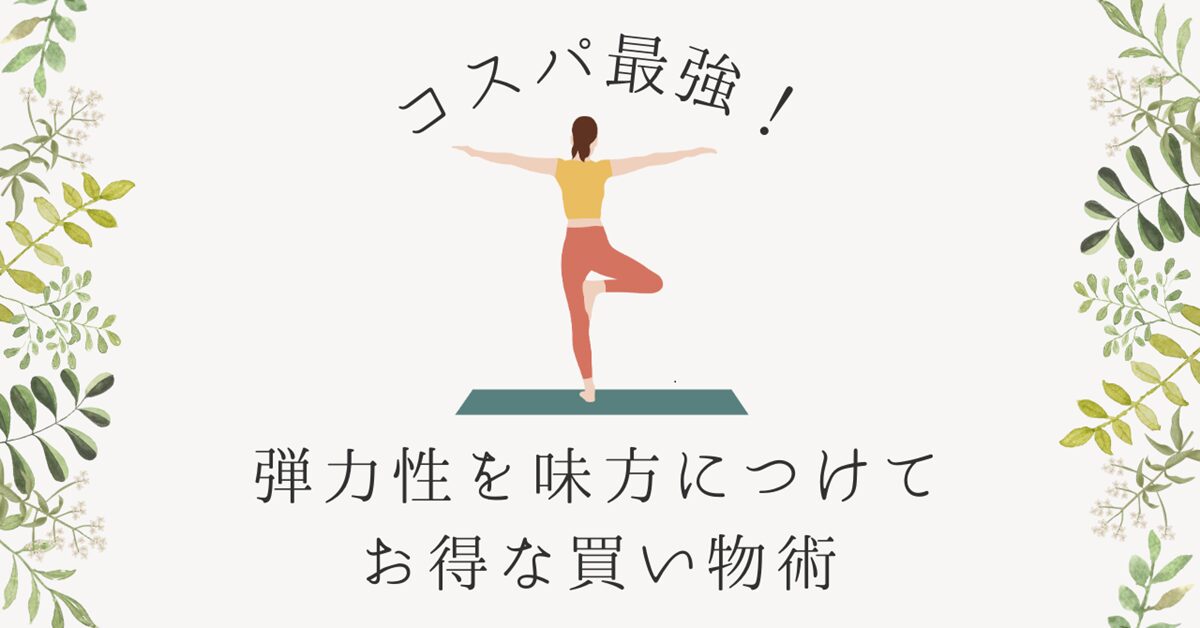最近モノが高くなってきている気がする・・・
欲しいものになかなか手が届かないな・・・
と感じていらっしゃる方も多いのではないでしょうか?
毎日の買い物に節約に努めていても、なかなか難しくて困ってしまいますよね。
それでも、ときどき行われるセールを活用してお得に買い物したいですね!
けれど、少し気になるのは、なぜ商品によって割引率が違うのでしょうか?
セールになりやすい商品、なりにくい商品などがあります。
それを知れば、もっとお得に買うことができるかもしれません。
商品の割引のタイミングや時期は、その商品の「弾力性」によって変わります。
ここではその「弾力性」を味方につけた、お得な買い物術をご紹介いたします。
ぜひご覧ください!

賢い買い物と弾力性
商品によって頻繁にセールしたり、割引率が高かったりするのはなぜでしょうか?
それには、経済学用語の「弾力性」という考え方で説明することができます。
「弾力性」とは、「ある商品の価格が変化したとき、それがその商品の売り上げ数にどのくらい影響があるか」ということを表す指標です。「弾力性」は、企業は価格を設定するときに大切な要素の一つになっています。
この「弾力性」の考えを使って、私たち消費者はどのように商品を選ぶことができるのでしょうか?
こちらもCHECK
-

-
知っておくと得する!弾力性と節約術
あなたは、毎日生活費にお金がかかって欲しいものが、買えないな・・・とかこの間までもう少し安かったのに・・・などと思うことはないでしょうか? 同じものなのになぜモノの価格は上下するのでしょうか?原材料価 ...
続きを見る
弾力性を意識して商品を選ぶ
「弾力性」を意識して商品を選ぶとはどのようなことでしょうか?
それは商品によって「弾力性」が高かったり低かったりするため、セールのタイミングや期間が違うので、それを意識して商品を選んでいこう!ということです。
なので「弾力性」を意識すると、ちょっと違った目線で選ぶことができます。
いくつが具体的な例をあげてご紹介します。
商品の代替品を調べる
まず、同じような機能を持つ商品が他にないか、ネットでチェックしている方は多いかと思います。
それは「弾力性」と、どんなかかわりがあるのでしょうか?
実は、似たような商品(代替品)が多い商品は「弾力性が高い」傾向にあります。
つまり、価格が少し上がっただけで、消費者は他の商品に簡単に乗り換えてしまう可能性が高いということです。なので企業は売り上げを伸ばすために、少しでも安くしようとする可能性が高いのです。
似たような機能を持つ商品を選ぶときは、比較サイトを多く検討することが、お得な買い物の鍵になります。
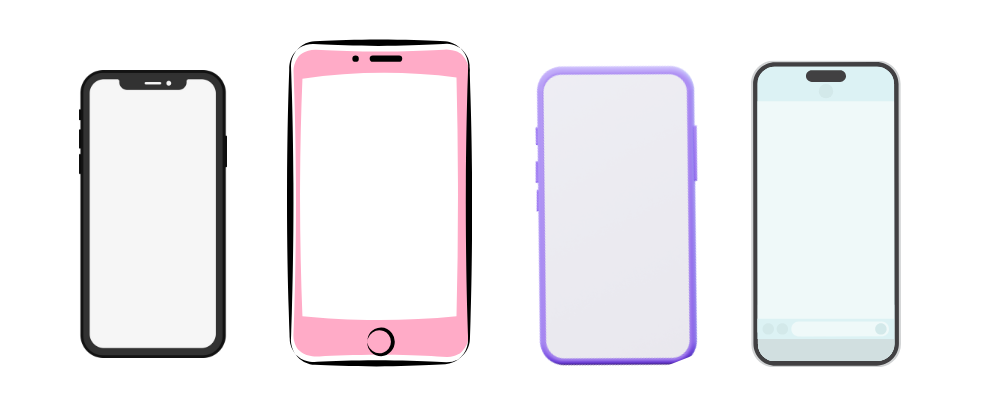
セールやキャンペーンに注意を払う
逆に、日用品などの生活必需品は「弾力性が低い」商品です。
「弾力性の低い」商品は、その価格を下げたとしても、買う人が一気にたくさん増えることはありません。
あれ?
でも、スーパーなどの日用品を扱うお店では、よくセールしていますよね?
なぜでしょうか?
日用品などの必需品は、売り上げを伸ばしたいお店としては、セールで売り上げを大きく伸ばすことはできません。お店はセールをして売り上げを伸ばすのが目的ではなく、お客様の満足度を上げて、お店に定着させる狙いがあるのです。
スーパーやドラッグストアなどの生活必需品を扱うお店では、セールのタイミングを狙って、まとめ買っておくと節約になります。

プライベートブランドに注目して節約
大手スーパーなどが展開するプライベートブランドは、一般的にナショナルブランドよりも価格が安いため、家計の支出を抑えることができます。
また、生活必需品は頻繁に購入する商品なので、プライベートブランドを選べば長期的に大きな節約効果が期待できます。
プライベートブランドは流通コストの削減、広告費の削減、シンプルなパッケージなどから価格を安く抑えることができています。同じような性能を持つ日用品の中でも、価格が低いので競争力が強く、競合他社から売り上げを引き離すために、セールを行って消費を喚起する必要もありません。
最近では、品質の向上や多様な選択肢が広がったこともあって大きな魅力があります。賢く利用すれば、家計の負担を軽減し、より豊かな生活を送ることができるでしょう。
ただし、商品によっては、品質にばらつきがあったり、ナショナルブランドに比べて、品揃えが限られている場合があります。予算に合わせて、自分のライフスタイルにあった商品を活用しましょう。

具体的な活用例
- スマートフォン
新しいスマートフォンを購入する際、性能がほとんど変わらないのに価格が大幅に異なる複数の機種がある場合、価格弾力性の高い商品であると考えられます。
この場合は、価格よりも性能を重視して選ぶか、より安い代替品を探すか、という選択肢が出てきます。 - 食料品
パンや牛乳などの生活必需品は、価格弾力性が低い傾向にあります。そのため、これらの商品は、多少価格が上がっても、消費者は買い続ける可能性が高いです。
このような商品はまとめ買いやプライベートブランドの利用がおすすめです。

自分の弾力性を知る3つの問い
私たち一般的な消費者が、それぞれの商品の弾力性を正確に推測するのは、専門的な知識やデータが必要となるため、一般的に難しいことです。
けれど、いくつかの目安や考え方を用いることで、自分にとっての弾力性を推測することは可能です。
ここに3つの質問を用意しました。
購入したいと思っているものを思い浮かべて、質問に答えてみて下さい。
- それは購入を延長できるものですか?
- 適切な代替品はありますか?
- 自分にとってそれはとても高額ですか?
この3つのうち「はい」が2つ以上あれば、その商品は弾力性が強い商品なので、安い商品をゆっくりと探すのがいいでしょう。
「いいえ」が2つ以上なら、弾力性が低いので、少し高くても購入を検討しても良い商品です。
ただし、医療費など高額で急を要するものはこのチェックに当てはまりません。

いかがでしたか?
欲しいものをいつ買えばいいのか少し見えてきたでしょうか?
ぜひ、買い物に迷ったらこの3つを思い出して、買うのか買わないのか参考にしてください。
まとめ
「弾力性」の考え方を使って、お得に買い物をする方法について解説しました。
商品を購入するときには、似たような商品が他にはないかどうか、まず比較することが大切です。
「弾力性の高い」商品は少しでも安くすると、よく売れるため、消費者にとっては多くの商品を比較することが節約の鍵になります。
日用品などの「弾力性が低い」商品は、安くしてもあまり売り上げに変化がありません。スーパーはこのような商品をセール品として時々戦略的に値下げをします。消費者にとっては、このような時まとめ買いをしておくと、お得に買い物ができます。
また、プライベートブランドを活用するのも節約になります。
コストを削減しているプライベートブランドは競争力が高いので、長期に賢く利用すれば節約になります。
実際の商品ひとつ一つの「弾力性」が高いのか低いのかを私たちがつかむのは、簡単ではありません。
けれど、自分にとっての弾力性なら難しくありません。
自分にとってその商品が安ければ欲しいのか?
高くても欲しいのか?
を知るには、次の3つの問いが役に立ちます。
- その商品の購入は急がないのものか?
- 商品の代替品があるか?
- 自分にとって高いかどうか?
欲しいものがあったとき、この3つを検討してみてください。
あなたにとって、その商品は、どれだけのお金を使っていいのかどうかが見えてくるでしょう。
商品購入に迷っているときは、参考にしてください。
参考文献
ティモシー・テイラー 経済学入門
アメリカの高校生が学ぶ経済学 ゲーリーE.クレイトン