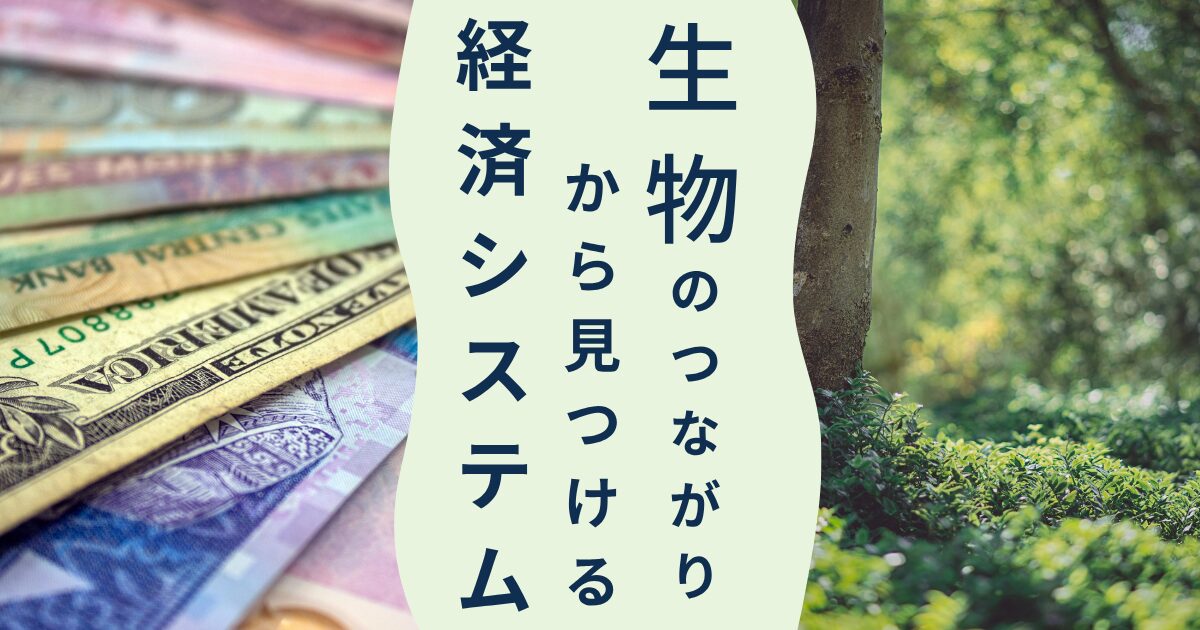あなたはお金の悩み、持っていらっしゃいますか?
お金のためにつまらない仕事を続けている・・・
将来が不安だから、貯金しなきゃだけどなかなかできない・・・
などなど、お金にまつわる悩みは尽きないですよね?
お金は生活のため必要だというのは分かるけれど、なんとかならないんだろうか?
この難しい悩みを抱えているのは、あなただけではありません。
多くの学者や哲学者もずっと悩み続けています。
ここでは、そんなお金の悩みを解決する、新しい視点を徹底解説します。
なぜ私たちはお金の心配をしなければいけないのか、疑問に思った方!!
ぜひご覧ください!
供給の力、経済と自然の共通言語
私たち人類はきっと「お金(貨幣)」を手にしてから、お金にまつわる多くの悩みを抱えてきたはずです。
一体「貨幣」の何が問題なのでしょうか?
その問題をはっきりさせるために、ここでは「経済」と「生物学」の視点を使って「お金」を考えます。
実は「経済」と「生物学」は、全く違う学問ですが、「お金」の考え方は似ています。その共通点に焦点を当ててお金について考えていけば、お金の悩みを解決するヒントが得られるかもしれません。
それではまず「お金」の働きを整理しましょう。
私たちは、生活に必要なものを手に入れるために「お金」というものを介して取引しています。お金(貨幣)は、腐らないし、価値の基準となって、交換するとき、とても便利に使えます。
そんなお金を介した経済活動には、モノやサービスが欲しい「需要」と、モノやサービスが生み出す「供給」があります。その「需要」と「供給」が一致したところに「価格」が決まります。
そんなとき、もしも「供給」が途絶えたらどうなるでしょうか?
世の中から、モノやサービスが提供されなければ、消費も投資も生まれず、経済は停滞してしまいます。
もちろん「供給」だけが実際に止まることはあり得ませんし、「供給」だけではなく「需要」も、両方大切なのですが、ここで注目したいのが、この「供給」の重要性に光を当てた考え方です。
なぜ「供給」の重要性に注目するのかというと、実はこの考え方が「生物界の生態系」に驚くほど似ているからなんです。

経済学における「供給が需要を創出する」セイの法則
初めに「生物界の生態系」に似ている経済の理論とはどんなものなのか見ていきましょう。
その理論は「セイの法則」といいます。
「セイの法則」は、19世紀初頭にフランスの経済学者ジャン=バティスト・セイによって提唱された古典経済学の基本的な原理です。その原理の核心は「供給が需要を創出する」というものです。
セイ自身は、政府はできるだけ市場に口出しせず、市場の自由な競争と貿易を促進することで、経済全体の効率性と豊かさが増す、と考える古典的自由主義者でした。そして、お金「貨幣」は経済の実体(生産量、雇用、人々の豊かさなど)には直接的な影響を与えず、単なる交換の道具に過ぎないと、世界で初めて主張した人でもあります。
「セイの法則」は、リカードやジョン・ステュアート・ミルといった古典派経済学者、さらにはワルラスが一般均衡理論を確立した新古典派経済学にも継承され、長らく疑われることのないまま、主流派経済学の基礎をなしていました。「セイの法則」が成立するなら、需要と供給は常に均衡し、過剰生産やそれによる不況、失業といった事態は生じないと考えられていました。
つまり「セイの法則」は、自由市場に任せれば需給は常に均衡するという市場原理の根拠とされたのです。

自然界に息づく「セイの法則」:植物と草食動物の繁栄
次に、生物界について考えてみましょう。
自然界では、植物が「生産者」として、太陽エネルギーと無機物から有機物を生成します。この有機物を生成すること、すなわち有機物の「供給」は、生態系全体の生命活動を支えています。
植物が豊富に生え(供給)ていて、それを食べるウサギやリスなどの(草食動物)が繁栄し、その個体数が増加するという食物連鎖が働きます。
例えば、草の量が増えれば、それを食べるウサギの個体数が増え、さらにそのウサギを食べるキツネの個体数も増えるといった具体的な繋がりが見られます。
このように、植物の供給量が増えることは、草食動物の繁栄を可能にし、ひいてはそれを捕食する肉食動物の個体数にも影響を与え、生態系全体のバランスと多様性を生み出しています。これはまさに、生物界における「供給が需要(生命活動)を創出する」というセイの法則の表したもの、と言えるでしょう。

また、太陽からもたらされるエネルギーの循環も同じように考えられます。
太陽エネルギーは、生物に消費されながら一方向に流れ、それにつられるように炭素や窒素、水などの物質が循環しています。植物が光合成で取り込んだ有機物は、動物による消費、そして微生物による分解を経て、再び大気や土壌に無機物として戻ります。この炭素循環の例は、資源の無駄を最小限に抑え、生態系全体の健全性を保つ上でいかに重要であるかを示しています。
自然界におけるこの物質とエネルギーの循環は、「供給の自己充足性」と「循環経済」の原型です。
生物学的なシステムでは、植物が生み出す有機物(供給)が消費され(需要)、その消費の副産物(排泄物や死骸)が分解者にとっての新たな供給となり、最終的に植物が再び利用できる無機物へと変換されます。
これは、単なる「供給が需要を生み出す」という線形的な関係を超え、供給されたものが消費され、そして別の形で再供給されるという、継続的で自己持続的なプロセスを意味します。システム自体が、供給されたものが消費され、そして循環を通じて再供給されることを保証しているのです。
この絶え間ない資源の変換と再利用は、廃棄物を最小限に抑え、資源の永続的な利用可能性を確保する、自然界の深い知恵を私たちに教えてくれます。
自然界の資源配分は、貨幣を介さず、直接的な消費と再利用の連鎖で、効率的行われています。
生産者による供給が、その後の全ての生命活動の需要を創出し、さらにその残余が分解者によって新たな供給へと変換されるという、無駄の少ない循環システムが構築されているのです。

貨幣経済の複雑さ:貯蓄と投資がもたらす「ずれ」
次に「セイの法則」についてもうすこし詳しく見ていきましょう。
セイは、生産活動によって生み出された所得は、すべて消費に使われるか、投資に回されると考えました。もしも、供給が多くなりすぎたとしても、価格が下がり、それが需要を呼び起こして売れ残りが出ないのです。
「セイの法則」では、お金(貨幣)の扱いが、非常にドライです。
「貨幣」は、単なる交換の媒介手段とみなし、それ自体が経済活動に影響を与えない「貨幣の中立性」を前提としていました。セイは、経済活動をモノとモノの交換(物々交換)と考え、「貨幣」は、その交換をスムーズにするための「一時的な媒介物」にすぎない、と考えます。
つまり、人が何かを購入できるのは、その人が何かを生産した(サービスを提供した)からであり、貨幣は単にそのプロセスを仲介するだけの役割だということです。
そのような社会では、人々は稼いだお金をタンス預金のようにしまい込むことなく、必ず何らかの形で経済活動に使います。
そもそもセイは、人々はお金そのものが欲しいわけではなく、お金で買えるもの(商品やサービス)が欲しいから、みんなお金を求めると考えました。私たちがお金を求めるのは、お金そのものを集めることではなく、それを使って食料品を買ったり、家賃を払ったり、旅行に行ったり、服を買ったりと、具体的な物やサービスを手に入れるためです。
なぜならお金は単なる交換手段に過ぎない紙切れだから、とセイは主張します。
けれどこの主張は、発表されたと当時から、生産物が常に生産物に交換されるという「物々交換幻想」に導かれた仮説にすぎないという批判されます。
セイは、貨幣が「価値の貯蔵手段」としての機能を持つことを見落としていました。
20世紀の「世界恐慌」を背景に、ジョン・メイナード・ケインズはセイの法則を厳しく批判します。ケインズは、不景気は需要不足が原因で起きるものではなく、供給を強化しても需要はつくられないので、不景気は克服できません。貨幣が存在する経済では、貯蓄の全てが投資されるとは限らないと主張しました。
つまり、人々は将来の不安や投資しても儲からない、と考えると、貯蓄の一部が「寝たお金」(タンス預金)になってしまいます。すると、貯蓄と投資の間にズレが生じ、供給されたものが全て需要になりません。
この貯蓄と投資の乖離が、生産されたものが全て消費・投資されない「有効需要の不足」(金銭を伴う支出の不足)を生み出し、それが不況や失業の原因となることをケインズは説きました。セイの法則が「設備がフル稼働している好況時」を前提とするのに対し、ケインズの「有効需要の原理」は「遊休設備が存在する不況」を前提としているともいわれます。
貨幣の「貯蔵機能」がもたらす経済システムの弱点は、「セイの法則」が前提とする「自動的な市場均衡を破綻させる」可能性を秘めています。
例えば「物々交換」は、生産者は消費するか、すぐに別の生産物と交換しなければいけない、という動機が働きます。
しかし、貨幣が「価値の貯蔵手段」として機能する場合、消費や投資を後伸ばしにして、貨幣を保有し続ける選択肢が生まれます。この延期された需要(貯蓄)が、適切な投資に結びつかない場合、所得の循環から「漏れ」が生じ、経済全体で供給過剰と需要不足が同時に発生しうるのです。
この「漏れ」は、供給があったとしても、需要に結びつきません。
その結果、一般的な過剰生産や需要不足、ひいては失業や景気後退といった事態を引き起こすメカニズムとなってしまいます。
この貨幣がもたらす経済にある、摩擦や潜在的な非効率性は、経済政策の必要性を強く示唆します。
もしも「セイの法則」が成立するならば、市場は自動的に自己修正し、外部からの介入は不要となります。
しかし、世界恐慌のような現実の経済危機は「セイの法則」が示す自動的な均衡が機能しません。貨幣が存在し、その貯蔵機能が「漏れ」を生み出す可能性がある以上、市場メカニズムだけでは完全雇用や経済の安定が保証されないことになります。
このため、政府による積極的な経済への介入、例えば有効需要の創出を目的とした財政政策や金融政策が、経済の安定と最適な資源配分を維持するために必要なのです。

貨幣なき生物界の効率性:理想的な資源配分の姿
では、生物界はどうでしょうか?
生物界には貨幣という概念がありません。
生産された有機物やエネルギーは、直接的に消費されるか、分解されて再利用されるかのいずれかです。経済における「貯蓄」(消費の延期)や「投資」(将来の生産能力への支出)といった概念は、生物界の資源配分には存在しません。資源は、いつも流れていて循環し、とどまることがありません。
例えば、植物が光合成で生産した有機物は、すぐに草食動物に消費されるか、枯れて分解者に利用され、その過程で無駄なくエネルギーと物質が次の段階へと受け渡されます。この直接的な資源配分が、生態系全体の効率性と持続可能性を高めているのです。
私たち全ての生き物は、生き続けるために、常に、そして途切れることなく、資源(エネルギーや物質)を取り入れ続けなければいけないという宿命を持っています。
それは、自分の体を維持するためのエネルギーは、一度使うと熱として環境中に散逸し、再利用できません。そのため、失われた分を補うために、常に新しいエネルギー源(食物など)を取り入れ続ける必要があります。これが止まると、生命活動が維持できなくなり、死んでしまいます。
また、私たちの体の貯蔵能力は限界があります。
例えば、人間は脂肪やグリコーゲンを貯蔵できますが、それも無尽蔵ではありません。また、ATP(エネルギー通貨)のようなものは、まさに「即時的な」使用のために存在し、大量に貯蔵されるものではありません。
したがって、必要な時に必要な資源が手に入るように、外部からの継続的な供給が必須となります。一日の食事を抜けば体調が悪くなり、数日間絶食すれば命の危険に晒されます。
生き物が生命を維持するために、資源の絶え間ない取り込みと利用が避けられません。
この流れが途絶えれば、システム(生命)そのものが機能しなくなり、崩壊します。
生き物の間には、有機物は消費され、分解され、あるいは形を変えて利用され続けます。システムの中に長期的に「貯蔵」され、循環から外れることはありません。この「強制的な流れ」は停滞を防ぎ、資源が常に変換され、再配分されます。個々の生物が「貯蓄」を最大化するのではなく、システム全体が生命の網を維持するために資源が動き続けることを優先するのです。
これにより、生物界はシステム全体の最適化を実現し、資源の無駄を最小限に抑えながら、生命活動の永続的な連鎖を可能にしています。
それは、生物の死骸や排出物が、菌類や細菌類といった分解者によって無機物へと分解され、再び生産者(植物)が利用できる形に戻る、という完璧な物質循環システムです。
これは単なる廃棄物処理ではなく、生態系における価値連鎖の要です。
ある栄養段階からの「廃棄物」(例えば、枯れた植物や動物の死骸)は、分解者にとっての主要な「投入物」あるいは「供給」となり、それがさらに植物が利用できる「供給」(無機栄養素)へと変換されます。
これにより、自然界では資源の枯渇が防がれ、持続可能な生態系が維持されています。
私たちが「リサイクル」や「循環経済」と呼んでいる、究極の形が自然界に自動的なメカニズムとして存在し、「価値の再創造」が絶えず行われているのです。
下の比較表で、経済と生物界における資源配分を比較してみましょう。
経済と生物界における資源配分の比較
| 比較項目 | セイの法則 (古典派経済学) | ケインズ経済学 | 生物界 (生態系) |
| 供給と需要の関係 | 供給が需要を創出する (常に均衡) | 有効需要が供給を決定する (需要不足で不均衡あり) | 生産者(供給)が消費者(需要)の基盤となり、生命活動を創出 |
| 貨幣の役割 | 単なる交換手段(中立的) | 交換手段に加え、価値の貯蔵手段(流動性選好) | 貨幣の概念なし |
| 貯蓄と投資の有無 | 貯蓄は常に投資に等しいと仮定 | 貯蓄が必ずしも投資に結びつかず、乖離が生じうる | 経済的な「貯蓄」や「投資」の概念なし。資源は直接的に消費・再利用される |
| 資源配分の効率性 | 市場メカニズムにより自動的に効率的(完全雇用) | 有効需要不足により非効率が生じうる(不完全雇用、不況) | 貨幣を介さない直接的なフローと物質循環により、高いシステム効率性 |
| 過剰生産/不況の可能性 | 一般的過剰生産や不況は起こらない | 有効需要不足による過剰生産や不況は起こりうる | システム全体での「過剰生産」は、より多くの生命活動を支える基盤となる(飽和点を除く) |
この表から、貨幣の存在が経済システムに与える影響の大きさがわかります。
生物界では、貨幣を介した「貯蔵」や「滞留」がないため、エネルギーや物質は生産→消費→分解という流れが上手に機能し、高い効率性が実現されています。

自然の知恵から学ぶ、持続可能な未来への道
ここでは、経済学における「供給が需要を創出する」セイの法則と、生物界の生態系における資源配分の仕組みを比較しました。
「供給」がシステムの活性化に不可欠であるという根源的な原理は、経済と自然の両方に共通していることがお分かりいただけたのではないでしょうか?
しかし、貨幣の存在が経済システムに複雑性をもたらしていて、「セイの法則」を単純に適用することができません。貨幣が「価値の貯蔵手段」になるので、貯蓄が必ずしも投資に結びつかず、経済の「滞留」や有効需要の不足が生じる可能性が生まれます。
貨幣のない生物界が示す、無駄のない「物質循環」と「エネルギーの流れ」の重要性は、人間社会に貴重な示唆を与えます。
生物界のシステムは「貯蔵」よりも「流れ」を重視し、あらゆるものを次の生命活動の「供給」へと繋げることで、システム全体の最適化と持続可能性を実現しています。
これは、人間社会が直面する資源枯渇、廃棄物問題、そして経済の停滞といった課題に対し、「流れ」と「循環」へ発想を根本的に転換する必要性を示しています。
線形的な「採取・製造・廃棄」モデルや、富の蓄積を暗黙的に奨励するシステムから脱却し、資源の継続的な利用、再利用、再生を積極的に促進するシステムへと移行することです。
これは、生産されたものが消費され、その残余が新たな供給としてシステムに再統合される、自然界の効率性を模倣する経済モデルの探求を意味します。
貨幣経済の利便性や必要性を認めつつも、その内在する課題(貯蓄と投資の乖離、需要不足の可能性)を乗り越える方策を模索することは、現代社会にとって喫緊の課題です。
私たちは、この自然界のシステムからヒントを得て、より効率的で、無駄が少なく、持続可能な資源配分の道を見つけることができるはずです。これは単なる経済成長を追求するだけでなく、生態系との調和を目指す新たな経済モデルの探求へと繋がります。
経済学と生物学という異なる分野からお金の問題を考えることは、一人一人のお金の使い方のヒントをつかむためだけではなく、私たちが直面する資源問題や環境問題に対し、新たな視点を提供します。
私たちは、供給の重要性を再認識し、自然の知恵に学び、より効率的で持続可能な社会構築に向けて行動を起こすことで、未来への希望を育むことができるでしょう。

参考文献
ティモシー・テイラー 経済学入門
最新世界史図説 帝国書院
ジャン=バティスト・セイ - Wikipedia
セイの法則 - Wikipedia
セイの法則|用語集|デジマール株式会社 (digimarl.com)