あなたは日本銀行を知っていますか?
「お札を発行しているところでしょ?」
「銀行の銀行って習った」
「ちゃんとやってくれているだろうから、良く分からなくてもとりあえず問題はない」
などなど、興味はないわけじゃないけど・・・まあ自分には関係ない。
と考える方がほとんどではないでしょうか?
日本銀行がどのようなことしているのか知らなくても、生活に影響はないかもしれません。
でも、もし経済の先行きが知りたくなった時、日本銀行がどのようなことをしているのか理解しておくことは、その国の将来の姿をイメージする良い材料になります。

日本銀行とは何か?中央銀行の三つの基本機能
日本経済の羅針盤としての日本銀行
日本銀行(Bank of Japan)は、日本の経済を支える中央銀行です。
日本銀行の業務について、意識することはほとんどありせんが、実は国民一人ひとりの暮らしや企業の経済活動に深く関わっています。日々の物価変動、銀行預金の金利、住宅ローンの動向、さらには日本経済全体の安定性まで、日本銀行の決定は社会に大きな影響を及ぼしています。
ところで、日本銀行の役割とは何でしょうか?
日本銀行がしていることは、「物価の安定」と「金融システムの安定」の2つです。
ここでは、そんな2つの役割を果たすために、どのような理想を持っているのか、また、それを実現させるための手段、そして歴史的背景や潜在的なリスクなど、さまざまな角度からくわしく解説します。
日本銀行の働きを理解することは、経済ニュースや政策動向をより深く理解することができ、将来の経済動向を予測したり、自身の資産運用を検討したりする際にも役立ちます。
日本銀行の2つの役割:「物価の安定」と「金融システムの安定」
日本銀行の役割は、「日本銀行法(平成九年法律第八十九号)」によって厳格に規定されています。
この法律の第一条には、日本銀行の二つの目的が明確に定められています。
一つは「物価の安定を図ることを通じて国民経済の健全な発展に資すること」であり、もう一つは「決済システムの円滑で安定的な運行を確保し、金融システムの安定に資すること」です。
1998年に規定された日本銀行法のポイントは、旧法(昭和十七年法律第六十七号)の全面改正であったという点です。
1998年の法改正は、単なる法制度の更新以上の意味を持っています。
改正が行われた1990年代後半は、バブル崩壊後の金融危機が深刻化し、金融機関の破綻が相次いだ時代でした。旧法の下では必ずしも明確でなかった「金融システムの安定」という使命が、新法では「物価の安定」と並ぶ主要な目的として明記されました。
これは、日本銀行が単なる物価の番人から、金融システムの守護者としての役割を強化した、日本にとって歴史的な転換点だったのです。
この法律によって、日本銀行が金融政策(物価の安定を追求する政策)とプルーデンス政策(金融システムの健全性維持政策)の両輪で、経済全体を多角的に守るという、現代の中央銀行に求められる役割を明確にしたのです。

中央銀行の三つの伝統的役割
日本銀行は「物価の安定」「金融システムの安定の維持」を果たすために、「発券銀行」、「銀行の銀行」、「政府の銀行」という三つの古典的な役割を担っています。
- 発券銀行 (Bank of Issue)
日本銀行は、日本で唯一、紙幣(日本銀行券)を発行できる特別な機関です。
発行された銀行券は独立行政法人国立印刷局で製造され、日本銀行が製造費用を支払って引き取ります。銀行券は、法貨としての強制通用力が法律により付与されており、支払いに用いた際に相手がその受け取りを拒絶することはできません。
日本銀行は、この銀行券の安定供給を確保するとともに、還収された銀行券の鑑査(真偽の鑑定や再利用の可否判断)を行い、偽造・変造を防ぐことで、国民が安心して紙幣を使用できる環境を維持しています。 - 銀行の銀行 (Bank for Banks)
日本銀行は、一般の個人や企業とは直接取引を行わず、民間の金融機関を主要な取引相手としています。民間金融機関は、日本銀行に当座預金口座を開設しており、この口座を利用して金融機関同士の資金決済を行います。
また、急な資金不足に陥った際には、日本銀行からお金を借りることもできます。
この機能は、後述する「最後の貸し手」機能と密接に結びついており、金融システム全体の安定性を確保する上で不可欠な役割を果たしています。 - 政府の銀行 (Bank for Government)
日本銀行は、政府の資金(税金や社会保険料など)の出し入れを行う口座を管理しています。国民から集められた税金は日銀の政府預金に預けられ、国の事業に必要な経費はここから支払われます。日本銀行の業務局は、年間で約4億6千万件、金額にして約2千5百兆円にものぼる国庫金の受払いを担っており、年金支給などの国民生活に直結する膨大な事務を、一件一円たりとも間違えることなく処理しています。
これにより、国民が国との金銭のやりとりを安心して行えるという「当たり前」が日々実現されています。

二大ミッションの詳細 — 物価の安定と金融システムの安定
物価の安定:なぜインフレ率2%が重要なのか?
日本銀行の第一の使命である「物価の安定」は、国民経済の健全な発展にとって不可欠な基盤です。日本銀行は、この「物価の安定」を、単に物価水準が変動しないこととは考えていません。
日本銀行の考える「物価の安定」とは、「家計や企業等の様々な経済主体が、財・サービス全般の物価水準の変動に煩わされることなく、消費や投資などの経済活動にかかる意思決定を行うことができる状況」です。
つまり、来週になっても、来月になっても商品の値段が大きく変わることがなく、安心して買い物することができて、将来の計画を立てやすい状況のことをいいます。
この目的を達成するため、日本銀行は2013年から「消費者物価の前年比上昇率2%」という具体的な「物価安定目標(インフレターゲット)」を掲げてきました。
なぜ2%なのでしょうか。
その理由は主に三つあります。
第一に、統計上の誤差を考慮するためです。
消費者物価指数は実際の物価変動よりも高めに出る傾向があるため、これを考慮して目標が設定されています。
第二に、景気悪化時に金融政策で対応できる余地を確保するためです。
インフレ率がゼロ%に近い場合、金利をゼロ以下にできない「ゼロ金利制約」(zero lower bound)に直面し、金融緩和の手段が限られてしまいます。
しかし、2%のインフレ目標があれば、金利を引き下げてもマイナス金利に陥る前に金融緩和の余地を確保できます。
第三に、2%が国際的な標準となっており、為替相場の安定にも寄与するためです。
このインフレ目標の導入は、日本が長らく直面したデフレとの闘いにおける戦略的な転換を象徴しています。バブル崩壊後の日本では、金利をゼロにしてもデフレが払拭できず、「流動性の罠(金利を下げて景気を刺激することができない状態)」と呼ばれる状態に陥りました。
このような状況下で、日本銀行は物価安定の明確なゴールを設定することで、市場参加者に政策意図を伝え、将来の物価に対する期待を形成させる「フォワードガイダンス」(時間軸政策)を効果的に機能させようとしました。
つまり、日本銀行が金融政策を通じて、単なる金利の調整だけでなく、将来どうしようと考えているかを知ってもらうことで、人々の心理や期待に働きかけ、政策効果を高めようとしたのです。
暮らしに役立つ身近なお金の知恵・知識情報サイト ─ 知るぽると:金融広報中央委員会
ホーム : 日本銀行 Bank of Japan
金融システムの安定:国民と企業が安心して取引できる基盤
日本銀行のもう一つの重要な使命は、「金融システムの安定」に貢献することです。
金融システムとは、お金の受け払いや貸し借りを行うしくみ全体を指します。
金融システムを使っているのは、さまざまな金融市場や多数の金融機関です。
多数の金融機関が使っているシステムを安定させる、とは「金融システムが正常に機能し、企業や人々が安心して『お金』を使用できる状態」を指しています。
金融システムの安定は、参加しているすべての金融機関が健全性であるだけではなく、システム全体として維持されるべき「公共財」としての側面を持っています。
つまり、金融システムは「みんなで使う道路や公園のように、誰もが無料でその恩恵を受けることができるものだけど、個々の金融機関は自分だけのためにその維持費用を負担しようとしません」
なので、社会全体で守るべき「公共財」として扱われているのです。

物価の安定を追求する手段:金融政策のメカニズム
金融政策の基本:「公開市場操作」と金利の調整
次に、日本銀行の役割に一つ「物価の安定」についてはどうでしょうか?
具体的にどのようなことをしているのか見ていきましょう。
「物価の安定」は、お金の量、そして金利を調整によって行います。
つまり日本銀行は「お金の量や金利を調整して、経済全体をコントロール」し、物価の安定を目指します。
その中でも特に注目されるのが「公開市場操作(オペレーション)」と呼ばれるミッションです。
「公開市場操作」では、日本銀行が市場で国債を売買することで、世の中に出回るお金の量を調整します。
- 資金供給オペレーション(買い入れ)
日本銀行が国債を買うことです。
これにより、世の中に出回るお金の量が増加し、金利を下げる効果があります。
金利が下がると、企業や個人がお金を借りやすくなり、投資や消費が活発化し、景気刺激につながります。 - 資金吸収オペレーション(売り出し)
日本銀行が国債を売ることです。
これにより、世の中に出回るお金の量が減少し、金利を上げる効果があります。
金利が上がると、お金を借りにくくなり、経済の過熱を抑えることができます。
このように金利を上げ下げすることは、社会全体の景気や物価に影響を与えることができます。このように日本銀行は、景気が良く物価が上がってしまったときは、金利が上がるように促し、景気が悪い時には金利を下げて景気を刺激させ「物価の安定」を目指すのです。
未知への挑戦:新しいデフレ克服方法
しかし、日本はバブル崩壊後、デフレと金融不安が長期にわたって深刻化しました。
これに対応するため、日本銀行は今までにどの国も行ったことのない未知の金融政策に挑戦することになります。
1999年:ゼロ金利政策の開始
デフレ懸念の払拭が展望できるまで、短期金利(無担保コールレート)をほぼゼロ水準に誘導する「ゼロ金利政策」が開始されました 。
2001年:量的緩和政策の開始
ゼロ金利政策でもデフレを克服できなかった日本銀行は、「流動性の罠(金利を安くしてもお金が流れず罠にかかったように身動きができなくなること)」に直面します。
このため、金融調節の主たる操作目標を、金利から「日本銀行当座預金残高」へと変更する「量的緩和政策」に移行することになります。これは、金融市場に大量の資金を供給することで、物価の下落に歯止めをかけることを目的とした異例の政策でした。
2013年:量的・質的金融緩和(QQE)の導入
第2次安倍内閣が掲げた「大胆な金融緩和」の一環として、日本銀行は「量的・質的金融緩和(QQE)」を導入します 。これは、2%の物価上昇率を目指し、長期国債やETF、J-REITなどのリスク資産の買入れを大幅に拡大する政策です。
2016年:マイナス金利政策とYCCの導入
QQEの補強策として、「マイナス金利付き量的・質的金融緩和」を導入しましす。
これは、金融機関が日本銀行に預ける一部の当座預金にマイナス金利を適用することで、銀行の貸出を促し、企業や個人の投資・消費を刺激することを目的としたものです。同年9月には「長短金利操作付き量的・質的金融緩和(YCC)」を導入し、短期金利だけでなく、長期金利も国債買い入れ額を調整することで、特定の水準に誘導する政策を開始しました。
過去の主要な金融政策の変遷を表にまとめました。
| 政策名 | 導入時期 | 目的 | 主な手法 | 備考 |
| ゼロ金利政策 | 1999年2月 | デフレ懸念の払拭 | 短期金利(無担保コールレート)をゼロ水準に誘導 | 「デフレ懸念が払拭されるまで」継続を表明 |
| 量的緩和政策 | 2001年3月 | デフレ脱却、経済の安定 | 金融調節目標を日銀当座預金残高に変更、長期国債の買入れを増額 | ゼロ金利制約に直面して導入 |
| QQE(量的・質的金融緩和) | 2013年4月 | 2%の物価目標達成 | 長期国債、ETF等の買入れを大幅に拡大 | 「大胆な金融緩和」として導入 |
| マイナス金利政策 | 2016年1月 | 銀行貸出の促進、投資・消費の刺激 | 日銀当座預金の一部にマイナス金利を適用 | 銀行の収益圧迫が懸念された |
| YCC(イールドカーブ・コントロール) | 2016年9月 | 短期・長期金利の低水準維持 | 短期金利にマイナス金利、長期金利は長期国債の買入れで調整 | 長期金利が0%付近で推移するように国債を買い入れ |
ホーム : 日本銀行 Bank of Japan
経済社会総合研究所 - 内閣府
政策の「正常化」:2024年の歴史的転換
そして2024年3月、日本銀行はデフレ脱却への道筋が見えたと判断し、約17年ぶりに金融政策の歴史的な転換を決定しましす。
具体的には、マイナス金利政策を解除し、長短金利操作(YCC)を撤廃 。金融政策の枠組みを、無担保コールレート翌日物の誘導目標を設定する「普通の金融政策」に回帰させました。
2024年の政策転換の背景には、賃金上昇と物価の好循環が確認され、物価安定目標の「持続的・安定的」な実現が見通せるようになったことがあります。今後は、賃金上昇やインフレの動きが持続すれば、段階的な利上げや日本銀行の収益の改善が進んでいく見通しです。
利上げは、銀行の預貸利鞘の改善を通じて収益にプラスに働く可能性がありますが、住宅ローンを抱える家計や、金利上昇に脆弱な企業にとっては利払い負担増という重荷になる可能性もあることに注目したいですね。

金融システムの安定を維持する手段:日銀の守護者としての役割
「最後の貸し手」機能:金融危機時のセーフティネット
日本銀行は、金融システムの安定を確保するため、「最後の貸し手(Lender of Last Resort, LLR)」としての役割があります。これは、一時的な資金不足に陥った金融機関に対し、他に資金供給を行う主体がいない場合に、中央銀行が文字通り最後の貸し手として一時的な資金の貸付け等を行うことを指します。
それは、金融機関を守るためということもありますが、他の健全な金融機関に連鎖的な破綻(システミック・リスク)を未然に防ぐことにあります。
過去の危機対応事例を比較すると、日本銀行の対応が進化してきたことがわかります。
- リーマンショック時
2008年のリーマンショック後、金融市場の混乱と企業の資金調達環境の悪化に対応するため、CP「コマーシャルペーパー(信用力の高い大企業向けに無担保で短期の資金の調達を支援する方法)」の買入れや企業金融支援特別オペを導入しました。これは、市場を通じて企業の資金繰りを支援する措置であり、LLR機能の応用として機能しました。 - 東日本大震災時
2011年の東日本大震災時には、日本銀行は地震発生直後に災害対策本部を設置し、被災地での現金供給を継続しました。また、日銀ネットの安定的な稼働を確保し、決済時間を延長するなど、物理的なインフラや決済システムの機能不全に対応する措置も講じました 。
このように日本銀行の危機対応は、単に資金供給を行うという伝統的なLLR機能にとどまらず、災害時の現金供給網の確保や決済システム全体の運用支援といった、より柔軟な対応になっています。
現代の危機が金融システムだけでなく、決済システムや物理的な流通網にも影響を及ぼすことが分かってきたためです。
日銀の危機対応は、単一の金融機関の破綻防止にとどまらず、社会インフラ全体としての「お金」の機能不全を未然に防ぐための、多角的な戦略へと変化してきています。
安全な決済のために:日銀ネット
日本銀行の役割の一つ「金融システムの安定化」のためにはスムーズな決済システムが欠かせません。
日本銀行は「日銀ネット」という決済システムを運用しています。
「日銀ネット」とは、「日本銀行金融ネットワークシステム」の略称で、日本銀行が運営する、金融機関間の資金や国債の決済をオンラインで処理するためのシステムです。
日銀ネットは、各金融機関が日本銀行に持つ当座預金口座を通じて、資金の振替ができるシステムです。国債の発行、入札、売買など、国債に関わる取引の決済も日銀ネットを通じて行うことができます。
日銀ネットは、私たちが直接使う機会はありませんが、各銀行などの民間の決済システムの情報を受けて、日銀ネットを使ってお金を動かすようになっていて、日本の金融システムを支える重要なインフラの一つになっています。
深い洞察 — 二つのミッションのトレードオフと潜在的リスク
物価安定と金融システム安定の「緊張関係」
日本銀行の二つの主要な使命、すなわち「物価の安定」と「金融システムの安定」は、必ずしも常に協調するわけではなく、時に「対立しうる」関係にあることが指摘されています。特に、物価の安定を追求するための長期にわたる金融緩和政策は、金融システムに潜在的な脆弱性をもたらす可能性があります。
- デュレーション・リスクの蓄積
緩和的な金融環境は、企業や家計が長期・低利の借入を行うことを促しました。
これにより、借り手は借り換えリスクを抑制できた一方で、貸し手である金融機関にとっては、低金利下での利鞘確保が難しくなり、収益を追求する過程で、より期間の長い債券投資などを行う傾向が見られました 。
この結果、金利が上昇した際に、金融機関が保有する債券の評価損や、貸出先の金利負担増といったリスク(デュレーション・リスク)が増加する要因となっています。 - ミドルリスク企業への貸出集中
低金利環境と激しい貸出競争の結果、金融機関は収益を確保するため、信用力が相対的に低い「ミドルリスク企業」への貸出を増やす傾向が見られました。日本銀行の論文要旨でも、こうした貸出案件は金利上昇への耐性が低い可能性があり、将来的に信用コストが増加するリスクを内包していることが指摘されています。 - 金融機関の収益力低下
過去25年間にわたる低金利環境は、金融機関の貸出金利と預金金利の差である利鞘を縮小させ、収益力を全体的に大きく低下させました。日本銀行の論文要旨によれば、特に地域金融機関においては、コア業務純益ROEが歴史的な低水準にとどまっており、ストレス耐性が低下している先も存在するとされています。
このように、長期にわたる金融緩和は、物価の安定という直接的な目標を追求する一方で、金融機関の収益力を圧迫し、結果としてシステム内に潜在的な脆弱性(ミドルリスク企業への貸出集中やデュレーション・リスク)を蓄積させてしまうという、相反する側面を持っていたと考えられます。
2024年の政策正常化は、物価の安定目標が達成されつつあるという認識に加え、こうした金融システムに生じた「隠れた歪み」を是正しなければいけないという表れでもあります。
日本銀行 Bank of Japan
超長期的な金融緩和の「副作用」と専門家の批判的見解
超長期にわたる金融緩和政策は、その効果と副作用について、専門家の間で多くの議論が交わされています。
例えば、日本銀行が巨額の国債を買い入れることで、長期金利が意図的に低く抑えられ、市場本来の価格発見機能が低下したという指摘があります。また、低金利が続くことで、政府が借入を容易に行えるようになり、財政規律が緩むという弊害も指摘されています。
異次元緩和とは何だったのか 山本謙三
また専門家を対象とした調査では、50%超が「量的緩和は景気刺激が困難」と回答しており、その効果に疑問を投げかけている見解も存在します。
公益社団法人 日本経済研究センター
また、日銀の異例の金融緩和が、日経平均株価の史上最高値更新や円安には大きな影響を与えた一方で、実体経済の改善には明確な証拠がないという批判もあります。これは、金融政策が「金融市場」と「実体経済」に異なる影響を与える可能性を示唆しています。
&N 未来創発ラボ|野村総合研究所
日本銀行の見解一方で、日本銀行は、非伝統的金融政策が実質GDPや消費者物価に一定の効果があったとする論文を発表しており、緩和的な金融環境が長期にわたる中でも、「大きな金融不均衡が蓄積した様子も観察されていない」と反論する見解も示しています。
日本銀行 Bank of Japan
このように、超長期的な金融緩和の効果と副作用の評価は単純ではありません。金融市場への影響は絶大だった一方で、それが必ずしも実体経済の持続的な成長に直結したとは言えず、専門家の間でも意見が分かれています。
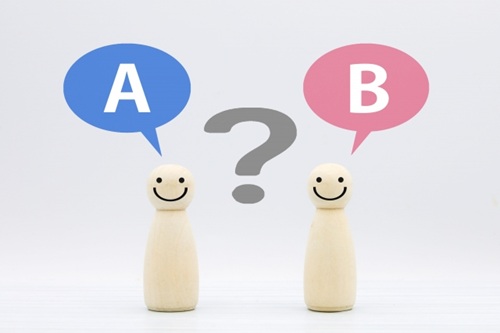
まとめ:日本経済の羅針盤としての日本銀行
ここでは、日本銀行の二つの主要な使命である「物価の安定」と「金融システムの安定」について、その定義、目的、そして具体的な手段を詳細に解説しました。
日本銀行は、発券、銀行、政府という三つの伝統的な役割に加え、これらの二大ミッションを達成するために、長年にわたり様々な金融政策を駆使してきました。特に、バブル崩壊後のデフレとの闘いの中で採用された非伝統的な金融政策は、2024年の政策正常化へとつながる歴史的変遷をたどりました。
しかし、物価安定を追求するための金融緩和政策は、金融システム内に潜在的なリスクを蓄積させる可能性があり、二つのミッション間には常に緊張関係が存在します。この複雑な関係性を理解することは、日本経済の現状と未来を読み解く上で不可欠です。
日本銀行の役割は、私たちの生活の基盤を支える重要なものです。
日本銀行が目指す「物価の安定」は、私たちが日々安心して買い物ができること、そして将来の計画を立てられることにつながります。
この記事をきっかけに、私たちの経済の今について、一緒に考えてみませんか?
参考文献
ティモシー・テイラー 経済学入門
日本銀行 Bank of Japan
日本銀行 - Wikipedia
e-Gov 法令検索
