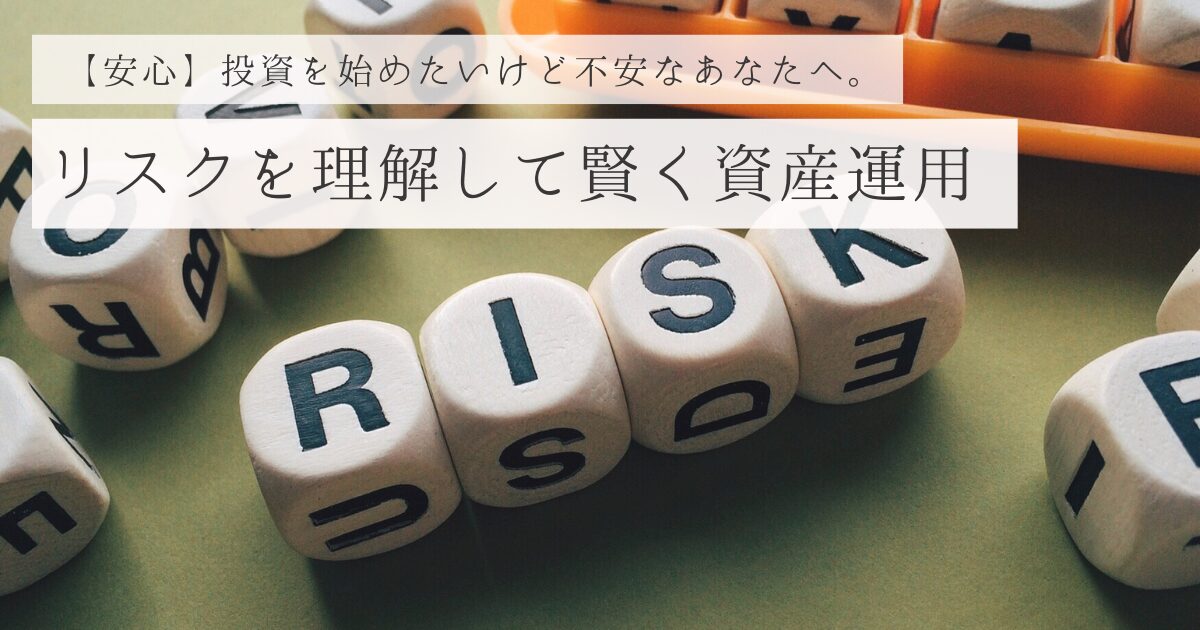将来が心配で投資を始めてみたいけれど、なにか心配で始められない、と感じている方も多いのではないでしょうか?
最近では、国を挙げて投資を支援する動きが活発化しています。
例えば、金融庁などは、投資を支援していますし、市民向けに金融リテラシーを高める活動を始めていて、私たちも自分の身は自分で守ることが必要な時代になっているのかもしれません。
「投資」は、お金を増やそうとする活動ですが、失うというリスクも抱えています。
投資でお金を増やそうとするならリスクは避けて通れません。
まずは、リスクの正体を知っておきましょう。
そうすれば、やみくもに怖がることはなくなります。
正体が分かれば、うまく付き合っていく方法も見つけることができます。
ここでは「株式投資」や「投資信託」のリスクについてゆっくり解説していきます。
リスクは楽しいことではないですが、リスクを完全になくすことはできません。
リスクと上手に付き合って、資産を少しづつ増やしていきましょう。

投資のリスクとはなんですか?
そもそも、投資のリスクとは一体なんのことでしょうか?
それは「投資によって期待した収益が得られない可能性、または元本が損失する可能性」のことです。
例えば、銀行に貯金してある、あなたのお金は、法に守られているため、預けたお金以上に減ってしまうことはありません。
けれど「投資」は預けたお金以上に減ってしまう、ということが起こります。
投資会社には、お客さまから預かったお金(元本)を、保証しなければいけないという法もありません。
「投資する」ということは、自分のお金を経済全体の中に組み込んで、社会全体と積極的にかかわることです。積極的にかかわるので、経済活動の利益を受け取ることができます。
逆に、積極的にかかわっているために、嫌なリスクも負わなければいけません。
経済に積極的にかかわったおかげて、うれしいこと、つまり高いリターンを得ることができる。
そして、嫌なリスクも負う。
というのが、投資の本質です。
なぜ投資にはリスクがあるの?
なぜ、投資にはリスクがあるのでしょうか?
元本を保証してくれたら安心なのに・・・
と思う方もいらっしゃるかもしれません。
そもそも「投資」とは、しばらく使う予定のないお金を金融商品に投資することで、将来のお金を増やすことを目的とした活動です。
ここで、大事なのは「将来お金を増やす」という目的です。
将来のお金を増やすということは、つまり現時点では、本当に増えるのかどうなのかということは、未来のことなので予想がついていません。
あなた自身のことについてちょっと想像してみてください。
例えば、あなたは明日の昼ご飯に何を食べるのでしょうか?
これは、予測がつく方が多いと思います。明日の昼のことは予想しやすいですね。
では、1週間後はどうでしょうか?
1か月後、1年後の昼ごはんは、どうですか?
どんどんと良く分からなくなっていくのではないでしょうか?
明日のことは今日の延長線上にあって、イメージが難しくはありませんが、1年後、5年後と時間が経てば経つほどイメージがわかなくなってくるはずです。
これと同じことが「投資」にも言えます。
近い未来のことは誰もがイメージしやすいので、イメージ通りに進みます。
けれど、何年も先になると、私たちの人生にも災害や病気、思いがけないうれしいことなどが、現れるのでどのようになっているかが良く分かりません。
投資は未来のことを考えて「今」お金を支払います。
期待するのは将来でているはずの利益です。
けれど「今」の時点で「未来」がどうなっているのか知ることはできません。
そのため、今、将来利益が出ると思って投資したけれど、思うようにことが進まなかった。
ということが、起こりやすいのが「投資」の特徴です。
順調にいけば利益を受け取ることができます。
けれど、未来の経済状況や市場の動きを正確に予測できないためリスクがあり元本は保証できないのです。
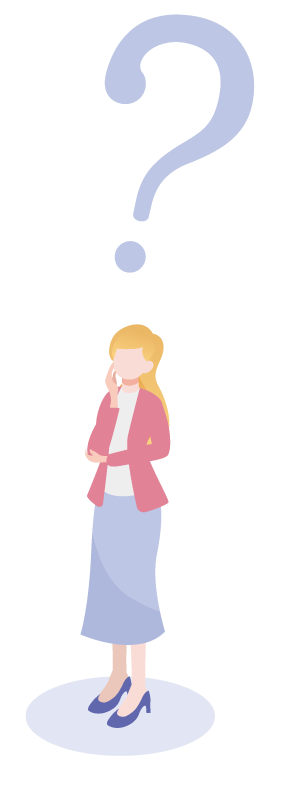
不確実なリスク
将来のことが良く分からない、ということについてもう少し掘り下げてみましょう。
株式投資は、いわば企業のオーナーになるようなものです。
企業の業績は、経済状況、競合他社の動き、新しい技術の登場など、様々な要因によって左右されます。これらの要因は、常に変化し、予測が難しいものです。
投資は、その企業のオーナーになり、未来の利益を期待して行います。
しかし、その成果がどのようになるかは、事前に正確に予測できません。
つまり「不確実」なのです。
それが、リスクがあるということなのです。
予想できないことというのは具体的に次のようなものがあります。
- 経済の状況
経済の景気や政策変更などが影響し、株価や債券の価格が変動することがあります。 - 企業の業績
企業の業績や経営状況の変化が株価に影響を与えることがあります。 - 市場の動向
市場全体の動向や投資家の心理が影響し、価格が予測不可能な動きをすることがあります。
投資を始めたころは業績が伸びていて、好感が持てる企業だったのに、急に内部告発でイメージが悪くなったり、不良品が見つかってリコールが行われる、ということが起こる可能性があるため、それがリスクとなります。
この将来が予想できないのは、多くの専門家たちが慎重に分析や予測を行っても、完全に排除することはできないと言われています。
変動(ボラティリティ)のリスク
将来を予測できないリスクには他にもさまざまなタイプがあります。
まず変動(ボラティリティ)のリスクと呼ばれるものがあります。
これは、企業の業績が良かったとしても、市場全体の動向や心理的な要因によって株価が大きく変動する現象のことです。
例えば、高成長が期待される最新テクノロジー企業は、高く評価されていますが、技術革新のスピードが速く、競合の参入や技術の陳腐化など、様々なリスクもはらんでいます。
また、最新の技術に関する情報は、世間から注目も高く日々更新され、投資家はその情報を基に判断を迫られます。情報が多すぎるがゆえに、解釈が分かれ、投資家の間でも意見が対立しやすくなります。
そのため、わずかな情報で投資家心理は常に変動しやすく、期待が高まれば株価は多く上昇し、裏切られると株価は大きく下落する可能性があります。
このように、株価が大きく変動することを、変動性(ボラティリティ)のリスクと呼んでいます。

変動性が高いとどうなる?
変動性が高い株式は、短期間で大きな利益を得られる可能性がある一方で、大きな損失が出るリスクも高くなります。まるで一攫千金のチャンスと大きなリスクが表裏一体になっているようなものです。
メリット
- 短期間で大きな利益
株価が上昇すれば、短期間で大きな利益を得られる可能性があります。 - 成長株の発掘
新しい技術や市場を開拓しているような成長性の高い企業の株は、変動性が高く、大きなリターンが期待できる可能性があります。
デメリット
- 短期間で大きな損失
株価が下落すれば、短期間で大きな損失が出る可能性があります。 - 心理的な負担
株価の変動に一喜一憂し、精神的なストレスを感じることがあります。 - 売買タイミングが難しい
株価が頻繁に上下するため、売買のタイミングを見極めるのが難しく、損失を被る可能性が高まります。
新技術の開発が激しいIT、バイオテクノロジー業界、経済の影響や規制の厳しい金融業界は特にボラティリティのリスクが高いと言われています。
金利の変動リスク
投資を行うときに意識しておきたいリスクのもう一つは、「金利変動のリスク」です。
「金利変動のリスク」とは、金利の上下によって、投資した資産の価値が変動するリスクのことです。
例えば、銀行に預けているお金があるとします。
金利が上がれば、将来受け取れる利息が増えてお得に感じます。
しかし、逆に金利が下がれば、利息が減ってしまい損をする可能性があります。
なぜ金利変動リスクが生まれるのか?
金利は、経済状況や中央銀行の政策によって変動します。
- 経済が活発なとき
企業の設備投資が活発になり、資金需要が高まるため、金利は上昇する傾向があります。 - 経済が低迷しているとき
企業の活動が鈍り、資金需要が低下するため、金利は低下する傾向があります。 - インフレが進むとき
物価が上昇すると、お金の価値が下がるため、物価上昇率を上回る利息を支払うために、金利は上昇する傾向があります。
中央銀行は物価の安定のため、調整しています。
そのため、金利はその時の状況に合わせて上下するので、金利の変動のリスクはなくならないのです。
金利変動リスクの影響を受ける主な資産
金利変動リスクは、主に以下の資産に影響を与えます。
- 債券
債券は、一定の利率で将来に元本が返済される有価証券です。
金利が上昇すると、新しく発行される債券の利率は上昇するため、以前から持っている債券の価値は相対的に下がってしまいます。 - 投資信託
投資信託の中には、債券に投資するものが多くあります。
そのため、債券の価格が変動することで、投資信託の基準価額も変動します。 - 変動金利のローン
変動金利のローンは、金利が変動するにつれて、返済額も変動します。
金利が上昇すれば、返済額が増えてしまうリスクがあります。
金利変動リスク対策
金利変動リスクを抑えるためには、以下の方法が考えられます。
- 固定金利の選択
ローンや預金を選ぶ際は、金利が変動しない固定金利を選ぶことで、金利変動リスクを回避できます。 - 複数の資産に分散投資
債券だけでなく、株式や不動産など、様々な資産に分散投資することで、金利変動リスクの影響を軽減できます。 - 金融機関のアドバイスを受ける
金融機関の専門家から、自身の投資目標やリスク許容度に合わせて、最適な商品を提案してもらうことも有効です。
中央銀行は物価を安定させ、ゆるやかに経済を成長させるため、金利を変動させます。金利変動は、経済活動にとって不可欠な要素であり、完全に予測することは困難です。金利変動のリスクを理解し、自分に合った対策を講じることでリスクを最小限に抑えることができます。

為替のリスク
海外の商品に投資することも最近は増えていますが、その時に注意したいのが為替のリスクです。
為替リスクとは、外国の通貨と日本の円との交換レート(為替レート)が変動することによって、投資の損益が変動するリスクのことです。
例えば、1ドル=110円で1万ドルの米国株を買ったとします。
- 円安に振れる場合
1ドル=120円になると、日本円に換算すると120万円になり、10万円の利益になります。 - 円高に振れる場合
1ドル=100円になると、日本円に換算すると100万円になり、10万円の損失になります。
このように、為替レートの変動によって、投資した資産の価値が変動してしまうのが為替リスクです。
なぜ為替レートは変動するのか?
為替レートは、様々な要因によって変動します。主な要因としては、
- 経済状況:各国の経済成長率、物価、金利などの経済指標
- 政治情勢:政権交代、政策変更、国際関係の動き
- 市場心理:投資家の心理、市場の需給バランス
などが挙げられます。これらの要因が複雑に絡み合い、為替レートは常に変動しています。
為替リスクの影響を受ける主な投資
為替リスクの影響を受ける主な投資には、以下のようなものがあります。
- 外国株式
米国株、欧州株など、外国の株式に投資する場合、為替リスクが生じます。 - 外国債券
外国の債券に投資する場合も、為替リスクが生じます。 - 外貨建て預金
外貨で預金する場合、円に換える際に為替リスクがあります。 - 海外不動産
海外の不動産を購入する場合、不動産価格だけでなく、為替レートの変動も考慮する必要があります。
為替リスク対策
為替リスクを完全に回避することは難しいですが、以下の対策を講じることで、リスクを軽減することができます。
- 分散投資
複数の通貨に分散投資することで、特定の通貨の変動による影響を小さくすることができます。 - 為替ヘッジ
先物取引やオプション取引など、為替レートの変動リスクを回避するための金融商品を利用する方法があります。 - 外貨建て資産の割合を調整
ポートフォリオ全体の外貨建て資産の割合を調整することで、為替リスクの許容度を調整することができます。 - 為替変動を予測する
為替の動向を分析し、予測することで、リスクを管理することができます。
為替リスクは、海外投資を行う上で避けて通れないリスクの一つです。
しかし、為替リスクを理解し、適切な対策を取ることによって、リスクを管理することができます。
信用のリスク
そして、将来がどうなるのか分からないために、起こるリスクの一つに「信用リスク」もあります。
このリスクは、株式や債券などを発行している企業や国が、倒産や債務不履行を起こし、投資したお金が回収できなくなるリスクのことです。
もし、ある企業が経営不振に陥り、倒産してしまった場合、その企業の株の価値はゼロになり、投資したお金が全額損失になる可能性があるリスクのことです。
なぜ信用リスクが生じるのか?
信用リスクは、主に以下の要因によって生じます。
- 企業の業績悪化
売上減少、競合他社の出現、新製品開発の失敗など、企業の業績が悪化すると、債務を返済できなくなる可能性が高まります。 - 業界全体の不況
特定の業界が不況に陥ると、その業界の企業は軒並み経営が厳しくなり、信用リスクが高まります。 - 経済全体の低迷
景気後退など、経済全体が低迷すると、多くの企業が経営難に陥る可能性があります。 - 自然災害や事故
大規模な自然災害や事故が発生した場合、企業の生産活動が停止したり、大きな損害を被ったりして、経営が困難になることがあります。 - 経営者の不正
経営者が不正行為を行ったり、経営判断を誤ったりした場合、企業の信用が失われ、信用リスクが高まります。
信用リスクの影響を受ける主な投資
信用リスクは、主に以下の投資に影響を与えます。
- 株式
企業が倒産すると、株式の価値はゼロになる可能性があります。 - 債券
企業や国が債務不履行になると、債券の価値が下落したり、利息が支払われなくなる可能性があります。 - 投資信託
投資信託の中には、特定の企業や業界の株式や債券に投資しているものがあります。
そのため、投資先の企業が経営破綻すると、投資信託の価値が大きく下がる可能性があります。
信用リスク対策
信用リスクを完全に回避することは難しいですが、以下の対策を講じることで、リスクを軽減することができます。
- 企業の財務状況を分析する
投資先の企業の財務状況をしっかりと分析し、健全な企業を選ぶことが重要です。 - 分散投資
複数の企業や業界に分散投資することで、特定の企業の倒産による影響を小さくすることができます。 - 信用格付けを参考にする
債券の信用格付けは、債務不履行のリスクを示す指標の一つです。信用格付けの高い債券を選ぶことで、信用リスクを軽減することができます。
その国や企業の未来がどうなるかは分からないですが、企業の分析や格付けを参考にすることで、リスクを回避することができます。
流動性リスク
最後に、大切な流動性のリスクについて見ていきましょう。
流動性リスクとは、投資した資産を現金化したい時に、希望する価格で、すぐに売却できないリスクのことです。
例えば、あなたが持っている株を急いで現金化したいとします。
しかし、その株を欲しい人がいなければ、希望する価格で売却することができず、損失を被る可能性があります。これが流動性リスクです。
なぜ流動性リスクが生じるのか?
流動性リスクは、主に以下の要因によって生じます。
- 取引量の少なさ
特定の銘柄の取引量が非常に少ない場合、買い手がつかず、売却に時間がかかったり、希望する価格で売却できない可能性が高まってしまいます。 - 市場の混乱
経済危機や自然災害など、市場が混乱している状況では、多くの投資家が同時に売却しようとするため、取引が成立しにくくなります。 - 規制の変化
政府の規制が変更になったり、新しい規制が導入されたりした場合、取引が制限され、流動性が低下することがあります。
取引量が引くかったり、市場が混乱していると自分が望むタイミングに現金化できない可能性が高まることを「流動性のリスク」と呼びます。
流動性リスクの影響を受ける主な投資
流動性リスクは、主に以下の投資に影響を与えます。
- 株式
上場しているすべての株式が、常に活発に取引されているわけではありません。
特に、中小企業の株式や、特定の業界の株式などは、流動性が低い場合があります。 - 投資信託
投資信託の中には、特定の銘柄に集中して投資しているものがあります。
その銘柄の流動性が低い場合、投資信託全体の流動性も低下します。 - 不動産
不動産は、株式や債券に比べて売却に時間がかかるため、流動性が低い資産と言えます。
流動性リスク対策
流動性リスクを完全に回避することは難しいですが、いくつかの対策が知られています。
流動性のリスクを軽減するためには下のような対策が有効です。
- 流動性の高い資産を選ぶ
日経平均株価に連動するETFなど、常に多くの取引が行われている資産を選ぶことで、流動性リスクを低減できます。 - 分散投資
複数の資産に分散投資することで、特定の資産の流動性が低い場合の影響を小さくすることができます。 - 現金化のタイミングを検討する
急な資金が必要になった場合でも、慌てずに、市場の状況を見ながら売却のタイミングを検討することが重要です。
将来を予測できないこと、変動性が高いものがあること、為替や金利、信用そして流動性のリスクを解説しました。
たくさんのリスクがありましたが、次にこれらのリスクを最小限に抑えていく具体的な方法を見ていきましょう。

リスクを減らすための4つの方法
では、リスクを少しでも小さくするためにはどうしたら良いのでしょうか?
リスクを減らすための研究は良くされていて、次のような方法が有効なことが知られています。
1.分散投資
投資先をいくつかに分けることでリスクを軽減できます。
いろいろな種類の投資を少しづつ組み合わせて、全体としてのリスクを減らすのです。
もし、ある投資先の事業が悪くなった時、その業績の悪くなった1社にすべてにかけていると、資産のほとんどがなくなってしまいますが、複数の投資先に分散していれば損失を緩和することがあります。
この分散投資を簡単にできるのが、投資信託です。
これは複数の株や債券を一つにまとめた金融商品なので、手軽にリスクを分散することが出来ます。
2.長期投資
みなさんもよくご存じかと思いますが、投資には長い時間をかけて行うことが良いと言われます。
長期投資が投資のリスクを減らすと言われるのは、次のような点が有利と考えられているためです。
市場の変動を平均化できる
- 短期的な上下動
株式市場は日々、様々な要因によって大きく変動します。
短期的な投資では、この変動に振り回され、損失を出してしまう可能性があります。 - 長期的な成長
一方、長期的に見れば、市場は一般的に成長傾向にあります。
短期的には下落することもありますが、長期的に見れば、その間の変動は平均化され、プラスのリターンを得られる可能性が高まります。
複利の効果
- 雪だるま式に増える
長期投資では、得られた収益を再投資することで、複利の効果が働き、資産が雪だるま式に増えていきます。 - 時間の力
長期にわたって複利の効果が働くことで、初期投資額が少なくても、最終的な資産額は大きく膨らむ可能性があります。
心理的な安定
- 短期的な損失に動揺しない
短期投資では、株価の変動に一喜一憂しがちですが、長期投資では、短期的な損失に一喜一憂する必要がありません。 - 冷静な判断
長期的な視点を持つことで、感情的な判断を避け、冷静に投資判断を行うことができます。
ドルコスト平均法の効果
ドルコスト平均法とは、投資する商品(株や投資信託など)を、一定額を定期的に購入していく投資方法です。価格の変動に関係なく、毎回同じ金額で購入することで、平均購入単価を抑える効果が期待できます。
- 購入単価の平準化
定期的に一定額を投資することで、高値のときには少ない株数、安値のときには多くの株数を購入できます。 - リスク分散
購入単価を平準化することで、市場の変動によるリスクを分散することができます。
3.自分のとれるリスクを設定する
投資で自分の取れるリスクを設定することは、非常に重要なステップです。
リスク許容度と呼ばれるこの概念は、個人の性格、年齢、財産状況、投資目標など、様々な要素によって違うので、下のような手順で自分にあった基準を探してみましょう。
リスク許容度を設定する方法
- 自己分析
- 年齢とライフステージ
若年層は、長期的視点でリスクを取れる傾向がありますが、高齢者になると安定を求める傾向が強まります。 - 財産状況
投資に回せる金額や、失っても生活に支障が出ない金額などを考えましょう。 - 投資経験
経験が少ない場合は、リスクを低く設定することが一般的です。 - 性格
冒険好きか慎重か、など性格もリスク許容度に影響します。 - 投資目標
短期的な目標か長期的な目標か、目標達成のために必要なリターンなどによって、リスク許容度は変わります。
- 年齢とライフステージ
- リスク許容度診断ツール
多くの証券会社や金融機関が、オンラインでリスク許容度を診断できるツールを提供しています。質問に答えることで、自分のリスク許容度を客観的に把握できます。
リスク許容度と投資商品
リスク許容度に合わせて、以下のような投資商品を選ぶことができます。
- 低リスク:銀行預金、国債など
- 中リスク:投資信託(インデックス型)、REITなど
- 高リスク:個別株式、ベンチャー企業への投資など
リスク許容度を調整する方法
- ポートフォリオの分散:複数の資産に分散投資することで、リスクを軽減できます。
- 定期積立:投資額を一定額に固定し、長期的に投資することで、市場の変動リスクを平均化できます。
- 損切りの設定:損失が一定額を超えたら売却するなど、損失を限定するルールを設定できます。
注意点
- リスク許容度は固定のものではない
人生における様々な変化に伴い、リスク許容度も変わることがあります。
定期的に見直すことが重要です。 - リスクとリターンは表裏一体
高いリターンを得たい場合は、ある程度のリスクを取らざるを得ません。 - 投資は元本保証ではありません
どんなにリスクを低く設定しても、元本割れの可能性はゼロではありません。
投資で自分の取れるリスクを設定することは、成功するための第一歩です。自分の状況や性格をしっかりと把握し、自分に合った投資計画を立てるようにしましょう。
4.定期的な見直し
投資環境は常に変化しています。
経済状況、市場のトレンド、個人の状況など、様々な要因が投資に影響を与えるため、一度組んだ投資先をそのままにしておくことは、必ずしも賢明とは言えません。
- 資産配分のバランスの変化
- 時間の経過による変化
各資産の価格変動により、当初計画していた資産配分が大きく変わることがあります。
例えば、特定の銘柄が急騰した場合、その銘柄の占める割合が大きくなり、リスクが集中してしまう可能性があります。 - 外部環境の変化
金利変動、新たな技術の登場、政策変更など、外部環境の変化も資産配分を大きく変える要因となります。
- 時間の経過による変化
- リスク許容度の変化
- 年齢の変化
年齢を重ねるにつれて、リスク許容度は低下していく傾向にあります。 - ライフイベントの変化
結婚、出産、住宅購入など、ライフイベントの変化は、投資に対する考え方や目標を変化させ、リスク許容度にも影響を与えます。
- 年齢の変化
- 投資目標の変化
- 短期的目標
住宅購入資金、留学資金など、短期的目標達成のために、より安全性の高い資産にシフトする必要があるかもしれません。 - 長期的な目標
老後資金など、長期的な目標に向けて、より成長性の高い資産に投資を続ける必要があるかもしれません。
- 短期的目標
定期的な見直しで得られる効果
- リスクの分散
資産配分を最適化することで、特定の資産に集中してリスクが大きくなることを防ぎます。 - 目標達成への貢献
投資目標に合わせて、ポートフォリオを調整することで、目標達成の可能性を高めます。 - 心の安定
ポートフォリオを定期的に見直すことで、投資に対する不安を軽減し、安心して投資を続けることができます。
見直しの頻度と注意点
- 頻度
一般的には、年に1回程度の見直しで十分ですが、市場が大きく変動した場合などは、より頻繁に見直す必要がある場合があります。 - 注意点
- 手数料
頻繁な売買は、取引手数料がかかるため、注意が必要です。 - 税金
売却益に対して税金がかかる場合があるため、税金対策も考慮しましょう。
- 手数料
投資は、一度決めてしまえば終わりというものではありません。
定期的に見直しを行い、市場の変化や自分の状況に合わせて投資先を調整していくことが、長期的な視点で資産を増やしていくために不可欠です。
ご自身の状況に合わせて、適切な頻度で投資の見直しを行ってみてください。

資産運用と人生
自分がどのように資産運用していこうかと考えることは、自分の人生をこれからどうしようかと考えることと同じです。
今、自分は人生でどのあたりにいるのか、家族構成はどうなっているのか、これから必要になる出費はいくらになりそうなのか、今の資産はどのくらいあって、遺産相続の可能性はどのくらいか、今の収入はどのくらいあって、将来はどのくらいになりそうなのか?
これらのことを一つ一つ考えて自分が取れるリスクを考えてみます。
いくら入る予定でいくら必要なのかが分かれば、なにをどう投資するのか決まってきます。
投資は自分がこれからどんな人生を送りたいか、を決めていくことなのです。
金融広報中央委員会のウェブサイトの「知るポルト」というサイトがあります。
暮らしに役立つお金に知恵や情報が載っています。
また、ライフプランシュミレーションといった自分の年収や生活費などを入力して自分の生活設計を計算してくれるページもありますので、何から手を付けていいか分からない方にぜひお勧めです。
暮らしに役立つ身近なお金の知恵・知識情報サイト ─ 知るぽると:金融広報中央委員会 (shiruporuto.jp)
まとめ
資産運用のリスクについて解説しました。
投資するということは、自分のお金を社会に積極的にかかわらせる活動です。
積極的にかかわるので、その利益を受けることができますが、そのリスクも受けなければいけません。
株価は経済や社会情勢などの影響を受けて、常に変動しています。
株価はその影響を受けて上下するしますが、それを前もって予想することはできません。
予想することができない「不確実性」があるため投資にはリスクがあります。
そして、最新技術を開発する企業やバイオテクノロジー業界などの将来多くの成長が期待できる業界では「変動(ボラティリティ)」のリスクが高いです。世間から注目、期待されているので小さなきっかけが大きな株価の変動を起こしやすくなる傾向があるリスクです。
また、金利のリスクがあります。
経済の状況によって金利はこまめに調整されています。
金利の変更で予定通りの収益にならない可能性があります。
そして、為替のリスクがあります。
海外の金融商品は為替の影響をうけるためリスクがあります。
また、企業自身やある国が倒産あるいは債務不履行になる可能性もあります。
最後に流動性のリスクがあります。
取引が活発でない投資先や、不動産は現金化しにくいので流動化が低いと言われリスクになります。
これらのリスクをできるだけ抑えるには、分散、長期投資、そして自分のリスクを設定すること、そして定期的な見直しすることでリスクを抑えることができます。
投資を行うことは自分の人生をどのようにしたいのか考えることと同じです。
リスクは避けることがで来ませんが、自分の投資スタイルや目標に合わせて、定期的な見直しを習慣化し、より良い投資成果を目指しましょう。
参考文献
経済学入門 ティモシー・テイラー
難しいことは分かりませんがお金の増やし方を教えてください 山崎努
お金以前 土屋剛俊
貧乏国ニッポン 加谷佳一
「金融リテラシー」って何? 最低限身に付けておきたいお金の知識と判断力 | 暮らしに役立つ情報 | 政府広報オンライン (gov-online.go.jp)