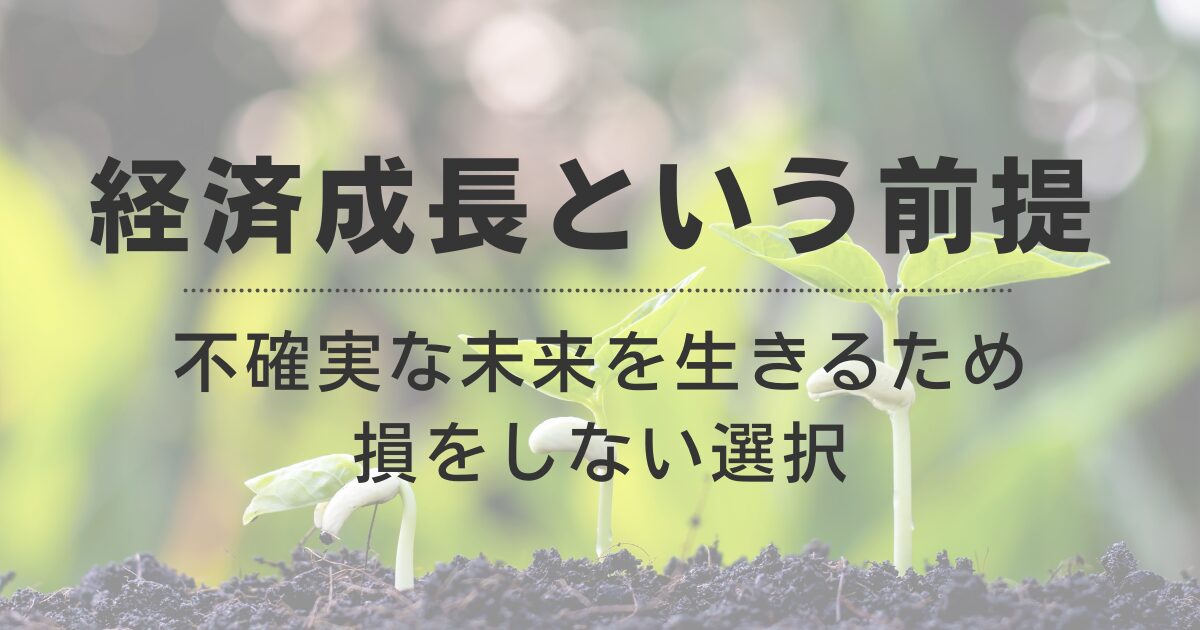もしあなたが「トヨタの販売台数が減った」というニュースを聞いたら、どう思われますか?
景気が悪いんだな・・・
と社会全体の景気に心を痛めるかたもいらっしゃるかもしれません。
また、自動車関係の仕事をしている人は大丈夫だろうか・・・?
知り合いの状況を心配される方もいらっしゃるかもしれません。
販売台数が減った理由は商品の魅力が低くなったのかもしれませんし、パンデミックのような社会全体の状況に合わせたものかもしれません。
私たちが、景気を判断する代表的な指標に「GDP」があります。
GDPは、注目度が高く、3か月に1回発表されています。
GDPの値は、みんなが想像していたよりも高い値になれば「喜ばしいこと」、逆に悪い値になれば「悪いこと」と報道されます。
良いことはいつまでも続いていてほしいものです。
けれど、私たちの経済活動は、国の情勢や景気、そして自然災害など複雑な影響を受けて、良くなったり悪くなったりを繰り返しています。
つまり、景気は永遠に上がり続けるのもではなく、上がったり下がったりするものです。永遠に上がり続けることはないのに、なぜ下がると悪いニュアンスで言われるのでしょうか?
それは、私たちの社会が「経済は成長することが前提」になって設計されていることが原因です。
この「成長することが前提の社会」は、私たちの生活に大きく関係があります。
一体どういうことなのでしょうか?
ここでは、社会の中に組み込まれている「成長」というキーワードを深掘りし、景気のよし悪しに関係なく、不確実な未来を生きていくためのヒントをご紹介いたします。
ぜひ、ご覧ください!

経済成長という前提
日本のような、市場経済を採用している国々では、企業の営業方針や政府の政策は「経済成長が前提」として組み立てられています。それは、日々のニュースを見てもわかります。
例えば、企業の収益増加や政府の景気対策、将来の社会保障制度に関する議論など、その多くが経済が拡大していくことを暗黙のうちに前提としているように見受けられるからです。
そして、私たちの生活もまた、給料が上がり、年金が安定し、社会保障が維持される、といった期待のもとに成り立っていると言えるでしょう。
しかし、未来のことは誰にも予測できません。「本当にこのまま経済は成長し続けるのだろうか?」という疑問は、実は多くの方が心のどこかで抱いているのではないでしょうか?
もし、その前提が崩れてしまったら、私たちの生活はどうなってしまうのでしょうか?
私たちは「経済成長が前提」となっている社会で、どのように考え、行動していくべきなのか考えてみましょう。
なぜ経済成長が前提となるのか?企業と政府の思惑
市場経済の中で、大きな役割を果たしている「企業」についてまず見ていきましょう。
「企業」が活動する主な目的は、売上を増やし、利益を拡大することです。
企業にとって、経済全体の規模が拡大し、消費者の購買意欲が高まる経済成長は、事業を成長させるための不可欠な要素となります。企業は、未来に向かって社会が成長していくであろうという前提をもとに、新たな設備投資を行ったり、新しい市場を開拓したりする戦略を立てます。
もし、計画通りに社会が成長せず、経済が停滞すれば、企業の売上が伸び悩み、投資計画の見直しを迫られる可能性が出てきます。
また、企業が自社の収益の増加を重視するもう一つの理由は、株主からの利益拡大への期待です。企業は株主の期待に答えるよう努力しないといけないからです。
次に「政府」の思惑も見ていきましょう。
「政府」もまた経済成長を強く望んでいます。
経済が成長すれば、企業の利益が増え、個人の所得も向上するため、税収が増加します。政府はこの増えた税収を、社会保障、教育、インフラ整備など、様々な公共サービスを充実させるために使うことができます。
また、経済成長は雇用を創出し、失業率の低下につながるため、社会の安定にも貢献します。
税収の増加や公共サービスの充実のために、政府は、経済成長を促進するために、様々な政策を打ち出しています。
例えば、企業の設備投資を促すための税制優遇措置や、公共事業への投資などがあります。
過去には、日本の高度経済成長期における所得倍増計画 のように、政府が明確な成長目標を掲げ、それを実現するための政策を積極的に推進した例もあります。
このように、企業と政府はそれぞれの思惑を持ちながら、経済成長を前提とした活動を行っているのです。

歴史から見る商売の目的の変化
このように、現在では企業と政府は経済成長を前提として活動していますが、実はその考え方は新しく、近代以前の商人たちは経済成長を望んで商売をしていませんでした。
例えば、中世の商人は、自分の利益を得ることだけが目的でした。
当時のアラビアのマフムード、イタリアのメヂィチやユダヤのソロモンなどの商人たちは、物資や情報の流通が不安定だったのでかなりのリスクを冒して商売を行っていました。
世界中でどこでも生産力は低く、生産手段や技術は限られ、経済活動が与える影響はごく小さな範囲だけでした。もしも、生産したものを、他の場所で売りたかったとしても、輸送手段がなく、現地の情報も少なく大きなリスクがありました。
そのため中世以前の商人は、取扱商品が高級品だけではなく、生活必需品のようなものでも高値で取引ができたので、「リスクを取って大きな利益を得る」ことができました。
そして、その商売の目的も自社の利益を得ることに集中していたのです。
しかも中世までは「経済成長」は、むしろ望ましくないものと考えられていました。
王様や貴族などの一部の人だけが権力を持っているような社会では、経済成長によって全体の生産量が増えると、モノが余ってしまって物価が下落すると考えられていました。また、成長によって領主の支配が揺らぎ、社会の秩序が乱れると怖れられたのです。
そのため、中世以前の社会では、経済活動は「現状維持が前提」と考えられていたのです。

変わる経済の目的
「成長を前提としない社会」から「前提とする社会」に大きく変わったのは、産業革命以後大量生産が可能になってからです。
産業革命によって生産性が大幅に向上し、大量生産が可能になります。多くの商品の価格が下落し、一般の人々が商品を買うことができるようになり経済活動が活発化しました。
現代では、生産性が高くなり、輸送コストも下がり、どこでも似たようなものが簡単に手に入るようになりました。すると商売の目的も変化していきます。
今までのように、単に利益を拡大することだけでは他の製品と差別化できません。そのため商売の目的を「社会の発展に貢献すること」や「顧客の満足を高めること」など、消費者に選ばれるイメージの良い企業になることも、商売の大きな目的になっていったのです。
また、資本主義という形の経済活動が生まれたことも大きな要因です。
産業革命以前は、事業を起こすのは、まとまった資金のある、生まれながらの富裕層だけでしたが、一般の市民でも資金を借りて、自らの工場を持ち、自由な経済活動を通して利益を追求することができるようになりました。
それは、商売のライバルを増やすことになりましたが、競争を通じて常に効率的な生産やサービスの提供が求められ、多様な商売の形が生まれ、社会全体が成長していくことができるようになりました。
産業革命によって社会構造も変化します。
農業社会から工業社会へと移行し都市化が進みました。都市部では、人々が集まり多様な価値観や生活様式が生まれます。これにより、経済成長が社会の進歩や繁栄につながるという考え方も広まっていきます。
このように、産業革命によって、生産手段や生産技術が進歩し、資本主義経済が普及したことが、私たちの生活を大きく豊かに変えることになったのです。
このような経済活動の変化から、社会は「経済の成長」を重要な目標と置くことになります。
市民の間に経済成長が社会の進歩や繁栄につながることが分かり、次第に人々は「経済成長するべきである」という考えに変化していきました。

成長を前提とする社会
私たちの身の回りには、成長が前提となっている計画がたくさんあります。
例えば、企業はどうでしょうか?
企業は事業を始めるときは、資金提供者にその事業が将来きっと成長するだろうと信じてもらわなければいけません。そのためには、自社の事業の必要性はもちろん、社会の取り巻く環境、国全体の経済成長がその利益を後押ししている、というのも事業が成功する可能性が高いことを補強してくれます。
また、政府はどうでしょうか?
政府は、経済成長を刺激するための財政政策をしています。
財政政策には、増税や減税、公共投資などがあります。増税や減税や公共投資を行うためには、議員、また国民に利益があることを分かってもらう必要があります。そのため政府は将来的に経済成長によって税収が増加したり、公共投資の効果によって経済成長が促進されると信じて政策を立案するようになります。
そして私たちの家計はどうでしょうか?
私たちは住宅ローンを組む時に、将来を見据えてローンを組んでいます。
例えば同じ会社で勤続し、出世などで収入が増えるので、そのころの返済額を増やしていこう、などと予定することもあります。
このように企業や政府、私たちも「経済が成長する前提」で計画をすると、次のような動きが加速されることになります。
- 企業は、将来の需要増加を見込んで、新製品の開発や生産設備の増強を行う
- 政府は、将来の人口増加や高齢化に対応するために、社会保障制度の拡充やインフラの整備を行う
- 国民は、将来の結婚や子育てを見込んで、住宅の購入や教育費の準備を行う
これらの経済活動はすべて将来の経済成長によって利益や収入、生活水準の向上などのメリットを得ることを前提として行われています。
もちろん、経済成長が予定通りに進めば、企業だけではなく私たちの大きなメリットがあります。けれど、景気循環によって停滞や後退が起こることもあります。
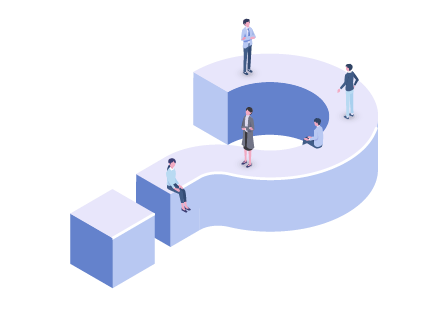
常に経済は成長しない
過去の経済の歴史を振り返ると、経済成長が常に続くとは限らないことがわかります。
日本においても、1990年代初頭のバブル崩壊は、それまで右肩上がりだった経済が長期にわたる停滞期、いわゆる「失われた〇〇年」に突入するきっかけとなりました。
バブル期には、株価や地価が異常なほど高騰しましたが、その崩壊によって多くの企業が多額の不良債権を抱え、経営破綻に追い込まれました。個人レベルでも、住宅ローンの返済に苦しむ人々が増え、経済全体が冷え込みました。
世界に目を向けても、1973年のオイルショックや2008年のリーマンショックなど、経済成長の前提が大きく揺らぐ出来事が度々起こっています。オイルショックでは、原油価格の高騰が世界経済に大きな打撃を与え、日本も例外ではありませんでした。リーマンショックは、アメリカの金融危機が世界中に波及し、輸出依存度の高い日本の経済も大きな影響を受けました。
これらの過去の事例は、経済成長が当たり前ではないこと、そして一旦成長が止まったり、後退したりすると、企業や政府の計画だけでなく、私たちの生活にも大きな影響を与えることを示唆しています。
| 期間 | 主な原因 | 個人・企業への主な影響 |
| 1990年代初頭(失われた〇〇年) | 資産価格バブル(不動産・株式市場)の崩壊 | 倒産、失業、賃金停滞、デフレ、投資の減少 |
| 1973年 オイルショック | OPECによる石油禁輸措置による原油価格の高騰 | 企業コストの増加、インフレ、景気減速 |
| 2008年 リーマンショック | 米国住宅市場の崩壊が引き金となった世界的な経済不況 | 世界的な需要の減少、特に日本の輸出産業への影響、雇用不安 |
個人への影響:成長が止まったらどうなる?
私たちの身の回りには「経済が成長するという前提」で計画されているものが多くあります。
もし、経済成長が鈍化したり、停滞したりした場合、私たちの個人生活にはどのような影響があるのでしょうか。
まず懸念されるのは、雇用情勢の悪化です。
企業は利益が上がらなくなると、新規採用を抑制したり、人員削減を行ったりする可能性があります。これにより、失業者が増え、就職難となることが考えられます。
また、賃金の上昇も期待できなくなるかもしれません。
経済が成長しなければ、企業の収益も増えにくいため、従業員の給料を上げる余裕がなくなる可能性があります。物価が上昇する一方で賃金が上がらなければ、実質的な所得は減少し、生活は苦しくなります。
さらに、将来の年金制度や社会保障制度も不安定になる可能性があります。
これらの制度は、現役世代の保険料や税金によって支えられていますが、経済成長が鈍化し、現役世代の所得が伸び悩むと、制度の維持が難しくなる可能性があります。
住宅ローンや教育費など、個人の経済的な負担が増える可能性も否定できません。
収入が伸びない中で、物価が上昇すれば、家計はますます圧迫されます。
このように、経済成長の停滞は、私たちの生活の様々な側面に影響を及ぼす可能性があるのです。

自分の身を守るために:個人ができること
経済成長が前提の社会で、私たち個人はどのようにリスクを回避し、自分の身を守るべきでしょうか?
最も重要なことの一つは、緊急時のための資金を確保しておくことです。
失業や病気など、予期せぬ事態に備えて、数ヶ月分の生活費を貯蓄しておくことが望ましいでしょう。
また、収入源を多様化することも有効な手段です。
本業以外にも、副業や投資などによって収入を得る道を探ることで、経済的な安定性を高めることができます。
自身のスキルアップも重要です。
常に新しい知識や技術を習得し、市場価値の高い人材であり続けることで、雇用不安のリスクを減らすことができます。
経済に関する情報を積極的に収集し、自分で考える習慣を持つことも大切です。
政府や企業の発表を鵜呑みにするのではなく、様々な情報を比較検討し、自分なりの判断を持つことが、不確実な時代を生き抜くためには不可欠です。
さらに、日本の制度を活用することも考えられます。
例えば、NISA(少額投資非課税制度)やiDeCo(個人型確定拠出年金)といった税制優遇のある制度を利用して、長期的な資産形成を行うことも有効な手段の一つです。
無駄な借金を避け、賢く支出を管理することも重要です。
経済が不安定な時期には、不必要な支出を控え、堅実な家計運営を心がけるべきでしょう。日本には、質素倹約の精神や、無駄を省くといった伝統的なよい考え方があります。このような考え方を日々の生活に取り入れることも、自分の身を守るためには有効かもしれません。

まとめ:不確実な未来に備える賢い生き方
経済成長は、社会全体の発展にとって重要な要素であることは間違いありません。
多くの企業や政府が経済成長を前提に計画を立てているのも、自然なことです。
しかし、未来は常に不確実であり、経済成長もまた例外ではありません。
過去の経済危機や停滞期から学ぶべきことは、経済成長への期待を持ちつつも、常に変化に対応できる柔軟な姿勢を持つことの重要性です。
大切なことは、私たちの暮らしは将来が分からなのに、良い方向に向かう場合のことを考えて設計されている、ということを頭に入れておきましょう。
私たち個人は、経済成長という「当たり前」の落とし穴に気づき、自分の身を守るための備えを始める必要があります。
良いことばかり書かれていたあの報告書は正しかったのでしょうか?
自分の身の丈に合わない借金をしようとしていないでしょうか?
政府の立案は楽観的すぎないでしょうか?
経済成長が本当に良いことなのか、そうでないのかは議論がありますが、経済成長は私たちに多くのメリットがありました。けれど所々に楽観的な成長計画が紛れ込んでいるので騙されないようにしましょう。
私たちは、緊急時のための貯蓄、収入源の多様化、スキルアップ、情報収集、そして賢い支出管理。これらの行動が、経済が停滞したとしても、私たちの生活を保ってくれるはずです。
不確実な未来に備える賢い生き方を、今から始めていきましょう。
経済成長という「当たり前」が揺らぐ今、私たちは変化にしなやかに対応し、持続可能な豊かさを追求する知恵が求められています。
この記事が、あなたと一緒に、未来への新しい羅針盤を探す一助となれば幸いです。