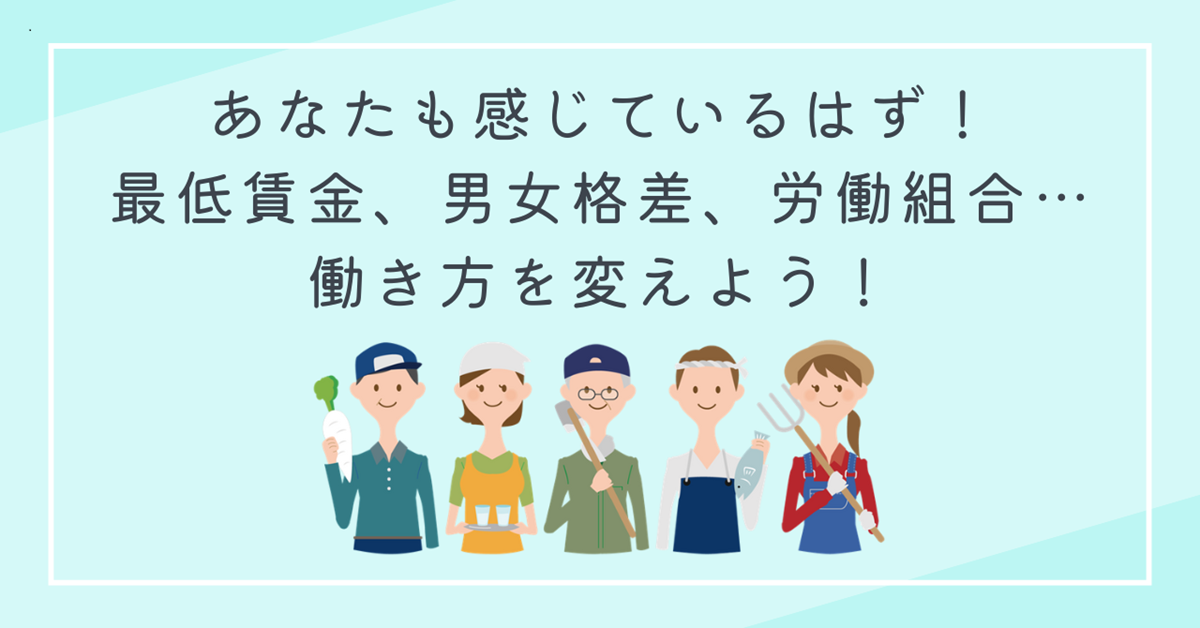「労働」は、私たち一人一人にとって多くの時間を割く活動の一つです。
そのため、労働を取り巻く環境は、私たちの生活に大きな影響を与えます。
「労働」の対価として受け取るのは「賃金」ですが、
「賃金」は、同じ時間労働に費やしたとしても平等に配当されません。
そのため、その配分に疑問が残りやすく、差別が格差に直結します。
人は「差別されている」と感じると後ろ向きになりやすく、仕事に打ち込むことができにくくなります。
雇用契約を結んでいる労働は、特にさまざまな差別の生まれやすい場所なので、どこの国もさまざまな対策がされています。
けれど、格差や差別などの多くの問題は今だ解決されているとは言えません。
ここでは、そんな「労働」にまつわる「最低賃金」「男女の格差」と「労働組合」の、3つの問題について見ていきます。
これらの知識は、より良い働き方をするためになくてはならないものです。
あなたも働き方に疑問をもっていたら、ぜひ一緒に考えてみませんか?

1 労働者にとっての最低賃金の問題
まず、アルバイトやパートなどの賃金でおなじみの「最低賃金」について見ていきましょう。
最低賃金とは、労働者の生活水準を確保し、不当な低賃金から労働者を保護するという点で非常に重要な制度です。「最低賃金」が設定されていることについては、一見何の問題もなさそうに思います。
けれど、最低賃金には労働者にとって多くの問題があるのです。
最低賃金の問題
国が最低賃金を設定して、違反した企業には罰則を課さないと、労働者に生活に苦しくなる低い賃金しか支払わない経営者が現れる可能性があります。
そんなことを避けるためにも、最低賃金は、労働者になくてはならない制度のように感じます。
一体どんな問題があるのでしょうか?
- 生活水準の確保が難しい
インフレなどによってモノの値段が上がってしまった場合、最低賃金の水準が変更されずに低いままに留まってしまうことがあります。
もしも、最低賃金が生活費を賄いきれない水準に設定されていると、労働者は、食事や住む場所、医療費などの費用をまかなうことが困難になり、生活水準が下がり貧困に陥るリスクが高まってしまいます。 - 労働意欲の低下させる
労働者自身の能力や経験に関わらず最低賃金でしか働けないという状況は、労働者のモチベーションを低下させ、生産性の低下につながります。 - 非正規雇用への固定化してしまう
最低賃金が低い水準に設定されている場合、企業はコスト削減のため非正規雇用を増やす傾向があります。非正規雇用は、社会保障や福利厚生が充実していないことが多く、労働者自身が将来不安定な生活につながります。 - 地域格差の拡大
最低賃金は地域によって異なり、都市と地方で大きな差があります。このような地域格差は、労働者の移動を阻み、都市と地方の経済格差をさらに拡大してしまいます。 - スキルアップの機会が少ない
低賃金で長時間労働を強いられる労働者は、スキルアップのための時間や費用を捻出することが難しく、キャリアアップが阻まれてしまいます。
このように最低賃金の水準が物価の水準と同じように推移していかない場合、労働者にとって最低賃金は大きな問題になります。
さらに、最低賃金の問題は労働者側だけにあるわけではありません。
実は企業側から見ても、最低賃金には多くの問題があります。
企業からみた最低賃金
企業にとって最低賃金とは、労働者を雇用するときに、必ず守らなければいけないルールの一つです。社会全体のためにも企業は、労働者の賃金を引き上げ、生活水準を向上させなければいけません。
しかし、そもそも賃金とは「労働力の量」と「求人数」が一致した点で決まる点です。
一致した点で「賃金」が決まれば、人材を効率的に配分できます。
しかし、「賃金」を政府の決めた政策によって強制されると、賃金と労働力の歪みをが生じて、企業はそのコストを補うため商品の値上げを行ったり、新規採用を減らしたりしてコスト削減に努めるようになります。
つまり、最低賃金を引き上げた場合、その結果は労働者の削減や、商品の値上げにつながり、必ずしも労働者や社会全体の利益にはならないのです。
最低賃金は、労働者の「生活の保障」と「経済全体の活性化」という二つの側面を持つ複雑な問題です。
最低賃金の引き上げは、労働者の生活水準向上に貢献する一方で、中小企業への負担増や雇用への影響といったいまだ解決できていない問題があるのです。

2 埋まらない男女格差
日本の労働市場は、男女格差が大きいと言われています。
男女格差とは、女性と男性が対等に就業・賃金を得ることができない状態のことを言います。
労働市場における男女格差は、性別による賃金、雇用機会、昇進の差異や職場環境における不平等を指します。
この問題は世界中で見られ、経済的な不平等や社会的な格差を助長する要因となっています。
日本の女性の働き方
日本の労働市場では、女性の就業率は男性より低く、また、女性の賃金は男性より低い傾向にあります。
その理由として、女性は男性より非正規雇用の割合が高く、また、女性は男性より管理職に就く割合が低いことが原因として考えられています。
さらに、女性は職場で、男性に比べて「女性らしさ」などの偏見や差別を受けやすく、昇進や昇給の機会が少なく、賃金が低い仕事をさせられていることも、男女格差の大きな原因となっています。
男女格差は、社会全体の経済成長や活力を阻害するだけでなく、女性の健康や幸福にも影響を与えます。そのため、男女格差を解消することは、日本社会にとって重要な課題です。
そこで、世界でも男女格差の低いと言われる、北欧の女性たちがどのように働いているのか見てみましょう。

北欧の女性の働き方:ジェンダー平等がもたらす働き方の多様性
北欧諸国は、世界的に見ても男女平等が進んでいることで知られています。その背景には、女性が働きやすい社会システムが構築されていることが大きく影響しています。
具体的にどんな社会システムになっているのか見ていきましょう。
- 共働きが一般的
北欧では、結婚や出産後も女性が働き続けることが一般的です。
これは、充実した社会福祉制度や、男女共同で家事や育児を行うという意識が根強いことが背景にあります。 - 柔軟な働き方ができる
フルタイムだけでなく、パートタイムやフレックスタイムなど、企業も柔軟な働き方を認める傾向があり、従業員が働きやすい環境づくりに力を入れています。これにより、子育てや介護と仕事を両立させることが容易になります。 - 育児休暇制度の充実
男女ともに長期間の育児休暇を取得できる制度や子供手当、育児休業給付金など、子育てを経済的に支援する制度が整っていて、仕事と育児を両立しやすい環境が整備されています。 - 高品質な保育施設
保育施設が充実しており、安心して子どもを預けることができます。 - 男女平等意識の浸透
社会全体で男女平等に対する意識が高く、男性も家事や育児に積極的に参加することが期待されており、女性だけの負担になりにくい社会と、女性が活躍できる環境が整っています。
このような、柔軟な働き方と、給付金、そして周囲への理解によって、女性が働きづづけることができる社会になっているのです。
男女平等の意識 日常のヒント
北欧の人たちができているのに、思いやりの深い日本の人々にできないことがあるでしょうか?
男女平等の意識を生み出すためには、日常の小さなことから始められます。
具体的な例を挙げながら、ご説明します。
- 自分自身の行動を見直してみましょう
日常生活の中で、無意識に性別役割分担に基づいた行動をしていないか振り返ってみましょう。
例えば、家事や育児を女性が担うべきという固定観念にとらわれていませんか? - 言葉遣いや表現に注意する
性別差別的な言葉遣いや表現を使わないように心がけましょう。
例えば、「何々ちゃん」「何々君」といった言葉は、固定的な性別役割を強化する可能性があります。 - メディアリテラシーを高める
テレビ番組、映画、広告など、メディアが描く男女像に注意深く目を向け、現状やその課題について考え、固定観念に疑問を持つようにしましょう。 - 多様な意見に耳を傾ける
性別、年齢、国籍、性的指向など、様々な背景を持つ人々の意見に耳を傾け、自分とは異なる価値観に触れる機会を増やしましょう。
男女平等を実現している人々をロールモデルとして、自分自身もそうありたいと意識することもいいですね。
ただし「男女平等」という概念は、人によって解釈が異なる場合があります。「平等」という言葉に過度にこだわりすぎず、多様な価値観を尊重している人を探してみるのも良いでしょう。
男女平等の意識を生み出すことは、一朝一夕にできることではありません。しかし、日々の生活の中で意識的に行動することで、少しずつ変化をもたらすことができます。自分自身の意識を変え、周りの人々と協力し合いながら、より良い社会を築いていきましょう。

3 労働組合の機能不全
労働者の労働問題の最後は「労働組合の機能不全」です。
日本の労働組合は、戦後、労働者の権利を守るため重要な役割を果たしてきました。
けれど近年は、組織率の低下や、非正規労働者の増加など、多くの課題に直面しています。
労働組合費払っているけれど、全くメリットが感じられない方や、組合に入っていない人など、集団になって交渉力をつけるメリットを受けられていない人は大勢いらっしゃるかと思います。
労働組合は意味ない?
労働組合は、労働者の権利を守り、より良い労働条件を実現するために組織する団体です。
労働者は、個々では企業に対して交渉力が弱いので、労働組合として団結し、多くの労働者が力を合わせ、企業との交渉力を高め、より良い労働条件を実現するために労働組合を使います。
労働組合への加入は、労働者の権利です。加入を強制されることはありませんが、労働条件の改善や権利の保護のために、積極的に加入を検討することをおすすめします。
日本労働組合総連合会(連合)ホームページ
けれど、近年では労働組合の組織率は減少傾向にあります。
日本の労働組合の組織率は、1950年代には約50%に達していましたが、現在では約18%にまで低下しています。
労働組合加入率の減少の理由として考えられるのは、終身雇用制の広がっていた日本では、労働組合の活動の成果を受けるメリットが多かったのですが、今では短期間での雇用される非正規労働者が多くなったため、労働組合の加入のメリットが減ったことが大きな原因の一つです。
しかし、労働市場のグローバル化や、IT技術の進歩などにより、フリーで働く人も増えている現在では労働組合の役割は高まっています。
国が主体の労働組合はないの?
もしも、国が主体になるような労働組合を組織してくれれば、個人が職場を変えても労働組合に参加したままいられます。
職場が変わっても加入できるような、国全体を主体とした労働組合はないのでしょうか
現在、全国規模の労働組合を組織する活動はなく、業種や地域別の活動を運営だけです。
その理由はまず膨大な人材と資金が必要となこと、また、国全体を主体とした労働組合の活動を行うためには、労働法の改正が必要となることが挙げられます。
一つには労働組合法という法の中には、労働組合は労働者自らの意思で自主的に組織され、運営されることを原則としています。
また国が労働争議に介入することも制限されています。
さらに、国が主体となる労働組合は、政府の意向が強く反映される可能性があり、多様性を損ない、中立性を欠いてしまう場合があるのです。
国際労働機関(ILO)の条約では、労働組合の自主性や団体交渉の自由が保障されています。
けれど、国が主体となる労働組合は、これらの国際的な基準に反する可能性もあるのです。
国が主体となる労働組合は、非正規雇用者の権利保護など、魅力的な側面もありますが、労働法の原則や多様な労働者のニーズとの整合性を図ることが非常に難しいという課題があります。
そのため今ある労働組合が、非正規雇用者を含む多様な労働者のニーズに対応できるよう、組織改革を進めることが重要です。
また、労働法を改正し、非正規雇用者の権利保護を強化するとともに、新しいタイプの労働組合の設立を促進する方法もあります。
国が主体となる労働組合は理想的な形ですが、現行の労働法の枠組みの中では実現が困難です。非正規雇用者の権利保護のためには、地域や産業別の組合の連携の強化などの改革や、新しいタイプの労働組合の育成など、より現実的なアプローチが必要となります。
働き方が多様化する中で、労働組合のあり方も変化していくことが予想されます。非正規雇用者の増加に対応するためには、労働組合がより柔軟な組織へと変革していくことが求められています。
より力強く働くためには、最低賃
金の問題や男女の格差があること、そして団結して意見していく環境を整えるための労働組合の力を認識することが、とても大切です。
自分の置かれている立場がおかしいと感じたら、友人や会社以外の人に話してみてください。
もしかしたら、そこには大きな問題が隠されているかもしれません。
総合労働相談コーナーのご案内|厚生労働省
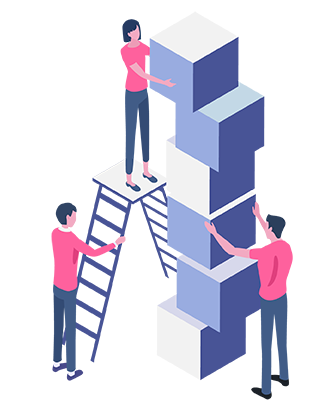
まとめ
労働市場の抱える3つの問題について解説しました。
「最低賃金」は貧困をなくすためには必要かもしれませんが、その余計にかかったコストが商品に上乗せされ、インフレを起こす可能性があります。
「男女格差」は日本では特に大きな問題です。女性は男性より賃金の低い仕事が優先的に与えられ、昇進の機会を損なわれています。社会全体の考え方も十分でなく解決には至っていません。
男女の格差をなくしていくためには、平等よりも多様な考えがあることを楽しめる雰囲気作りが必要です。
「労働組合」は労働者を守るために必要な組織のはずですが、日本では組合費ばかり高額で、それに合った働きがないので加入率は低いです。職種別地域別にしか組織されていな現状をもっと大きな枠組みに変えて、加入者がメリットを感じられるような組織に変わっていき本来の目的を果たさなければいけません。
会社全体が同じような価値観を持っている場合、おかしいな‥と思っても、自分がおかしいのかもしれないと感じてしまう方も多いかと思います。
けれど、そのおかしいと感じたことは、社会的には大きな問題があることかもしれません。
納得できなかったら、ぜひ友人や信頼できる場所に行って相談をしてみてください。
きっと道が開けるはずです。
参考文献
ティモシー・テイラー 経済学入門
令和4年労働組合基礎調査の概況|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
総合労働相談コーナーのご案内|厚生労働省