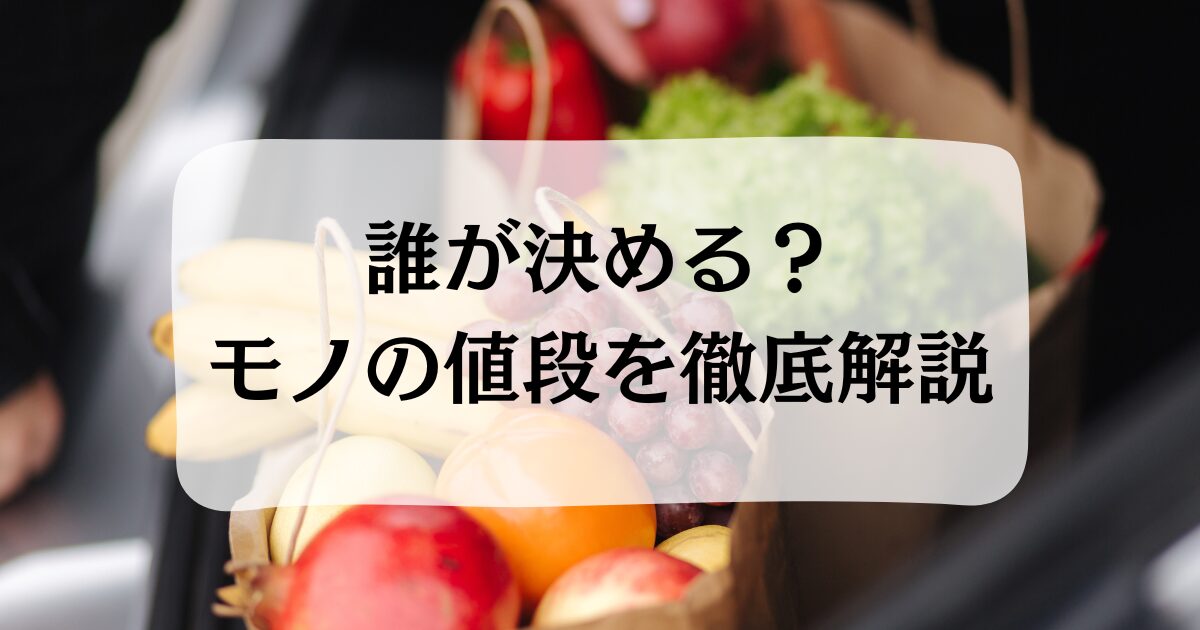あなたは普段買い物するとき、どんなことに注目してモノを買いますか?
必要があるから買った、
自分の気に入ったデザインだったから、
信頼しているブランドだったから、
また、価格に魅力を感じたから・・・
など様々な理由があると思いますが、その中でも「値段」というのは、きっと大きな理由の一つではないでしょうか?
もし、値段が、20%割引していたら、そんなに必要な商品じゃなくてもあなたは買うかもしれません。また、半額になっていたら、あなたは2つ買うかもしれません。
モノの値段は、買い物の非常に重要な要素です。
値段の高い、安いでモノの売り上げが大きく変化します。
そんな値段の決まり方を、知りたくないですか?
値段の決まり方を知っていると、モノの価値と価格の関係性を理解することができて、高すぎる商品や安すぎる商品を見極め、適正な価格で商品を購入することができます。
ここではモノの値段の決まり方を、徹底的に解説します。
ぜひ、日常の買い物に役立てて下さい。
モノの値段のしくみ
あなたはモノの値段がどのように決まっているのか、考えたことがありますか?
それは原材料費や人件費、開発費に利益をプラスした金額を、売り上げた数で割って決めているのでは?
そうです、開発にかかったコストは価格に反映しなければいけません。
けれど、商品の価格設定は、開発費や材料費といったコストの他にも、様々な要素を考慮して決定されます。単純に開発費や材料費を売り上げ数で割るという方法だけでは、必ずしも適切な価格を設定できるとは限らないからです。
一般的な価格設定の考え方
価格は原価だけではなく、需要、競業他社との比較から検討されます。
- 原価に注目する方法
- 原価(開発費、材料費、製造費など)に利益率を加えて価格を決める方法です。
- 最低限の利益を確保できるというメリットがありますが、市場の状況や競合製品との比較を十分に行わないと、売れない価格になってしまう可能性があります。
- 需要に注目する方法
- 顧客がどの程度の価格なら購入したいか、つまり需要を調査し、その範囲内で価格を設定する方法です。
- 安くすれば顧客の満足度を高めることができますが、原価を十分に回収できない可能性もあります。
- 競合他社に注目する方法
- 競合製品の価格を参考に、自社の製品の価格を設定する方法です。
- 市場での競争力を維持するために有効な方法ですが、自社の製品の独自性や付加価値を十分に反映できない可能性があります。
価格設定に影響を与えるその他の要素
また、販売者側の事情だけではなく、世間からどう見られているのか、季節性などが考慮されます。
- ブランドイメージ
高級ブランド品は、高品質な素材や優れたデザインをアピールするため、高価格で販売することができます。 - 季節性
需要の変動に合わせて価格を調整することもあります。 - 販売チャネル
小売店、オンラインストアなど、販売チャネルによって価格設定が異なる場合があります。 - マーケティング戦略
新製品導入時の価格戦略(低価格戦略、高価格戦略など)や、プロモーション活動なども価格設定に影響を与えます。
なぜ単純な計算だけでは不十分なのか
さらに、季節や社会状況によって変動する需要も追加されます。
- 固定費
人件費、家賃など、生産量に関わらず発生する固定費も考慮する必要があります。 - 変動費
生産量に応じて変動する変動費だけでなく、販売数量や販売地域によっても変動する費用も考慮する必要があります。 - 市場の状況
景気動向、競合製品の動向、消費者の購買行動など、市場の状況は常に変化するため、それに合わせて価格設定を調整する必要があります。
このように商品の価格は、開発費や材料費といったコストだけでなく、ライバルの価格、ブランドイメージ、そしてどれだけ需要があるのか?という多くの要素を総合的に考慮して決定されます。
値段は需要と供給のバランスできまる
モノの値段に占める材料費は、商品の生産コストの大きな部分を占めるため、価格に大きな影響を与えます。材料費が高くなれば、一般的に商品の価格も上昇する傾向があります。
しかし、材料費が価格の全てを決めるわけではありません。
価格は、材料費などのコストだけでなく、需要と供給のバランスによって決定されます。
- 需要とは
ある商品を消費者が買いたいと思っている量のことです。
需要が高まれば、供給が追い付かなくなり、価格が上昇する傾向があります。 - 供給とは
ある商品を生産者が売りたいと思っている量のことです。
供給が増えれば、価格が下落する傾向があります。
例えば
- スマートフォン
新しい機能が搭載されたスマートフォンが発売されると、需要が高まり、価格が高騰することがあります。
しかし、競合他社が同じような機能を持つスマートフォンを大量に生産し始めると、供給が増えて価格が下がる可能性があります。 - 農産物
干ばつなどの自然災害で農作物が不足すると、供給が減り、価格が上昇します。
しかし、新しい品種の開発や栽培技術の向上により、生産量が増えれば、価格が下がる可能性があります。 - 政府の政策
税金や関税などの政府の政策は、商品の価格に直接的な影響を与えることがあります。
このようにものの価格には、材料費、需要、供給、ブランドイメージ、季節性、政府の政策など、様々な要素が複雑に絡み合って決まっています。
人件費や材料費は、商品の価格を決める重要な要素の一つですが、それよりも需要と供給のバランスのほうが、価格に大きな影響を与えています。
水とダイヤモンドのパラドックス
材料費などよりも、需要と供給のバランスの方が「価格」に大きな影響を与えている、ということがはっきりわかるのが、この交換価値と利用価値の話です。
経済学者の父と呼ばれるアダム・スミスの考えた、価値について考えた有名なたとえ話があります。それは「水とダイヤモンドのパラドックス」です。スミスはモノの価値には「交換価値」と「使用価値」の2つがあるということに気が付きました。
ダイヤモンドは欲しい人がたくさんいるのに、世の中に少ししか存在してないので高いです。
逆に、水は生きていくうえでなくてはならないものですが、たくさんあるので安いです。
このようにダイヤモンドは、使うという点においては何の価値もありませんが、欲しい人がたくさんいますが、その量が少ししかありません。つまりダイアモンドの「使用価値」は低く、「交換価値」は高くなります。
反対に水は飲むだけではなく、発電ができるなどの高い価値を持っています。水は「使用価値」が高いですが、たくさん存在するので「交換価値」は低くなります。

このように、交換価値と使用価値というのはいつも一致するわけではありません。
経済学の視点で考えるときは、モノの実用的な価値や必要性ということは一切考えません。
そのような価値判断はしないで、価格だけに注目します。
この考えはとてもドライに感じられますが、モノの価値が「正しい」のか「間違っている」のか、自分の価値感にあっているのか、そうでないのか一切考えないので、どんな文化を持つ人とでも、同じ認識が持てるというメリットがあります。
価格とは世の中の需要と供給のバランスで決まってくるものです。人々は何を欲しがっているのか? そしてそれはどれだけあるのか?
価格とはその関係を反映したものにすぎないのです。
まとめ
モノの値段がどのように決まるのか解説しました。
それをつくったときにかかった材料費、人件費、それに利益を乗せて価格としますが、それだけではモノは売れない可能性があります。
なぜなら、それを欲しい人がどれだけいるのか、どれだけそれが市場にあるのかが非常に重要です。価格はその需要と供給のバランスの上で決まります。
水を手に入れるのは地域によっても差はありますが、手に入りやすいため価格は抑えられています。
逆にダイヤモンドはどの地域でも手に入りにくいために、価格が非常に高くなります。
経済学では、そのものがもっている価値を参考にしません。
それはどのくらいあるのか、欲しい人はどのくらいいるのか、ということだけに注目します。
私たちは、高額な商品を特別に考えてありがたがったり、逆に安い商品を軽く見たりすることがあります。
けれどモノの値段は、ほしい人が多くて、その数が少ないときに高くなり、
そのものが欲しい人すべてに行き渡ると、価格が安くなる、
ということに過ぎないのです。
価格にはだまされずに冷静な判断がしたいですね。
参考文献
経済学入門 ティモシー・テイラー