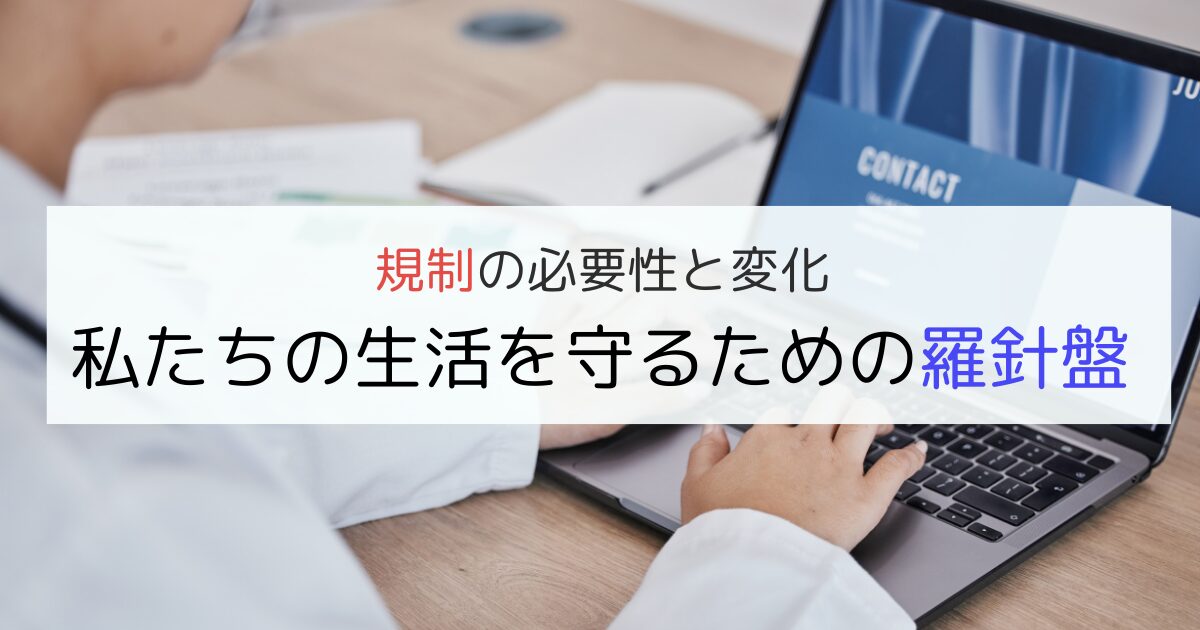あなたは「規制」についてどのようなイメージをお持ちになるでしょうか?
自分は何も悪いことをしていないので、全く関係がない・・
規制は企業にかけられるものだから、きっと自分の生活には何も影響がない・・
と考える方が多いかもしれません。
多くの「規制」は企業に関係しているので、自分には関係がないと思われる方も多いかもしれません。
けれど、「規制」がなければ私たちの生活は非常に混乱する可能性が高いです。
例えば、もしも道路に信号がなかったらどうなるでしょうか?
もしも、建築に関する「規制」や、廃棄物処理に関する「規制」がなかったらどうでしょうか?
「規制」の詳しい中身が分からなくても、どうもまずいことになりそうだ・・・・ということはイメージできるかと思います。
このように「規制」は、私たちの生活に大きな影響を与えています。
「規制」は、私たちを束縛するものではありません。
私たちの安全や生活を守るために必要不可欠な「規制」について、ちょっと考えてみませんか?
「規制」を味方につけて、安心安全な生活を手に入れましょう!

規制が強まるきっかけ
まず「規制」は、どのようにつくられるのか見ていきましょう。
少し前のことになりますが、2000年代の日本は、食品偽装問題が相次いで発覚し、社会問題化した時期でした。このような違法や改ざんが「規制」をさらに強化させることになります。
過去に起きた重大な食品偽装事件
次にあげる事件の数々は、規制を強化させるきっかけになった事件です。
これらの事件は、消費者の食品に対する信頼を大きく損ね、食品関連法の改正につながる契機となります。
- 2001年 牛肉偽装事件
BSE(牛海綿状脳症)対策として行われた国産牛肉買い取り事業を悪用し、複数の食肉卸売業者が輸入牛肉を国産牛肉と偽って国に買い取りを要請し、補助金を不正に受給していた事件です。
雪印食品やハンナンなどの大手企業も関与していたことから、社会に大きな衝撃を与えました。
雪印牛肉偽装事件 - Wikipedia
ハンナン事件 - Wikipedia - 2007年 不二家による消費期限切れ商品販売
不二家が、洋菓子の一部で消費期限切れの原材料を使用したり、消費期限を改ざんして販売していたことが発覚しました。長年親しまれてきた老舗お菓子企業の不祥事として、消費者の信頼を大きく失墜させました。
不二家 - Wikipedia - 2007年 石屋製菓「白い恋人」賞味期限改ざん
北海道土産として有名な「白い恋人」を製造販売する石屋製菓が、賞味期限の改ざんを行っていたことが発覚しました。人気商品の不正行為は、観光業界にも影響を与えました。
石屋製菓 - Wikipedia - 2007年 ミートホープ牛肉偽装事件
食肉加工会社ミートホープが、ひき肉に本来使用すべきでないくず肉や内臓などを混ぜていたことが発覚しました。また、産地偽装も行っていたことが明らかになり、食品業界の倫理観が問われる事態となりました。
ミートホープ - Wikipedia
このような食品にまつわる偽装が次々に発覚し、食品の「規制」の問題が世間の注目を浴びたのです。
これらの事件の背景
これらの事件に共通するのは、企業が利益を追求するあまりに、倫理観や法令遵守意識が低下していたことがあげられます。
長年培ってきたブランド力や消費者の信頼を悪用し、「多少ごまかしてもバレない」という安易な考えがあり、偽装を見逃す要因となりました。事件はある一企業で起きてしまったことですが、消費者は「他の企業も同じようなことをしているのではないか・・・?」「何を信じて買えばいいのか分からない・・」と、消費者の不信感が高まり、その不安は食品業界全体に及ぶことになります。
これを受けて、政府は「食品衛生法」や「JAS法」などの改正を行い、食品の表示に関するより厳しい基準が設けられたのです。
このようにある問題が見つかってから「規制」が強化されることがあります。
つまり「規制」は、単なる束縛ではなく、私たちの安全や生活を守るために必要不可欠なものなのです。

逆に、社会の変化や技術の進歩などによって、既存の規制が時代に合わなくなる場合があります。
そんなときは「規制」が緩められることもあります。
緩められる規制
私たちの生活を守るためにつくられた「規制」も、時代や社会の変化とともに、経済活動の妨げになったり、技術革新を阻害するようになってきます。
そこで、必要に応じてルールを少なくしたり、簡単にします。
これを「規制緩和」と呼んでいます。
昔は必要だった「規制」も、今ではかえって邪魔になっていることがあります。
例えば、通信規制がインターネットの普及の発展を阻害していました。
また、金融の規制が大きくて一般の人々が気軽に金融商品を買うことができずらかったことがありました。(両方とも今は規制が緩められています)
「規制」が厳しいと、技術革新によって新しいサービスが生まれたとしても、古い規制が残っているために、そのサービスが提供できない、ということが起こりえます。このようなことがないように「規制緩和」を行って、新しいサービスやビジネスが生まれやすい環境をつくり、経済を活性化させるのです。
そのため、「規制」は時代に合わせて見直して緩めることも大切です。
規制緩和のメリット
規制緩和には次のようなメリットがあります。
- 競争の促進
規制が緩和されると、新しい企業が市場に参入しやすくなり、既存の企業との間で競争が生まれます。競争が激しくなると、企業はより良い商品やサービスを、より安い価格で提供しようと努力するため、消費者にとってメリットとなります。 - イノベーションの促進
規制が少ない方が、企業は新しい技術やサービスに挑戦しやすくなります。
これにより、イノベーションが促進され、経済全体の発展につながります。
規制緩和のデメリット
しかし逆に、今まで必要だった「規制」を少なくすることは、当然デメリットもあります。
- 安全性の低下
規制が緩くなることで、安全性や品質が低下する可能性があります。
特に、食品や医薬品などの分野では、安全性を確保するための適切な規制が必要です。 - 弱者への影響
規制緩和によって、大企業が有利になり、中小企業や個人事業主などが不利になる可能性があります。また、高齢者や障害者など、特定のグループが不利益を被る可能性もあります。 - 環境への影響
規制が緩くなることで、環境汚染が進む可能性があります。環境保護のための適切な規制が必要です。 - 格差の拡大
規制緩和によって、一部の企業や個人が大きな利益を得る一方で、そうでない人々との格差が拡大する可能性があります。
規制緩和は、経済を活性化し、私たちの生活を豊かにする可能性を秘めていますが、同時にデメリットも存在します。そのため、規制緩和を行う際には、メリットとデメリットを十分に考慮し、バランスの取れた政策を行うことが重要です。
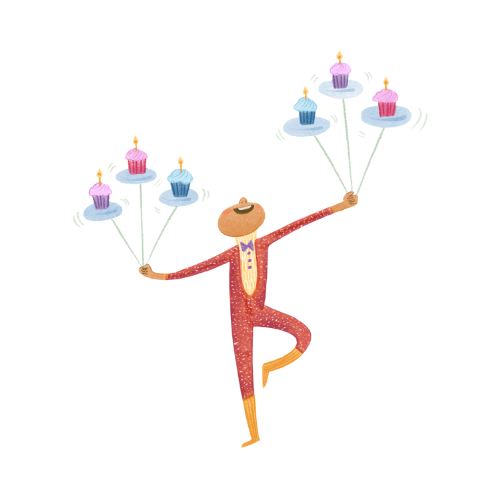
規制の見直しの大切さ
あなたの身の回りにも、いろいろなマイルールがあるかと思います。
靴下はここに置くとか、これをした次はこれをする・・・とかいろいろありますよね?
そのようなルールも、新しい電化製品を買ったり、生活パターンが変わったりしたときは、昔のルールにこだわっているとかえって面倒・・・なんてことはありませんか?
これと同じようにいったん決められた「規制」も、変えていくことが大切です。
その理由をもっと詳しく見ていきましょう。
1. 社会の変化への対応
社会の価値観や生活様式は時代とともに変化します。
かつては一般的だった考え方が、現代では受け入れられないということも少なくありません。
例えば、かつてはプライバシーの概念が現在ほど重要視されていなかったため、個人情報の取り扱いに関する規制が緩やかだったかもしれません。
しかし、情報化が進んだ現代においては、個人情報の保護は非常に重要な課題となっており、より厳格な規制が求められています。
このように、社会の変化に合わせて規制を見直すことが、社会のニーズに合った適切なルールを維持することができるのです。
2. 技術革新への対応
技術革新は社会に大きな変化をもたらします。
新しい技術が登場すると、既存の規制では対応しきれない問題が生じることがあります。
例えば、インターネットの普及により、従来の法律では想定されていなかった著作権侵害やサイバー犯罪などの問題が発生しました。このような技術革新に対応するためには、規制を柔軟に見直し、必要に応じて新しい規制を導入していくことが不可欠です。
3. 経済活動の活性化
時代に合わなくなった規制は、経済活動の足かせとなることがあります。
例えば、新規事業の参入を阻害するような規制や、煩雑な手続きを強いる規制は、企業の活動を抑制し、経済の活力を奪う可能性があります。規制を見直し、合理化することで、企業の自由な活動を促進し、経済の活性化につながることが期待できます。
4. 国際的な整合性
グローバル化が進む現代は、国際的なルールと自国のルールとがかけ離れていては、消費者の理解が得られません。
国際的なルールを参考にして「規制」を見直すことは、国際社会との協調を保ち、円滑な国際関係を築くことができます。円滑な国際関係は、お互いの信頼関係を結ぶためには欠かせません。
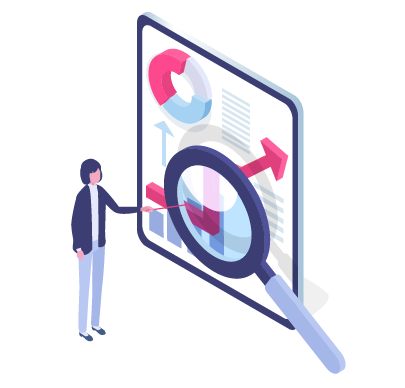
このように「規制」は社会のルールで、時代に合わせて適切に変えていく必要があります。
規制の見直しは、社会の発展と人々の生活の向上に欠かせないプロセスなのです。
まとめ
「規制」について解説しました。
「規制」は、私たちを束縛するものではなく、安全で豊かな生活を守るために必要なものです。
世間に大きく注目された事件をきっかけにして、多くの「規制」が強化されました。
しかし「規制」は、時代や技術の進化によって、かえって邪魔になることがあります。
そのような時は「規制」を少なくしたり、簡単にしたりすることが大切です。
変化する時代に合わせて、規制は常にアップデートしていく必要があります。
私たち一人ひとりが、「規制」の意義を理解し、その変化に関心を持つことで、より良い社会を築いていくことができるのです。
参考文献
経済学入門 ティモシー・テイラー
航空輸送産業の規制緩和 (tohoku.ac.jp)
中高の教科書で分かる経済学 菅原晃