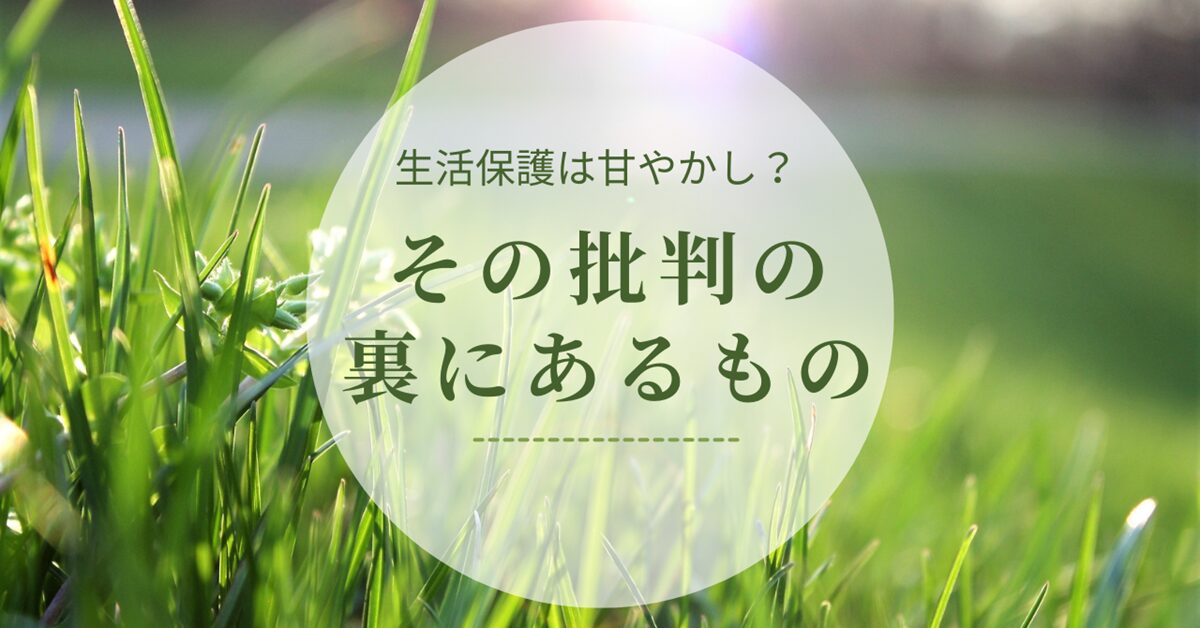あなたは最近、日本の貧困率が先進国の中でも高くなっている・・・
という話をきいたことがありますか?
SNSでも「生活保護」が、話題に上がることが多いですよね。
あなたは「生活保護」というお金を受け取れる、ということについてどのように感じますか?
「お互いが助け合うためにあるのだからよいこと」
と多くの人が考えていると思います。
でも一方で
「働く気がなくなってしまうんじゃないか?」
「働かなくてお金がもらえるなんて甘えだ!」
のように感じる方も多いのではないでしょうか?
生活保護は私たちの生活を支える最後のセイフティーネットです。
でも、それが働く気を削いでいるとしたら問題です。
生活保護は働く気持ちを削ぐのでしょうか?

生活保護は甘え?
もし、生活にギリギリのお金を、働かないでもらえることになったら、あなたはどうしますか?
やっぱり働き続けるでしょうか?
それとも「働くのをやめてだらだらしたい」と思うでしょうか?
もし、生活できるお金が働かないでももらえるのなら、多くの人が「働こうとする気持ち」を、なくしてしまうことは十分考えられます。
やっぱり「生活保護」は働く気を削ぐものになっているということでしょうか?
もう少し深掘りしていく必要がありそうです。
まず、生活保護について基本的なことをおさらいしておきましょう。
生活保護制度の基本
生活保護制度とは、日本で生活に困っている人たちに対して、国が最低限度の生活を保障するための制度です。
有名な「健康で文化的な最低限度の生活」つまり、ただ生きていくだけでなく、人間らしく、文化的な生活を送るために必要な水準を誰もが送れるように、日本は国民をサポートする国ということです。
でも、だれもが無制限に「生活保護」をもらえるわけではありません。
「生活保護」の対象となる人は、病気やケガで働けなくなったり、高齢になって収入がなくなったり、様々な理由で生活が苦しくなってしまったと認めれらた場合に、「生活保護」を受けることができます。

どんな人が対象になるの?
生活保護を受けることができる人をもう少し具体的に見ていきましょう。
それは、次のような条件が当てはまる人です。
- 収入が少ないこと
生活していくためのお金が足りない状態である必要があります。
具体的にどれくらいの収入だと対象になるかは、世帯の人数や住んでいる場所によって変わります。 - 資産がないこと
預貯金や不動産など、すぐに生活費にできるような資産が少ない必要があります。
ただし、生活に必要な家や家具などは考慮されます。 - 働くことが難しい状況であること
病気や障がい、高齢、子育てなどの理由で、十分に働くことができない状況である必要があります。
働けるのに働かない場合は、原則として生活保護を受けることはできません。 - 親族からの援助が期待できないこと
親や兄弟、子どもなど、親族から生活の援助を受けることが難しい状況である必要があります。 - 他の制度を活用しても生活が維持できないこと
年金や失業保険など、他の制度で生活を維持することが難しい場合に、生活保護が検討されます。
どんな種類の扶助があるの?
生活保護には、8種類の扶助があります。これらの費用が現金または現物で支給されます。
- 生活扶助:日々の生活費(食費、被服費、光熱費など)のためのお金です。
- 住宅扶助:家賃を補助するためのお金です。上限額が定められています。
- 教育扶助:小・中学生に必要な学用品費や給食費などを補助します。
- 医療扶助:病気やケガの治療に必要な医療費を補助します。原則として自己負担はありません。
- 介護扶助:介護が必要な場合に、介護サービスを利用するための費用を補助します。
- 出産扶助:出産にかかる費用を補助します。
- 生業扶助:働くために必要な技能を習得したり、事業を始めるための費用を補助します。
- 葬祭扶助:葬儀を行う費用を補助します。
生活保護は、このような生活に必要な費用を、必要な人に一定の範囲内で支援をしています。

受給者への批判
生活保護は何らかの理由があって働けない人への、最低限の生活をおくるための費用です。
けれど、生活保護の受給者の方々が、「楽をしている」「良くないことをしている」という目で見られたり、窓口で疑いの目で見られたりすることは、 残念ながら、そのような偏見や誤解が社会に存在するのは事実です。
なぜそのような見方をされてしまうのでしょうか?
それには、いくつかの理由が考えられます。
1. 生活保護制度への誤解や偏見
- 「働けるのに働かない」という誤解
生活保護を受けている人の中には、病気や障害、高齢、介護、子育てなど、様々な理由で働くことが難しい方も多くいます。
しかし、「働けるのに働かない」「怠けている」といった誤解が根強く存在します。
これは、生活保護制度が、本当に困窮している人を支えるための最後のセーフティネットであるということが、よく理解されていないことから起こっています。 - 「不正受給が多い」という誤解
一部の不正受給の事例が報道されることがありますが、不正受給は生活保護受給者全体のごく一部です。
あたかも多くの人が不正受給をしているかのような印象を与えられがちですが、実際には、自治体による厳格な審査や指導が行われており、不正受給は摘発される仕組みになっています。 不正受給の一部の事例が誇張され、生活保護受給者全体への不信感につながっている可能性があります。 - 「税金で生活している」という反感
生活保護費は税金から賄われているため、「自分たちの税金が楽をしている人に使われている」と感じる人がいるかもしれません。 特に経済状況が厳しい時ほど、そのような感情が強まりやすい傾向があります。
しかし、生活保護は憲法で保障された国民の権利であり、誰もが安心して生活できる社会を維持するために必要な制度であることを理解する必要があります。 - 生活保護基準への誤解
生活保護基準は、最低限度の生活を保障するためのものであり、決して贅沢な暮らしができるような金額ではありません。 生活保護基準や実際の受給額について正確な情報が十分に伝わっていないため、「楽をしている」という誤解が生じやすいと考えられます。
2. 勤労に対する価値観と自己責任論
- 「労働は美徳」という価値観
日本では古くから「労働は美徳」という価値観が強く、勤勉に働くことが良いこと、評価されることとされています。
そのため、働いていない人、特に生活保護を受けている人に対して、「怠惰だ」「社会に貢献していない」といった批判的な目で見ることがあります。 - 自己責任論の浸透
近年、自己責任論が強まる傾向にあり、「自分の生活は自分で責任を持つべき」という考え方が広がっています。 この考え方が行き過ぎると、生活困窮に陥った人を「自己責任」で片付け、社会全体の責任や相互扶助の精神が薄れてしまう可能性があります。
生活保護受給者を「自己責任を果たしていない」と捉え、冷たい視線を向ける背景には、このような社会的な風潮も影響していると考えられます。
3. メディア報道や政治的言説の影響
- ネガティブな報道の偏り
メディアは、生活保護に関するニュースを報道する際、不正受給や問題事例に焦点を当てがちです。
もちろん、不正受給は問題であり、報道されるべき側面もありますが、生活保護を受けて真面目に生活を立て直そうとしている人々の姿や、生活保護制度が実際に多くの人を支えているという側面もバランス良く報道されるべきです。 報道の偏りによって、生活保護制度や受給者に対するネガティブなイメージが固定化される可能性があります。 - 政治的な利用
一部の政治家やコメンテイターが、生活保護制度を批判したり、受給者を「叩き」の対象にしたりする発言をすることがあります。 このような言説は、人々の不安や不満を煽り、生活保護受給者への偏見を助長する可能性があります。
4. 貧困や格差に対する無理解
- 貧困の可視化の困難さ
貧困は目に見えにくく、表面化しにくい問題です。
生活困窮者の苦しみや困難さが社会全体に十分に理解されていないため、生活保護受給者が置かれている状況に対する想像力が欠如しがちです。 - 格差拡大への不安
近年、日本社会における格差が拡大しており、将来に対する不安を感じている人が増えています。 そのような状況下で、生活保護受給者を「特権階級」のように捉え、不公平感を抱く人がいるかもしれません。
しかし、実際には生活保護基準は非常に低く、受給者が豊かな生活を送っているわけではありません。
5. 人間の心理的な側面
- 妬みや嫉妬
人は、自分よりも恵まれているように見える人に対して、妬みや嫉妬の感情を抱くことがあります。 生活保護受給者を「働かずに生活できている」と誤解し、妬ましいと感じる人がいるかもしれません。 - 優越感の欲求
他人を貶めることで、自分の優位性を確認しようとする心理が働くことがあります。 生活保護受給者を「下に見る」ことで、自分の立場が優れていると感じたいという心理が、偏見の背景にある可能性も否定できません。
体を壊したり、高齢になったりして働けなくなった時に生活保護を受給するのは、最低限の暮らしを守るためにも国から認められた私たちの権利です。
生活保護が最後のセーフティネットとして、本当に困っている人が、偏見や差別を受けることなく安心して生活できるよう、私たち一人ひとりが意識を変え、行動していくことが求められています。

生活保護をもらっていると労働意欲は削がれる?
もう一つの疑問「生活保護をもらっていると働き気持ちが削がれる」という指摘は本当でしょうか?
実は、日本の生活保護をもらっている人たちは、高齢者世帯と傷病者・障害者世帯が大多数を占めています。令和4年度の被保護者調査結果概況によると、保護開始世帯の理由別構成割合は、高齢者世帯が49.8%、傷病・障害者世帯が29.3%となっており、この2つで約8割を占めています。令和4年度被保護者調査結果概況
これらの人々は、そもそも年齢や健康上の理由により働くことが困難な状況にある方が多く、生活保護は、そのような方々の生活を支えるための最後のセーフティネットとしての役割を担っています。
したがって、「生活保護が働く意欲を削ぐ」という指摘は、これらの大多数を占める高齢者や傷病者・障害者の方々には当てはまらない、もしくは非常に限定的なのです。
けれど、この指摘が完全に的外れであると断言することは、少し注意が必要です。
なぜなら、
- 若年層やその他の理由で受給している人も存在する
少数ではありますが、若年層や、その他の理由(例えば、就職難、家族構成の変化など)で生活保護を受けている人も存在します。これらの層の中には、制度の利用によって働く意欲に影響を受ける可能性が全くないとは言えません。 - 制度設計上の課題の可能性
生活保護制度の設計によっては、働くことによる収入増が、生活保護費の減額によって相殺されてしまい、結果として働くインセンティブを弱めてしまう構造的な問題が指摘されることもあります。
けれど
- 日本の生活保護制度は、働く能力のある人には就労支援を行います
病気や怪我、精神的な問題、またはその他の理由で働くことができない状態でなければ、まず就労支援が行われます。働けるかどうかは、生活保護を判断する非常に重要な材料になります。 - 生活保護費は最低限の生活を保障するものであり、決して裕福な生活を送れるものではない
生活保護基準は、あくまで最低限度の生活を維持するためのものであり、生活保護だけで十分、働く必要がないと考える人は少ないと考えられます。
つまり「生活保護が働く意欲を削ぐ」という指摘はは、日本の生活保護受給者の実態(高齢者や傷病者・障害者が多数)を踏まえると、その妥当性は非常に低いと言えます。
特に、高齢者や傷病者・障害者の方々にとっては、そもそも働くことが困難な状況であるため、この議論はほとんど当てはまらないと言えます。
ただし、制度の運用や、一部の受給者層においては、働く意欲への影響が完全にゼロとは言い切れない可能性も残ります。 重要なのは、制度全体として、本当に困窮している人々を支えるセーフティネットとしての役割をしっかりと果たしつつ、働ける人には自立を促すための適切な支援を行うことが大切です。

教育:文部科学省 (mext.go.jp)
生活保護を申請したい方へ|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
特別児童扶養手当・特別障害者手当等 |厚生労働省 (mhlw.go.jp)
仕事をお探しの方へ|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
働いたら減額 貧困の罠への対策
最後にもう一つ、生活保護を受給しているときに、働いていると受給金額が減らされたら、働く気がなくなってしまうという「貧困の罠」という問題があります。
貧困の罠とは、生活保護などの公的扶助を受けている人が、働いて収入を得ようとすると、扶助が減額・停止されるために、かえって生活水準が低下してしまう、あるいは向上しない状態を指します。これにより、人々は生活保護から抜け出すことができず、結果として貧困から脱却できなくなるという問題が起きることを指します。
日本の生活保護制度が貧困の罠に陥らないように、いくつかの対策が講じられています。
1. 収入認定の仕組みと累進的な減額
生活保護制度では、受給者が得た収入は、一定のルールに基づいて生活保護費から差し引かれます。
しかし、収入がそのまま全額差し引かれるわけではありません。
- 基礎控除
まず、収入の中から必要経費(社会保険料、通勤費など)が控除されます。 - 勤労控除
さらに、就労意欲を損なわないように、一定額の勤労所得控除が設けられています。
これは、働いて収入を得ることに対するインセンティブを高めるための仕組みです。
例えば、2023年度の制度改正では、勤労控除が一律15,000円から最大20,000円に拡充されました。
これらの控除があるため、収入が増加しても、生活保護費の減額は収入増加分よりも緩やかになります。
つまり、収入が増えるほど、手元に残るお金は確実に増えるように設計されており、収入が増えることが生活水準の低下に繋がるという貧困の罠には陥りにくい仕組みになっています。
2. 最低生活費の算定基準
生活保護費は、厚生労働大臣が定める基準に基づいて、世帯の構成や年齢、居住地域などに応じて算定される最低生活費から、世帯の収入を差し引いた額が支給されます。
最低生活費は、食費、住居費、光熱費、被服費、医療費、教育費など、生活に必要な費用を細かく積み上げて計算されます。この基準は、定期的に見直され、社会経済状況の変化や物価上昇などを反映して改定されます。
最低生活費は、健康で文化的な最低限度の生活を維持するために必要な水準として設定されており、単純に低く抑えられているわけではありません。むしろ、捕捉率(生活保護を受けられるはずの人が実際に受けている割合)が低いことや、申請のハードルが高いことなどが課題として指摘されています。
3. 自立支援プログラム
生活保護制度では、単に生活費を支給するだけでなく、受給者の自立を支援するための様々な取り組みが行われています。
- ケースワーカーによる相談支援
すべての受給世帯にケースワーカーが配置され、就労支援、家計相談、健康管理など、様々な相談に乗ります。 - 就労支援プログラム
ハローワークと連携した就労支援、職業訓練の斡旋、履歴書・職務経歴書の作成支援、面接対策など、就職活動をサポートするプログラムが提供されています。 - 一時的な就労収入の活用
就職が決まった場合、一時的な就労収入を生活立ち上げ費用に充てることができる場合があります。
これらの自立支援プログラムは、受給者が生活保護から脱却し、自立した生活を送るための後押しとなることを目指しています。
4. 課題と今後の取り組み
日本の生活保護制度は、貧困の罠に陥らないように様々な工夫が凝らされていますが、完全に「貧困の罠」を解消できているわけではありません。
- 低い就労意欲と負い目
長期間生活保護を受けている人の中には、就労意欲が低下している人や、生活保護受給に対する社会的な負い目を感じている人もいます。これが就労への抵抗感を高め、貧困からの脱却を難しています。 - 制度の複雑さと申請のハードル
生活保護制度は複雑で、申請手続きも煩雑であるため、本当に必要な人が制度を利用できていない可能性があります。また、水際作戦と呼ばれる、窓口での申請抑制が行われているという批判もあります。 - 地域間格差
最低生活費の算定基準は全国一律ですが、物価や生活コストは地域によって異なります。都市部では最低生活費だけでは生活が厳しい場合もあります。
今後の取り組みとして、
- より効果的な就労支援プログラムの開発
個々の状況に合わせた、きめ細やかな就労支援プログラムを開発し、就労意欲を高める取り組みが必要です。 - 制度の簡素化と申請手続きの改善
制度をより分かりやすく、申請しやすいものにすることで、必要な人がスムーズに利用できるようにする必要があります。 - 誤解や偏見の軽減と社会全体の理解促進
生活保護に対する誤解や偏見を解消し、社会全体で生活困窮者を支える意識を高めることが重要です。
日本の生活保護制度は、貧困の罠に陥らないように一定の配慮がなされた設計になっています。収入認定の仕組みや勤労控除、自立支援プログラムなどは、受給者の就労意欲を損なわずに、生活保護からの脱却を促すための工夫と言えるでしょう。
しかし、制度の運用面や社会的な課題も存在し、貧困の罠を完全に解消できているとは言えません。今後、より効果的な制度運営と社会全体の意識改革を通じて、真に貧困から人々を救い出す制度へと進化していくことが期待されています。
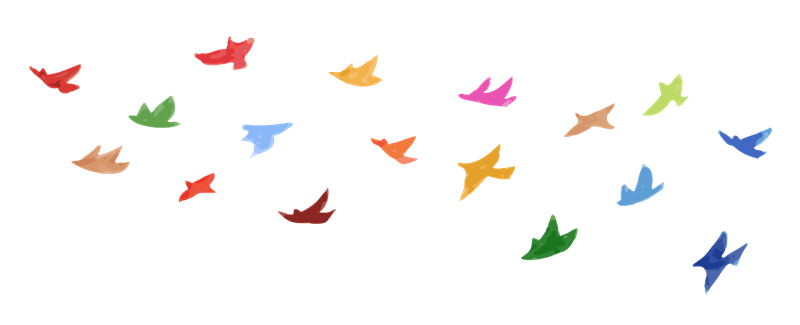
まとめ
生活保護を受けていると、働く気がなくなってしまうのではないか?
という疑問について解説しました。
日本で生活保護を受けている人の8割の人は、高齢であったり、健康上の理由から働くことが難しい人なので「働く気がなくなってしまう」と言ことは当てはまらないこと。
また、生活保護を受けて働いた場合、支援金額が減額されて働き損になるので働かず、貧困から脱げだせなくなるという指摘については、日本の生活保護は、働き損にならないように設計されていること、こまめな見直しで物価高に対応していることを見てきました。
生活保護の申請の難しさをなくし、受給していることへの負い目を感じたり、差別や偏見をなくしていくよう、社会全体で支え合う必要を周知していくことが大切です。
私たちができることは、貧困に陥っている人に対して生活ギリギリのお金を分け与えることではありません。目まぐるしく変化と成長を続けていく社会の中で、自分の力で生きていけるだけの技能を身につけてもらうことなのです。
参考文献
経済学入門 ティモシー・テイラー
日本における貧困の実態 | グラミン日本 (grameen.jp)