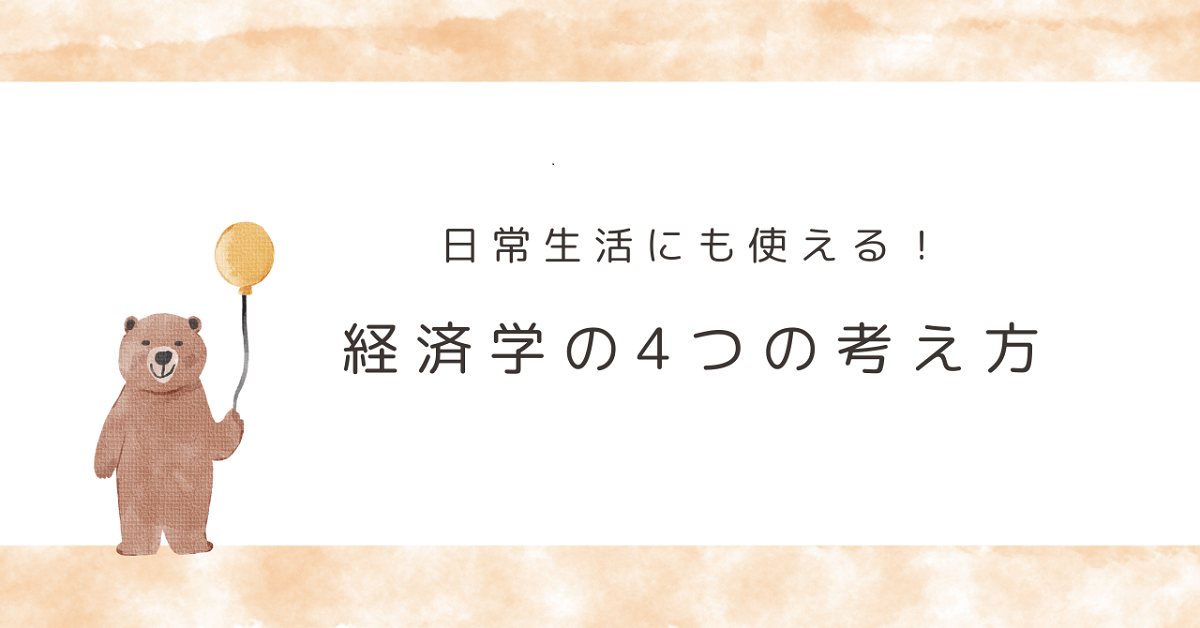経済学なんて何から始めたらいいのかわからないニャー
まずは、経済学の本編に行く前に、まず経済学的な4つの考え方をご紹介します。
日常生活にも役立つのでぜひ押さえておきましょう!
- ものごとにはトレードオフがある
- 利己的な行動が社会の秩序をつくる
- あらゆるコストは機会費用である
- 価格を決めるのは生産者ではなく市場である
この4つの視点が経済学的な考え方の基本になります。
一つ一つ見ていきましょう。
ものごとにはトレードオフがある
一つ目は「トレードオフ」です。
「トレードオフ」とは、簡単に言うと「こちらを立てるとあちらが立たず」とも言い換えられます。
つまり、何かをしたとき、
または、あるモノを得たときには、
別の何かが失われる。
ということが成り立つ、と経済学では考えます。
なにかを手に入れれば、お金や時間が無くなっている。
このことを経済学では重要視するのです。
トレードオフの例
なぜ、経済学ではトレードオフを重視するのでしょうか?
それは、私たちのまわりにある資源は限られ、すべての人の欲求を同時に満たすことはできないためです。限られた資源をどのように配分するかが、経済学の根本的な問題なので、このトレードオフを非常に重視します。
限られた資源には具体的には「時間」「お金」「土地」そして「労働力」などがあります。
これらの資源はすべて限られており、ある目的に使用すると、他の目的に使用できなくなります。
トレードオフはどんなときでも現れるものですが、その影響が大きく現れるのは、政府の政策をつくるときです。関係者が多いのでどうしても利害関係が対立してしまいます。
また、新しい政策を始めようと、歳入を増やさなければいけない場合、その財源を個人の税金で賄うのか、それとも企業の法人税で賄うのかが問題になることがあります。
この問題を経済学者がトレードオフを意識して考えると下のような流れになります。
- 企業の法人税で賄うなら法人税を引き上げなければいけません。
- 法人税を引き上げられた各企業はその支払いを捻出のため商品価格に上乗せする
- または、ボーナスを減らしたり、株主への配当が減少する
- そして結局「どちらにしても個人が痛みを受ける」ことになります。
経済学では、政府が税金をどこから取るのか?
ということよりも、その税金はだれの懐から出ているのか、より本質的なことに注目するのが、経済学的な視点をもつということなのです。
経済学におけるトレードオフの代表的な例をいくつか挙げてみましょう。
- 失業率と物価上昇
一般的に、失業率と物価上昇はトレードオフの関係にあります。
政府が積極的な財政政策や金融政策を実施して経済成長を促進すると、失業率は低下する傾向がありますが、同時に物価上昇も起きやすくなります。 - 経済成長と環境問題
経済成長は、より多くの商品やサービスを生み出し、人々の生活水準を向上させることができます。
しかし、経済活動の活発化は、環境汚染や資源枯渇などの環境問題を引き起こす可能性もあります。 - リスクとリターン
投資において、リスクとリターンはトレードオフの関係にあります。
一般的に、リスクが高い投資ほど、高いリターンが期待できます。逆に、リスクが低い投資は、リターンも低くなります。 - 労働時間と余暇
労働者は、より多くの収入を得るために長時間労働を選ぶことができます。
しかし、その結果、余暇時間が減少し、休息や家族との時間などに費やす時間が少なくなります。
私たちは、何かを決めるとき常にトレードオフを考慮し、限られた資源を最も効率的に利用できる選択肢を選ぶ必要があります。
トレードオフとウィンウィンの関係性
けれど、すこし疑問が残ります。
よく耳にする「ウィンウィンの関係」のように、両者が得することも確かにありますよね。
トレードオフとウィンウィンの関係は一体どのようになっているのでしょうか?
経済学における「トレードオフ」という言葉は、確かに「何かを得るためには、何かを諦めなければならない」という、両立しない関係性を指す言葉です。
けれど「両者両得」となるケースも数多く存在します。
あなたが何かを選んだら、他の人も何かいいことがあったら、つまり「ウィンウィン」になったら、そのほうが良いわけです。
なぜトレードオフがウィンウィンの前段階と言えるのか?
トレードオフはウィンウィンという理想的な関係をつくるための、その前段階にあると考えることができます。
それには次のような理由があります。
- 選択肢の明確化
まず自分のトレードオフを考えることで、自分が本当に何を重視しているのか、何が譲れないものなのかが明確になります。 - 交渉力の向上
相手の立場を理解し、トレードオフを意識することで、より効果的な交渉を行うことができます。 - 創造的な解決策の発見
両者のニーズを満たすために、新たな選択肢やアイデアを生み出すきっかけが両者にとって利益になります。
このように、理想的には両者がウィンウィンの関係になることですが、その前に自分のトレードオフを意識しておくことがより良い選択をできる可能性が一段と高まるのです。
トレードオフを踏まえてウィンウィンを実現するための3つのヒント
ウィンウィンの理想にできるだけ近づけるにはどうしたらいいでしょうか?
- 共通の利益を見つける
両者にとってメリットのある、共通の目標を設定することで、ウィンウィンを実現しやすくなります。 - 創造的な解決策を考える
固定観念にとらわれず、新しい視点から問題解決にあたることで、より良い選択肢が見つかることがあります。 - 長期的な関係を築く
一度の取引で終わらせるのではなく、長期的な関係を築くことを目指すことで、互いに信頼関係を深めることができます。
自身のトレードオフを意識して、信頼し合える相手と、新しい視点で物事に当たることが、ウィンウィンを実現するために必要です。トレードオフを単なる「諦めること」と捉えるのではなく、「より良い選択をするための前提」として捉えると、全く違う視点が開けるかもしれません。
トレードオフを踏まえて、いかに創造性と交渉力を発揮し、ウィンウィンを実現していくか が、ビジネスやだけではなく、ちょっとした日常の生活の中にでも、役に立つ考え方なのです。
利己的な行動が社会の秩序をつくる
経済学の考え方の2つめは、人々は利己的な行動をすることが社会の秩序をつくっていくと考えます。
一体なんのことでしょうか?
「利己的な行動」とはどんな行動でしょうか?
利己的な行動、それはつまり「自己の利益を最大化しようとする」ことです。
例えば、勉強するとゲームを買ってもらえるから勉強に励むとか、売り上げを伸ばすために、使う人が便利な生活になる商品をつくる、といった行動のことです。
経済学で利己的な行動をしている人とは「利益ばかり追求する嫌な経営者」ばかりではありません。経済学では「私たちすべての人間が、自分自身の利益を優先して行動している人」と考えます。
その「自己の利益を最大化しようとしている人」は、以下の3つの特徴を持っています。
- 完全な情報を持っている
人は、意思を決定するときに、必要な情報をすべて持っている。 - 合理的に行動する
人は、自身の利益を最大化するために、論理的に意思を決定する。 - 利己的である
人は、自身の利益を最優先に行動する。
経済学では、多くの理論が「人は合理的であり、自分の利益を最大化するために行動する」という前提に基づいています。私たちは意思決定をするときは、自分の満足度や効用を最大化する選択をする(はずだ)ということになります。
でも、ちょっとまってください、なんだか現実離れしていないでしょうか。
私たちは合理的に選択することがあまりありませんし、情報は偏って存在します。自分の利益ばかり考えているだけでもありません。
「人は自分の利益を最大化する」という前提と現実のギャップ
「人は自分の利益を最大化しようとする」という前提は、経済行動を分析する上で非常に便利な仮説で、多くの経済モデルはこの前提に基づいて構築されてきました。
しかし、現実は、人は必ずしもこの前提通り動くわけではありません。
なぜ「現実と異なる」と言われるのか?
- 非合理的な行動
人は感情に左右されたり、衝動的な行動を取ったりすることがあります。
また、社会的な規範や道徳的な価値観を重視し、自分の利益を犠牲にして他人を助けることもあります。 - 情報不足
人は完全な情報を持っているわけではなく、不確実な状況の中で意思決定を行う必要があります。
そのため、必ずしも最善の選択ができるとは限りません。 - 複雑な動機
人の行動は、経済的な利益だけでなく、社会的承認、自己実現、自己肯定感など、様々な動機によって複雑に影響を受けています。 - モデルの簡略化
経済モデルは、現実を単純化して分析するために作られています。
そのため、現実の複雑な状況を完全に捉えきれないという限界があります。
最近では、この現実とのギャップを埋めるために行動経済学や実験経済学という分野の研究も進んでいます。
「人は自分の利益を最大化する」という前提は、経済学の重要な考え方ですが、現実の人間の行動を完全に説明できるものではありません。経済学は、この前提を踏まえつつ、より現実的な人間の行動を理解するために、様々な研究を進めています。
利己的な行動はいけないの?
経済学では、人を「利己的な行動をする」という、現実とは違う単純化したモデルを使って研究を進めてきました。
けれど、人は「利己的な行動する」ということは間違っているでしょうか?
例えば、みんなにエネルギーの節約をしてもらいたいとき、経済学者なら有名な女優さんを使ったコマーシャルを流すより、電気を使った分だけ税金が掛かることになれば、多くの人が電気を使う量が減るのではないでしょうか?
また、太陽光発電の導入を増やしたい場合は補助金や減税をすればみんな導入に前向きになるでしょう。
つまり、あなたの心にもある「利己心」が、日常と違った行動をうながすきっかけになるはずです。
人々は必ず損得で動くわけではありませんが、なにか行動を変えてもらいたいとき、損得を提示することで行動が変化するきっかけになるということを、経済学では大切にしています。

あらゆるコストは機会費用である
そして経済学の考え方の3つめは「あらゆるコストは機会費用」であるということです。
機会費用とは、ある行動をし選択したことで、選択されなかった行動の利益(お金)または時間のことを指します。
簡単に言うと「何かを選んだとき、選ばれなかった選択肢の価値」です。
例えば、大学に進学するのをやめて就職した場合、大卒という肩書で得られるもっと大きな給与のことを「機会費用」と呼びます。また、アルバイトをしないで、映画を観に行くことを選択した場合、アルバイトで得られたはずだった収入を「機会費用」と呼びます。
もう少し大きな例としては、企業が新製品の開発に投資する代わりに、既存製品の生産を拡大することを選択した場合、企業の機会費用は、新製品の開発によって得られたはずだった利益となります。
機会費用の重要性
「機会費用」は、意思決定を行うときに大切になる考え方です。
あなたが、ある選択を選ぶとき、他の選択肢を捨てることになります。
その捨てた選択肢の価値を意識すること、それが「機会費用」の考え方です。
簡単にいうと「他の選択肢も考えてみよう!」ということです。
どんなときに機会費用が重要になるでしょうか?
いくつか日常の場面の例を見て見ましょう。
- 投資
投資先を選ぶ際、それぞれの投資の期待収益だけでなく、他の投資先で得られるはずだった収益も考慮する必要があります。 - 事業
新規事業に参入するかどうかを判断する際、その事業で得られる利益だけでなく、既存事業を拡大することによって得られる利益も考慮する必要があります。 - 日常生活
勉強するか遊ぶか、家事をするか外食するかなど、日常生活における様々な選択においても、機会費用を意識することはとても大切です。
このように、毎日私たちは選択をしながら生活していますが、その時に他の選択をしたら、かかるお金や時間がどう変わるのか。それを意識することが「機会選択」ということです。
最高の選択はありますか?
でも、あなたが自分で決めた選択が「一番利益が出る選択だ」と考えられる場合も当然ありますよね?
あなたが選択したものが最も利益が出るものだと考えている場合、その選択によって失われる他の選択肢の価値(機会費用)は、あなたの認識の中では「0」と考えることができます。
しかし、ここで重要なのは「あなたの認識」です。
あなたの認識には狂いはないでしょうか?
- 情報不足
全ての選択肢について、正確かつ完全な情報を得ていない可能性があります。 - 予測の困難さ
将来の状況は不確実であり、当初最も有望に見えた選択肢が、必ずしも最も良い結果をもたらすとは限りません。 - 価値観の変化
時間経過とともに、あなたの価値観や優先順位が変化し、当初選択しなかった選択肢が、後からより重要だと感じる可能性があります。
これらの要素を考慮すると、「最も利益が出る」という判断は、あくまで現時点での推測に過ぎません。
機会費用が「0」になることは、理論上はあり得ますが、現実的には非常に稀なケースなのです。
つまり経済学では常に、ある選択をすると、必ず失うものがあるのでそれを客観的に見つめてみること、これがより良い選択の一歩と考えます。
機会費用の注意点
機会費用を計算することは必ずしも簡単ではありません。
なぜなら、すべての選択肢の利益を正確に把握することは難しいからです。
また、機会費用は将来の利益を推定する必要があるため、不確実性も伴います。
けれど、これらの不確実性があったとしても機会費用は意思決定において重要です。
機会費用を意識することで、より合理的な選択をすることができるからです。
機会費用は、経済学の重要な概念ですが、日常生活でも役立つ考え方です。
何かを選択する際には、必ず機会費用を意識すれば、より良い決断をすることができるでしょう。
価格を決めるのは生産者ではなく市場である
最後に、経済学では「価格は市場が決める」ということについて考えましょう。

モノの値段は、作った人が決めるんじゃないにゃー?
スーパーに売っている商品の値段は誰が決めていると思いますか?
商品をつくった会社の人たちが決めた値段だったり、農家さんがその手間賃を考えて決めた値段だって考えていませんか?
もちろん、農家や企業が価格を設定することは可能です。
しかし、その価格が市場で受け入れられるかどうかは、最終的には需要と供給のバランスによって決まります。
具体的なイメージ
経済学では、モノの値段は需要と供給という2つの要素によって決まることを重視します。
- 需要
ある商品やサービスを求める人の数や程度のことです。
需要が多いほど、価格は上昇する傾向があります。 - 供給
ある商品やサービスを提供できる量のことです。
供給が多いほど、価格は下落する傾向があります。
この需要と供給が均衡する点が、その商品の価格となります。
なぜ市場が価格を決めるのか?
- 自由な取引
市場経済では、企業は自由に商品を生産・販売し、消費者は自由に商品を選び購入することができるので、価格が決まります。 - 競争
多数の企業が同じような商品を販売しようとするため、価格競争が生まれ、結果的に市場価格が決定されます。 - 情報伝達
市場価格を通じて、消費者の需要や生産者の供給状況が効率的に伝達されるので価格が決まります。
価格の例
モノの価格は季節や社会情勢、災害、また新しい技術の誕生などの影響で日々変動しています。
- 農産物
農作物の収穫量によって供給量が変化し、消費者の需要によって価格が変動します。 - ガソリン
原油価格や国際情勢の変化によって供給コストが変動し、結果的にガソリン価格が変動します。 - スマートフォン
新しいモデルの発売や競合製品の登場によって、スマートフォンの価格が変動します。
「価格が市場が決める」ことの重要性
価格が変動することはどんなメリットがあるでしょうか?
- 資源の効率的な配分
市場価格を通じて、資源が最も必要とされる分野に効率的に配分されます。 - イノベーションの促進
新しい商品やサービスの開発を促し、経済全体の成長に貢献します。 - 消費者の選択の自由
消費者は、価格を比較して、自分のニーズに合った商品やサービスを選択することができます。
「価格は市場が決める」という考え方は、一見シンプルですが、市場経済の仕組みを理解する上で非常に重要な概念です。この考え方を理解することで、経済ニュースや私たちの日常生活における価格変動をより深く理解することができます。

まとめ
経済学の4つの考え方について解説しました。
ものごとにはトレードオフがありました。
何かを手に入れるときは、必ずそれによって失うことがあります。
それを踏まえて、信頼のおける人と、新しい解決を見つけ出すことによってウィンウィンの関係が築ける可能性があります。
経済学では、社会はみんなが合理的、そして利己的に行動すれば上手く回っていくはずだ、と考えられています。
しかし、現実には情報の偏り、常に合理的な行動をするわけではないため、経済学者の書く理想通りには進みません。
そのため、行動経済学などの現実に合った、新しい経済の研究もおこなわれています。
経済学では実際に選択しなかった選択肢にも注目します。
選択されなかった方にも利益があること、それを「機会費用」として意識することで、選択をより客観的に捉えます。
モノの価格は農家や企業はそのコストによって設定しますが、最終的に価格を決めるのは市場です。どんなに手間をかけたとしても市場で価値なしと判断されれば、経営はなりたちません。逆に社会的に違法だったり、倫理に反していたとしても価値があると判断されれば高い値段が付きます。
トレードオフ、利己的な人たち、機会費用、そして市場が決める価格。
これら4つは、経済学の基本的な考え方ですが、毎日の生活にも利用できる考え方です。
なにかを決めようとしている時、ちょっと頭の片隅に思い出して選択を考えてみませんか?
もしかしたらもっと良い選択が見つかるかもしれません。
参考文献
経済学入門 ティモシー・テイラー かんき出版