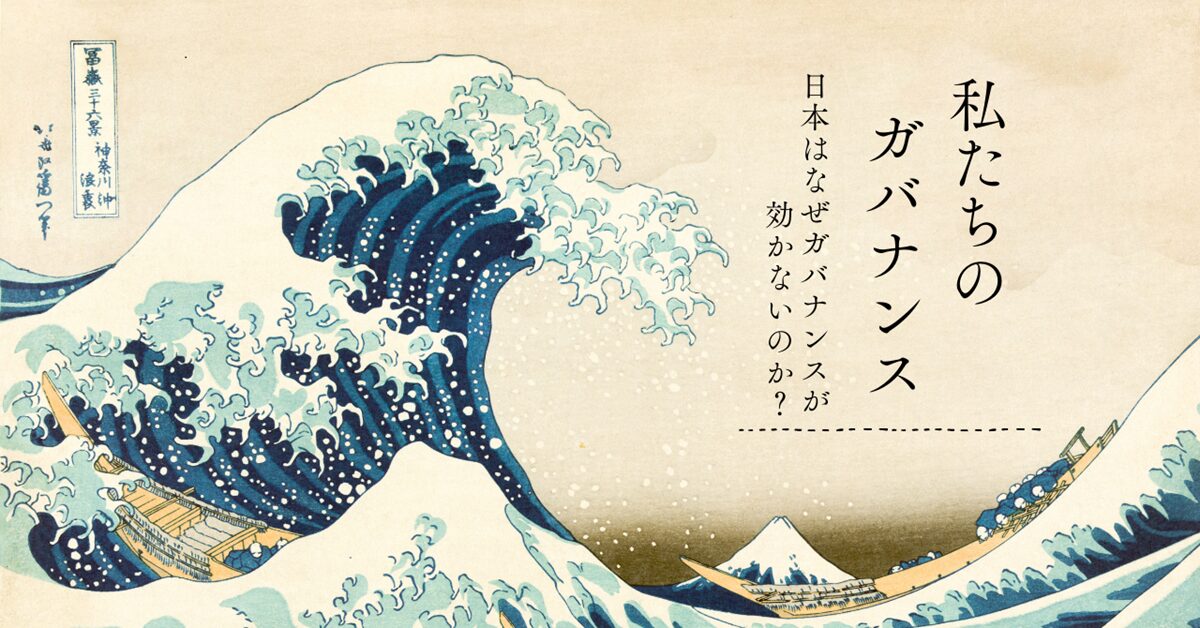あなたの職場の透明性はどうですか?
なにかを決めるとき、その判断された経緯を確認することができるでしょうか?
「何の情報も回ってこない」
「情報を公開する習慣がない」
「言われたことをするだけ」
「理解させるのが大変だし、反発されると時間がかかるだけ」
「ルールを作っても利益に結び付かない」
もし、このような状態なら、その企業は「ガバナンス」に問題があるかもしれません。
企業が健全に運営され、持続的に成長していくためには、しっかりとした組織体制と管理体制が不可欠です。この組織運営の仕組みを「ガバナンス」と呼びます。
たとえば、スポーツチームが勝利を目指すためにルールを守り、監督の指示に従って練習するように、企業もまた、目標達成のために適切なルールと管理体制を構築・運用していく必要があります。
日本の中小企業においては、大企業に比べてガバナンス体制が弱い傾向があると言われています。その背景には、オーナー経営者が強い影響力を持つことや、企業規模が小さく組織構造が、比較的シンプルであることが挙げられます。
ガバナンスを強化することは、企業のメリットのため、ということが注目されますが、ここでは働く人々にも大きなメリットがあるというについて解説していきます。

なぜガバナンスが重要なのか?
皆さんの中には「うちのような小さな会社にはガバナンスなんて関係ない」と思われる方も多いかもしれません。
かつては「ガバナンス」というと、主に株式を公開している大企業が対象となるイメージがありました。
しかし、現代のビジネスの環境においては、規模の大小に関わらず、あらゆる企業にとって健全なガバナンス体制を作ることの重要性は、増しています。
なぜでしょうか?
それは、企業を取り巻く社会の目が厳しくなっていて、倫理的な行動や透明性の高い経営が強く求められるようになっているからです。
近年、大手企業における不正会計や品質偽装といった不祥事が相次いで報道され、社会全体の企業に対する信頼を揺るがす事態となっています。
これらの事例は、規模の大小を問わず、ずさんな管理体制やチェック機能の欠如が、いかに深刻な事態を引き起こす可能性があるかを示唆しています。
それは、規模が大きくても小さくても、その可能性は避けられません。
ガバナンスとは:企業は航海する船
ガバナンスとは、簡単に言うと「組織をうまく運営するためのルールや仕組みのこと」です。
ここで、たとえ話としてガバナンスの効いている船と、効いていない一つの船があるとしましょう。
ガバナンスは、この船を安全に目的地まで運ぶための「航海規則」や、船内の「管理体制」のようなものです。
ガバナンスが利いている船は、安全に目的地に向かうため、それぞれの役割の人が守るべきルールを知っていて、それを果たすために協力し合っています。そして、目的を果たすことができるでしょう。
反対にガバナンスの効いていない船はどうでしょうか?
ガバナンスが利いていない船は、日々海の流れにさすらうだけで、目的地を知っている人はいません。
そのため、航路が頻繁に変更されたり、目標とする航路から大きく外れても気が付きません。
また、乗組員の知識不足などから、レーダーなどの航海機器の整備が不十分だったり、見張り員の数が不足していたりして、他の船舶や障害物と衝突するリスクが高まります。
さらに、船長と乗組員間でコミュニケーションが十分に行われていないため、意見対立や、食料や水の不足などから、乗組員が暴動を起こし、船の制御が不能になる可能性も出てきます。
つまり、ガバナンスの効いていない船は目的地に到着することができず、ただ漂流しているだけか、沈没する可能性が高まります。
もし、急な天候変化や問題が生じたとしても、船にガバナンスが機能していれば、危機を未然に防ぐことができます。
例えば、航海計画をしっかりと作り、定期的に見直しを行うことで、航路を間違ったときには修正を行い、もとの航路に戻ることができます。
また、船員の教育訓練を徹底し、緊急時の対応マニュアルを作成することで、事故発生時の対応をスムーズに行うことができます。
このような例は、一般の企業でも同じように考えることができます。
ガバナンスが機能していない組織では、目標が達成できず、組織が混乱状になってしまうでしょう。

船が確実に目的地に着くために必要なこと
この船の例から分かるように、組織におけるガバナンスは、組織を目的地へと導く羅針盤のようなものです。ガバナンスが機能していない組織は、目標が達成できず、外部からの脅威にさらされ、最終的には崩壊してしまう可能性があります。
組織におけるガバナンスの重要性をまとめると、次のようになります。
- 組織の方向性を定める:組織全体の共通認識を形成し、行動の統一性を図る。
- リスクを管理する:潜在的なリスクを事前に特定し、適切な対策を講じる。
- 法令遵守を確実にする:法律や規制に違反する行為を未然に防ぐ。
- ステークホルダーとの信頼関係を構築する
株主、従業員、顧客など、様々なステークホルダーとの信頼関係を築き、組織の持続的な成長を促す。
このように、船を目的地に向かわせるためには、明確な航海計画に基づいて、船員が協力し、航海の進捗状況を常に確認することがとても大切です。
つまり、組織を成功へと導くためには、ガバナンスを機能させ、組織の方向性を定めリスクを管理し、利害関係者との信頼関係を構築することが不可欠です。
日本のガバナンス
日本では、バブル経済崩壊後の企業倒産や不正事件の多発、そして国際的な競争激化を背景に、ガバナンスの重要性が認識されるようになりました。
けれどその導入には、まだまだ次のような課題があります。
- オーナー経営者の強い影響力
日本では、全体の動きを監視するのは経営者だけで十分だ、という間違った考え方が横行しています。
その原因は、中小企業の経営者はオーナーであることが多く、経営陣と取締役会、株主などの利害関係者との間で、ガバナンスの考え方を共有するのが難しいのです。
オーナーと経営者が同じということは「企業は経営者(オーナー)の所有物」と考えたとしてもおかしくありません。そのため経営判断がオーナーの意向に左右されやすく、他の役員や従業員の意見が反映されにくくなります。
これは、迅速な意思決定というメリットがある一方で、客観的な視点や多様な意見が欠如するリスクを孕んでいます。 - 不明確な意思決定プロセスと組織構造
誰がどのような権限を持ち、どのように意思決定が行われるのかが明確になっていない場合が多くなっています。
これは、業務の遅延や責任の所在が曖昧になるなどの非効率が生じる可能性があります。 - 外部人材の活用への抵抗感
日本の経営者の中には、社外取締役や監査役といった外部の視点を取り入れることに抵抗がある人が多いことが指摘されています。
これは、経営の透明性や客観性を高める機会を失うことにつながります。
このように日本では、ガバナンスは経営者だけが担うものであり、他の利害関係者は関与する余地がない、という考え方が広まっています。
しかし、ガバナンスは「経営者」だけでなく、すべての利害関係者が関与することで初めて機能するものです。
経営者だけでなく、取締役会、監査役会、社員、株主などの利害関係者全員が、それぞれの立場からガバナンスに参加することで、企業の持続的な成長と発展が実現されます。日本での「ガバナンスするのは経営者だけ」という考え方は改め、すべての利害関係者がガバナンスに参画する意識改革が重要です。
さらに、近年では、企業が環境(Environment)、社会(Social)、ガバナンス(Governance)に配慮した経営を行う「ESG経営」が重視されるようになっており、中小企業においてもその対応が求められています。
しっかりとしたガバナンス体制は、ESG経営を推進するための基盤となるため、その重要性はますます高まっています。

経営者にとってのメリット:強い企業を作る
企業が社外に相談役を置いたり、広く情報を公開したりガバナンスを強化することは、一見すると手間やコストがかかるように思えるかもしれません。
しかし、長期的な視点で見ると、経営者にとって多くのメリットをもたらし、結果としてより強い企業へと成長させることができます。
- ステークホルダーからの信頼向上と資金調達の円滑化
強固なガバナンス体制は、顧客、取引先、金融機関、投資家といった企業の利害関係者(ステークホルダー)からの信頼を高めてくれます。
透明性の高い情報開示や責任ある意思決定を行う企業は、信頼性が高いと評価され、金融機関からの融資を受けやすくなりますし、投資家にとっても、ガバナンスがしっかりしている企業はリスクが低いと判断され、出資を検討する際の重要な要素となります。
このように、ガバナンス強化は、企業の成長に必要な資金調達を円滑にする上で大きなメリットになります。 - 意思決定の質の向上とリスク管理の強化
明確な役割分担や責任体制、そして多様な意見を取り入れる仕組みを構築することで、経営者はより質の高い意思決定を行うことができます。
例えば、取締役会やアドバイザーを迎えて、外部の専門家の意見を聞くことは、経営判断の偏りを防ぎ、新たな視点をもたらします。
また、ガバナンスには、事業を取り巻く様々なリスクを特定・評価し、対応策を講じるリスク管理の側面も含まれます。
予期せぬ事態への対応力を高めることで、事業の継続性を確保することができます。 - 企業イメージとブランド力の向上
健全なガバナンス体制は、企業の倫理的な行動や社会的責任への取り組みを示すものであり、顧客や社会からの信頼を高め、企業イメージの向上につながります。
近年、消費者は企業の倫理観を重視する傾向が強まっており、良いガバナンス体制を持つ企業は、競争優位性を確立することができます 。
また、企業イメージの向上は、優秀な人材の獲得にもつながります。 - スムーズな事業承継の実現
後継者育成や事業承継は、特に中小企業にとって重要な課題です。
しっかりとしたガバナンス体制があれば、経営者の交代がスムーズに行われ、事業の継続性を高めることができます。
透明性の高い後継者選定プロセスや、経営を引き継ぐための明確な計画は、従業員や取引先の不安を軽減し、円滑な事業承継を可能にします。 - 長期的な持続可能性と成長
上記のような様々なメリットは、最終的に中小企業の長期的な持続可能性と成長に貢献します。信頼性の向上、効率的な経営、リスクへの対応力強化は、変化の激しい現代において、企業が生き残り、成長していくための重要な要素となります。
従業員にとってのメリット:より良い職場環境と安心
ガバナンス強化の恩恵を受けるのは、経営者だけではありません。
そこで働く従業員にとっても、多くのメリットがあります。
- 雇用の安定と安心感の向上
しっかりとしたガバナンス体制のもとで健全に経営されている企業は、財務状況も安定しやすく、長期的な事業継続が期待できます。企業の不正や不祥事のリスクも低減されるため、従業員は安心して働くことができます。 - 公正な評価と透明性の高い人事プロセス
適切なガバナンス体制は、従業員の評価や昇進、給与決定などの人事プロセスにおける公平性と透明性を高めます。明確な評価基準やキャリアパスが示されることで、従業員は自身の成長に向けて安心して取り組むことができます。 - より良い労働環境と倫理的な企業文化
ガバナンスの強化は、ハラスメントや差別といった不当な行為を防止し、従業員が安心して働ける倫理的な企業文化の醸成につながります。内部通報制度などが整備されることで、従業員は不正行為や問題点を安心して報告できる環境が整います。 - キャリアアップと能力開発の機会
健全なガバナンス体制を持つ企業は、従業員の育成にも力を入れる傾向があります。研修制度やキャリアパスが整備されることで、従業員は自身のスキルアップやキャリアアップの機会を得やすくなります。 - 企業への信頼感と一体感の向上
倫理的な経営を行い、従業員を大切にする企業で働くことは、従業員のモチベーションを高め、企業への信頼感や一体感を醸成できます。
また、自分の働く会社が社会から評価されることは、従業員の誇りにもつながります。
ガバナンスを強化するための簡単なステップ
企業がガバナンスを強化するために、すぐに取り組める簡単なステップをご紹介します。
- 明確な社内規則と規範の策定
まずは、基本的な業務手順や従業員が守るべき行動規範、倫理規定などを文書化しましょう。
出勤・退勤のルール、経費精算の手続き、情報セキュリティに関するガイドラインなどが考えられます。
これらは、経営者にとっては従業員に対する明確な期待を示すものとなり、従業員にとっては自身の権利と責任を理解する上で役立ちます。 - 社内コミュニケーションと透明性の向上
定期的なチームミーティングや全体会議、社内報などを活用し、経営状況や目標、重要な決定事項などを従業員に共有しましょう。 風通しの良い職場環境を作ることは、従業員のやるきを高め、不正の抑止にもつながります。 - 外部からのアドバイスや専門家の活用を検討
必要に応じて、中小企業診断士や弁護士、公認会計士などの専門家からガバナンスに関するアドバイスを受けることを検討しましょう。
また、業界団体などが開催するセミナーや研修に参加することも有益です。 - 段階的な導入と継続的な改善
最初から完璧なガバナンス体制を構築しようとするのではなく、まずはできることから始め、徐々にその範囲を広げていくことが大切です。
定期的にガバナンス体制を見直し、改善を重ねていくことで、より実効性の高いものへと進化させていくことができます。
日本では、ガバナンス強化させることは、株主や投資家向けに体裁を整えて行われる単なる形式的な取り組みで、日々の利益に結び付くことはほとんどない、と考えられていることがまだまだ多いです。
経営者にとってはより強く持続可能な企業を築き、また従業員にとってはより安心で働きがいのある職場環境を実現するための重要な戦略です。
信頼の向上、意思決定の質の向上、企業イメージの向上、そして雇用の安定といった多岐にわたるメリットは、最終的に企業の成長と発展に大きく貢献します。
今こそ企業の経営者の皆様には、ガバナンス強化を前向きに捉え、その第一歩を踏み出していただきたいと思います。
第3章 第2節 成長力強化に向けて企業の積極的な行動を促す仕組み - 内閣府 (cao.go.jp)
デジタルガバナンス・コード (METI/経済産業省)
まとめ
企業のガバナンスについて解説しました。
ガバナンスとは、その組織の持続的な成長と発展をするために、組織のメンバー全員が主体的に全体の動きを監視・評価することです。それぞれの権限と責任が適切に配分され、守るべき規範となります。
ガバナンスの効かない船が目的地に着くことができないように、ガバナンスの効かない企業は利益を上げることができません。
日本は、ルールを作ってもコストだけかかり利益に直結しない、経営者だけがガバナンスを担っているという誤解があります。
これらの誤解を解消し、ガバナンスが企業の持続的な成長と企業価値の向上に不可欠な要素であることを理解することが重要です。
このブログを通して、ガバナンスに対する誤解が少しでも解消されたなら幸いです。今日からできることとして、まずは社内の情報共有の活性化や、風通しの良い職場づくりから始めてみませんか?
その小さな一歩が、やがて大きな変化になっていって、希望に満ちた未来を自らの手で創ることができるでしょう。

参考文献
ティモシー・テイラー 経済学入門
コーポレートガバナンスに関する各種政策について (METI/経済産業省)
コーポレート・ガバナンス - Wikipedia