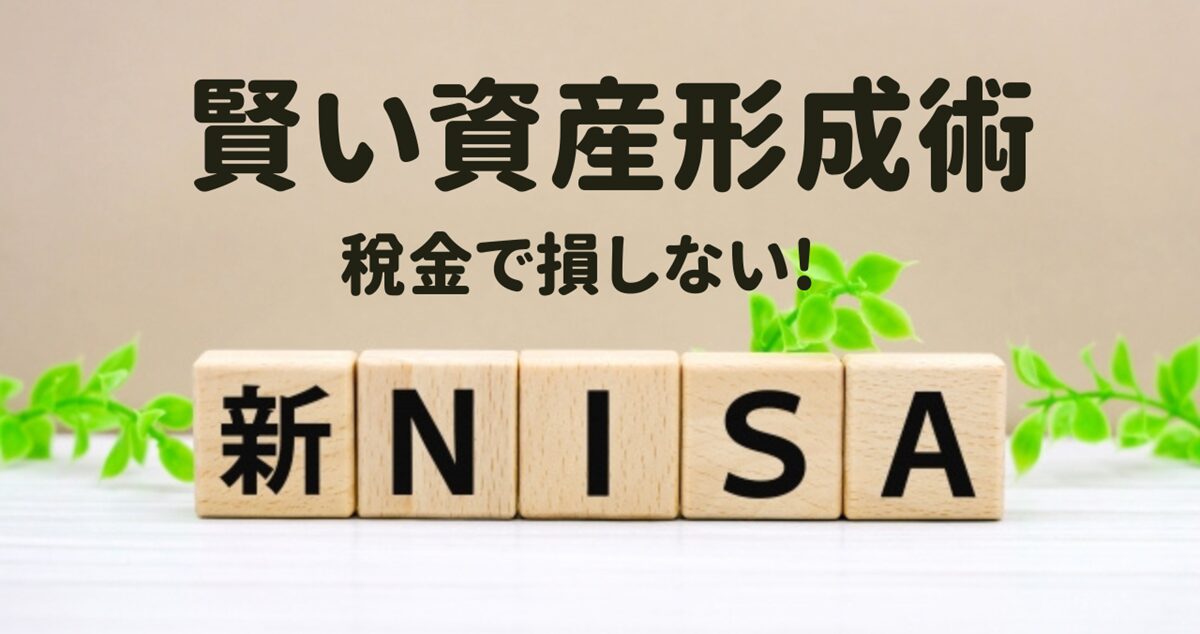あなたは、税金について考えたことがありますか?
「言われたままに払っている・・・」
「複雑で良く分からない・・・」
と感じていらっしゃる方も多いかと思います。
現代社会において、所得税や住民税、消費税など、私たちの生活には様々な税金が課されています。
特に、資産運用で得た利益にも税金がかかることをご存知でしょうか?
この税金は、せっかく増やした資産の手取り額を減らしてしまう要因となります。
そんなことにならないように、賢く税金を抑える「節税対策」が、将来の豊かな生活を送る上で非常に重要になってきます。
節税対策は医療控除や住宅控除などたくさんありますが、ここでは、今注目の「NISA」について分かりやすく解説していきます。

あたらしいNISAって大丈夫?
NISAは知っているけれど、なんか不安で怖い・・・
と感じているのは実はあなただけではありません。
実は、一般NISAで52.5%、つみたてNISAで28.4%の口座が、年間で一度も買い付けが行われなかったといわれてます(ニッセイ基礎研究所)。結構多くの人が、口座開設まではしても、その後の商品購入まで進まない人が多いんです。
けれど、NISAは国の事業です。
投資は普通銀行よりリスクが高いですが、何十年と言う長期の目線に立てば、資産を増やすことのできる方法の一つです。そして、節税対策にもなるという「お得な事業」なので、少しでも興味を持った方は、ぜひ続きをご覧ください。

もしNISAを利用しないとどうなりますか?
もし、NISAを使わないで普通に株式を買うとどうなるでしょうか?
NISA口座を使わずに、普通に株式や投資信託を購入したとします。
株を買ったときは税金はかかりませんが、売るときに利益が出ていたり、配当金などをもらうときには、その利益に原則として20%の税金が付きます。
具体的には、所得税15%、住民税5%、そして復興特別所得税0.315%の合計20.315%です。
この税金は、利益が大きくなるほどその負担も増し、複利効果による資産増大の恩恵を一部相殺してしまいます。投資における税金は、表面上は見えにくいコストです。
このコストは、長期投資を考えている私たちにとって、資産の増加のスピードが減ってしまいます。それは、利益の一部が税金として徴収されることで、本来再投資に回せるはずだった資金が減少し、複利のサイクルが弱まるため、将来得られるはずだった大きなリターンが失われるからです。
節税は、税金を減らすだけでなく、手元に残るお金を増やし、それを再投資することで、さらに資産形成を加速させることができます。特に、長期的な視点で見ると、税金による控除が積み重なることで、最終的な資産額に大きな差が生まれます。
2024年から始まった新NISA制度は、非課税保有期間の無期限化、制度の恒久化、投資枠の拡大といった大幅な変更が加えられました。これは、国が単なる制度改正にとどまらず、政府が国民の資産形成を強く後押しし「貯蓄から投資へ」という大きな経済政策の転換を本気で推進していることの表れなのです。
NISAは「貯蓄から投資へ」という政策の核として、税を優遇して個人の投資を活発にさせる役割を担っています。これにより、国民全体の金融リテラシー向上と経済活性化への貢献という、より広く社会的・経済的影響が期待されています。

投資の利益に税金がかかるってホント?税金の基礎知識
投資で得た利益には、税金がかかります。
しかし、その種類や課税方法は少し複雑です。
けれど知らないままでいると損をしてしまうかもしれません。
そこで、NISAのメリットを理解するために、投資にまつわる基本的な税金を確認しましょう。
投資で得られる利益にかかる税金の種類と税率
投資で得られる主な利益には、「譲渡益(売却益)」と「配当金・分配金」の2種類があります。
- 譲渡益(売却益)
株式や投資信託などを売ったときに得た利益を指します。
株を売ったとき利益が出るとそこに税金がかかります。
具体的には、所得税15%、住民税5%、そして復興特別所得税0.315%の合計20.315%の税金です。
譲渡益の計算は、売却価額から、購入にかかった費用(取得費)や証券会社に支払う委託手数料などを差し引いて算出されます。 - 配当金・分配金
株式の配当や投資信託の分配金として受け取る利益です。
上場株式等の配当金は、原則として20.315%が源泉徴収されます。
これらの利益に対する課税方法には、他の所得と合算して課税される「総合課税」と、他の所得とは分離して課税される「申告分離課税」の選択肢があります。NISA以外の一般口座や特定口座(源泉徴収なし)で運用している場合、原則として確定申告が必要です。
このように、投資で利益を得たら約20%の税金を支払うことが「所得税法」や「租税特別措置法」という法律によってきまっています。
特定口座と一般口座の違いと確定申告の手間
次に、投資をする場合証券会社に口座を作ることになるのですが、その口座も税金に関係していくつかの種類があるので見ていきましょう。
証券会社に口座を開設するのは、銀行に口座を開設するよりも、すこし複雑なところがあります。用語なども分かりずらく、そこで前に進めなくなってしまう方もいらっしゃるのではないでしょうか?
まず、証券会社に口座を開設することは、つまり「総合口座」を開設することになります。「総合口座」がお金を預け入れたり、購入した証券を保管したりするための、いわば「投資のベースとなる口座」になります。
そして、総合口座を開設したら、さらに税金の支払い方法によって、別々の口座を選ぶことになります。
例えば「一般口座」「特定口座」「信託口座」「NISA口座」などです。
- 特定口座(源泉徴収あり)
まず、多くの人が選ぶのがこれです。
「特定」と言う名前がとても分かりにくいのですが、この口座は、証券会社が年間の損益を計算し、税金を自動的に徴収・納付してくれる口座です。なので投資家自身が確定申告をする手間は原則として不要です。また、売却益と配当金、そして売却損(譲渡損)が自動的に損益通算されるため、税務処理が非常に簡単です。
「特定口座」という名前は分かりにくいので「税金おまかせ口座」とか「自動納付口座」というような分かりやすい名前にしてくれればいいのですが・・・。 - 特定口座(源泉徴収なし)
特定口座(証券会社が計算はしてくれる)ではあるけれど、自分で税務署に確定申告しなければいけない口座です。
つまり、証券会社が年間の売買損益を計算し、「特定口座年間取引報告書」を作成してくれますが、投資家自身がその報告書を使って確定申告を行う必要があります。
例えば、複数の証券会社に口座をもっていて、合算して計算したい人、税金に詳しくて他の所得と合わせて上手に節税したい人がこの口座を選ぶと有利になります。 - 一般口座
この口座は、証券会社は一人一人の取引を計算をしません。
投資家自身が全ての取引を記録し、年間の損益を計算して確定申告を行う必要があります。
この方法は手間が非常に大きいため、多くの投資家には推奨されません。
この口座を使うのは未公開株や、一部の海外証券など特定口座で扱えない商品を取引する場合、または取引が税務署にばれると困る人がこの口座を選びます。ただし、利益が出たら申告しないと違反になります。 - NISA口座
NISA(ニーサ:少額投資非課税制度)口座は、その名の通り、一定の投資枠内で得た利益(配当金や売却益など)が非課税になる制度です。通常、投資で得た利益には約20%の税金がかかりますが、NISA口座を利用することでこの税金がかからなくなる特別な口座です。
ちなみに「特定口座」が導入されたのは、2003年です。
政府が税収の簡素化や株取引の活性化を狙って始まりました。
そのころネットの取引も始まっていましたが、多くの投資家は電話注文でした。
また、株券が電子化されたのは2009年のことです。
「特定口座」の始まったころは、まだ紙の株券が取引されていたので、2003年は、電話とネットの過渡期のような時代でした。
また、2013年から2037年までの25年間、所得税額に対して2.1%が追加的に課税される「復興特別所得税」は、単に現在の税率を構成する要素の一つとして捉えるだけでなく、もしかしたら将来にわたって予期しない税の負担が発生するかもしれないと、考えざるを得ません。
このように新しく税が増えることは、長期的な資産形成計画を立てるとき、将来の税制変更リスクになります。そこで、NISAのような「非課税」という特徴をもっていれば、このような将来の不確実な税負担からも利益を守る、一種の「保険」のような役割も果たすことができます。
以下の表は、投資利益にかかる税率と口座の種類をまとめたものです。
| 利益の種類 | 口座の種類 | 税率 | 確定申告の要否 |
| 譲渡益・配当金 | 特定口座(源泉徴収あり) | 20.315% (所得税15%, 住民税5%, 復興特別所得税0.315%) | 原則不要 |
| 譲渡益・配当金 | 特定口座(源泉徴収なし) | 20.315% (所得税15%, 住民税5%, 復興特別所得税0.315%) | 必要 |
| 譲渡益・配当金 | 一般口座 | 20.315% (所得税15%, 住民税5%, 復興特別所得税0.315%) | 必要 |
| 譲渡益・配当金 | NISA口座 | 0% | 不要 |

税金ゼロで資産を増やす!新NISAの驚くべき節税効果
2024年からスタートした新NISA制度は、私たちの資産形成を大きく後押しする、まさに「ゲームチェンジャー」とも言える制度です。その節税効果はどうでしょうか?
新NISAとは?(2024年からの変更点に焦点を当てる)
新NISA制度は、2023年までの旧NISAから大幅な変更が加えられ、より利用しやすくなりました。
- 非課税保有期間が無期限化
旧NISAでは一般NISAが最長5年間、つみたてNISAが最長20年間と非課税期間に制限がありましたが、新NISAでは無期限となりました。これにより、期間を気にすることなく、さらに長期的な視点で投資を続けられるようになりました。 - 制度が恒久化
2023年までのNISAは時限的な制度でしたが、2024年からの新NISAは恒久的な制度となり、いつでも投資を始められるようになりました。 - つみたて投資枠と成長投資枠の併用が可能
旧NISAの「つみたてNISA」と「一般NISA」がそれぞれ「つみたて投資枠」と「成長投資枠」に引き継がれ、両方を併用できるようになりました。これにより、積立投資と個別株投資などを柔軟に組み合わせることが可能になりました。 - 年間投資枠が拡大
年間投資枠は大幅に拡大され、つみたて投資枠が年間120万円(旧つみたてNISAの3倍)、成長投資枠が年間240万円(旧一般NISAの2倍)となりました。両方を併用すれば、年間最大360万円まで投資が可能になります。 - 非課税保有限度額(総枠)が新設
生涯を通じての非課税投資枠として、最大1,800万円の上限が新たに設けられました。このうち成長投資枠は1,200万円が上限となります。なお、2023年までのNISAで保有していた資産は、この1,800万円の枠とは別に管理されます。 - 非課税枠の再利用が可能
投資商品を売却した場合、その翌年以降に売却した商品の「簿価(取得金額)」分の非課税投資枠が復活し、再利用できるようになりました。これにより、より柔軟な資産運用が可能になります。これについては次に詳しく説明いたします。
旧NISAは、時限的で非課税期間も限定的でしたが、新NISAが恒久化され、非課税期間が無期限になったのは、投資家にとって制度の改善以上の意味があります。
それは、短期的な利益追求や非課税期間終了時の売却といった制約から解放されて、文字通り「一生涯」の資産形成計画をNISA口座で立てられるようになりました。この変化は、投資家の心理に「焦らず、じっくりと」という長期志向を根付かせ、結果として、より安定した資産形成ができ、また市場全体を安定化させる効果があります。

新NISAの非課税枠の復活・再利用
先ほどもあったように、新NISAは、売却したNISA枠を、また再利用できるという大きなメリットが加わっています
これは、旧NISAにはなかった非常に柔軟な仕組みで、投資家にとって大きなメリットとなります。
ちょっと複雑なのでもうすこし詳しく見ていきましょう。
新NISAでは、生涯投資枠1,800万円(成長投資枠は1,200万円まで)という上限が設定されています。
これは、NISA口座で購入した商品の購入時の合計が、生涯投資枠の上限に達するまで利用できるということです。
つまり、NISA口座で保有していた商品を売却すると、その売却した商品の購入金額に相当する金額分の非課税枠が、翌年以降に復活し、再び利用できるようになる、という仕組みです。
具体的な例で考えてみましょう。
- 初期投資
あなたが新NISA口座で、100万円の投資信託を購入しました。- この時点で、生涯投資枠1,800万円のうち、100万円分を使用しました。
- 残りの非課税枠:1,700万円
- 値上がり後の売却
数年後、その投資信託が200万円に値上がりしました。あなたがこの投資信託を200万円で売却したとします。- この場合、売却したことによって、購入時の金額である100万円分の非課税枠が「復活」します。
- ただし、この枠が復活するのは「売却した年の翌年」です。
- 翌年以降の再利用
翌年になると、復活した100万円分の非課税枠を、再びNISA口座での新しい投資に利用できるようになります。- 例えば、その年に年間投資枠(年間360万円)の範囲内で、新たに100万円分の投資商品を購入することができます。
つまり、値上がりして売却したとしても、購入時の金額分の枠が来年復活します。
ちなみに、復活した非課税枠を利用して投資する場合でも、その年の年間投資枠(つみたて投資枠120万円、成長投資枠240万円、合計360万円)を超える投資はできません。
- 柔軟な資産運用が可能に
旧NISAでは一度使った非課税枠は戻らず、商品を売却するとその枠は消滅しました。そのため、売却に躊躇するケースもありましたが、新NISAでは売却しても枠が戻るため、市場環境の変化に応じてポートフォリオを見直したり、利益確定して再度投資し直したりといった、より柔軟な運用が可能になったのです。 - 生涯投資枠の有効活用
生涯投資枠1,800万円を使い切った後でも、保有商品を売却することで枠が復活し、再び投資ができるようになります。これにより、長期にわたって非課税の恩恵を受けながら、資産を循環させることが可能になります。 - ライフイベントに合わせた資金活用
例えば、将来大きな資金が必要になった際に、NISA口座の資産を一部売却して資金を確保し、その後、再度投資できる余裕ができたら、復活した非課税枠で投資を再開するといった使い方も可能です。
このように、新NISAの非課税枠の復活・再利用は、投資家がより長期的に、そして柔軟に資産形成に取り組めるように設計された画期的な仕組みと言えます。

NISAが「節税」に直結する理由(非課税のメリット)
NISA口座内で得た売却益や配当金は、通常かかる約20%の税金が一切かかりません。
この「非課税」というメリットは、手元に残る利益を最大化し、それを再投資することで、複利効果をさらに高めることができます。
例えば、月3.3万円を25年間年利3%で運用した場合、約97.9万円もの節税効果が期待できます。さらに30年間運用すれば、約149.3万円です。月5万円を30年間年利3%で運用すれば、約226.2万円もの節税効果が見込める試算もあります。

長期・積立・分散投資と複利効果でリスクを抑えながら資産を増やす
NISAの非課税メリットを最大限に活かすためには、「長期・積立・分散投資」という投資の基本原則を守ることが大切です。
- 長期投資
長い時間をかけて投資を行うことで、「複利効果」を最大限に活かし、資産を効率的に増やすことができます。
また、長期投資は元本割れのリスクを低減する効果もあります。金融庁のデータによると、毎月同額を国内外の株式・債券に積立投資を行い、20年間運用した場合、元本割れの出現頻度は0%という結果が出ています。一般的には、15年以上の長期で投資を続けていれば、仮にその間に暴落があったとしても元本割れしない可能性が高いと考えられています。 - 積立投資
毎月一定額を投資することで、価格変動リスクを抑える「ドルコスト平均法」の恩恵を受けられます。高値掴みのリスクを避け、平均購入単価を平準化する効果が期待できます。 - 分散投資
複数の資産クラス(株式、債券など)や地域(国内、先進国、新興国など)に投資することで、リスクを分散し、安定的なリターンを目指します。
新NISAの「非課税期間無期限」という特徴は、この長期投資のメリットを最大限に享受するために設計されています。
長期投資が複利効果を味方につけ、元本割れリスクを低減させるという原則に、NISAの「非課税」という要素が加わることで、その効果は飛躍的に高まります。
通常、複利で増えた利益にも税金がかかるため、その分だけ再投資に回せる金額が減り、複利の力が弱まります。
しかし、NISAではこの税金がゼロになるため、利益の全額が再投資に回り、複利の雪だるま式増加が税金に邪魔されることなく最大化させることができます。
以下の表は、旧NISAと新NISAの主な変更点を比較したものです。
| 項目 | 旧NISA(一般NISA) | 旧NISA(つみたてNISA) | 新NISA(2024年〜) |
| 非課税保有期間 | 最長5年 | 最長20年 | 無期限 |
| 制度の恒久化 | 時限的(2023年まで) | 時限的(2023年まで) | 恒久化 |
| 年間投資枠 | 120万円 | 40万円 | つみたて投資枠:120万円成長投資枠:240万円(合計最大360万円) |
| 非課税保有限度額(総枠) | 600万円(最大) | 800万円(最大) | 1,800万円(生涯)(うち成長投資枠は1,200万円まで) |
| 併用可否 | 不可(どちらか一方を選択) | 不可(どちらか一方を選択) | 可能 |
| 非課税枠の再利用 | 不可 | 不可 | 可能(売却した翌年以降、簿価分が復活) |
Money Journey
投資&お金の総合サイト! ザイ・オンライン
損しない!新NISAを始めるためのステップ
新NISAのメリットを最大限に活かすためには、正しいステップで口座を開設し、賢く運用することが大切です。
口座開設の流れ(ネット証券での開設方法)
ぜひ手数料の安いネット証券で口座を開きましょう。
NISA口座を開設する手順は以下の通りです。
- ステップ1:証券会社の選ぶ
手数料の安さ、取扱商品の豊富さ、サポート体制などを比較検討し、自分に合ったネット証券を選びましょう。松井証券や楽天証券、マネックス証券などは手数料無料化を進めており、選択肢として有力です。 - ステップ2:口座開設の申し込み
選んだ証券会社のウェブサイトからNISA口座開設を申し込みます。
本人確認書類(マイナンバーカードなど)や銀行口座情報が必要になります。 - ステップ3:審査・開設
証券会社での審査を経て、NISA口座が開設されます。通常、数日から数週間かかります。 - ステップ4:入金・投資開始
口座に資金を入金し、いよいよ投資を始めます。

つみたて投資枠と成長投資枠の活用戦略
新NISAには「つみたて投資枠」と「成長投資枠」の2種類があり、それぞれ対象商品や投資目的が異なります。
- つみたて投資枠(年間120万円)
主に金融庁が定めた要件を満たす投資信託(指定インデックス投資信託、一部のアクティブファンドなど)が対象です。長期・積立・分散投資に適しており、初心者の方にはまずこの枠から始めることをお勧めします。世界全体に投資するインデックスファンドなどが人気です。 - 成長投資枠(年間240万円)
上場株式、投資信託、ETF、J-REITなど、幅広い商品が対象です。
個別株投資や、より積極的なリターンを狙いたい場合に活用できます。
ただし、信用取引はNISAの対象外です。 - 併用戦略
新NISAの「つみたて投資枠」と「成長投資枠」という二つの枠の併用が可能になったため、投資家が自身の「リスク許容度」や「投資目標」に応じて、より自分らしく資産形成戦略を練ることができます。
例えば、安定的な資産形成を目指すなら「つみたて投資枠」で積立投資を継続しつつ、余裕資金で「成長投資枠」を使って個別銘柄や高配当株に投資するといった柔軟な運用ができます。
より多くの人々が、自分に合った形で長期的に継続して投資できるように、また、みんなの資産を増やす、という大きな役割がNISAはあるのです。
投資におけるリスク(元本割れリスクと長期投資による軽減)
私たち国民一人一人の資産を増やすためNISAは導入されましたが、しかし、「NISAだから安心」「NISAなら絶対にお金が増える」というわけではありません。
なぜなら、NISAは「投資」の制度だからです。
投資には、どんなに優れた制度を使っても、必ず「元本割れ」のリスクがつきまといます。
「元本割れ」って何?
簡単に言うと「投資したお金(元本)が減ってしまうこと」です。
例えば、10万円を投資したのに、あとで見てみたら9万円に減ってしまっている、という状態が元本割れです。
投資のリスクって、もっと具体的にどういうこと?
「リスク」と聞くと「危険」というイメージがあるかもしれませんが、投資の世界では「値動きの幅(ブレ幅)」のことを指します。
つまり、「プラスにもマイナスにも大きく動く可能性がある」ということです。
具体的には、以下のような理由で、投資したお金が減ってしまう可能性があります。
- 価格が上がったり下がったりするリスク(価格変動リスク)
- 投資する株や投資信託の値段は、会社の業績、景気、世界情勢など、色々な理由で毎日変わります。
- 買った時よりも値段が下がってしまうと、元本割れになります。
- NISAの口座で買っていても、この値動きは普通の投資と同じように起こります。
- 外国のお金と日本のお金の交換レートが変わるリスク(為替変動リスク)
- もし、アメリカ株や外国の投資信託を買った場合、日本円と米ドルの交換レート(為替)が影響します。
- 例えば、1ドル150円の時に買ったものが、1ドル140円になってしまうと、同じ株を持っていても日本円で見た価値は減ってしまいます。
- 会社や国が破綻するリスク(信用リスク)
- 投資した会社の業績が悪くなったり、最悪の場合、倒産してしまったりすると、株の価値がなくなってしまうことがあります。
- 国が発行する債券なども、その国の財政が悪化すると、お金が返ってこなくなる可能性がゼロではありません。

NISAでも元本割れするなら、意味ないの?
いいえ、そんなことはありません。
前にもお話したように、NISAは「税金がかからない」という大きなメリットがあります。
例えば、10万円が12万円に増えた場合、普通の投資だと増えた2万円に約20%の税金がかかりますが、NISAなら2万円まるまる手元に残ります。
また短い期間では元本割れする可能性が大きくなりますが、多くの投資は、長い期間(例えば10年、20年)続けることです。長い機関投資を続ければ、プラスになる確率が高まる傾向があります。NISAは非課税期間が無期限になったので、この長期投資のメリットを活かしやすくなりました。
まとめ:今日から始めるNISAで、未来の自分に投資しよう!
いかがでしたか?
新NISAは、「税金で損せず、賢く資産を増やす」ための強力なツールであることがお分かりいただけたでしょうか?
「貯蓄から投資へ」の流れが加速する今、新NISAは誰もが活用すべき制度です。
リスクを理解し、賢く活用することで、きっとあなたの資産は着実に育っていくでしょう。
未来の自分への投資として、今日からNISAでの資産形成を始めてみませんか。
まずはネット証券で口座開設の検討からスタートし、無理のない範囲で積立投資を始めてみましょう。
参考文献
経済学入門 ティモシー・テイラー
税の学習コーナー|国税庁 (nta.go.jp)
日本の財政問題 - Wikipedia
Ⅰ 国税庁について|国税庁レポート2022(HTML)|国税庁レポート|活動報告・発表・統計|国税庁 (nta.go.jp)
身近な税 : 財務省 (mof.go.jp)
NISA特設ウェブサイト:金融庁