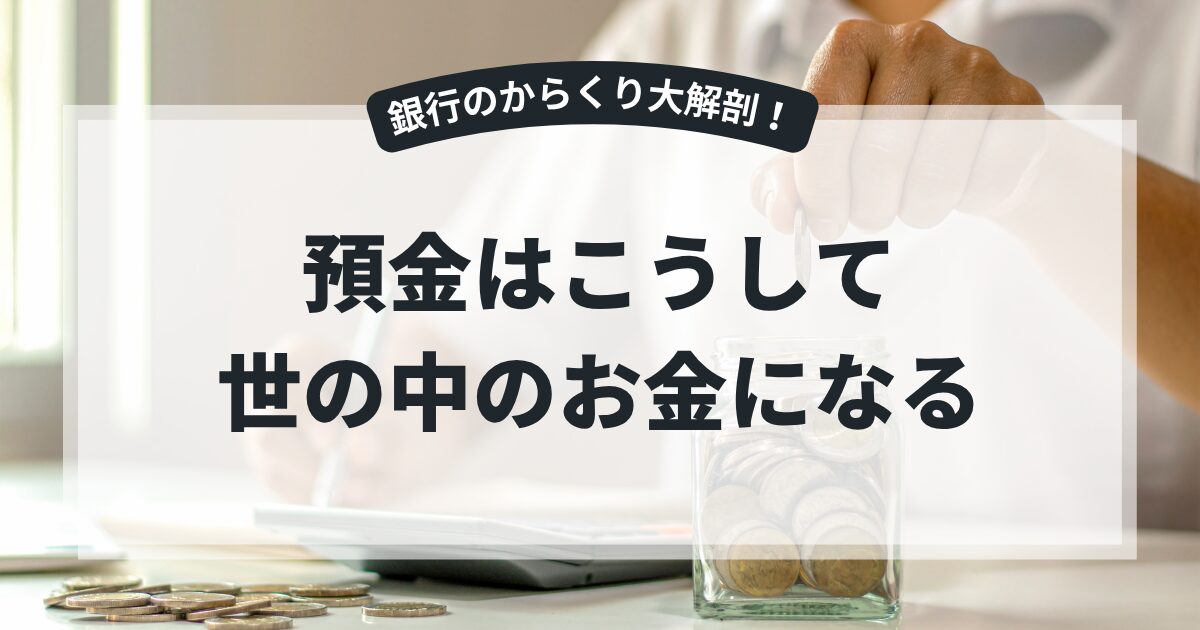お金って、どこから生まれてくるの?
私たちが日々当たり前のように使っているお金。
紙幣や硬貨は日本銀行が発行していることをご存知の方も多いかもしれません。
けれど、通帳に書かれている「預金」というお金は、私たちの知らないところで増えていくことはご存知でしょうか。
多くの方が、「銀行は、私たちから預かったお金を、必要な人に貸している」と考えているかもしれません。確かに、それは銀行の重要な役割の一つです。
しかし、それだけでは現代経済の複雑な仕組みを十分に説明できません。
実は銀行には、世の中に出回るお金の総量を大きく増やし、経済全体を動かす「信用創造」という、あまり知られていませんが、非常に重要な機能があるのです。この「信用創造」という業務は、私たちにとっては、なかなか理解しにくいものかもしれません。
この記事では、一見難解に思えるこの「信用創造」の仕組みを、誰にでも分かりやすく、具体的な例を交えながら徹底的に解説します。
この「からくり」の正体を知ることで、私たちの経済や社会がどのように成り立っているのか、そして日々のお金の流れがどのように生み出されているのかを、より深く理解できます。「信用創造」の知識は、現代社会を賢く生きるための強力なツールとなるはずです。

銀行の基本機能をおさらいしよう!
「信用創造」という銀行の核心的な機能について深く掘り下げる前に、まずは私たちの日常生活において果たしている基本的な「銀行の役割」を確認しておきましょう。

お金の「仲介役」としての銀行
銀行の業務でもっとも知られているのは、皆さんもご存じのとおりお金に余裕のある人から、お金を必要としている人へお金を安全に貸すこと、つまり「資金の仲介」としての役割です。
例えば、車や家を購入するために資金が必要な人、あるいは設備投資や原材料の購入、従業員の雇用などのために資金が必要な企業に対して銀行は融資を行います。
この「資金の仲介」を通じて銀行は、社会で使われていないお金を有効に活用される場所へと移動させることで、経済活動を活発にさせる役割があります。

便利な「決済機能」
銀行のもう一つの大切な機能は、買ったもののお金を支払いを手伝う「決済機能」です。
例えば、カードで支払いをしたときには自分の銀行からお店の銀行に支払いの情報が移動し支払いを済ますことができます。他にも振込み、手形や小切手による決済、公共料金の口座振替、なども同じです。
銀行の持つ「決済機能」があれば、私たちは多額の現金を物理的に持ち運んだり、その正確性を確認したりする手間を省くことができます。また、現金の紛失や盗難といったリスクを回避できます。このことが経済活動を活発にさせ、企業間の取引や個人の消費がスムーズに進むようになります。
普段あまり意識しませんが、この買い物の支払いをする「決済」は、後でお話しする「信用創造」の時、とても重要なのでちょっと覚えておいてください。

銀行の「からくり」の正体:信用創造の仕組みを解き明かす
銀行は、お金を貸したい人と借りたい人を仲介する活動、また金を決済する活動、この2つの活動を中心として経済活動を支えています。
それでは次に「信用創造」について深く掘り下げていきましょう。
これはまさに、銀行が「何もないところからお金を生み出す」と表現される機能であり、その仕組みは多くの人にとって驚きに満ちた「からくり」のように感じられるかもしれません。
man@bow まなぼう|野村と日経が運営する金融経済について楽しく学べるサイト
よくある誤解:「預かったお金を貸している」は間違い?
銀行の大切な業務の一つ「信用創造」の仕組みを理解する上で、まず「銀行」への大きな誤解を解いておきましょう。
その誤解とは「銀行は預金者から預かった現金を、そのまま貸し出している」という考え方です。これは、現代の銀行には当てはまりません。
実は、銀行が融資を行うとき、借り手に現金そのものを手渡すことはほとんどありません。現金は渡しませんが、銀行は借り手の銀行口座に、貸し付けた金額分の「預金」を記帳します。
この通帳に書かれた数字が、銀行が新たに創造したお金なのです。
これは、銀行がどこかからお金を借りてきて貸し出す必要も、もともと誰かから預金として現ナマとしてのお金を用意している必要もないことを意味しています。
銀行は、物理的な現金を移動させるのではなく、借り手の口座に「数字を書き込む」ことで新たな預金(銀行の負債)を生み出します。そして、この銀行の負債である新しい預金が社会で流通する「お金」になるのです。
つまり銀行は、生のお金がなくても、まるでお金が湧いたように通帳に数字を記帳してお金を貸しているという事実が、私たちの認識と「信用創造」の間に大きなギャップになっています。

貸し出しが「新しいお金」を生み出す瞬間
「信用創造」は、銀行が企業や個人に融資を決定し、その金額を借り手の口座に記帳した瞬間に、その金額分の「新しい預金」が生まれます。この預金は、それまで世の中に存在しなかったお金で、銀行が自らの「信用」を基に創造したものです。
これは、銀行の「貸し出し行為そのものが預金を産んでいる」ということです。
つまり、銀行は預金者の現金を単に貸し出すのではなく、貸し付けたお金が将来的に返済されるという期待、すなわち「信用」を元手に、新たな預金という形のお金を生み出しているのです。
この「無から有を生み出す」それが「信用創造」です。
繰り返しになりますが、銀行が貸し出しを行うと、その貸し出し額と同額の預金が同時に生成されます。これは銀行にとって資産(貸付金)と負債(預金)が同時に増加する取引で、この銀行の負債である預金が社会で流通する「お金」となります。そして信用創造は、世の中のお金の量を増やす原動力となっています。
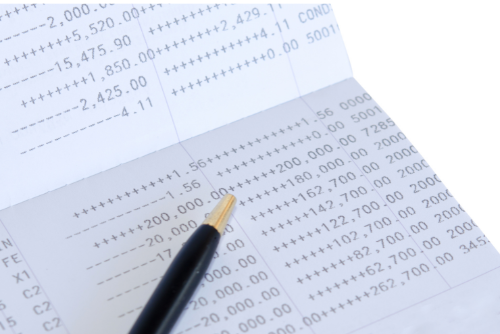
信用創造のキーポイント:預金準備率とは?
銀行が「無からお金を生み出す」と言われると、無限にお金を作り出せるように聞こえるかもしれませんが、実際にはそうではありません。信用創造の規模には限界があり、その重要な制約となるのが「預金準備率」です。
銀行は、預金者がいつでもお金を引き出せるように、預金の一部を「支払準備金」として日本銀行に預けておく義務があります。この、預金総額に対する支払準備金の割合が「預金準備率」と呼ばれ、金融機関の種類や預金量によって異なります。銀行は預かったお金の全てを貸し出すことはできず、この準備率の分だけは手元に残す必要があるため、信用創造の規模に上限が生まれます。
預金準備率は、信用創造の規模を決定する重要な要素であると同時に、金融システムの安定性を保つための規制でもあります。この制度により、銀行は無制限に貸し出しを行うことはできず、預金者が一斉に預金を引き出そうとする「取り付け騒ぎ」などのリスクを一定程度抑制しています。
預金準備率は、中央銀行による金融政策の手段の一つでもあり、銀行システムの健全性と安定性を維持するための重要な安全弁として機能しています。
大和総研 これで納得金融調節
数字で見てみよう!信用創造の連鎖プロセス
抽象的な説明だけでは分かりにくい信用創造の仕組みを、具体的な数字を使って見ていきましょう。ここでは、預金準備率を10%と仮定し、最初の100万円の預金がどのようにして社会全体で何倍ものお金に「化ける」のかをシミュレーションします。
- 最初の預金(本源的預金)Aさんが銀行Aに100万円を現金で預金しました。
この最初の預金は「本源的預金」と呼ばれ、信用創造の出発点となります。 - 銀行Aの貸し出し銀行Aは、この100万円のうち、預金準備率10%にあたる10万円を日本銀行に預け、残りの90万円をBさんに貸し出します。この90万円は、Bさんの口座に「預金」として記帳されます。この時点で、銀行Aの貸し出しによって、Bさんの口座に新たな預金が生まれました。
- お金の移動と新たな預金(派生預金)Bさんは90万円を使ってCさんから商品を購入しました。Cさんはその90万円を自分の取引銀行である銀行Bに預金します。この90万円は、銀行Aの貸し出しによって生まれた「派生預金」の一部です。
- 銀行Bの貸し出し銀行Bは、Cさんの預金90万円のうち、預金準備率10%にあたる9万円を日本銀行に預け、残りの81万円をDさんに貸し出します。この81万円もDさんの口座に「預金」として記帳されます。
これらを繰り返し、貸し出しが行われるたびに新たな預金が生まれ、その預金の一部がまた貸し出されるという連鎖が繰り返されます。このプロセスを通じて、銀行全体の預金残高はさらに増加していきます。
この連鎖が理論上無限に繰り返されると、最初の100万円の預金から、最終的には最大で1,000万円もの預金が生まれることになります(計算式:最初の預金額 ÷ 預金準備率 = 100万円÷0.1=1,000万円)。
つまり、当初の100万円を除くと、900万円が新たに信用創造されたことになります。信用創造の規模は「信用乗数」という概念で表され、「信用乗数 =1÷預金準備率」で計算されます。預金準備率が低いほど、信用創造の乗数は大きくなり、世の中のお金が増えやすくなります。
信用創造の連鎖シミュレーション(預金準備率10%の場合)
| 段階 | 新規預金 (万円) | 支払準備金 (10%) (万円) | 新規貸出 (万円) | 累積預金 (万円) |
| 銀行A | 100 | 10 | 90 | 100 |
| 銀行B | 90 | 9 | 81 | 190 |
| 銀行C | 81 | 8.1 | 72.9 | 271 |
| 銀行D | 72.9 | 7.29 | 65.61 | 343.9 |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| 合計 | 1,000 | 100 | 900 | 1,000 |
信用創造が私たちの生活と経済に与える大きな影響
「信用創造」は、単なる銀行の業務の一つだけではなく、私たちの日常生活、物価の安定、そして国全体の経済成長に深く関わる、非常に重要な機能です。
「信用創造」のしくみが、どのようにマクロ経済全体に波及していくのかを理解することは、現代経済を読み解くカギになります。

社会全体のお金の量(マネーストック)が増える意味
銀行の「信用創造」によって、世の中に流通するお金の総量が増加します。
この「社会全体に供給されるお金の総量」を「マネーストック(またはマネーサプライ)」と呼びます。マネーストックは、現金と預金通貨の合計で構成され、経済活動の活発さを測る重要な指標の一つです。
日本銀行のような中央銀行は、このマネーストックの量を金融政策を通じてコントロールし、物価や通貨価値の安定を図るという重要な役割を担っています。中央銀行が供給する「マネタリーベース」(市中に流通する現金と、銀行が日本銀行に預けている当座預金残高の合計)が、信用創造の土台となります。
中央銀行は、このマネタリーベースをコントロールすることによって、経済全体の貨幣供給量を調節することができると言われています。「信用創造」が個々の銀行の活動にとどまらず、国全体の貨幣供給量に影響を与えるマクロ経済的な現象であることを理解することで、私たちは日々のニュースで耳にする「金融政策」や「物価」といった概念との繋がりをより深く理解できるようになるのです。
ごんぎつね(空想金融教室) | みずほフィナンシャルグループ
経済活動の「潤滑油」としての役割
信用創造は、経済活動の「潤滑油」ともいわれます。
「信用創造」によって世の中のお金の量が増えることは、企業は新しい設備に投資したり、従業員を雇ったり、新しい事業を始めたりするための資金を調達しやすくなっていることです。
もちろん、個人も住宅や自動車の購入など、大きな買い物をしやすくなります。買い物をしやすくなれば、消費や投資が活発になり、経済全体が成長する原動力になるというわけです。
また、経済活動を活発にさせるためには、「信用創造」でお金を生み出すだけではなく、お金がスムーズに素早く移動させることも大切です。そこで銀行の行っている「決済」が、経済全体のお金の流れをスムーズにし、お金が必要なところに効率的に届ける役割を果たします。
もし、銀行の決済機能が十分に働かなければ、経済は停滞し成長が難しくなるでしょう。スムーズな決済は経済の「潤滑油」のように機能します。
「信用創造」は、銀行の単なる技術的なしくみではなく、経済の成長エンジンとして働き、そして「決済」は、そのエンジンの力を社会全体に伝えるギアの役割を果たし、スムーズな経済活動を可能にしています。

信用創造と物価の関係:インフレ・デフレとのつながり
世の中のお金の量(マネーストック)の変動は、物価に大きな影響を与えます。
お金の量が増えすぎると、物の値段が上がる「インフレ」になる可能性があります。これは「貨幣数量説」という経済学の基本的な考え方に基づいています。
貨幣数量説では、貨幣の数量が増加すれば物価も上昇すると考えられています。生産能力の拡大がない状態で貨幣供給量を増やすと、その分一般物価が上昇し、インフレを招くとされています。
貨幣数量説 - Wikipedia
経済学の需要と供給の法則によれば、供給量が一定のままで需要が増加すれば、価格は上昇します。「信用創造」によって「通貨供給量」が増加すると、売り手は販売価格を上げざるを得ない状況になることがあります。これは、お金の価値が相対的に下がるためです。
例えば、日本の公債残高の対GDP比率が上限を超え、国債の海外消化が必須となった場合、大幅な金利上昇、円安、インフレが発生するリスクが指摘されています。
逆に「信用創造」が滞り、お金の量が減りすぎると、物の値段が下がる「デフレ」になる可能性があります。デフレは企業の収益を圧迫し、失業を増加させ、経済全体の活力を奪う深刻な事態です。
マネーサプライの変化が物価に影響を及ぼすまでには時間的なラグが生じることもあり、その影響は経済状況、特にインフレ期待の形成に依存します。中央銀行がマネーストックをコントロールする主な理由の一つは、この物価の安定を維持することにあります。信用創造は経済を活性化させる一方で、その過剰な拡大はインフレを招くリスクがあるため、適切な管理が不可欠なのです。
暮らしに役立つ身近なお金の知恵・知識情報サイト ─ 知るぽると:金融広報中央委員会
「信用収縮」とは?経済が停滞する恐れ
信用創造の逆の現象として、「信用収縮(Credit Crunch)」というものがあります。
これは、銀行が融資枠を縮小したり、融資基準を厳格化したりして貸し出しを減らすことで、世の中のお金の量が減っていく状態を指します。信用創造によって大きく膨らんだ信用が縮む局面であるため「信用収縮」と呼ばれます。
「信用収縮」が起こると、事業者は資金調達が困難になり、必要な投資を行うことができません。その結果、企業の業績が悪化し、さらに融資基準から遠ざかってしまうという悪循環に陥る可能性があります。中には、倒産や事業撤退に追い込まれる企業も出てくるでしょう。これは、経済全体の停滞や悪化を招く深刻な事態であり、デフレを加速させる要因にもなります。信用創造が経済成長のエンジンである一方で、信用収縮は経済を停滞させるブレーキとなりえます。
信用収縮 - Wikipedia

信用創造を理解するためのQ&A:よくある疑問を解消!
なぜ消費者金融は信用創造できないの?
銀行と同じようにお金を貸している消費者金融(例えば、アイフルや武富士といった企業)は、なぜ銀行のような「信用創造」ができないのでしょうか?
これは、多くの人が抱く素朴な疑問の一つです。
その理由は、消費者金融が銀行のように「預金口座」を持っていない点にあります。銀行が貸し出しによって新しい預金(銀行の負債)を生み出すことができるのは、借り手の口座にその金額を記帳することで、新たな「銀行預金」という負債を発行できるからです。
つまり、銀行は自らの貸し出しによって、同時に自らの負債である預金を生み出すことができます。一方、消費者金融は自前の預金口座を持っておらず、顧客の預金口座に自分自身の負債を発行することで融資を実行することは不可能です。そのため、消費者金融は、銀行と同じ意味で「信用創造による融資」を行うことはできず、既存の資金(例えば、銀行からの借り入れや自己資金など)を移動させることしかできません。
この違いによって、信用創造は「預金を取り扱う金融機関」に固有の機能であることがはっきりします。銀行が単なる貸金業者ではなく、金融システムにおける銀行の特別な位置づけ表しています。

銀行の「信用」がなぜそんなに大切なの?
信用創造という名前の通り、「信用」が非常に重要であると聞きますが、具体的にどのような意味合いを持つのでしょうか?
この「信用」は、信用創造システムが機能するために最も重要です。
信用創造のシステムは、銀行が健全に運営され、貸したお金がきちんと返済されるという「信用」の上に成り立っています。もし銀行が信用を失えば、預金者が一斉に預金を引き出そうとする「取り付け騒ぎ」が発生する可能性があります。
このような事態に陥ると、銀行は支払いに応じきれなくなり、金融システム全体に大きな混乱を招きます。これは、デジタル上の数字でしかない預金が、人々の信頼が失われた瞬間にその価値を失いかねないという、金融の根源的な弱さを示しています。
このため、銀行は常に健全な経営を維持し、中央銀行や政府も金融システムの安定に努めています。銀行の信用は、単に個々の銀行の存続に関わるだけでなく、社会全体のお金の流れ、ひいては経済全体の安定に直結する極めて重要な要素なのです。
信用創造の「からくり」は、実は非常に人間的な要素である「信頼」に深く依存しています、金融システムがこのようなふわっとしたバランスの上に立っていることを理解することは、自分たちの資産を守るためにとても大切です。

「無からお金を生み出す」って、本当?
銀行が「無からお金を生み出す」と聞くと、まるで無限にお金が作れるからくりのように感じます。本当にそうなのですか?
確かに銀行は「無からお金を生み出す」と言われますが、これは「現金や準備金が一切不要」という意味ではありません。貸し出しによって預金が生まれた後、その預金が引き出されたり、他の銀行に移動したりする際には、現金や準備金が必要になります。
例えば、借り手が融資されたお金を別の銀行の口座に振り込んだ場合、その銀行間で資金の移動(決済)が必要となり、その際に銀行間の準備金が動きます。銀行は、これらの支払いに備えて、常に適切な量の現金や準備金を保有・管理しています。
また、銀行の貸し出し能力は、「預金準備率」という法的な制約だけでなく、「自己資本比率(銀行が健全な経営を維持するために必要な自己資金の割合)」や「中央銀行の金融政策」、さらには企業や個人の実際の資金需要など、様々な要因によって制約されています。
例えば、定期預金のように引き出し時期が指定された預金は、銀行にとって安定した資金源となり、より安定的な運用(貸し出し)を支えることができます。これは、銀行が貸し出しを継続するための資金管理の重要性を示すものです。
したがって、「無からお金を生み出す」という表現は、分かりやすいために使われた言葉で、実際は銀行が既存の現金や預金を無制限に貸し出したり、無条件にお金を生み出せるという意味ではありません。
信用創造のメカニズムは、単なる「からくり」ではなく、厳密なルールと管理の下に成り立つ、現代金融の高度な技術なのです。
まとめ:信用創造を知ることは、経済を知ること
銀行の「信用創造」は、現代の経済システムを支える最も重要な機能の一つです。
銀行が単にお金を預かり、貸し出すだけでなく、社会全体のお金の量を増やし、経済活動を活発にする「からくり」のような力を持っていることを、この記事を通じてご理解いただけたでしょうか。
この仕組みを理解することで、日々のニュースで報じられる金融政策、物価の変動、経済の動向などが、より立体的に見えてくるはずです。例えば、近年進展している金融デジタル・トランスフォーメーションは、現金の利用を減らし、信用創造をさらに活発化させる可能性も指摘されています。これにより、増加した預金が経済活性化に貢献することが期待されています。
お金は私たちの生活に密接に関わるものです。
信用創造という銀行の「からくり」を知ることは、現代社会を賢く生き、経済の大きな流れを理解するための強力なツールとなるでしょう。
ぜひ、この知識を日々の経済活動や情報収集に役立ててください
参考文献
3時間目 | 政治・経済 | 一般社団法人 全国銀行協会 (zenginkyo.or.jp)
預金保険法 - Wikipedia
お金以前 土屋剛俊
ティモシー・テイラー 経済学入門