あなたは月々のスマホ代金をいくら払っていらっしゃいます?
少し高いな・・・と感じていませんか?
実は、日本の通信会社は、ドコモとau、そしてソフトバンクの3社で80%のシェアを占めています。
そのため競争が十分に働かず、価格が下がりにくい構造になっています。
最近、楽天モバイルも業界に参入しましたが、ドコモ、auそしてソフトバンク3社の牙城を崩すまでには至っていません。
ここでは、通信業界の構造について身近な例を使ってわかりやすく解説します。
通信業界の構造について知れば、どのように通信料が決まっているか分かりますし、毎日の費用を納得して抑えることができます。
ぜひ、通信料にお悩みの方ご覧ください!

3大キャリアという言葉を聞いたことがありますか?
毎月の通信料もっと抑えられたらいいのにと思っていらっしゃるあなた!
費用を抑えるために、まずは払っている業者について整理しておきます。
「3大キャリア」という言葉をよく聞くけど…
テレビCMや街の広告で、「ドコモ」「au」「ソフトバンク」という名前をよく目にしますよね。これらは日本の携帯電話サービスを提供している主要な3社で、「3大キャリア」と呼ばれています。
実は日本のスマホ業界は、この3社で大部分のシェアを占めています。
このような状態を、経済学用語で「寡占(かせん)」と呼んでいます。
寡占の「寡」は、わずかという意味で、例えば、口数が少ない人のことを「寡黙(かもく)」のように使われます。
つまり、わずかな企業に業界が占められている、そんな状態のことを「寡占」は指しています。
例えるなら…
例えば、街のパン屋さんを想像してみてください。
その街にはパン屋さんが3軒しかなく、ほとんどの人がその3軒のパン屋さんでパンを買っているとします。他のパン屋さんが参入しようとしても、材料の仕入れルートやお店の場所、宣伝など、様々な面でハードルが高く、なかなか新しいパン屋さんができないとします。
このような状態が、携帯電話業界の「寡占」と似ています。
寡占だと何が問題なの?
もしも、町にパン屋さんが3軒しかないと、お店同士で激しい値下げ競争が起こりにくくなります。お客さんは、多少高くてもその3軒で買うしかないからです。
携帯電話業界も同じで、3大キャリアが市場をほぼ独占しているため、大幅な値下げ競争が起こりにくく、料金が高止まりしやすいという問題があります。
具体的な例で見てみよう
- 料金プランが似ている
3大キャリアの料金プランを見てみると、データ容量や料金設定が似通っていることが多いことに気づくと思います。これは、競争が十分に働いていないため、各社が横並びの料金設定をしているためと考えられます。 - 乗り換えが面倒
キャリアを変更しようとすると、メールアドレスが変わったり、場合によっては端末のSIMロック解除が必要だったりと、手続きが面倒に感じる人も多いでしょう。これも、ユーザーがキャリアを乗り換えにくい要因の一つで、寡占状態を維持する要因となっています。 - CM合戦
テレビCMなどで、3大キャリアが派手な宣伝合戦を繰り広げているのを目にすると思います。これは、新規顧客を獲得するためというよりは、既存の顧客を囲い込むための戦略とも言われています。
街にほとんどお店がない場合、私たちはそのお店の「言い値」でモノを買うしかなくなります。
このように、ある業界の「寡占」はいくつかの問題があります。
もうすこし詳しく見ていきましょう。
寡占がもたらす3つの問題
もし、ある業界のシェアが少数の企業だけに独占されていたらどうなるのでしょうか?
そのような状態がいつまでも続くと、私たちは次のような3つの問題を抱えることになります。
- 価格の高止まり
企業間の競争が少ないため、各社は無理に価格を下げる必要がありません。
他社と足並みを揃えて高めの価格設定を維持することが容易になり、通信費の高止まりにつながります。 - サービス内容の画一化
競争が激しくないため、各社は斬新なサービスを開発したり、他社と大きく差別化を図るインセンティブが働きにくいです。結果として、どの会社のサービスも似たり寄ったりになり、消費者の選択肢が狭まってしまいます。 - 新規参入の困難
寡占状態の市場では、既存の大手企業が圧倒的なブランド力、顧客基盤、資金力を持っています。新規参入企業はこれらの壁を乗り越えるのが非常に難しく、市場に参入できたとしても、シェアを拡大するのは容易ではありません。
これが新規参入の困難につながっています。
シェアを数社の企業だけで占められてしまうと、料金やサービスが同じようになり、新しい業者が参入しにくい業界になってしまいます。
けれどそもそも、なぜ通信業界は競争が少ないのでしょうか?
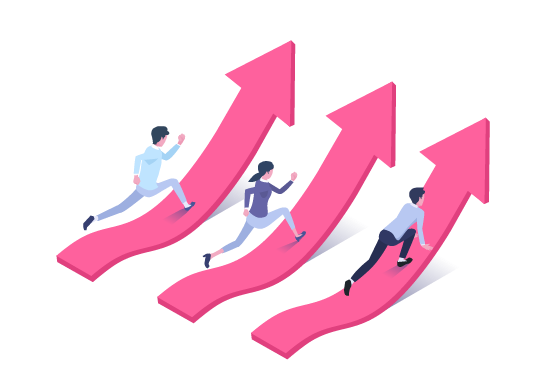
なぜ日本の通信市場は寡占になったのか?
日本の通信業界が寡占状態になっている原因は、通信業が始まった明治時代に遡ります。
- 歴史的経緯
日本の通信事業は、長らく日本電信電話公社(電電公社、現在のNTT)による独占体制でした。
その後、民営化によってNTTが分割されましたが、依然としてNTTグループは強い影響力を持っています。このような歴史的経緯から、新規参入が難しい状況が続いています。 - 巨額の設備投資
通信事業には、基地局などのインフラ整備に巨額の設備投資が必要です。
新規参入者は、既存の大手キャリアと同等のネットワークを構築するために巨額の資金を投じる必要があり、参入障壁が高くなっています。 - 電波の割り当て
電波は有限の資源であり、国によって割り当てられています。
新規参入者が事業を行うためには、電波の割り当てを受ける必要がありますが、既存の大手キャリアが既に多くの電波を保有しているため、新規参入者にとって十分な電波の確保が難しい場合があります。 - ブランド力と顧客基盤
大手キャリアは、長年の事業活動を通じて強固なブランド力と顧客基盤を築いています。
新規参入者は、これらの大手キャリアから顧客を獲得するために、大規模な広告宣伝や割引キャンペーンなどを展開する必要があり、これも参入障壁となっています。
通信事業のような、すべての人が必要なサービスで初期投資が高額になるような事業は、創立当初から国がその利益を独占しています。そのため、その後民営化されていても独占していた企業は大きく信頼もあるため、新規参入できたとしてもサービスや信頼性が低いと思われてしまったり、規制がかかっていたりして、なかなか思うように事業が展開しにくいのです。
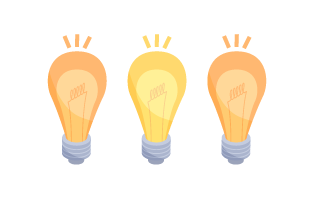
もっと安く便利に使うためにできること
通信業界のような規模の大きな事業には、なかなか新規参入が進まないという特徴があります。
しかし、通信業界が寡占状態にあることは、私たちにとって選択肢が限られ、価格競争が起こりにくい状況を生み出しているため、必ずしも良いこととは言えません。
このような状況を変えることはできないのでしょうか?
そんなことはありません、私たちにもできることがあります。
見ていきましょう。
消費者としてできること
私たちが不利益を被らないために、次のような行動が寡占状態に変化を促すことができます。
- 積極的に情報収集と比較検討
各社の料金プランやサービス内容を比較検討し、自分に最適なものを選択しましょう。
単にCMやブランドイメージだけで選ぶのではなく、実際の料金や通信速度、提供エリアなどを比較することが重要です。 - MVNOの利用を検討
MVNOは料金が比較的安く、多様なプランを提供しています。
大手キャリアにこだわらず、MVNOの利用を検討することで、市場の活性化に貢献できます。
MVNO(Mobile Virtual Network Operator、仮想移動体通信事業者)とは、簡単に言うと、大手キャリア(NTTドコモ、KDDI(au)、ソフトバンク)の通信回線を借りて、独自のブランドで通信サービスを提供している事業者のことです。ワイモバイル、UQモバイル、LINEMOなど多くの企業が参入しています。 - 消費者としての意見を発信
通信行政を管轄する総務省や消費者庁などに、料金の高止まりやサービス内容への不満などの意見を積極的に伝えましょう。SNSなどで情報発信することも有効です。 - 不当な行為には声を上げる
キャリアによる不当な囲い込みや、不透明な料金設定などがあれば、消費者センターなどに相談し、問題を指摘していくことが大切です。
企業としてできること
事業者側も、以下のような意識改革と行動が求められます。
- 新規参入の促進
大手キャリアは大手以外の企業が通信市場に参入しやすい環境を整えることが重要です。
そのためには、規制緩和やインフラの共有などが求められます。 - 革新的なサービスの提供
既存のサービスにとどまらず、消費者のニーズに応える新しいサービスや料金プランを開発することで、市場の活性化につながります。 - 公正な競争の促進
不当な囲い込みや優越的地位の濫用など、公正な競争を阻害する行為を排除することが重要です。
政府としてできること
政府は、以下のような政策を通じて、通信市場の競争を促進し、消費者利益の向上を図る必要があります。
- 規制緩和と市場の開放
新規参入を促進するために、周波数割り当ての見直しやMVNOへのインフラ開放などを進める必要があります。 - 競争政策の強化
独占禁止法を厳格に運用し、不当な行為を排除することで、公正な競争環境を整備する必要があります。 - 消費者保護の強化
消費者が安心してサービスを選択できるような情報開示の義務付けや、苦情処理体制の整備などが求められます。 - eSIMの普及促進
eSIMは、物理的なSIMカードが不要で、オンラインで簡単にキャリアを切り替えられるため、消費者の選択肢を広げ、市場の競争を促進する可能性があります。政府がeSIMの普及を積極的に推進することで、状況を変える一助となるでしょう。
大手通信業界は規模が大きく、とても太刀打ちできないように思えますが、これらの取り組みを、企業、政府が一体となって進めてきて私たちの通信費も諸外国のレベルにまで下がってきています。
私たち一人ひとりは消費者としては小さい存在ですが、日々の情報収集と比較検討、MVNOの利用検討、そして何よりも意見を発信していくことが重要です。一人ひとりの声は小さくても、それが集まることで大きな力となり、社会を変える原動力となります。
企業、政府そして私たちの選択によって、日本の通信市場における寡占状態を打破し、私たちにとってより良い環境を実現できると信じています。

まとめ
スマホ業界の「寡占」について解説しました。
寡占は少数の大企業がその業界のシェアのほとんどを占めている状態を言います。
日本の通信業界はドコモ、au、ソフトバンクの3社がほとんどを占めていて「寡占」状態になっています。
「寡占」の状態になっていると、価格競争が起きにくく、サービスが停滞し、新規参入が起きにくくなり、私たちは不利益を被ることになります。そのため政府や各企業そして私たちも「寡占」を見過ごさないようにしなければいけません。
企業の経営者はできるだけ競争は避けたいと思っています。
少ない利益を他の企業と奪い合うより、独占状態で大きな利益を受けながら、価格や生産数を自社の有利なように決められた方がずっとうれしいのです。
けれど、消費者にとっては「寡占」は好ましくありません。
競争が高まれば低価格で良いものが手はいるからです。
私たちは、いつも同じような会社の製品が目に入ると、つい安心して信用してしまいます。
けれどよく考えると、もしかしたらその会社が業種全体を占めていて競争相手が少ない状態になっていて目につきやすいだけなのかもしれません。
そして、企業は競争相手がいなければ価格を引き上げるので、もしかしたらその商品は不当に高い商品かもしれません。
通信業界でも最近は、政府の働きかけや規制緩和などによって新規参入が増え、状況は変化しつつあります。今後、市場の競争がより活発になり、ユーザーにとってより良いサービスや料金プランが提供されることが期待されます。
モノを選ぶとき、ちょっと「企業の競争」について考えてみてください。
もしかしたら、もっと良い選択肢が見つかるかもしれません。
参考文献
経済学入門 ティモシー・テイラー
業界の動向やランキング、シェアなどを分析-業界動向サーチ (gyokai-search.com)
スタティスタ – 世界の統計調査データを使い放題 | Statista
日本電信電話公社 - Wikipedia
