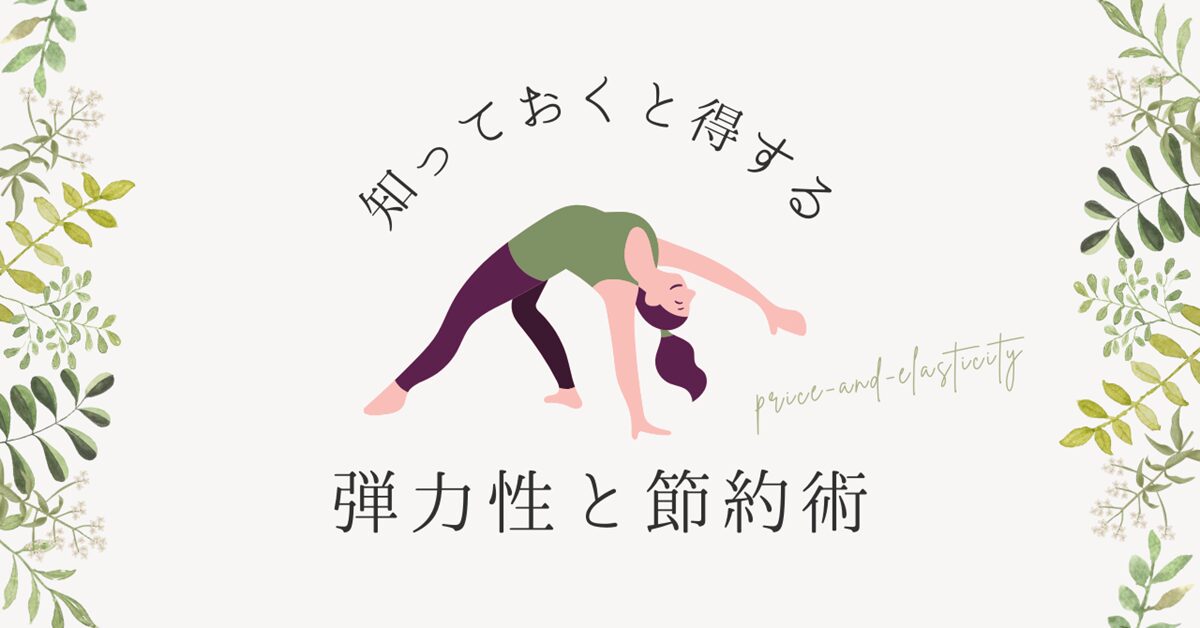あなたは、毎日生活費にお金がかかって欲しいものが、買えないな・・・とか
この間までもう少し安かったのに・・・
などと思うことはないでしょうか?
同じものなのになぜモノの価格は上下するのでしょうか?
原材料価格が高騰したからじゃないの?
それも大きな理由です。
けれどモノの価格が上下する理由はそれだけではないのです。
私たちがもつ欲しいという気持ちや、企業側が提供しようという気持ちが価格には大きく反映されています。
そして商品の種類によって、価格が上下すると、売り上げが大きく変化する商品というものがあることが分かっています。
経済学では、価格の変化が売り上げの数に与える影響のことを「弾力性」と呼んでいます。
「弾力性」とは簡単に言えば、価格が上昇すると、売り上げが大きく減少するような商品を「弾力性が高い商品」などと呼んで、企業の戦略の一つの指標として使うのです。
企業にとって重要かもしれないけど、私たち消費者にとっては関係ないのでは?
と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、そうでもありません。
企業がどのような戦略で価格をつけているのかを知れば、あなたはきっと次の買い物から、より厳しい目で商品を見ることができて、余計な買い物を避け、節約ができるようになるでしょう!
ぜひ「弾力性」の知識を身につけて、自分を守るツールを手に入れてください。
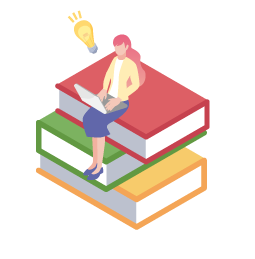
価格の弾力性とは
まず、モノの価格はどうやって決まるのでしょうか?
それをつくるときにかかったコスト、競合他社の様子、流通のコスト、商品のブランド力・・・などさまざまな要因が考慮されて決められます。
価格を考えるための要素の中でも一番重視されるのは、その商品を欲しい人の数(需要)と、その商品を提供する数(供給)です。この2つが釣り合ったところに価格は決まってきます。
価格の弾力性とは、簡単に言うと、商品の価格が少し変わったときに、その商品を買いたいと思う人がどれくらい増えたり減ったりするかを示すものです。
価格の変化と弾力性の関係は、次の3つにまとめられます。
- 価格が変化しても、欲しい人の数が変化しにくい商品(弾力性が低い)
- 価格が変化すると、欲しい人の数が大きく変化する(弾力性が高い)
- 価格は欲しい人の数と供給量に合わせて変化する(弾力性が等しい)
要するに、「お客さんは価格をどのくらい上げても平気で買ってくれるのか?」を販売者側が知るための一つの指標になっているのです。

価格が変化しても、欲しい人の数が変化しない(弾力性が低い)
もう少し詳しく見ていきましょう。
「価格が変化しても欲しい人の数が減らない商品」とはどんなタイプの商品なのでしょうか?
いくつかの例を挙げていきましょう。
1 生活必需品
- 食料品:米、パン、野菜、肉類など
- 水道代、電気代、ガス代などの公共料金
- 医薬品
- 住宅
これらの生活に欠かせない商品は、価格が多少変動しても購入を控えることができません。食料品の価格が多少値上がりしても、ある程度までは受け入れるしかありません。さらに大幅に値上がりしたとしても完全に購入をやめるということは難しく、食生活の内容を変更したり、節約で乗り切る、ということになります。
つまり、価格が上がったとしても、購入をやめるわけではないので「弾力性が低い」と考えます。

2 ブランド品
- 高級ブランドの衣料品、バッグ、時計など
- 高級車
ブランド品は、品質やステータス性などの付加価値が高い商品であるため、価格が多少変動しても購入する熱烈なファも多いです。むしろ、値上げによって希少価値が高まると考える消費者もいるでしょう。
熱狂的なファンはブランド品が値上がりしたとしても、購入をやめることは少ないので「弾力性が低い」と言われます。
3 嗜好品
- タバコ
- アルコール飲料
- ギャンブル
嗜好品は、習慣性や依存性がある商品であるため、価格が多少変動しても購入を控えることができません。
むしろ、値上げによって購入を抑制しようとする政府の政策に対して、反発する消費者もいるでしょう、つまり弾力性が低いと言われます。
4 医療サービス
- 手術
- ガン治療
- 透析
医療サービスは、生命や健康に関わる重要なサービスであるため、価格が多少変動しても利用を控えることができません。むしろ、高額な医療サービスでも、必要であれば受けるでしょう。
5 教育
- 大学教育
- 塾
教育は、将来のキャリアや人生に大きな影響を与える重要な投資であるため、価格が多少変動しても受けることを控えることができません。むしろ、高額な教育でも、将来の利益につながると考える親は多いでしょう。
このように、価格が値上がりしたとしても、それを買わないと生きていけなかったり、人生に大きな影響を与えるような商品は購入をやめるということができません。このような商品は「弾力性が低い」と呼ばれるのです。
ちなみに、ここに挙げた以外にも、弾力性が低い商品には戦争に使う「武器」があります。武器は他に代わりになるモノがないので、弾力性は低く売り手の言い値になり高額になります。
弾力性が低いことのメリットとデメリット
「弾力性が低い」商品は、企業にとって価格の変動の影響を受けにくいという大きなメリットがあります。
値上げをしたとしても、必ず買ってもらえる商品なので、企業はその利益を当てにして、今後の予定も立てやすくなります。そうすれば、企業は価格競争に巻き込まれにくく、安定的な収益を上げられます。
逆に「弾力性の低い」商品はデメリットもあります。
「弾力性が低い」商品は、クリスマスや正月などの、大きく売り上げを伸ばしたいときに、派手なセールなどをして値下げしたとしても、欲しい人が増加しないため、販売には工夫が必要となります。

価格が変化すると欲しい人の数が大きく変化する(弾力性が高い)
次に「価格が変化すると欲しい人の数が大きく変化する」ような商品はどんなものがあるでしょうか?
いくつかの例を挙げます。
1 嗜好品・贅沢品
- 高級ブランドの衣料品、バッグ、時計など
- 高級車
- 旅行
- 外食
- ジュエリー
一般的に贅沢品や嗜好品は生活必需品ではないため、価格が変動すると購入を控える消費者が多いです。
例えば、高級ブランドのバッグが値上げされると、別の安いバッグを購入したり、購入自体を先延ばしにする人が増えます。このような値上げが購入数に大きな影響を与える商品を「弾力性が強い」と表現します。

2 代替品が多い商品
- 食料品:米、パン、野菜、肉類など
- 日用品:洗剤、シャンプー、ティッシュなど
- 家電製品:テレビ、冷蔵庫、洗濯機など
お米ならパンに、牛肉なら鶏肉になどのように代替品が多い商品は、価格が変動すると、消費者は別の商品に代替しやすいです。代替品が多い商品は、価格を上げると消費者が他の商品に流れてしまうので、売り上げが大きく下がってしまいます。
このような商品を「弾力性が高い」と言います。
3 所得によって変化が大きい商品
- 高級住宅
- 高級外車
- ヨット
所得が上がると欲しいという気持ちが大きくなり、よく売れるようになる商品です。
例えば、高級住宅は、所得が高い人しか購入できないため、所得が上がると需要が大きく増加します。
このように所得の変化が購入に大きな変化をもたらす商品を「弾力性が高い」と言います。
4 短期的な変動が大きい商品
- ファッション 流行の最先端を行く衣料品など
- イベント: コンサート、スポーツ観戦チケットなど
短期的な需要変動が大きい商品は、一時的に需要が急増したり、急減したりする商品です。
例えば、流行の最先端を行く衣料品は、流行が過ぎると需要が急減します。
5 価格が比較的安価な商品
- 菓子パン
- ペットボトル飲料
- ファストフード
価格が比較的安価な商品は、消費者が気軽に購入できるため、価格が変動すると需要が大きく変化しやすいです。例えば、菓子パンが値上げされると、購入量を減らしたり、別の商品に代替したりするでしょう。
弾力性が高いことのメリットとデメリット
「弾力性が高い」商品は、企業の価格戦略の効果が大きいというメリットがあります。
例えば、値下げすれば、買ってくれる人が増える可能性が大きくなるからです。
逆にデメリットもあります。
石油価格の高騰などの原材料価格の高騰で値上げすれば、商品は売れなくなる可能性があります。そのため、企業は常に市場動向を注視し、適切な価格設定を行う必要があります。

弾力性がちょうど等しくなる
最後に、現実にはないのですが、価格が上昇した分、同じように欲しい人の数(需要)が同じように減っていく場合、また同じように提供する量(供給)が増える場合、「弾力性が一致している」と言います。
具体的にどんな状態なのか見ていきましょう。
- 価格に関係なく買う嗜好品
推しの商品など価格に関係なく購入する財・サービスなどは「弾力性が一致」している商品と言えます。
例えば、高級ブランド品、希少価値の高いコレクターズアイテムなどです。
価格が多少上がっても、欲しい人は他の商品を買うというわけにはいきません。
そのため、価格変化に対して比較的鈍感になり、弾力性が均衡すると考えられます。 - 期間が短い
短期間であれば、企業は生産量を大幅に増減することが難しいため、弾力性が一致する可能性があります。
例えば、農産物の場合、収穫量はある程度決まっており、短期間で増やすことはできません。そのため、価格が上昇しても、供給量は大きく変化しません。
また短い期間では、代替品を見つけたり、生活習慣を変えたりすることが難しいので価格の変化を受け入れざるを得ない場合などは、欲しい人と供給は一致します。 - 錯覚財
錯覚財とは、消費者が価格が高いほど質が高いと誤解している財・サービスです。
例えば、高価なワインや高級レストランなどが挙げられます。錯覚財の場合、価格が上がることが良い商品になったと勘違いするため、価格が変化しても売り上げに影響はほとんどない場合があります。 - 政府による価格統制
政府が価格を規制している場合、供給量と価格の関係は等しくなる場合があります。
例えば、公定価格制度では、政府が定めた価格でしか商品を販売することができないため、企業は価格を自由に設定することができません。
価格に弾力性がない場合、企業にとって重要な意味を持ちます。
弾力性のない商品は、価格を上げても売上は減少しないため、利益を最大化することができます。
しかし、あくまでも理論的な可能性であり、現実世界では様々な要因が複雑に絡み合い、供給量と価格の関係は常に変化しています。
私たちが弾力性を知る3つのメリット
価格の変化が、商品の売れ行きの上下にどのくらい影響するかを表す指標が「弾力性」でした。
「弾力性」の知識は消費者にとって企業戦略を見抜く上で非常に役立ちます。
なぜなら、価格の弾力性によって、企業がどのような価格設定戦略を取ろうとしているのか、また、その製品やサービスに対する消費者の反応をある程度予測できるからです。
価格の弾力性を知ることのメリットは、次の3つにまとめられます。
- お得な商品を見つけられる
価格弾力性の低い商品(価格を変えても需要が大きく変わらない商品)は、企業が価格を大幅に下げる可能性は低いと考えられます。逆に、価格弾力性の高い商品(価格が少し変わるだけで需要が大きく変わる商品)は、セールや割引などの価格変動が起こりやすい傾向があります。 - 品質の良い商品を選べる
一般的に、価格弾力性の低い商品は、新商品だったり、品質が高かったり、ブランド力があることが多いです。これは、価格を変えても需要が大きく変わらないため、企業が品質にこだわり、ブランドイメージを構築しようとしていると考えられるからです。 - 企業の戦略を予測できる
価格弾力性を分析することで、企業が新製品を発売する際に、どの程度の価格を設定するのか、また、競合製品との価格競争をどのように展開していくのかをある程度予測することができます。
このような価格弾力性に基づいた消費行動を取ることで、より少ない予算で欲しいものを賢く手に入れることができる可能性が高まります。もちろん、日々の買い物だけでなく、長期的な資産形成や経済状況の変化への対応など、幅広い場面で役立つ知識です。
弾力性はあくまで一つの指標であり、それだけで消費者の購買行動を完全に予測することができるわけではありません。
けれど、弾力性を知れば、企業の戦略を見抜き、より賢く、より満足のいく消費を行うことができます。また企業の置かれている状況からその収益の安定性を考えるときにも使える知識です。
あなたもぜひモノの値段を見たら、その価格の弾力性を考えてみてください。
きっとあなたの節約に役に立つはずです。
まとめ
値段が商品の売り上げ数に与える影響を計る指標「弾力性」について解説してきました。
値段が変化しても、売り上げ数に影響のない「弾力性が低い商品」
値段が変化すると、売り上げ数に大きな影響がある「弾力性が高い商品」
値段が変化すると、同じような比率で売り上げ数が変化するモノ「弾力性が等しくなる商品」
弾力性を理解すれば、企業の戦略を見抜くことができて、賢い消費活動に役に立てられます。
弾力性の低い商品は、ほとんど値下がりさせないので自分のタイミングで購入すると良いでしょう。弾力性の高い商品は、セールを頻繁に行うため、そのタイミングを狙って買い物すると安く買えます。
企業がどのような戦略を取ろうとしているのかを理解することは、企業の収益を考えるためにも重要です。
賢い消費と節約のために、ぜひ「弾力性」を理解して日常生活にお役立てください。
参考文献
ティモシー・テイラー 経済学入門