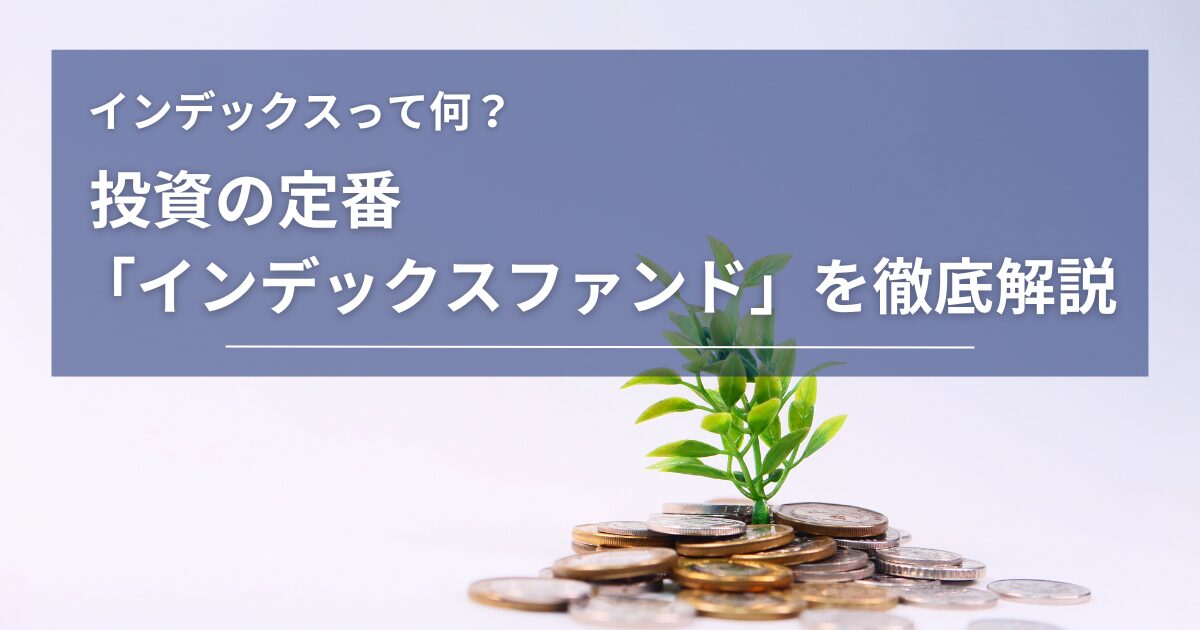「将来が心配なので投資をやってみたいけど、不安・・・」というあなたにご紹介したいのがインデックスファンドです。
インデックスファンドは「日経平均株価」や「ダウ平均株価」など、ニュースでよく耳にするような数字に連動している商品が多いので、ニュースを耳にすれば、自分の投資しているファンドの状況をイメージしやすく、身近に感じることができます
もちろん、身近に感じるからと言っても、リスクがないわけではありません。
けれど、もしも数字が下がってしまったとしても、その理由がニュースで解説されることも多く、理由が分からない不安を感じることは少ないです。
ここでは今、非常に人気の高まっているインデックスファンドを徹底解説します。
ぜひインデックスファンドを投資に活かしましょう!
インデックスファンド徹底解説
ところで、インデックスファンドとはなんのことでしょうか?
インデックスファンドの「インデックス」とは、英語では一般的に index と訳されます。index には、日本語の「索引」「指標」「指数」といった複数の意味がありますが、インデックスファンドの文脈では、主に 「指数」 の意味で使われます。
「ファンド」という言葉は、日本語では「基金」と訳され、幅広い意味を持つ言葉ですが、この場合は、一般の投資家から集めたお金を、指数に合わせて様々な資産に分散投資し、その運用成果を投資家に分配する金融商品を指しています。
インデックスファンドとは
つまり、インデックスファンドとは、ある指数に合わせて値が動く金融商品です。
その指数には、例えば「日経平均株価」「NYダウ」「S&P500指数」など金融商品によっていろいろ設定されています。その値動きと同じ動きをするしくみをつくった金融商品がインデックスファンドと呼ばれます。
インデックスファンドには、銘柄選定や売買判断などの運用コストがかからないので、手数料が低く抑えられてるため人気があるのです。

インデックスファンドの歴史
今では人気となったインデックスファンドの歴史を見てみましょう。
インデックスファンドの概念は1960年代にアメリカ出身経済学者のウイリアム・シャープによって提唱されました。
彼は、現代のインデックスファンドの理論の枠組みになっている「現代ポートフォリオ理論と資本資産価格モデル」を提唱し金融経済学に大きな影響を与えました。
その功績が評価され1990年にノーベル経済学賞を受賞しています。
シャープの理論は、それまでの投資理論と比べて、なにが新しく、画期的だったのでしょうか。
シャープ理論の新しさ
シャープ登場の前の投資理論は、投資のリスクといえば個々の業者にある「個別のリスク」例えば、一つの企業の業績の悪化、新製品の失敗、訴訟問題などがリスクとして考えられていました。
しかし、シャープは、投資のリスクとは「個別のリスク」以外にも、市場全体にある「市場のリスク」という大きなリスクに初めて注目しました。「市場のリスク」には、景気後退、金利変動、政治情勢不安など、市場全体に大きな影響をあたえるリスクが考慮されています。
今では当たり前のことですが、シャープは、そのリスクとリターンの関係を初めて明らかにしたことで投資理論に大きな貢献をしました。
1970年代以降のインデックスファンド
シャープによって提唱されたインデックスファンドの論理が、金融商品として発売されたのは、10年後の1970年代になってからです。
1970年代の米国のウォール街は、有名トレーダーの行うアクティブファンドが主流であり、運用者が独自の銘柄選定や売買判断によって市場平均以上のリターンを追求し実績をあげていました。
しかし、1970年代後半からアクティブファンドの運用成績が市場平均を下回る傾向が見られるようになります。その理由はさまざまですが、主な理由として挙げられるのは株価指数や債券指数などの指数の精度が上がり、市場全体の値動きを正確に反映するようになったからとも言われています。
そのような状況の中で、1971年、米国の資産運用会社ウェルスファーゴが機関投資家向けに最初のインデックスファンドを設立されます。初めニューヨーク取引所が取り扱っている1500銘柄すべて等しく組み入れたポートフォリオでしたが、維持管理が難しかったので、S&P500を時価総額比で組み入れるインデックスファンドを導入します。
続いて米国の投資家のジョン・ボーグル氏も、市場平均と同じ値動きを目指すインデックス投資を提唱します。ボーグル氏は、アクティブファンドの運用コストが高すぎること、そして、市場平均を下回ってしまう投資家が多いことを指摘し、インデックス投資こそが、長期的な資産形成に適した方法であると主張しました。
そして、1976年にボーグル氏はバンガード・グループを設立し、米国初の個人向けインデックスファンドを設定します。このファンドは、低コストで運用されるという特徴から多くの投資家に支持されインデックス投資の普及を後押しすることになります。
その後、インデックス投資は米国から世界へと広がり、日本では、1985年に国際投信委託(2004年11月5日金融庁より行政処分を受け業務停止。2015年7月1日、三菱UFJ投信と合併した)が、国内初のインデックス・ファンドを立ち上げたのです。
インデックス投資の歴史のまとめ
- 1970年代:アクティブファンドの運用成績が市場平均を下回る傾向が見られるようになる
- 1976年:ジョン・ボーグル氏がバンガード・グループを設立し、米国初の個人向けインデックスファンドを設定
- 1985年:日本で最初のインデックスファンドが設定
- 1990年代:インデックス投資の普及が加速
- 2000年代以降:インターネットの普及により、インデックス投資がより身近なものになる

インデックスファンドのメリット
インデックスファンドが人気なのは大きなメリットを感じる人が多いからです。
そのメリットから見ていきましょう。
- 分散投資が簡単
数多くの銘柄に一度に投資できるため、個別株のように特定の銘柄の株価が大きく下落しても、全体のリスクを分散できます。 - 低コスト
アクティブファンドと比較して、運用コストが低い傾向にあります。
これは、インデックスファンドが特定の指数に連動することを目指すため、銘柄選定などの手間が少ないからです。 - 長期的な成長
歴史的に見ると、株式市場は長期的に成長する傾向にあります。
インデックスファンドに投資することで、この長期的な成長の恩恵を受けることができます。 - シンプルでわかりやすい
特定の指数に連動することを目指すため、投資初心者でも値動きを把握しやすく、運用方針が分かりやすいです。
インデックスファンドのデメリット
もちらん、デメリットもあります。
- 市場平均のリターン
インデックスファンドは、市場全体の動きに連動するため、市場が下落すれば、インデックスファンドの価値も下落します。 - 大きなリターンは期待できない
アクティブファンドのように、市場平均を大きく上回るような高いリターンを期待することは難しいです。 - 元本割れの可能性
株式市場には常に変動リスクがあり、元本が保証されているわけではありません。
メリットもデメリットもあるインデックスファンドですが、長い目で資産形成を目的としている方や、投資初心者の方におすすめです。一方、短期的な大きなリターンを求めている方や、積極的に投資戦略を立てたい方は、アクティブファンドも検討するとよいでしょう。
インデックスファンド選びの具体的な手順
インデックスファンド選びは、投資の第一歩としてとても重要です。
初心者の方でも、次の7つステップを踏んでいけば、必ず自分に合ったインデックスファンドを選ぶことができます。
若干ステップが多すぎる気がしますが・・・
一つ一つ大切なステップですのでぜひ見ていってください。
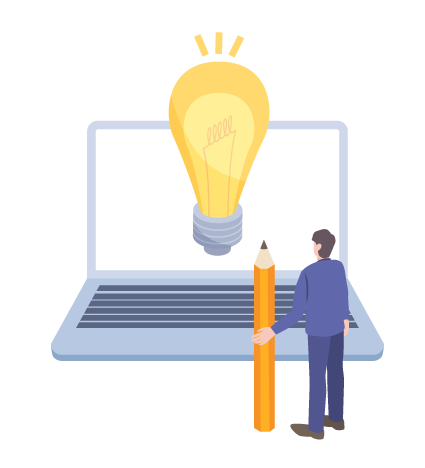
1. 投資の目的と期間を明確にする
- なぜ投資をするのか
老後資金の準備、住宅購入資金の積み立てなど、目的を明確にすることで、必要な金額や期間がわかります。 - どのくらいの期間投資を続けるのか
短期的な投資なのか、長期的な投資なのかによって、選ぶべきインデックスファンドが変わってきます。
2. 投資できる金額を決める
毎月どれくらいの金額を投資に回せるか考えてみましょう。
無理のない範囲で、継続できる金額を設定します。
3. 投資対象を選ぶ
次に、投資対象はどうしたら良いのか、考えてみましょう。
- 国内株式
日本企業に投資したい場合。日本を応援したいとか、安心感が得られます。 - 海外株式
世界の成長に投資したい場合。力強く成長している海外を選べば高い利益が望めるかもしれません。 - 全世界的株式
世界全体の株式に分散投資したい場合。全世界に広げればリスクは分散される可能性があります。 - 債券:安定した収入を得たい場合。
4. インデックスファンドの種類を知る
インデックスファンドにもたくさんの商品があります。
自分にはどんな商品が良いのかイメージしておくと商品選びで迷子になりません。
- 株式型:株式に投資するファンド。利益が高いことが多いです。
- 債券型:債券に投資するファンド。株式に比べると利益は低いです。
- バランス型:株式と債券の両方に投資するファンド。
5. 比較検討するポイント
一つ一つの商品には多くの注意書きが書かれています。
どんなことに注目するべきでしょうか?
- 信託報酬:運用にかかる費用で、低いほど良い。
- 購入手数料:ファンドを購入する際にかかる手数料。
- 最低投資額:初めての投資額。
- 過去のパフォーマンス:過去のデータは将来の成績を保証するものではありませんが、参考にはなります。
6. 証券会社を選ぶ
銀行や郵便局、ネット証券など多くの窓口があります。
- 取扱商品:自分が選びたいインデックスファンドを取り扱っているか。
- 手数料:取引手数料や信託報酬が安い証券会社を選ぶ。
- 情報提供:投資に関する情報が充実しているか。
7. つみたてNISAを活用する
株式投資には、購入時には税金はつきませんが、解約時に利益が出たら税金を払う必要があります。その税金の優遇策としてNISAがあります。ぜひ利用しておきましょう。
- 非課税投資:投資で得た利益が非課税になる制度。
- 初心者におすすめ:NISAは長期的な投資に適しており、初心者でも始めやすい。
インデックスファンドを選ぶときのコツ
- 過去のパフォーマンスに振り回されない
過去の成績が良いからといって、将来も必ず良い成績になるとは限りません。 - 分散投資
複数のインデックスファンドに分散投資することで、リスクを軽減できます。 - 長期投資
短期的な値動きに一喜一憂せず、長期的な視点で投資を続けることが大切です。
具体的な選び方としては、
- 初心者向け
日経平均株価連動型のインデックスファンドや、世界全体の株式に分散投資するインデックスファンドがおすすめです。 - リスク許容度が高い方
ある程度のリスクが受け入れられる方は、成長性の高い新興国の株式に投資するインデックスファンドも検討できます。
インデックスファンド選びは、ご自身の投資目標やリスク許容度に合わせて、慎重に行うことが大切です。焦らず、自分に合った商品を選び、長期的な視点で投資を続けていきましょう。
※注意:投資は元本保証ではありません。ご自身でよく調べて、ご自身の判断で投資を行ってください。
まとめ
インデックスファンドについて解説しました。
インデックスファンドとは、ある指数に合わせた動きをする金融商品です。
日経平均株価やダウなどの指数を参照して、その比率に合わせて組み合わせ、値動を指標と同じように動くよう調節します。個別の株に投資するのと違って値動きの上下が少なく、リスクが低いのが特徴です。
インデックスファンドの論理は、1960年のアメリカの経済学者ウイリアム・シャープの論理から始まりました。個別銘柄への投資のリスクと市場全体のリスクを分けて考えて、投資家がリスクをどの程度許せるのかを計算し、効率的なポートフォリオを構築することを目標にしています。
インデックスファンドが実際に金融商品として発売されたのは、1970年のアメリカです。アクティブファンドの成績が悪くなってきたのを境にウェルスファーゴ、バンガード社などが次々とインデックスファンドを発売しました。
自分一人では指数全体の株をすべて購入することは、コストがかかるのでできませんでしたがインデックスファンドならコストも低くまたリスクも抑えられるということもあり、多くの人に支持され世界中に広がります。
インデックスファンドは、その低コスト、シンプルな運用方針、そして市場全体のリターンを追求する戦略により、長期的な投資手段として広く支持されています。
インデックスファンドを選ぶときには、自分の投資する目的、その期間、金額、自分のリスクの許せる範囲をはっきりさせてから始めましょう。
参考文献
お金以前 土屋剛俊
国際投信投資顧問 - Wikipedia
発足から40年を迎えるインデックスファンド—その軌跡と今後の展開— (toushin.or.jp)
ウィリアム・フォーサイス・シャープ - Wikipedia
インデックスファンド - Wikipedia
資本資産価格モデル - Wikipedia