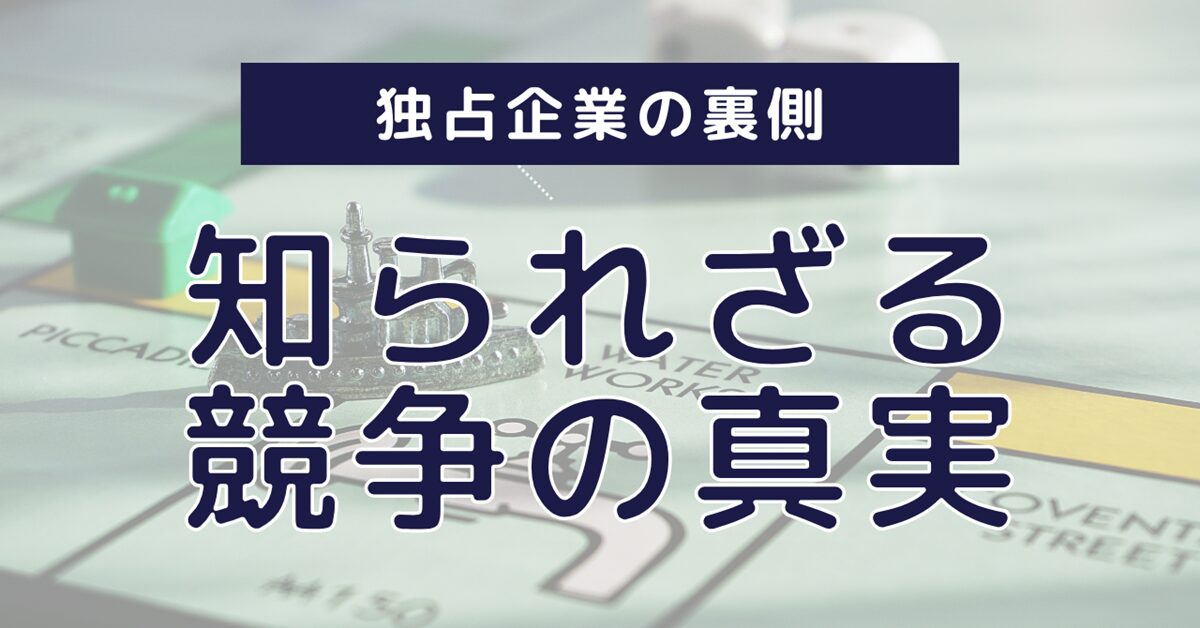あなたのスマホの基本ソフトは何を使っていらっしゃいますか?
iPhone でしょうか?
Android でしょうか?
日本のスマホ基本ソフトの市場は、世界的な傾向と同じように、事実上米国の2社が占めています。
具体的には、AppleのiOSとGoogleのAndroidが市場のほぼ全てを占めていています。
「選択肢がないな・・・」と感じたことはないでしょうか?
企業にとって競争相手が少ないのは、収益率を高く設定できるので大きなメリットがあります。
けれど、どんな業種でも儲かっていれば、必ずライバルが出てくるはずです。
なぜ、一つの業界を特定の企業が独占し続けられるのでしょうか?
その秘密を解き明かしていきましょう。
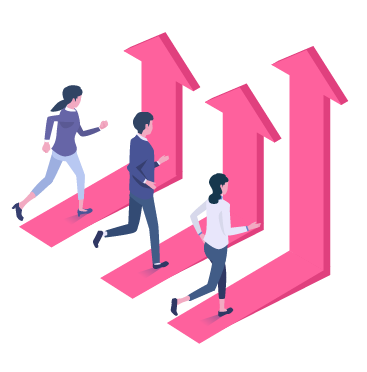
独占ってなんですか?
スマホの基本ソフト業界は2社が独占しているので「寡占」と呼ばれる状態になっています。
「寡占」についてはこちらを参照していただくことにして、ここでは「独占」について徹底解説していきます。
こちらもCHECK
-

-
スマホ料金はなぜ高い?通信業界の寡占構造を徹底解説
あなたは月々のスマホ代金をいくら払っていらっしゃいます?少し高いな・・・と感じていませんか? 実は、日本の通信会社は、ドコモとau、そしてソフトバンクの3社で80%のシェアを占めています。 そのため競 ...
続きを見る
独占とは
「独占」とは、ある市場で、一つの企業が圧倒的な力を持っていて、他の企業がなかなか参入できない状態を指します。
つまり、ある特定の産業や市場で、他の競争相手がほとんど存在せず、その企業が市場を支配している状態です。
例えば、その企業だけがお店を開いていて、他のお店がない状態を想像してみてください。お客さんはそのお店で買うしかないので、お店側は値段を自由に決めたり、サービス内容を決めたりすることができます。
もう少し詳しく「独占」を説明するために、いくつかのポイントに分けて解説します。
- 競争相手がいない、または非常に少ない
独占状態では、他の企業が市場に参入するのが非常に難しく、事実上競争がありません。これは、特許や技術的な優位性、莫大な資金力、政府の規制など、様々な要因によって引き起こされます。 - 価格支配力
競争相手がいないため、独占企業は商品の価格を自由に設定することができます。需要と供給のバランスで価格が決まる通常の市場とは異なり、独占企業は利益を最大化する価格を設定しやすいです。これが「独占価格」と呼ばれるものです。 - 市場への影響力
独占企業は、商品の供給量や品質、販売方法など、市場全体に大きな影響力を持っています。消費者は選択肢が限られているため、独占企業の決定に従わざるを得ない状況になります。
独占状態は、企業の経営戦略や市場の状況、法律など、様々な要因によって発生する複雑な現象です。
上記の説明で、独占とはどういうことか、大まかに理解できたかと思います。
独占企業の具体例:マイクロソフト
次に、ある市場を独占している具体的な例を見ていきましょう。
ソフトウェア業界の多くを占めている、世界的な企業の「マイクロソフト」があります。
マイクロソフトは、1990年年代後半から2000年代初頭にかけてWindows OSやOfficeなどのソフトウェア製品で市場を独占していました。独占禁止法違反の疑いで、米国やEUから複数の訴訟を起こされたこともあり、マイクロソフトは、これらの訴訟において、一部の行為について違反を認め、罰金を科されています。
けれど2023年現在、マイクロソフトの独占状態は、徐々に緩和されています。Windows OSのシェアは低下していますし、GoogleやAppleなどの競合企業もソフトウェア製品でシェアを伸ばしています。
競争を阻害した罪に問われたマイクロソフトですが、クラウドコンピューティングやゲームなどの分野で強力な地位を築いています。そのため、今後も完全に独占が崩壊する可能性は低く、一定のシェアを維持し続ける可能性は高いと考えられます。
独占企業の具体例:郵便局
日本では国の専売事業として始まった、いわゆる「郵便局」は、業務の一部を独占していることで有名です。
郵便局はたくさんの業務を行っていますが、その中の「第一種郵便物(書簡、葉書、はがき、ゆうパケット、ゆうパックなど)」事業を独占しています。第一種郵便物における国内シェアは、2023年3月時点で約99.9%です。2位の佐川急便は約0.1%で、日本郵政グループと2位の差は約99.8%もあります。
日本郵便は、2007年に民営化されましたが「郵便法」により、日本郵政グループが第一種郵便物の取扱を行うことが義務付けられています。新規参入には一定の条件を満たす必要があり、参入許可には高い障壁があるため今後も日本郵便の独占が続くと考えられます。
独占が起こりやすい3つの要因
そもそも、なぜ市場を独占するということが起こるのでしょうか?
独占は起こりやすい要因というものが知られています。
- 自然独占
自然独占とは人為的な要因ではなく、経済的な要因によって自然に発生する独占のことです。
事業の規模が大きければ大きいほど利益が大きくなる事業によく見られます。
例えば、自動車工場をつくるには巨額な費用が掛かります。
工場で生産量を増やすためには小規模の工場よりもより大きい工場の方が一台当たりのコストが下がります。いったん大規模な投資によってつくられた事業が動き出すと、新たに参入することが困難です。初めに規模で負けてしまうと、利益を握られてしまってそれを覆すことが簡単にできません。
自然独占は水道や電気などの公共サービスによく見られます。
大規模に整備されてしまうと、次に参入するのが難しい状態になり特定企業の独占を生むことになります。 - 技術的優位性
技術的優位性とは、ある企業が他の企業よりも優れた技術力や製品を有している場合を指します。
例えば、マイクロソフトは、Windows OSやOfficeなどのソフトウェア製品において、技術的優位性を有しており、独占状態を維持しています。 - 政府による規制
政府による規制とは、政府が特定の企業に対して、市場の独占を許可したり、新規参入を制限したりすることです。例えば、先ほどの郵便局は、「郵便法」に基づき、法的に第一種郵便物の取扱を独占しています。
また「特許」も新規参入を阻む障壁になっています。
「特許」とは有用な発明をした人は、一定期間その発明を独占的に使用しうる権利を国が一定期間付与するものです。
例えば、ある企業が新薬を製造する特許を取得したら他の企業はその薬に手を出すことはできません。少なくとも特許期間はその企業が市場を独占することになります。
一定期間ある企業が市場を独占することで、さらなる新薬の開発が促進される面もありますが、高い代金を払わなくてはいけません。人々の利益と引き換えに技術の進歩を促すというトレードオフが存在しています。
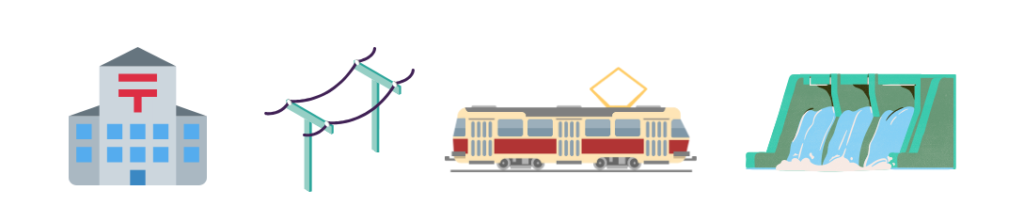
独占のメリットとデメリット
このように企業が市場を独占していることはデメリットだけではなく、メリットもあります。
独占のメリット
- 高い利益の確保
競争相手がいないため、企業は自由に価格を設定できるので、高い利益を上げることが可能です。 - 継続的な利益の確保
安定した利益が見込めるため、長期的な事業計画を立てやすくなります。 - 研究開発への投資
豊富な利益を研究開発に投資することで、技術革新や新製品開発を促進できます。 - ブランド力の強化
市場を独占することで、企業のブランドイメージを高めることができます。 - ニッチな市場の開拓
他の企業が参入しないような小規模な市場でも、独占によって利益を上げることが可能です。
独占のデメリット
- 価格の高騰
競争がないため、企業は価格を高く設定しがちなので、消費者は不利益を被る可能性があります。 - 品質の低下
競争がないため、品質改善のインセンティブが働きにくくなります。 - 技術革新の停滞
競争がないため、技術革新のスピードが遅れる可能性があります。 - 消費者の選択肢の減少
市場に一つの企業しか存在しないため、消費者は商品やサービスを選ぶことができません。 - 不当な取引の可能性
独占的な地位を利用して、下請け企業などに不当な取引を強いる可能性があります。
独占は「市場の失敗」をもたらす可能性があります。
「市場の失敗」とは、市場のメカニズムが十分に機能せず、資源の最適な配分が実現されない状態のことです。独占によって価格が高騰したり、品質が低下したりすると、消費者は不利益を被り、経済全体の効率も低下します。
そのため、多くの国では独占禁止法などの法律によって、過度な独占を規制しています。日本では、公正取引委員会が市場を監視し、独占的な行為を取り締まっています。
ただし、独占が常に悪いとは限りません。
例えば、創業間もない企業が新しい技術や製品を開発し、一時的に市場を独占することは、イノベーションを促進する上で重要な役割を果たします。
また、公共性の高い事業(例えば、水道や電気など)は、独占によって効率的なサービス提供が可能になる場合もあります。
重要なのは、独占がもたらすメリットとデメリットを総合的に判断し、適切な規制を行うことです。
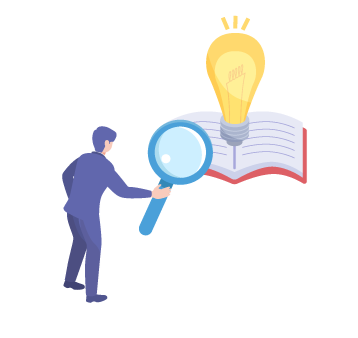
独占禁止法の役割
業界がある企業に独占されることを防止し、祖のデメリットを最小にするために「独占禁止法」という法律が多くの国で制定されています。「独占禁止法」の役割と基本的なルールについて見ていきましょう。
独占禁止法の4つの目的
独占禁止法(正式名称:私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)は、自由で公正な競争を促進し、消費者の利益を守り、経済の健全な発展を促すことを目的としています。
その目的は次の4つにまとまられます。
- 自由な競争の促進
市場では、企業が自由に競争することで、より良い商品やサービスが提供され、価格も適正になると考えられています。独占禁止法は、この自由な競争を阻害する行為を排除して、市場の活性化を図ります。 - 消費者の利益の保護
企業間の競争が活発になることで、消費者はより多くの選択肢の中から、より良い商品やサービスをより安く手に入れることができます。独占禁止法は、このような消費者の利益を保護する役割があります。 - 経済の健全な発展
自由で公正な競争は、企業のイノベーションや効率化を促進し、経済全体の活力向上につながります。独占禁止法は、このような経済の健全な発展に貢献しています。 - 民主的な市場経済の維持
特定の企業が市場を支配することを防ぎ、中小企業を含む様々な事業者が自由に活動できる環境を整備することで、民主的な市場経済を維持します。
独占禁止法の基本的なルール
独占禁止法は、主に以下の3つの行為を規制しています。
- 私的独占の禁止
ある企業が、他の企業の活動を排除・支配して、競争を実質的に制限することを禁止しています。
具体的には、次のような行為が該当します。- 他の企業を市場から排除する行為
(例えば、不当に低い価格で販売し、競合他社を追い出すなど) - 他の企業の事業活動を支配する行為
(例えば、他の事業者の株式を過半数取得し、経営を支配するなど)
- 他の企業を市場から排除する行為
- 不当な取引制限(カルテル・談合)の禁止
複数の事業者が、価格や販売数量などを共同で取り決めることを禁止しています。- カルテル
複数の事業者が、商品の価格、生産量、販売地域などを協定すること。 - 談合
入札において、事前に落札者や落札価格を決定すること。
これらの行為は、価格の高止まりや供給量の減少を招き、消費者の利益を損なうため禁止されています。
- カルテル
- 不公正な取引方法の禁止
他の事業者の競争を不当に阻害する行為は禁止しています。- 共同の取引拒絶(ボイコット)
複数の事業者が、特定の事業者と取引しないことを合意すること。 - 再販売価格の拘束
メーカーが小売業者に対し、商品の販売価格を指示し、自由に価格を決めさせないこと。 - 優越的地位の濫用
取引上で優位な地位にある事業者が、その地位を利用して不当に不利な条件を押し付けること。
例えば、下請業者に対して不当な値下げを要求するなどが該当します。
- 共同の取引拒絶(ボイコット)
独占禁止法違反に対する措置
独占禁止法に違反した場合、公正取引委員会による排除措置命令や課徴金納付命令などの行政処分が科されるほか、刑事罰(罰金や懲役)が科される場合もあります。
また、被害を受けた事業者から損害賠償請求をされる可能性もあります。
独占禁止法は、市場経済において非常に重要な役割を果たしています。
自由で公正な競争が確保されることで、消費者はより良い商品やサービスをより安く手に入れることができ、経済全体の活力も向上します。企業は独占禁止法を遵守し、公正な取引を行うことが求められます。
さらに詳しく知りたい方は 公正取引委員会 を参考にしてください。
独占が私たちに与える影響と対策
企業が市場を独占した場合、私たちの生活に様々な影響が及びます。
その具体的な影響と、私たちが日頃から気を付けるべきことをまとめました。
市場独占による生活への影響
- 価格の高騰
競争がないため、その企業は自由に価格を設定できます。
そのため、消費者は不当に高い価格で商品やサービスを購入せざるを得なくなります。 - 品質の低下
競争がないため、企業は品質向上への努力を怠る可能性があります。
消費者は質の低い商品やサービスを受け入れざるを得なくなるかもしれません。 - 選択肢の減少
独占企業は、自社製品以外の商品を市場から排除しようとする可能性があります。
消費者の選択肢が狭まり、多様なニーズに応えられなくなる可能性があります。 - イノベーションの停滞
競争がないため、企業は新しい技術やサービスの開発に意欲を失う可能性があります。
技術革新が遅れ、社会全体の進歩が阻害される可能性があります。
不利益を避けるためにできること
企業の独占は大抵の場合、私たちに不利益になります。
それを避けるためにもちょっとした気遣いで、不利益を避けることができます。
- 情報収集と批判的思考
特定の企業が市場を支配している場合、その企業の行動や価格設定に注意を払い、批判的に評価することが重要です。 - 代替品の探索
独占企業の商品やサービスに依存せず、代替品や他の選択肢を探す努力をしましょう。 - 消費者運動への参加
消費者団体や市民運動に参加し、独占企業の不当な行為に対して声を上げることも有効です。 - 政府の規制への関心
独占禁止法などの政府の規制に関心を持ち、その適切な運用を求めることも重要です。
独占状態は、必ずしも全ての場合に悪影響を及ぼすわけではありません。
例えば、初期投資が非常に大きい事業や、公共性の高い事業(水道や電気など)では、独占状態が効率的な場合もあります。
しかし、そのような場合でも、政府による適切な規制や監督が不可欠です。
市場の独占は、私たちの生活に大きな影響を与える可能性があります。
日頃から情報収集を怠らず、批判的な視点を持ち、必要に応じて行動を起こすことが、消費者として重要な姿勢と言えるでしょう。
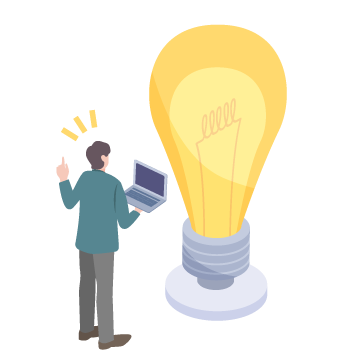
まとめ
企業の独占について見てきました。
ある市場で、一つの企業が圧倒的な力を持っていて、他の企業がなかなか参入できない状態を指します。
「独占」が起こりやすいのは鉄道や通信、郵便、水道、電気などの初期投資が大きくなりがちで多くの人が必要とするサービスによく現れます。このような事業は古くから政府が先に押さえていることも多く、規制がかけられ新規の事業者が入りにくくなっています。
ある市場を独占している企業は、価格を自由に設定できるでの価格が高くなりやすく、競争相手もいないので品質も落ちがちになります。これは、消費者にとって不利益です。
このような問題が起こらないように、多くの国では「独占禁止法」が設定され、競合他社との競争を阻害するような行為は違法になっています。
ある市場を企業が独占することにはメリットもあります。
独占していればその事業の規模が大きくなりやすいため、その利益も莫大になります。そしてその潤沢な利益を使って、さらなる技術革新が進みやすくなります。
しかしデメリットもあります。
企業が価格設定を自由にできることから、経営の効率化が進みにくく、競争の必要性がないため品質の悪化や新製品の開発に消極的になります。
新しい技術を使った商品はその利益を一定期間独占することはやむを得ないですし、水やガス、電気のような公共性の高いものは一つの企業が独占していた方が効率が良いです。
けれど多くの場合、企業が市場を長期間独占していることは、私たちにとって不利益になります。
損な不利益を受けないように、日頃から価格の設定について注意し、批判的な心を持つことが大切です。また、おかしいと思ったら代替品を探すことも有効です。
もちろん「独占禁止法」という法律に興味を持ち、不当な行為を見つけたら声を上げることも大切です。
参考文献
pmi.com
特許 - Wikipedia
ティモシー・テイラー 経済学入門