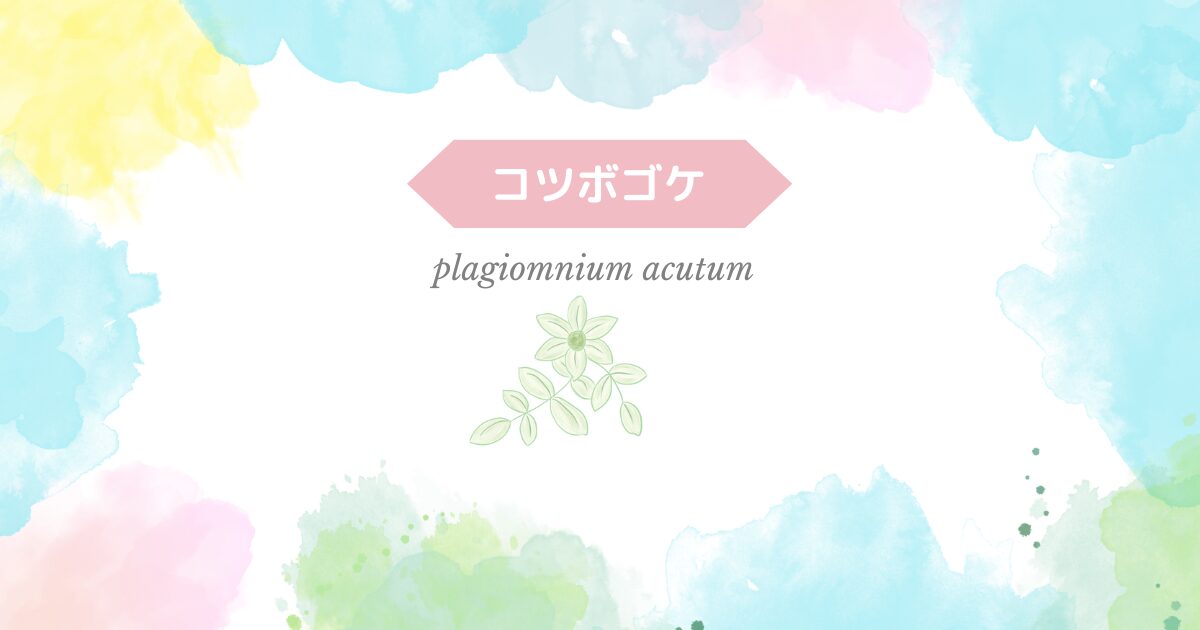コケを見ているとなんだかほっとしませんか?
もしも、心を和らげてくれるコケの名前が分かったらもっと楽しいのに・・・・
とあなたも感じているかもしれません。
でも・・・コケの見分け方って難しいですよね?
コケは葉っぱだけではなく、体全体も小さくて、見分け方が本当に難しいです。
でも実は、コツボゴケはコケの中でも大きくて特徴のある葉をもっているので、苔の中では見分け方はやさしいです。
コツボゴケは日本全国に広く分布しています。
都会にも普通に見られるので、ぜひ見つけてみませんか?
ここでは、コツボゴケの特徴を徹底解説します!
ぜひ、身近なコツボゴケに出会って楽しんでください!

透き通るような葉が印象的なコツボゴケ
コツボゴケはまるで緑の宝石のような愛らしい苔です。
日の当たりにくい場所にひっそりと透明感のある葉を広げています。
苔の見分け方は難しいですが、コツボゴケの葉は5mmほどで、しっとりとした場所で這うように茎をのばしたり、直立させたりしています。
コツボゴケは踏まれやすい場所は好きではありません。
踏まれにくく安定していて、日光が当たることの少ない少し湿った場所が好きです。
コツボゴケは、数年から数十年かけてゆっくり成長します。
もしも、コツボゴケに覆われた庭があったら、そこは、長い間同じような環境を保っている静かな環境ということが分かります。
コツボゴケは雄の株と雌の株があります。
それぞれの株から精子と卵ができます。
雄の株から成熟した精子は、雨などを利用して卵細胞まで泳いでいきます。
そして、精子が卵細胞まで到達できれば受精が行われます。
受精が行われた雌株は胞子がつくられる「胞子体」に成長します。
「胞子体」の先には、胞子を入れる壺のような「さく」と呼ばれる場所ができます。
「さく」の中の胞子は大きくなっていき、成熟すると飛び出します。
生育するのに適した場所を見つけられた胞子は糸のように伸びて発芽します。
そして新しいサイクルが始まります。
コツボゴケは、小さな昆虫や小動物の避難所や餌となる場所となります。
また、ちょっとした踏み付けや、汚染や環境の変化に対して敏感に反応するため、その存在や状態から環境の健康を示すバロメーターになります。

出会いたい!コツボゴケの見分け方
コツボゴケを見分けるには、葉に注目すると簡単です。
上の写真をご覧ください。
コツボゴケの葉は、ふっくらとしたたまご型をしていて、透き通るような透明感があります。
踏まれることのない安定した日影に、キラッとした5ミリほどの丸い葉が見えたらコツボゴケかもしれません。
コツボゴケの葉は、横に広がったり、立ち上がったりして成長します。
そして、条件が良いと、まるで緑色の絨毯が敷き詰められたような、美しい景観を作り出します。日本全国の低地や都市部でも見ることが出来、山沿いのお寺の庭や散策路などでも見つけることができます。
実は、コツボゴケの中には、ダニやトビムシなどの昆虫、小さなカタツムリなどの小さな生き物が生活していることがあります。私たちにとって小さくなんて事のないコケですが、小さな生き物にとっては、青々とした自分を守ってくれる生活の場所なのかもしれません。
あなたも、ミニチュア動物園のような、苔の世界を覗いてみてはいかがでしょうか?
この小さな宝石のようなコケが、あなたの散歩コースにも彩りを与えてくれるかもしれません。
参考文献
じっくり観察特徴がわかるコケ図鑑 大石善隆 ナツメ社
野外観察ハンドブック 校庭のコケ 中村俊彦 古木達郎 原田浩 全国農村教育協会
日本の野生植物 コケ 平凡社