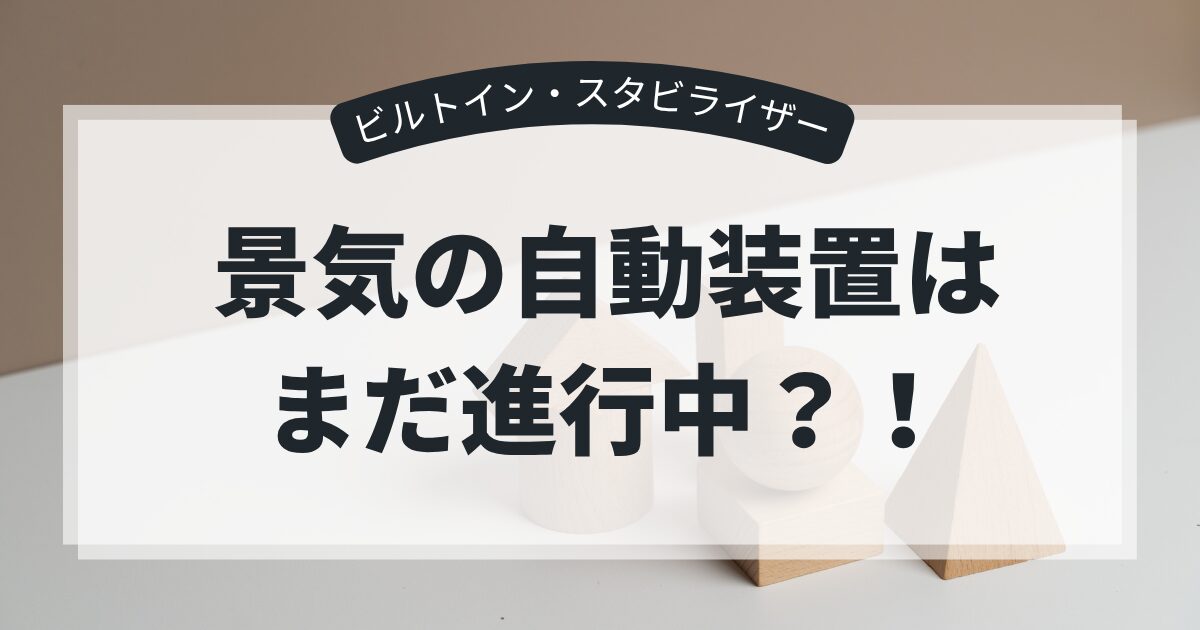なにかと批判の絶えない政府の景気対策ですが、実は政府が積極的に対策を行わなくても自動的に景気が調整されるしくみがあります。
それがビルトイン・スタビライザーというしくみです。
ビルトイン・スタビライザーとは、自動安定化装置とも呼ばれ、景気が悪くなると自動的に総需要を増やす方向にはたらき、景気が良くなると総需要を減らす方向に働くようなしくみのことを指します。
ここではそんな、積極的に法律を改正するような派手さはありませんが、確実に行われる景気対策「ビルトイン・スタビライザー」について詳しく解説します。

ビルトイン・スタビライザーとは?
ビルトインスタビライザー(Built-in Stabilizer)とは、経済学、特にマクロ経済学や財政政策の分野で用いられる専門用語です。日本語では「自動安定化装置」と訳されます。
学校で経済学を専攻したり、経済に関する専門的な議論に触れたりする機会がなければ、日常生活で耳にする機会は少ないかもしれません。
ビルトインスタビライザーは、ある特定の政策を指すのではなく、既存の税制や社会保障制度に「内蔵されている」るもので、景気の変動を緩和する機能を指します。
例えば、所得税の累進課税制度や失業保険制度は、ビルトイン・スタビライザーが設計されている政策です。景気が過熱すれば税収が増えたり、失業者が減ってたりして給付が減って景気を抑制できます。逆に、景気が悪化すれば税収が減ったり、失業者が増えたりして給付が増え景気を下支えします。
このような、景気の行き過ぎを抑え、社会のバランスを保つような設計のことを「ビルトインスタビライザー」と呼んでいます。
つまり意識的に「景気対策としてビルトインスタビライザーを導入しよう」といわれるのではなく、政策の効果から「結果的に」生じるものです。そのため、政策決定の場でこの言葉が直接的に使われることはあっても、一般のニュースなどで頻繁に解説されることは少ないのかもしれません。

ビルトインスタビライザーの具体的な例
日々変化する私たちの生活の安定を支えるには、ビルトイン・スタビライザー(Built-in stabilizer)のような、常に制度上バランスが保たれるように設計しておくと、景気の変化に柔軟に対応できます。
具体的な見ていきましょう。
まずは所得税があります。
所得税
所得税は所得が多くなれば多く支払い、少なければ少なくてよいという「ビルトイン・スタビライザー」の典型的な設計になっています。
例えば、社会全体の景気が拡大している場合、心配なのはインフレです。
人々の給料が上がらないのに、モノの値段が上がり生活が厳しくなる社会は避けなければいけません。このようなとき政府がとる対策の一つが、税金を上げることです。税金を上げて人々が使えるお金を減らしてしまうことがインフレ対策には有効です。
今の日本の所得税は、人々の所得が上昇してくると自動的に税金が増える設計(累進課税性)になっています。(5%から最大45%)
累進課税はなぜ導入されているのでしょうか?
「高所得者は、ずるいのでたくさん税金をとっておこう」ということではありません。景気が良くなり多くの人の所得が増えた場合、景気の過熱を抑えるために税金を増加させ景気の過熱を抑制する働きがあるためです。
個人的には、自分だけ多くお金を持っていたとしても「景気を左右させることはないので、たくさん税金を払う必要がない」と思いますが、不動産価格や賃金、株などは上昇するときは皆一斉に上昇しているので、全体を見ると物価の上昇を招いている可能性があります。
なので所得税を所得が増えていくと割合が高くなっていく制度は、景気の過熱を冷やすことに有効に働きます。
逆に、景気が悪くなったときは、税金を下げて人々にもっとお金を使ってもらうことが有効な対策になります。
景気が後退してきたとき、累進課税を取っていれば、わざわざ税制を変えなくても、自然と納める税金は少なくなり自動的に税金は減ります。そして社会保障給付などの支出が増加するので、今度はこれが景気刺激策となり、景気回復を促進する方向に働きます。
このようにシーソーのように景気の安定をはかる政策を「ビルトイン・スタビライザー」が利いている政策といえるのです。

社会保障:失業保険・生活保護
次に社会保障制度はどうでしょうか?
失業保険や生活保護などの社会保障制度は、景気が良ければ生活保護や失業手当を必要とする人は少なく社会保障費が減っていきます。
逆に、景気が悪いときは、失業者や貧困層が増え社会保障費の支出が増えます。
実は、この支出が総需要に貢献し景気を刺激させることができるのです。
つまり、失業保険や社会保障制度は、低所得者を中心とした困窮層への経済的な支援が、ビルトイン・スタビライザーとして働きます。
具体的には、次にあげる4つのメカニズムが働きます。
- 自動的な所得再分配
社会保障制度は、所得の高い層から低い層への自動的な所得を再配分します。
景気後退時には、高所得者の収入減少にともなって、社会保険料全体の収入も減少します。逆に失業者や低所得者向けの社会保障給付は増加する傾向にあります。
この結果、所得格差が縮小し、低所得層の購買力低下を抑制する効果が生まれます。 - 消費の維持・拡大
低所得者層は、収入の大部分を消費に回すため、彼らの購買力維持は、景気回復にとって重要です。つまり、社会保障給付は、低所得者層の消費を支える重要な役割を果たします。
特に、医療費や介護費などの生活必需品にかかる支出を軽減することで、低所得者層の生活を安定させ、消費活動を下支えします。
例えば、生活保護制度では生活困窮者に対して、食費や住居費、医療費などの生活費を支給はこれは、最低限の生活必需品の購入を可能にし、経済全体の需要を下支えする効果があります。 - 経済活動へのインセンティブ付与
社会保障制度は、病気や失業、老後などのリスクに対して備えるためのセーフティネットを提供することで、国民が安心して経済活動に参加できる環境を作り出します。
例えば、国民年金制度は老後の生活資金を準備するための制度です。老後の生活が保障されていることで、国民は安心して働いたり、起業したりすることができます。 - 財政支出の増加
景気後退時には、政府は社会保障制度を通じて、財政支出を増加させます。これは、公共事業への投資と同様に景気刺激効果をもたらします。
例えば、公共事業では道路や橋などのインフラ整備を行うことで、雇用創出や経済活性化を図ります。
このように、社会保障制度は不況時に自動的な所得再分配、消費の維持・拡大、経済活動へのインセンティブ付与、財政支出の増加という4つのメカニズムを通じて、経済全体の安定化に寄与するビルトイン・スタビライザーとして機能します。
ただし、社会保障制度の持続可能性を確保するためには、景気回復時には財政支出を抑制するなど、適切な財政運営が必要となります。
このように、政策にビルトイン・スタビライザーが設計されていれば、自動的に景気を調整することができます。
ちなみにビルトイン・スタビライザーとは反対に、政府が状況判断して政策を実行する場合は「裁量的な財政政策」や「積極的な財政政策」または「デマンドマネジメント」などと呼ばれます。
ビルトイン・スタビライザーは、あらかじめ税制のルールに組み込まれている対策のため、より早く景気の安定効果を得ることが出来るため多くの国で採用されています。

ビルトイン・スタビライザーのメリットとデメリット
政府の自動的な財政政策(ビルトイン・スタビライザー)にはどんなメリットとデメリットがあるのでしょうか?
メリット
- 迅速な対応
制度さえできていれば自動で経済状況の変化に迅速に対応できるため、景気後退やインフレなどの問題を迅速に解決することができます。 - 透明性
政策ルールが事前に定められているため、政策の透明性が高く、国民や企業が経済状況を予測しやすくなります。 - 政治的バイアスの排除
政治的圧力から影響を受けずに、客観的な経済指標に基づいて政策が決定されるため、政治的バイアスの影響を受けにくいというメリットがあります。 - 財政規律の強化
自動的な財政規律ルールを設けることで、政府の財政出動を抑制し、財政赤字や債務の累積を防ぐことができます。
デメリット
- 経済状況の誤判断
経済指標が必ずしも経済状況を正確に反映しているわけではないため、誤った判断に基づいて政策が進んでいく可能性があります。 - 根本的な問題解決にならない
景気悪化の原因はその時々で違います。自動的な財政政策は人々に与える影響をいくらか和らげることが出来ますが、根本的な解決にはなりませんし、その原因への対策にもなりません。 - 政治的責任の希薄化
政治家が財政政策の決定に関与していないため、政策の失敗に対する政治的責任が希薄化してしまう可能性があります。 - 技術的な複雑さ
自動的な財政政策を設計し、実行するには高度な技術が必要であり、コストがかさむ可能性があります。 - 政治との相性の悪さ
一番大きな問題として政治との相性の悪さがあります。
つまり景気の良いときに財布のひもを締め、景気の悪い時には気前良くお金を使う。という政策が人々の感情として相容れないものになるからです。
景気が良くて政府にお金がたくさん入っているときに、お金を使わずに黒字をなるべく多くして、支出を削って増税する政策。逆に景気が悪い時にどんどんお金を使う政策は「市民から税金の無駄遣い」また「せっかくの景気に水を差すな」といった批判を浴びやすいです。
各国のビルトイン・スタビライザー
メリットもデメリットもある、政策のビルトイン・スタビライザーですが、初めに設計しておけば景気の安定化に貢献できるということで、ほとんどの国で導入されています。
ビルトイン・スタビライザーの大きさは、国の経済規模や財政制度によって異なります。
一般的に北欧諸国や欧州大陸諸国では自動安定化機能が大きく、アメリカや日本などの国では比較的小さい傾向があります。近年では、財政規律の強化や景気循環への柔軟な対応などを理由に、ビルトイン・スタビライザー(自動安定化機能)を縮小する国もあります。
- アメリカ
2017年に制定された税制改革法により、法人税率が大幅に引き下げられた結果財政赤字が拡大した結果、自動安定化機能が縮小。 - 日本
2014年に消費税率が8%に引き上げられたことで政府の歳入が増加しましたが、同時に景気減速懸念も高まり自動安定化機能が縮小。
一方、自動安定化機能が大きいとされる国としてはドイツ、スウェーデンがあります。
- ドイツ
憲法に財政規律に関する基本法が定められており、歳出と歳入の均衡を義務付けています。
また、景気後退時には景気刺激策を講じることが可能ですが、財政赤字が一定の水準を超えると自動的に歳出削減措置が発動される仕組みになっています。 - スウェーデン
政府は、景気変動に応じて財政支出を自動的に調整する「予算枠」と呼ばれる制度を導入しています。
予算枠は、政府の歳出と歳入の最大限度を定めたものであり、景気後退時には歳出枠を拡大することで景気を刺激し、景気拡大時には歳出枠を縮小することで財政赤字を抑制することができます。
このように、全ての国は財政政策を講じていますが、自動安定化機能の大きさは国によって異なります。近年では、財政規律の強化や景気循環への柔軟な対応などを理由に、自動安定化機能を縮小する国も増えています。
自動的な財政政策の有効性は、政策の設計と運用に大きく依存します。高度に専門的知識が必要なこの制度の組み立てについては、まだ発展途上の分野です。
近年では、人工知能などの技術を活用した、より高度な自動的な財政政策の開発も進められています。ビルトイン・スタビライザー(自動安定化機能)の研究は、まだまだ発展途上の分野であり、今後もさらなる研究が必要な分野なのです。
まとめ
政府の政策で景気に合わせて柔軟に税率や支援を変えられる、自動的な財政政策(ビルトイン・スタビライザー)について解説しました。
政府が行う財政政策には、ビルトイン・スタビライザーが利いているような、自動的にルールが変更できるような「自動的な財政政策」と、積極的に政府が政策案を立てる「裁量的な財政政策」があります。
「自動的な財政政策(ビルトイン・スタビライザー)」とは、景気が良いときは、所得の高い人から税金を多くとり、景気の悪い時には低所得者に向けて社会保障費を充実させることで、景気の安定をはかります。
「自動的な財政政策」のメリットは、政策そのものがルールに組み込まれているので、政策実行は自動で行われ、時間はかからず迅速に対応できます。また、ルールが明確に決まっているため分かりやすく状況を判断しやすいことや、政治家の圧力を受けにくいメリットがあります。
しかし、デメリットも多く、経済指標が必ずしも経済状況を正しく判断したものではない可能性があること、根本的な原因に基づいた対策でないため効果が限定的なことや、そもそもルール作りが難しいこと、そして景気の良いときに財布のひもを締め、悪い時に財布を緩めるという考え方自身が、一般的な心情を考えると難しいことが挙げられます。
自動的な政策のルール作りはまだまだ発展の途上にあり、これといった正解がまだありません。最近ではAIを使ったより高度な政策の開発も進められ、これからのさらなる研究が期待されています。
「自動的な財政政策」と「積極的な財政政策」は、車の二つの車輪に例えることができます。
どちらか一方だけが機能しても車は前に進みません。経済状況を的確に判断し、状況に応じて二つの政策を適切に組み合わせることで、経済を安定かつ持続的に成長させることができます。
財政赤字と債務残高の増加や、政策効果の不確実性、国・地域間の政策協調など、様々な課題が議論されています。これらの課題を克服し、二つの車輪のバランスを最適化することが、今後の財政政策の重要なテーマとなるでしょう。
この記事を読んで、もし皆さんの心の中に「こんな政策があれば、もっと安定するんじゃないか?」「こんな仕組みはどうだろう?」といった新しいアイデアの種が一つでも芽生えたなら、ぜひご意見をお寄せください。
未来のより良い社会を形作るために、この「見えない安定装置」について、これからも一緒に考え、楽しんでいきましょう。
参考文献
ティモシー・テイラー 経済学入門
日本銀行 Bank of Japan (boj.or.jp)
ビルト・イン・スタビライザー - Wikipedia