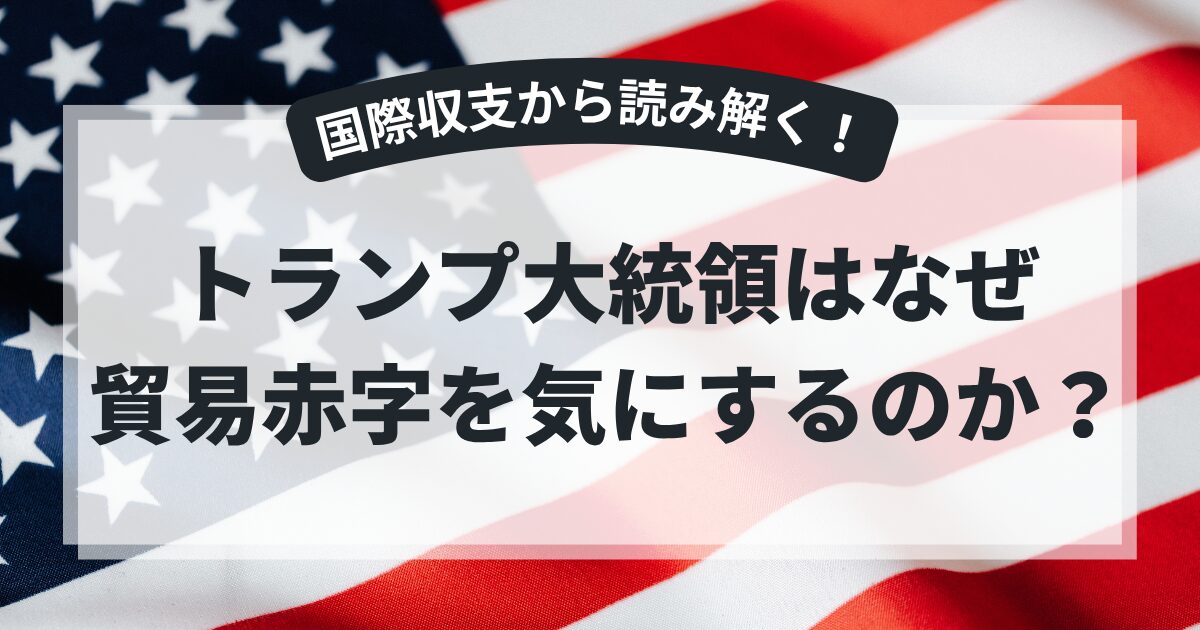はじめに:トランプ大統領はなぜ「貿易赤字」を気にするのか?
あなたも最近のニュースで「貿易赤字」という言葉を耳にしない日はないかもしれません。
特にドナルド・トランプ前大統領は、この言葉を頻繁に使い、まるで「悪者」のように扱う姿が印象的ですよね? 彼はなぜこれほどまでに貿易赤字を問題視するのでしょうか?
トランプ大統領は、自国の貿易赤字を「敵」にすると公言してきました。
彼は、輸入相手国が黒字(つまり米国が赤字)であれば、その国に「トランプ関税」を課すと息巻く一方、対米貿易赤字の国(例えばオーストラリア)には関税適用免除を検討するといった具体的な行動を示しています。こうした姿勢は、彼の掲げる「アメリカ第一主義」という政策思想の根幹をなすものです。
ここでは、トランプ大統領が貿易赤字を問題視する背景にある考え方を掘り下げつつ、経済学の視点から「貿易赤字」が本当に「悪」なのか、そして「国際収支」という大きな枠組みの中でどのように捉えるべきかを、家計簿に例えながら分かりやすく徹底解説していきます。
そもそも「貿易赤字」って何?トランプ氏の言い分
まずは「貿易赤字」という言葉について確認しておきましょう。
そんなことわかっているよ、と言う方は飛ばしてください。
貿易赤字の基本定義
「貿易赤字」とは、ある国が外国から輸入するモノやサービスの金額が、輸出する金額を上回っている状態を指します。
例えば、アメリカが日本から100兆円分の商品を輸入し、日本へ80兆円分の商品を輸出している場合、アメリカの対日貿易赤字は20兆円になります。これは、日本から見れば日本の対米貿易黒字が20兆円あるということになります。
トランプ大統領が問題視する理由
トランプ大統領が貿易赤字を問題視する主な理由は「アメリカ国内の製造業の縮小に伴って雇用が減少しているのは、貿易赤字が原因である」と考えているためです。
そして「貿易赤字」が国内産業の衰退や、アメリカから外国への「富の流出」につながっていると主張しています。その解決のため、この先の10年間で2,500万人の雇用創出を目指し、貿易赤字の縮小をその対策の一つと位置づけているのです。
特定の国への言及も目立ちました。特に中国との貿易赤字が巨額であり、トランプ政権は中国に対して高関税を課すなどの政策を実行しました。
また、日本に対しても自動車や農産物の輸入を問題視し、「対日貿易赤字をゼロにしたい」と述べています。
そして「貿易赤字」を是正するための手段として、彼は関税を重視しました。
例えば、日本の自動車の安全基準の見直しなどを迫ったり、米、肉、ジャガイモなどの農産物の輸入拡大を促したりしています。

トランプ氏の貿易観の重商主義
トランプ大統領の貿易に対する考え方は、16世紀から18世紀にかけてヨーロッパで主流だった「重商主義」の思想に非常に近いです 。
「重商主義」とは、国が豊かになるためには、輸出を最大限に増やし、輸入を制限することで、国内に金銀などの富を蓄積すべきだという考え方です。トランプ氏の政策は、消費者利益や税収の確保よりも、米国企業の業績改善を重視していることを示唆しており、これは重商主義者が生産者の利益を重視し、高い雇用水準と賃金で生産者を支えようとする姿勢と一致します。
彼は、輸出を増やし輸入を減らすことが、アメリカの雇用を増やし、国を豊かにすると信じているようです。
しかし、彼の貿易政策には、経済合理性だけではない政治的な動機も含まれている可能性が指摘されています。
例えば、経済学では、関税率の引き上げが社会全体の厚生を悪化させるにもかかわらず、政府が政治献金を社会厚生よりも重視するほど、関税率が高くなるという見方があります。
また、日本の自動車安全基準の見直し要求のように、経済的な根拠が「全くない」と指摘されるような要求も存在し、これは経済的合理性よりも政治的な圧力が背景にある可能性を示唆しています。
さらに、トランプ政権が長期目標として掲げたアメリカの1.2兆ドルもの貿易赤字を「ゼロにする」という目標は、経済学的には非現実的かつ非効率的であると考えられています。
そもそも、貿易収支がゼロになるべき経済的な理由は存在しません 。
国によって得意な製品や天然資源、人的資源が異なるため、それぞれが得意な分野に特化し、自由に貿易を行うことで、世界全体と各国がより豊かになるというのが、現代経済学の基本的な考え方である比較優位の原則です。輸入を減らせば米国経済が良くなるという発想は、経済学の観点からは誤りであると指摘されています。
重商主義 - Wikipedia
比較優位 - Wikipedia

「国際収支」で見る貿易赤字の全体像:家計簿に例えてみよう
貿易赤字をより深く理解するためには、「国際収支」という大きな枠組みで考える必要があります。
国際収支とは、ある国と外国との間で行われるすべての経済取引を記録した統計のことで、いわば「国の家計簿」のようなものです。
国際収支の主要な構成要素
国際収支は主に「経常収支」「資本移転等収支」「金融収支」「誤差脱漏」の4つの項目で構成されます。
- 経常収支(生活費・日々の稼ぎ)
モノやサービスの取引、投資からの収益、援助や送金など、日常的な経済活動によるお金の出入りを記録します。- 貿易収支(給与からモノの購入費をひいたもの)
モノの輸出入の差額(輸出-輸入) - サービス収支(旅行費・通信費・交通費などのサービス費の差)
旅行、輸送、特許使用料など、サービスの取引の差額。
例えば、外国人観光客が日本でお金を使えば日本にとっては収入(プラス)となり、日本人が海外旅行でお金を使えば支出(マイナス)となります。 - 第一次所得収支(貯蓄からの利息収入・株式の配当金など)
海外への投資から得られる配当金や利子、あるいは海外からの投資への支払いなど。 - 第二次所得収支(経常移転収支)(仕送り・贈与・寄付など)
国際機関への拠出金や、個人間の送金など、対価を伴わないお金のやり取り。
- 貿易収支(給与からモノの購入費をひいたもの)
- 資本移転等収支(無償の援助)
固定資産(インフラなど)の無償援助や債務免除など、対価を伴わない資本取引。
家計簿で言えば、例えば「実家からの住宅購入費の援助」や「借金の肩代わり」のような、一度に大きな額が動く無償のやり取りに近いかもしれません。他の値に比べると小さな値です。 - 金融収支(預貯金の増減、株式・債券の購入・売却、不動産の売買、借入金・返済など)
株式や債券への投資、工場建設などの直接投資といった、お金そのものが国境を越えて動く取引を記録します。海外の企業への投資は「株式購入」、海外からの借り入れは「借金」というイメージです。 - 誤差脱漏(記入漏れ)
非公式な取引やデータ収集の限界、また国によってデータの扱いが違うこと、各国の時間差などから、帳簿にずれが出てきます。その差額を誤差脱漏として計上して帳尻を合わすことができます。

国際収支の恒等式:「経常収支+金融収支=ゼロ」の不思議
国際収支統計には、「経常収支+資本移転等収支-金融収支+誤差脱漏=0」という恒等式が成り立ちます 。これは、国の家計簿の「収入」と「支出」はいつも必ず一致するという、一見すると不思議な関係です。
これは、家計なら使いきらなかった予算は貯蓄に回したり、もし予算が足りなければ借金したり貯金を切り崩したりしますが、国際収支では収入と支出はいつも一致する関係にあるということになります。
詳しく見ていきましょう。
一般的な家計簿での「収入と支出の一致」
家計簿と国際収支は大きく見ると似ていますが、違う点もあります。
それは、国際収支と家計簿では「収入」と「支出」の定義が少し異なるのです。
「収入」と「支出」の違いを理解するためには「何が収入で、何が支出なのか」という定義と、その裏側にある資金の流れを深く掘り下げて考える必要があります。
詳しく見ていきましょう。
家計簿では、例えば「収入(給料)30万円」と「支出(生活費)25万円」の場合、残りの「5万円」は「貯金」や「預貯金残高の増加」として扱われます。
この場合・・・
- 収入30万円
- 支出25万円
- 貯金5万円
となって、収入と支出は一見一致していません。
そこで、貯金(貯蓄)を支出側に加えて、収入30万円 = 消費支出25万円 + 貯蓄5万円 と考えると両者を一致させることができました。
つまり、収入は「消費に充てられた部分」と「貯蓄に回された部分」に分けられる、と捉えることができます。
なぜこんな考え方をしなければいけないのかと言うと、この家計簿でいう「貯蓄」が、国際収支における「金融収支」の役割と似ているのです。
国際収支における「収入」と「支出」、そして「金融収支」
先ほどにもありましたが「国際収支」には
経常収支 + 資本移転等収支 - 金融収支 + 誤差脱漏 = 0
という恒等式が成り立ちます。
資本移転等収支と誤差脱漏は比較的小さな値なので、式をもっとシンプルにすると
経常収支 - 金融収支 = 0
と言う式が成り立ちます。
経常収支は、売り上げとして得たお金から、買ったものを引いた値です。
もし、経常収支が黒字(プラス)であれば、その国は海外から、モノやサービス、投資収益などで「余分にお金を受け取った」ことになります。
逆に、経常収支が赤字(マイナス)であれば、その国は海外へ、モノやサービス、投資収益などで「余分にお金を支払った」ことになります。
そこで「金融収支」がポイントになります。
金融収支は、海外との間での「資金そのものの動き」のことです。
海外の株式を買ったり、海外の銀行にお金を預けたりして、海外に投資すること、これは、国内のお金が海外に流れていくことを意味します。金融収支では、国内のお金が海外に流れていくことを「マイナス」と表現します。
例えば、経常収支がプラス(貿易黒字)なら、そのプラスのお金は、必ずどこかに投資されマイナスの金融収支を生み出します。つまり、日本が貿易黒字になれば、外貨(ドル)を、国内の銀行(日本銀行)に預けます。そしてその外貨は、海外の投資て使われるものとみなされマイナスで表現されます。
逆に、海外からお金を借りたり、海外の投資家が、国内の株式を買ったりすること、これは、海外のお金が国内に流入することを意味します。国内にお金が流れ込んでくることを「金融収支」では「プラス」と表現します。
例えば、経常収支がマイナス(貿易赤字)であればその穴埋めとして、どこかからお金を持ってこなければなりません、それはプラスの金融収支を生み出すことになるのでプラスと表現されます。つまりもし貿易赤字なら、その足りない分を海外から借金をしてお金を貸してもらう、アメリカならドルが国内に流入するということになります。
初めに紹介した、国際収支の恒等式の「金融収支」の符号が「マイナス」だったのは、国内からお金が「流出」するとマイナス、国内に「流入」するとプラスという考え方に基づいているからです。(IMFの国際収支マニュアルのルールに則っています)
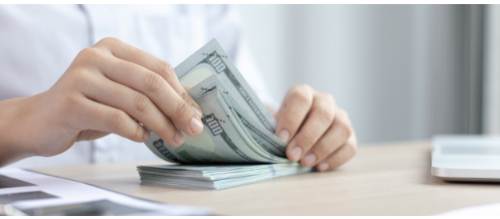
ポイントは金融収支
経常収支の赤字と黒字は、金融収支のプラス(負債増加)またはマイナス(資産増加)として必ず現れるということを、もう少し詳しく見ていきましょう。
例:日本が海外に車を売って100億円の黒字(経常収支プラス100億円)になったとします。
この100億円は、どこに行くでしょうか?
日本の企業がその100億円で海外の企業の株を買う(金融収支の資産増加、つまりマイナス100億円)
日本の銀行が海外の銀行に預金する(金融収支の資産増加、つまりマイナス100億円)
海外から借金を返済してもらう(金融収支の資産減少、つまりプラス100億円)
つまり、経常収支の黒字は、その国が海外に対して「貯蓄」をしたことと同じであり、その貯蓄は「海外の資産を増やす」または「海外からの借金を減らす」という形で金融収支に現れます。
家計簿で言えば、「収入 - 支出 = 貯蓄」ですが、この「貯蓄」を「お金の使い道の一つ」と捉えると、「収入 = 消費(支出)+ 投資(金融収支に当たるお金の動き)」と見ることができます。
経常収支の赤字(マイナス)は、金融収支のマイナス(資産減少)またはプラス(負債増加)として必ず現れる。
例:日本が海外から100億円のモノを買って赤字(経常収支マイナス100億円)になったとします。
この100億円は、どこから来るでしょうか?
海外からお金を借りる(金融収支の負債増加、つまりプラス100億円)
過去に海外に投資した資産を売却する(金融収支の資産減少、つまりプラス100億円)
つまり、経常収支の赤字は、その国が海外から「借金」をするか、過去の「貯蓄」を取り崩すことによって補填される、ということを示しています。
金融収支は資金調達または運用
国際収支は家計簿とは収支と支出が違いました。
国際収支の「金融収支」は、家計簿の「支出」とは違って「資金の調達または運用」として捉えるのがポイントです。
一般的な家計簿の感覚では、「給料が収入で、食費が支出」と捉えがちです。
しかし、国際収支では、海外との間のあらゆる資金のやり取りを「収入」と「支出」の概念で整理し、最終的にプラスとマイナスが釣り合うように定義されているため、結果として恒等式が成り立ちます。
「経常収支の黒字」がそのまま「外貨預金の増加」や「海外証券投資の増加」といった「金融収支のマイナス」として計上されることで、全体の収支がゼロになるように設計されているのです。
この式を家計簿に例えて考えてみましょう。
私たちが海外から何かモノを買う(輸入=経常収支の赤字)と、その代金としてドルを支払います。そのドルは、海外の企業や投資家の手元に渡ります。彼らはそのドルを、ただ持っているだけでなく、アメリカの株式や債券を買ったり、アメリカ国内に工場を建てたり(金融収支の黒字)する形で、アメリカ経済に「投資」として還流させることが多いのです。
つまり、「モノの赤字(貿易赤字)」は、「お金の黒字(金融収支の黒字)」によって必ず埋め合わせられる仕組みになっているのです 。これは、まるで私たちが海外で買い物をしてお金を使ったとしても、そのお金が巡り巡って自分の銀行口座に預金として戻ってくるようなものです。
特に「経常収支+金融収支=ゼロ」という恒等式が、各項目によってどのようにバランスが保たれているかを示すことで、貿易赤字が単独で存在するのではなく、他の収支項目と密接に連動していることを明確に伝えます。
この恒等式が示すのは、貿易赤字が「国内の貯蓄と投資の不均衡」の鏡であるという点です。
国全体で貯蓄が投資を下回ると、その不足分を海外からの資本流入で補う必要が生じ、結果として貿易赤字が発生します。財政赤字が貿易赤字を招き、両者が連動して悪循環を形成する現象も起こり得ます。
これは、貿易赤字が単に「輸入が多い」という表面的な現象ではなく、その国のマクロ経済における貯蓄と投資のバランス、さらには財政状況というより深い構造的な問題が背景にあることを示しています。つまり、貿易赤字は、その国の「お金の使い方」の傾向を映し出す指標とも言えるのです。
また、この関係性から、貿易赤字は必然的に「資本流入(金融収支の黒字)」を伴うということが分かります。
貿易赤字で海外に流出したドルは、日本企業による米国債購入や工場建設といった「投資」としてアメリカに還流し、金融収支の黒字化につながるメカニズムが存在します。
これは、貿易赤字が必ずしも「富の流出」を意味するのではなく、むしろ外国からの投資を呼び込む「富の流入」と表裏一体であることを示唆しています。この点は、貿易赤字に対する一般的な負のイメージを覆す重要な視点となります。

貿易赤字は本当に「悪」なのか?経済学の視点
トランプ大統領は貿易赤字を「目の敵」にしていますが、実はこの疑問に答えるのはそれほど簡単ではありません。経済学の視点から見ると、貿易赤字が必ずしも悪いとは限らず、むしろ健全な経済活動の結果である場合もあるのです。
「ドル高の結果」としての貿易赤字
アメリカ経済が健全で、生産性(特に非貿易財=サービス)が高いと、ドル高になりやすい傾向があります。ドルが高いと、輸入品は安くなり、輸出されるアメリカ製品は高くなるため、輸入が増え、輸出が減り、結果として貿易赤字になりやすくなります。
「トランプ大統領が問題視する貿易赤字はドル高の結果として起こっている」という見方もあります。
つまり、ドルが高すぎるから貿易赤字なのだと考えることもできます。ドル高の時、日本に輸出される米国製自動車の円建て価格は上昇して売れにくくなり、輸出数量が伸びにくくなります。貿易収支は、輸出数量が減って、輸入数量が増えることで赤字化するのです。
これは、貿易赤字が経済の弱さではなく、むしろその国の経済の強さや魅力(高い潜在成長率、金融サービスの競争力など)の裏返しである可能性を示唆しており、トランプ氏の「原因と結果」の認識が逆である可能性を指摘する重要な視点です。
外国からの投資(金融収支の黒字)による資金還流
前述の国際収支の恒等式が示すように、貿易赤字で海外に流出したお金は、外国からの投資(金融収支の黒字)として国内に還流する仕組みがあります。
例えば、日本企業がアメリカ国内に工場を建設したり、米国債を購入したりすることで、アメリカ国内の雇用創出や経済成長にプラスの影響を与えています。日系自動車メーカーがアメリカに多くの生産拠点を持ち、数万人のアメリカ人を雇用しているのはその良い例です。
消費者のメリットと選択肢の拡大
貿易赤字は、消費者が海外の高品質で安価な製品(自動車、電子機器など)を手に入れることができるというメリットをもたらします。これは消費者の選択肢を広げ、生活の質を向上させます。
もし保護主義的な政策で輸入を制限すれば、消費者は選択肢が減り、価格も上昇する可能性があります。

比較優位と経済構造の反映
貿易赤字や黒字は、各国の経済構造や「比較優位」(得意な分野)の違いを反映しています。
例えば、日本は製造業(特に自動車、電子機器)に強みがあり、アメリカはサービス業、金融、ハイテク、知的財産などに強みを持っています。各国が得意な分野に特化し、自由に貿易を行えば、世界全体と各国がより豊かになるというのが経済学の基本です。
実際に、貿易赤字でも高所得を維持している国々も存在します。ルクセンブルクや香港、シンガポール、デンマーク、アイルランド、ベルギーなどは、常に貿易赤字であるにもかかわらず、金融などの得意分野で稼ぐことで高所得を実現している国々です。
これは、貿易赤字が必ずしも国の経済的な弱さや衰退を意味するものではないことを示しています。貿易赤字が問題か否かは、その国の産業構造(製造業中心かサービス業中心か)、比較優位、そして国際金融市場におけるその国の通貨や資産の地位によって大きく異なるということが分かります。つまり、「一律に貿易赤字は悪い」という見方は、各国の経済的特性を無視した単純化であると言えるでしょう。
アメリカの特殊な立場
米ドルは世界の準備通貨として広く保有されており、米国債は世界的に安全資産とみなされています。また、アメリカは対外資産への投資リターンが高いという特徴もあります。
これらの要因が、アメリカが貿易赤字を抱えながらも、安定した経済を維持できる一因となっています。貿易赤字は、各国が最も効率的に生産できるものに特化し、それを交換することで、世界全体の生産性が向上し、消費者がより多くの恩恵を受けるという自由貿易の原則の表れでもあるのです。
貿易赤字は、このグローバルな効率性の副産物と見なすこともできます。
トランプ大統領の政策と経済学のギャップ
トランプ氏の「重商主義」的アプローチ
トランプ大統領の貿易赤字に対する考え方は、先述の通り、歴史的な「重商主義」の思想に近いと言えます。彼は、国富を増やすためには輸出を最大化し、輸入を制限すべきだと考え、国内産業の保護を重視しました。彼の政策は、消費者利益や税収の確保よりも、米国企業の業績改善を重要視していることを示唆しています。
関税政策の限界と副作用
トランプ政権が実施した関税強化は、貿易赤字を一時的に解消するかもしれませんが、国内の根本的な貯蓄・投資バランスの不均衡を修正しない限り、赤字の再発は避けられないとの見解があります。経済学者のマイケル・ペティス氏もこの考え方を提唱しています。
関税は輸入品の価格を上昇させ、結果的に消費者の負担を増やし、生活を悪化させる可能性があります。もし保護主義的な政策で輸入を制限すれば、消費者は選択肢が減り、価格も上昇する可能性があります。
また、他国からの報復関税を招き、貿易戦争に発展するリスクも伴います。これらのことから、トランプ氏の保護主義的なアプローチは、貿易赤字の根本的な原因(国内の貯蓄・投資バランス)を解決せず、かえって消費者や経済全体に負の影響を与える可能性が高いことが示唆されます。

アメリカ経済の真の強みと課題
アメリカ経済は過去半世紀、非常に好調でした。
貿易赤字は、アメリカが金融サービスやソーシャルメディア技術などのサービス分野で大きな黒字を抱えていることの裏返しでもあります。
問題は、その富がすべての部門に均等に分配されなかったことにあります。
貿易赤字を問題視する背景には、製造業の空洞化や国内の所得格差といった、より複雑な国内問題が存在している可能性も指摘されています。トランプ氏が雇用創出を目的としていることは明らかですが、貿易赤字の縮小がその唯一または最善の解決策ではない可能性が示唆されます。
貿易赤字という「分かりやすい敵」に焦点を当てることで、国内の所得格差や構造的な失業といった、より複雑で解決が困難な問題から国民の目をそらし、単純な解決策を提示しているという、政治的な側面も考えられます。
まとめ:貿易赤字を多角的に捉える重要性
トランプ大統領が貿易赤字を問題視し、国内雇用や産業保護を目指す姿勢は、彼の支持層にとっては理解しやすいものです。
しかし、国際収支という大きな視点で見ると、貿易赤字は単なる「輸入超過」というだけでなく、その国の経済構造や国際的な資金の流れ、さらには国内の貯蓄・投資バランスといった、より複雑な要因が絡み合って生じる現象であることが分かります。
貿易赤字は、必ずしも国の経済的な弱さを示すものではなく、むしろ健全な経済活動(ドル高)や、外国からの活発な投資、消費者の選択肢の拡大といったプラスの側面を持つこともあります。国際収支の恒等式が示すように、貿易赤字は金融収支の黒字と表裏一体の関係にあり、お金が巡り巡って国内に還流する仕組みがあるのです。
トランプ大統領の関税政策は、一見するとシンプルな「アメリカ第一」の旗印の下に掲げられていましたが、国際収支というレンズを通して見ると、その影響の複雑さが浮き彫りになります。
貿易赤字と国際的な資金の流れは密接に絡み合っており、ある一面だけを見て性急な判断を下すことはできません。
この解説が、これからの世界経済のニュースを、より深く、多角的な視点から理解するためのヒントとなれば幸いです。

参考文献
ティモシー・テイラー 経済学入門
財務省 (mof.go.jp)
一般社団法人日本貿易会(Japan Foreign Trade Council, Inc.) (jftc.or.jp)
国際収支関連統計 : 日本銀行 Bank of Japan (boj.or.jp)
国際通貨基金 (imf.org)