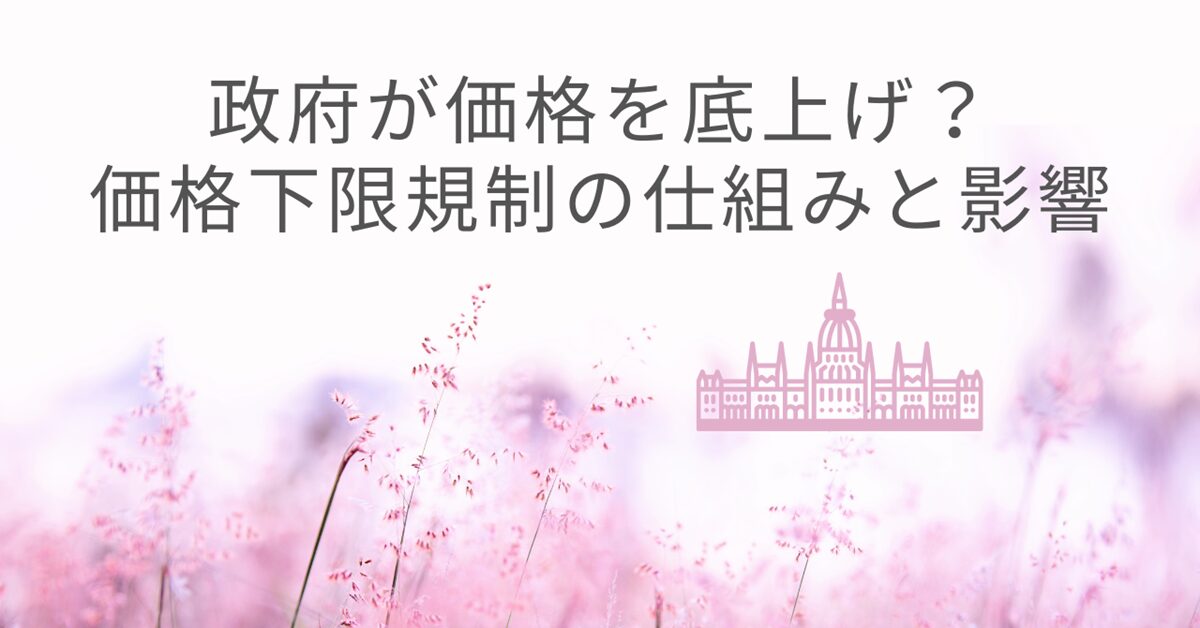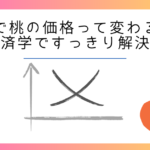あなたは、モノの値段はどのように決まっているのか知りたくないですか?
「そりゃ、かかった経費にちょっと利益を乗せて決めているんでしょ?」
と感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、よくよく考えてみると、品薄になったマスクが高値で売られたり、野菜のように値動きの激しい商品があって、かかった経費は同じなのに価格が上下することがありますよね?
どうやらモノの値段には、つくるときにかかった費用以外もなにかが乗っているようです。
実は、価格の中には「つくるときに必要な経費」だけではなく、欲しい人と売りたい人のうつろいやすい思惑がつまっています。
-

-
参考なんで桃の価格って変わるの?経済学でスッキリ解決!
日本が世界に誇れる農産物の一つ、桃!その芳醇な香りやとろっとした食感、そしてその甘さ・・・・きっとあなたもお好きですよね? その、おいしい桃の価格も、時期や天候、害虫、肥料の価格、農薬の価格、人件費、 ...
続きを見る
けれど、モノの値段に影響を与えるのは「欲しい人と売りたい人の思惑」だけではありません。
ここではさらに「価格」の知識を深めるために「価格と政府の関わり」についても見ていきましょう。
政府が価格を下支えする
価格に政府が絡んでいるの?
と驚くかもしれませんが、あなたが利用するタクシー、そして働くときの最低賃金、薬の価格には政府が深く関わっています。
政府は、特定の産業や労働者の保護のため、また価格や賃金の下支えのため、規制をかける場合があります。
ものの価格の低下は、消費者にとって一見うれしいことですが、必ずしも小売価格が下がるわけではなかったり、安売り合戦で売り手の利益が少なくなり、商売を続けられなってモノ不足になったり、質の低下、不正行為の蔓延といったデメリットが起こりやすくなります。
このようなことが起きないように、政府がある特定のモノの値段を下がりすぎないように、最低価格を決めてそれ以下で販売した場合は違法とする規制をかけること、つまり価格を下支えすることを、経済学では「下限価格規制」と呼んでいます。
「価格下限規制」は、政府が供給者を保護し、安定的にものを供給させるために導入されています。
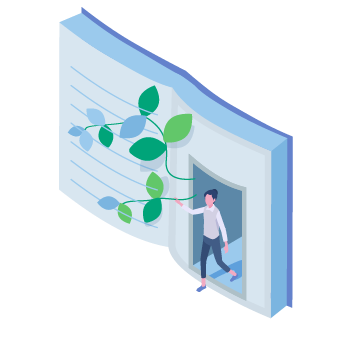
価格下限規制の歴史:市場の安定と社会政策の狭間で
なぜ政府がモノの価格を下支えするようになったのでしょうか?
簡単にその歴史を紐解いていきましょう。
「価格下限規制」の歴史は、市場経済の発展とともに、政府が市場に介入しようとした歴史、といえます。
歴史的な展開
戦争や災害などの社会的な混乱期には、物価が急激に上昇し、国民生活が困難になることがありました。このため政府は、物価の安定化を図ろうと価格規制を導入することが古くからありました。
- 古代ローマ
ローマ帝国は国土の拡大に伴って、都市人口が急増します。
食糧の安定供給は、帝国の安定維持に不可欠です。
特に、大規模な軍隊を維持するためには、大量の食糧が必要だったため、古代ローマ帝国では、政府が穀物の価格を安定させるため穀物を買いだめして、市場に供給する政策が行われていました。
これは、現代の価格安定政策の原型と言えるかもしれません。 - 中世ヨーロッパ
ギルドに所属する職人は、長年の経験と技術を蓄積し、高品質な製品を作り出すことを誇りとしていました。価格競争が激化すると、質の低い製品が市場に溢れ、ギルドの評判が損なわれることを恐れていたのです。
そのため、商品の価格の下限を設定し、職人が最低限の収入を得られるようにします。これにより、職人の生活水準を維持し、安定した生産活動が継続を目指したのです。
外部から見ると、ギルドのルールは「特権」です。
ギルドの職人たちはこの「特権」を守るために、外からの競争を厳しく制限します。
価格の下限は、外部の商人や職人が安価な製品で同じ市場に参入することを防ぐための手段の一つだったのです。
また、ギルドは、共通の利益を守るために、会員間の結束を固める必要がありました。
ギルドの規制は、会員間の協力関係を強化し、ギルドの安定を維持するための重要な役割を果たしました。
しかし、産業革命という技術革新以降、ギルドは競争力を失っていきます。
新しい産業から生まれるニーズに対応できなかったこと、また労働者の権利意識の高まりからギルドの親方制度は批判が高まり、衰退していきます。 - 産業革命以降
産業革命以降の価格下限規制は、社会的な安定維持、産業の保護、社会福祉の充実など、多岐にわたる目的で導入されてきました。
しかし、価格下限規制は、市場メカニズムの歪みなど、様々な問題点も指摘されています。
現代においては、価格下限規制は、その目的と効果を慎重に検討し、必要最小限にとどめることが求められています。
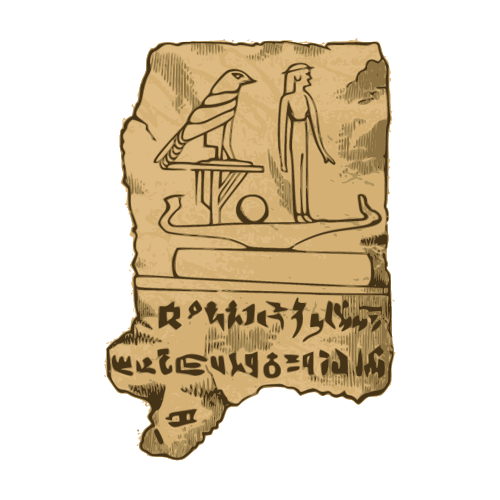
政府か価格を下支えする3つの理由
政府が価格に介入するのは、古くから世界で行われてきましたが、日本でもタクシー業界、一部の薬、そして賃金には「価格下限規制」が行われています。
なぜ、これらの業界の最低価格を決めなければいけないのでしょうか。
その理由は大きく3つあります。
1. 事業者の保護
初乗り運賃の規制、また薬の価格の規制は、事業者の保護のためにあります。
- 中小企業の保護
特にタクシー業界のように、中小企業が多く参入している業界では、価格競争が激化すると、大手企業に比べて資金力や規模が小さい中小企業が生き残ることが難しくなります。
価格下限規制は、中小企業が最低限の利益を確保できるようにすることで、多様な事業者が共存できる環境を維持することを目的としています。 - サービス品質の維持
過度な値下げ競争は、サービスの質低下につながる可能性があります。
価格下限規制によって事業者が最低限の利益を確保できるようになれば、車両の維持や運転手の育成、新しい薬の研究などのサービス品質の向上に投資することが可能になります。
2. 消費者保護
- サービスの安定供給
価格が自由市場に任された場合、何らかの原因で急に安くなってしまうと、事業者の倒産やサービスの縮小につながり、結果的に消費者が、商品やサービスを利用できなくなる可能性があります。
価格下限規制は、モノやサービスの安定供給を確保することで、消費者の利便性を保つことを目的としています。 - 品質の確保
価格が下がることで、モノやサービスの品質が低下する可能性があります。
価格下限規制は、一定の品質を確保することで、消費者が安心してモノやサービスを利用できるようにすることを目的としています。 - 労働者の生活水準の向上
最低賃金という価格下限規制は、労働者が、その労働によって最低限の生活を送れるだけの賃金を保障されるべきという考えに基づいています。最低賃金を設定することで、貧困を削減し、社会全体の生活水準を向上させる必要があります。
3. 社会全体の安定
- 雇用の維持
タクシー業界は、多くの雇用を創出しています。
価格下限規制は、最低限の収入を事業者が確保することによって倒産を防ぎ、雇用の維持に貢献することを目的としています。 - 消費の活性化
労働者の所得が増加することで、消費が活発化し、経済全体の活性化に繋がります。
このように政府の価格の下支えは、供給者の保護、そして社会にとって必要なサービスへ向けて、供給者(企業、労働者)を保護し、社会全体の利益を守る目的で各国で導入されています。
価格下限規制のメリット
供給者(企業や労働者)を保護する価格下限規制のメリットはどんなものでしょうか?
- 供給者の保護
特に、生活必需品なのに価格を上げることが難しく競争力の弱い業種、または、個人の労働者に対して、価格(賃金)が下がりすぎて経営(生活)が困難になることを防ぎ、産業(生活)を保護することができます。 - 品質の維持
最低価格を保証することで、生産者が品質の低下を招くような安価な製品を生産することを抑制し、製品の品質を維持することができます。また、労働者の働く意欲をなくすことを防止できます。 - 地域経済の活性化
地域の特産品など、地域経済に重要な役割を果たす商品の価格を下支えし、地域経済の活性化に繋がる可能性があります。
価格下限規制のデメリット
また、価格の規制を行うことは、デメリットもあります。
- 消費者の負担増
価格が上昇するため、消費者の負担が増加し、生活に影響を与える可能性があります。 - 市場の歪み
自由な競争が阻害され、市場の効率性が低下する可能性があります。 - 過剰生産
最低価格が設定されると、生産者が供給過剰になる可能性があり、資源の無駄遣いを招くことがあります。 - 新規参入の障壁
新規参入企業にとっては、高い価格水準が参入障壁となり、市場の競争が阻害される可能性があります。 - ブラックマーケットの発生
価格規制が厳しすぎると、闇市などのブラックマーケットが発生し、違法な取引が横行する可能性があります。
価格下限規制は、生産者を保護し、品質を維持するといったメリットがある一方で、消費者の負担増や市場の歪みといったデメリットも存在します。
そのため、価格下限規制を導入する際には、その目的や対象となる産業、そして経済全体への影響などを常に見直していく必要があります。
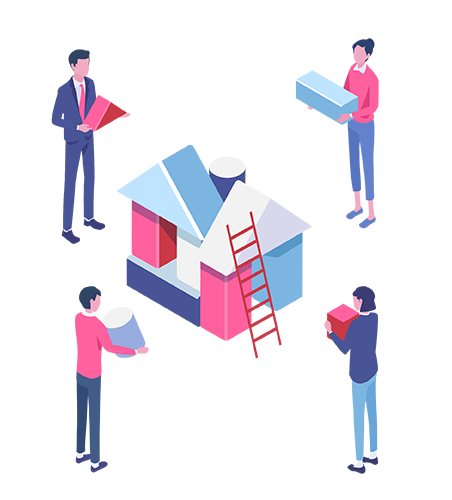
最低賃金の引き上げのメリットとデメリット
最後に最低賃金について詳しく見ていきましょう。
最低賃金の設定とその引き上げは、労働者にとって生活水準の向上や労働条件の改善につながるというメリットがある一方、企業や経済全体に、以下のような多くのデメリットをもたらす可能性も指摘されています。
最低賃金のデメリット
- 雇用の減少
最低賃金が引き上げられると、企業にとって人件費負担が大きくなり、特に中小企業の場合、雇用を抑制したり、パート・アルバイト労働者を雇用したりする動きが懸念されます。
特に、単純労働や低生産性の仕事は、機械化や自動化で代替されやすいため、雇用が失われるリスクが高くなります。 - 価格上昇
人件費増加分を価格に転嫁することで、消費者物価が上昇する可能性があります。
特に、サービス業や飲食業など、人件費がコストに占める割合が高い業種では、価格上昇が顕著になる可能性があります。 - 中小企業の経営悪化
人件費負担が大きい中小企業にとって、最低賃金の引き上げは経営悪化につながる可能性があります。
特に、利益率が低い企業の場合、採算が合わずに廃業したり、事業規模を縮小したりする可能性があります。 - 地域格差拡大
最低賃金は地域ごとに設定されていますが、地域によって経済状況や物価水準が異なるため、引き上げ幅が均一だと、地域格差が拡大する可能性があります。
特に、地方と都市部の格差が大きくなることが懸念されています。 - 労働市場の硬直化
最低賃金が引き上げられると、企業は労働者を解雇しにくくなり、労働市場の流動性が低下する可能性があります。
また、企業が新しい雇用を創出しにくくなることも懸念されます。 - 脱法行為の増加
最低賃金を遵守せずに、実際よりも低い賃金を支払うような脱法行為が増加する可能性があります。
特に、監督が行き届きにくい中小企業でこのような問題が発生しやすいと考えられます。
最低賃金の引き上げには、労働者にとってのメリットと、企業や経済全体への弊害の両方があります。これらのメリットとデメリットを慎重に比較検討し、経済状況や地域の実情に合致した適切な引き上げ幅を設定することが重要です。
また、最低賃金の引き上げおおこなう場合は、雇用促進策や中小企業支援策などの対策を合わせて講じることも必要です。
近年では「価格下限規制」は、その効果と弊害が常に議論されています。
経済全体の効率性を重視する立場から、価格下限規制を撤廃すべきだという意見も出ています。
一方、低所得者層や農林水産業などの保護が必要だという意見もあり、価格下限規制のあり方については今後も議論が続くことが予想されます。

まとめ
政府の価格の下支えの一つ「価格下限価格」について詳しく見てきました。
価格下限規制とは、政府などが特定のモノやサービスに対して、販売できる最低価格を法律で定める制度です。供給者保護と生活必需品の安定供給のために各国で導入されています。
しかし、需要と供給の均衡点より「上」に設定された下支え価格は、供給が多くなり、買う側に「価格が高いな・・・」と感じさせ、モノ余りを増やします。
また、最低賃金も世界中で行われている価格下限規制の一つです。
労働者の保護のため必要な政策ですが、雇用の減少、価格への転嫁、労働市場への影響などの問題も指摘されています。
政府の価格の規制は本当に困っている人だけではなく、困っていない人にも影響があり不公平感がでやすく、規制の隙をついて儲けようとする人も現れ不正の温床になる場合があり注意しなければいけません。
政府は、価格に介入しているものについて、常に実情に合っているのかどうか確認し続け、必要に応じて変更を加えていくことが大切です。
参考文献
お米の生産・流通・価格に関する情報 (zennoh.or.jp) JA農協
経済学入門 ティモシー・テイラー
農産物・食品の適正な価格形成について(maff.go.jp) 農林水産省
健康・医療 |厚生労働省 (mhlw.go.jp)