最近あなたも、毎月のスマホの通信費「高いな・・・」と思っていらっしゃいませんか?
もう少し安くならないのかな・・・
と思って他のプランを見てもあまり料金に変わりがないように見えます。
日本の通信会社はドコモ、au、ソフトバンクの3社がそのシェアの80%を占めています。通信事業は古くは国の独占事業でした。1985年に通信事業が民営企業に開放され、その時から競争原理が導入、その後大きく発展しました。
もし今でも、NTTだけが通信事業を独占していたら、通信費はもっと高い状態のままになっていたでしょう。
そのようなことのないように今では「独占禁止法」という法律があります。
「独占禁止法」なんて私たちに関係がない・・・
と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、「独占禁止法」は、私たちの利益を守ってくれる頼もしい法律です。
企業はどのような制約を受けているのでしょうか?
私たちの利益を守るためだけではなく、市場の健全な競争を守るためにも「独占禁止法」は大切な法律です。
ここではちょっととっつきにくい「独占禁止法」について分かりやすく解説します!
知って得する!独占禁止法が私たちの生活をまもるしくみ
独占禁止法(正式名称は「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」)とは、私たちに必要な商品やサービスが、常に公正で自由な競争のもとに販売されることを目的につくられた法律です。
独占禁止法には、次のようなルールがあります。
- より良い商品をより安く
あらゆる商品やサービスは、それぞれの企業が自由に競争することで、品質の良い商品が開発されたり、また価格が下がったりします。
もし、競争が行われなくなったり、阻害されたりすると、商品の質が下がり、価格が高止まりする可能性があります。
例えば、企業がお互いに話し合ったり(談合)して、一斉に商品の価格を吊り上げたり、他の企業の参入を妨害したりすると、私たちは高い値段で質の悪いものを買わざるを得なくなります。
独占禁止法は、このような事態を防ぎ、私たち消費者の利益を守ります。 - 選択肢の多様性
多くの企業が自由に競争することで、様々な種類の商品やサービスが提供されます。
もし、特定の企業が業界を独占してしまうと、私たちは限られた選択肢しか選べなくなるので、消費者の不利益になります。
消費者の利益を守るために、企業の自由な競争を守り、多様な選択肢を確保することで、私たちの豊かな生活を支えます。 - 中小企業や新規参入者の保護
大企業がその特権を利用して、中小企業や新規参入者を不当に排除することを防ぐ狙いがあります。
これにより、中小企業も安心して事業を行うことができ、新しいアイデアや技術が市場に参入しやすくなります。これは、経済全体の活性化にもつながります。
このように「独占禁止法」は、企業が公正で自由な競争をすることで、私たちがより良い商品やサービスをより安く購入できるようにすることを目的にした重要な法律なのです。
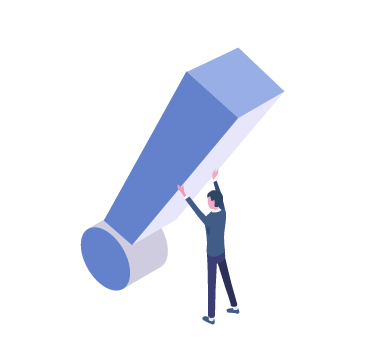
独占禁止法が禁じている4つのこと
独占禁止法には、企業が守るべきルールを定めています。
どのような行為を禁止しているのか見ていきましょう。
- 私的独占の禁止
一つの企業が市場を独占し、他の企業の活動を排除したり、支配したりすることで、市場の競争を実質的に制限してはいけません。
例えば、ある企業が市場の大部分を支配し、他の企業が参入できないように価格を極端に下げたり、仕入先を独占することを禁じています。 - 不当な取引制限の禁止
複数の企業が共謀して、商品の価格や数量、販売地域などを取り決めることで、市場の競争を制限する行為です。
代表的なものに、以下の2つがあります。- カルテル:複数の会社が、商品の値段を事前に話し合って決めることです。
これによって、消費者は本来もっと安く買えるはずの商品を高く買わされる可能性があるので禁止されています。 - 入札談合:入札で、参加者同士が事前に落札者を決めておくこと。
これによって、本来もっと安く公共事業が行えるはずなのに、無駄な税金が使われる可能性があるので禁止されています。
- カルテル:複数の会社が、商品の値段を事前に話し合って決めることです。
- 不公正な取引方法
大企業が下請け企業に対し、著しく低い価格で納品させたりするような不当な要求をすることを禁じています。
例えば、正当な理由なく、特定の企業との取引を拒否したり、競合他社との取引をしないように強制したり、商品を販売する際に、他の商品の購入を強制したりするなど、優位な地位を利用して、取引先に対し不当な要求を行ったりすることは禁止です。 - 企業結合の規制
企業合併や事業買収など、企業結合によって市場の競争が大きく制限される場合、独占禁止法によって規制されることがあります。
これらの行為は、消費者がより良い商品をより安い価格で手に入れる機会を奪い、市場の健全な発展を阻害する可能性があります。このような行為をなくし、公正で自由な競争を促し、消費者の利益を守るために「独占禁止法」は多くの国で導入されています。
独占禁止法を取り締まる公正取引委員会
「独占禁止法」に違反すればそれ相応の罰が与えられます。
それを監視しているのは警察ではありません。
警察も犯罪捜査を行う機関ですが「独占禁止法違反」は、通常の刑事事件とは異なり、経済活動における競争秩序の維持という観点から取り締まりが行われるため、専門的な知識と経験のある「公正取引委員会」が、中心的な役割を担っています。
もちろん悪質で大きな違反など刑事告発を行った場合は、警察は検察の指揮の下で捜査を行います。
例えば、談合事件などで、関係者が逮捕されるケースなどがこれに当たります。
つまり、「独占禁止法違反」の取り締まりは、「公正取引委員会」が中心となって行い、警察は公正取引委員会からの刑事告発を受けた場合や、他の犯罪との関連がある場合に限って関与する、という役割分担になっています。
これは、独占禁止法犯罪が、単なる犯罪の取り締まりだけでなく、市場における公正な競争を維持するという目的を持っているため、専門的な知識と経験を有する公正取引委員会が中心となって執行を行うことが適切であると考えられているためです。
独占禁止法を取り締まる役割をもつ「公正取引委員会」については、多くの人がニュースなどで、耳にしたことがあるのではないでしょうか?
公正取引委員会とは?
公正取引委員会は、自由で公正な市場経済を守るための日本の行政機関です。
「独占禁止法」という法律を運用し、企業が自由に、そして公正に活動できるように目を光らせています。消費者の利益を守ることも重要な役割です。
「公正取引委員会」は、「独占禁止法」のルールに違反してる企業がないかどうか日々調査をしています。
カルテルや談合などの独占禁止法違反の行為は、自由で公正な市場を歪め、消費者の利益を損なうため厳しく監視し、違反行為には排除措置命令や課徴金納付命令などの処分を行います。悪質な場合は、刑事告発も行います。
私たちにとって「公正取引委員会」あまりなじみのない機関かもしれません。
けれど「公正取引委員会」は、私たちの生活に欠かせない、自由で公正な市場を守る重要な役割を担っています。それは、企業のルール違反にイエローカードを出す、審判のような存在と言えるでしょう。
さらに詳しく知りたい場合は、公正取引委員会のウェブサイト(https://www.jftc.go.jp/)をご覧ください。
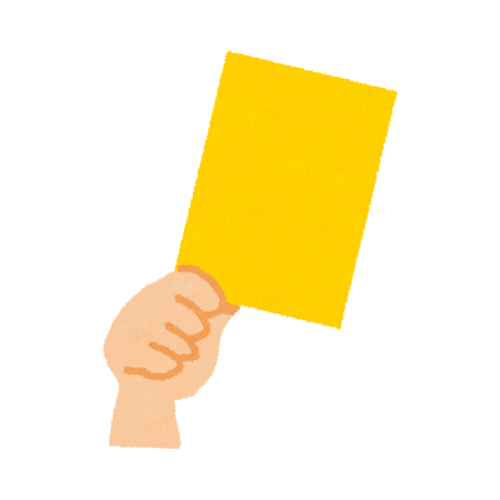
私たちのメリット
独占禁止法が私たちの生活に身近なもので、利益のあることということがお分かりいただけましたでしょうか?
「独占禁止法」は、公正で自由な競争を促進することで、私たちの生活に様々なメリットをもたらしています。
どのようなメリットがあるのか具体的な例をあげてさらに深掘りしてみましょう。
1. より安く、より良い商品を手に入れることができる
- 価格カルテルの禁止
企業同士が話し合って商品の値段を高く設定すること(価格カルテル)は、独占禁止法で禁止されています。これにより、企業は価格競争を強いられ、消費者はより安い価格で商品を購入できます。- 例:もし、複数のビール会社が「今後はビール1缶300円で売ろう」と合意した場合、消費者は高い値段でビールを買わざるを得ません。
独占禁止法によってこのような行為が禁止されているため、各社は競って価格を下げ、消費者はより安くビールを購入できます。
- 例:もし、複数のビール会社が「今後はビール1缶300円で売ろう」と合意した場合、消費者は高い値段でビールを買わざるを得ません。
- 品質向上のインセンティブ
企業は競争に勝つために、商品の品質向上に努めます。
独占禁止法によって公正な競争が保たれることで、消費者はより高品質な商品を手に入れることができます。- 例:スマートフォンの開発競争では、各社が新機能や高性能な部品を搭載した機種を開発しています。これは、独占禁止法によって公正な競争環境が保たれているため、各社が切磋琢磨しているからです。
2. 多様な選択肢から商品を選ぶことができる
- 新規参入の促進
独占禁止法は、大企業が市場を独占し、中小企業や新規参入企業を排除することを禁止しています。
これにより、様々な企業が市場に参入しやすくなり、消費者は多様な商品やサービスから選択できます。- 例:もし、あるオンラインショッピングサイトが市場を独占した場合、他の企業は参入が難しくなり、消費者はそのサイトでしか商品を購入できなくなります。独占禁止法によってこのような状況が防がれているため、様々なオンラインショッピングサイトが存在し、消費者は自由に選択できます。
3. イノベーションの促進
- 自由な競争環境
独占禁止法は、企業が自由な発想で事業活動を行うことを保証しています。
これにより、イノベーションが促進され、新しい商品やサービスが生まれます。- 例:もし、ある企業が特許を濫用し、他の企業が新しい技術を開発することを妨げた場合、技術革新は停滞してしまいます。独占禁止法によってこのような行為が規制されているため、企業は自由に研究開発を行い、新しい技術を生み出すことができます。
4. 消費者の利益保護
- 不当な取引の禁止
独占禁止法は、企業が消費者に対して不当な取引を行うことを禁止しています。
これにより、消費者は安心して商品やサービスを利用できます。- 例:もし、ある企業が商品の重要な情報を隠して販売した場合、消費者は不利益を被る可能性があります。独占禁止法によってこのような行為が規制されているため、企業は適切な情報開示を行い、消費者は安心して商品を購入できます。
このように、独占禁止法は私たちの生活の様々な側面でメリットをもたらしています。公正な競争環境を維持することで、より良い商品やサービスが提供され、私たちの生活がより豊かになるのです。

まとめ
独占禁止法について解説しました。
独占禁止法は企業の独占を取り締まり、企業同士の価格の調整や談合、また大企業の不当な権力乱用の取引を禁止した法律です。
企業は基本競争をしたがりません。
競争が行われないと、消費者は不当に高い値段で商品やサービスを支払わされたり、手に入りづらくなったりして不利益になります。そのため「独占禁止法」によって、競争する環境を保つことが欠かせません。
「独占禁止法違反」を取り締まるのは「公正取引委員会」です。
「公正取引委員会」は、企業が法に違反していると思われた場合は立ち入り検査し、違法行為が行われたと判断したら行政処分を行います。必要があれば警察と協力し捜査します。
「公正取引委員会」は、競争の意義を国民や事業者に広く理解してもらって、競争を維持すること、そして「独占禁止法」の問題点の改善や新たな課題に取り組むことが求められています。
つまり、独占禁止法は、私たち消費者がより良い商品やサービスをより安く、多くの選択肢の中から選べるという、公正な競争環境を守るための大切な法律なのです。
あなたも、もしお店で商品を選ぶとき、その背景には「独占禁止法」というルールがあることをちょっと思い出してみてください。
きっとその価格が適当なのかどうか、もっと鋭く考えることができるようになるでしょう。

参考文献
経済学入門 ティモシー・テイラー
公正取引委員会の紹介 | 公正取引委員会 (jftc.go.jp)
公正取引委員会 - Wikipedia
sanken.keio.ac.jp/law/law/anti_monopoly_law/chp-08.html
