あなたは毎日、自分にとって一番良い選択ができていますか?
「選ぶなんて簡単!直感でいつも選んでいる」
という素晴らしい方もいらっしゃるかもしれません。
でも、
「声の大きい人の意見に流されてしまう・・・」
「初めは良いと思ったけど、後で考えたら違った・・・」
「初めに決めたことだから、続けなくっちゃ・・・」
というかたも多くいらっしゃるのではないでしょうか?
そこで今回は、「3びきのくま」というイギリスで有名な童話から「選ぶことの難しさ」について解説します。
どうしたら良いのか分からなくなったとき、ぜひここでの話を思い出してください。
きっと納得のいくヒントが見つかるはずです!
ではいきましょう!
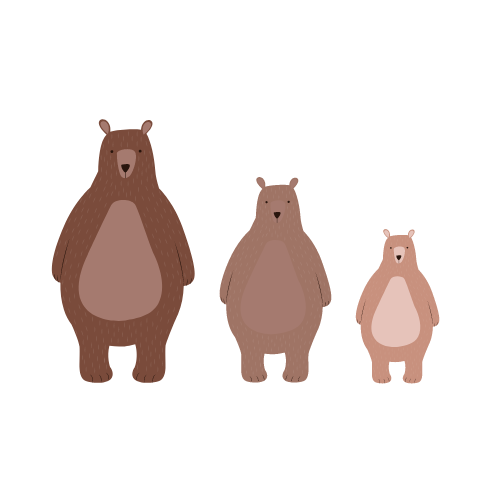
3びきのくま:ちょうど良いをさがして
日本ではあまり馴染みのない「3匹のクマ」の話は、古くからイギリスに伝わる童話です。
物語は、森で道に迷った女の子が、クマの家を見つけるところから始まります。
道に迷った女の子は、クマの家の中に入って、テーブルの上にあった大中小のスープ、椅子、そして寝室のベッドを試していきます。
その中で、女の子が自分にとって「ちょうどいい」ものを見つける様子を描いています。
しかし、女の子が見つけた「ちょうどいい」は、その家に住むクマたち、お父さんのミハイル・イワノビッチ、お母さんのナスターシャ・ペトローブナ、そして小さなクマの子ミシュートカにとっての「ちょうどいい」とは違いました。
物語の元々の設定では、女の子は意地の悪い老婆として描かれており、ちょうど良い椅子やベッドを探しながら部屋を荒らしてしまうという内容でしたが、時を経て子供へのしつけやマナーを教える作品へと変化し、少女へと設定が変わって広く知られるようになりました。

自分にとって最適なもの
この物語では、少女が無断でクマの家に入って、食事したり、椅子を壊したり、ベットで寝たりします。物語の最後はクマが帰ってきて、少女は逃げ出すことになります。
つまり、この童話は、人の家に勝手に入らないこと、また人のものを勝手に使ってはいけないことを教えてくれます。
この童話で、行動経済学が注目したのは、少女が「大きすぎる」もの「小さすぎる」ものを避け、「ちょうど良い」ものを見つけるという行動です。
このように私たちは、いくつかの選択肢があると真ん中のものを選ぶ傾向があることが分かっています。
また物語にはありませんが、選択肢がたくさんあると、選ぶことにストレスを感じて、選ぶことをやめてしまうことも知られています。
童話の少女は、3つの中からちょうどいいものを選ぶ、という簡単な選択でしたが、日常でも人間関係や生活の中で「自分にとって最適」なものを見つけるということは、いつの時代も悩ましいことです。
最適なものは人によって違う
さらに、自分にとってちょうど良いものを選んだとしても、他者にとっては最適ではないことがあります。
クマの家族にとっての「ちょうどいい」と、少女にとっての「ちょうどいい」が異なるように、私たちが選択するときも、一見「最適」に見えた状態が、立場や視点によって「最適ではない」と認識されることがあります。
例えば、学校の決め事や会社の決定ような、多くの人が話し合うとき、人によって最適が変わるため、決定まで時間がかかります。
さらに政府の政策などはどうでしょうか?
例えば、インフレを改善させたい場合、金利を上昇させたり、増税を行うと、失業率が高くなる傾向があります。逆に失業率の上昇を抑えるために、政府が金利を低くしたり、減税を行うとインフレが起こりやすくなります。
低い失業率は、雇用されている人々にとっては望ましいかもしれませんが、それによって引き起こされるインフレに苦しむ消費者にとっては、決して「ちょうどいい」とは言えない状況かもしれません。
このように、一見失業者を支援する政策を充実させようとする政策が、インフレという物価高を招いてしまうような問題は、解決しにくいのです。
さらに、物語の結末が、少女がクマに見つかり慌てて逃げ出すという形で終わることは、彼女が見つけた「ちょうどいい」状態は一時のものだったかもしれません。
これは、どんなに良い選択だったとしても状況が変われば、それは変化すること、つまり短い期間ではちょうど良かったかもしれませんが、長い目で見ると想定外の出来事に見舞われる可能性も十分考えられるということなのです。
経済の「熱すぎず、冷たすぎず」問題:失業率とインフレ
少女がクマの家から、ちょうど良いものを見つけるのは、選択肢が3つしかなかったので難しくありませんでした。
けれど、複雑なことがたくさん絡まった問題、例えば「失業とインフレ」の関係のような「失業率が高すぎず、インフレ率が高すぎず」のような「ちょうどいい」状態を見つけるのはとても難しいです。
社会問題と言われる問題の中でも特に、この「失業率」と「インフレ」は、私たちの生活に直接的な影響を与えるため、政府や中央銀行は常にそのバランスを模索しています。
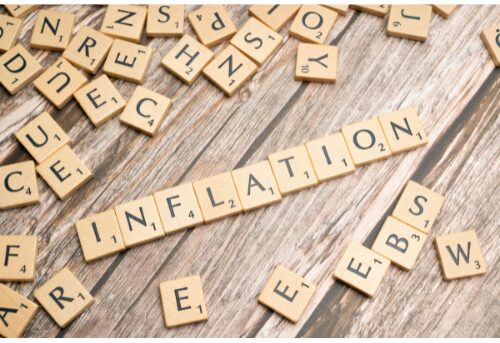
失業率:仕事がないのは「冷たすぎる」お粥?
失業率は、労働市場の健全性を示す重要な経済指標であり、特定の期間において仕事を探しているにもかかわらず見つからない人々の割合を示します。先進国では一般的に2%から5%の間で維持されることが多く、この数値が高い状態が続くと、経済全体に深刻な「痛み」をもたらします。
高い失業率は、働きたいのに働くことができない人々が多いことを意味します。
その結果、国内総生産(GDP)が低下し、人々の所得も減少します。これは、労働力が有効に活用されていないという経済的な無駄が増えている状態であり、効率性が低下していることを示します。
さらに、失業がもたらす「痛み」は経済的な側面に留まりません。失業率の上昇は、犯罪発生率や自殺率の上昇といった、社会全体の安定を揺るがす深刻な問題にも繋がることもあります。
失業は労働者のスキルや専門性、好みなどによって需要との間にズレが生まれることもありますが、より深刻なのは景気が後退し社会全体が生産性が低下するときです。
もし失業率が上昇したときには、その理由を分析して一人一人の生活の質や社会の健全性のために異なる支援をしていく必要があります。
インフレ:物価が高すぎるのは「熱すぎる」お粥?
一方、インフレ(インフレーション)とは、物価水準が持続的に上昇し、それに連動してお金(通貨)の価値が相対的に下がる状態を指します。インフレが続くと、以前は千円で買えた物や利用できたサービスが、同じ千円では買えなくなってしまうなど、私たちの買おうという力が低下します。
特に、現金として保有している資産は、物価上昇によってその実質的な価値が目減りしてしまうリスクに弱いです。
一般的に、適度なインフレ率は経済成長を伴うものとされています。企業は物価やサービス価格を上げられることで収益が増え、株価が上がりやすくなる傾向があるのです。
しかし、過度に高いインフレ率は経済の過熱を意味し、消費者の生活を圧迫します。
例えば、輸入企業にとっては仕入れ価格が上昇するマイナス要因となることもあります。
理想的なインフレ率は、2%から5%が「適度」であることは、多くの先進国で認識されています。けれど、社会が許容できる「痛み」のレベルや、経済成長のステージによって「適度」な水準は変化します。
また、健全な失業率も2%から5%程度とされていますが、なにが「健全」なのか、その線引きは常に議論の対象です。
失業率を下げようと政策を立てると、インフレが進むという関係にあることが分かっている場合、いったいどのように問題を解決していけばいいのでしょうか?
経済政策のジレンマ:失業率とインフレの「トレードオフ」
失業率とインフレはトレードオフの関係になっています。
トレードオフとは、何かを選ぶと、選ばなかったものは諦めないといけないという関係のことを指します。
経済の「ちょうどいい」状態を探す政策立案者は、まるでクマの家で最適なスープやベッドを探す女の子のように、失業率とインフレ率の間にある「トレードオフ」に頭を悩ましています。
失業率とインフレはトレードオフ
このトレードオフの関係性を明確に示したのは、1958年に英国の経済学者アルバン・ウィリアム・フィリップスが提唱した「フィリップス曲線」です。
フィリップス曲線 - Wikipedia
この仮説は、短期的に見ると「インフレ率が高い時期は失業率が下がり、インフレ率が低い時期は失業率が上がる」という負の相関関係、つまりトレードオフが存在することを示しています。
これは、政府が総需要拡大策(例えば、財政出動や金融緩和)を実施して経済を刺激し、失業率を低下させようとすると、経済活動が活発になり、企業はより多くの労働者を雇用します。これにより雇用は増えますが、同時に財やサービスへの需要が供給を上回り、物価が上昇しやすくなります 。
逆に、中央銀行がインフレを抑制しようと金融引き締めを行うと、金利が上昇し、経済活動が抑制されるため、失業率が上昇する傾向にあります。
そのため、政策立案者は「失業を減らすか、インフレを抑えるか」という難しい選択を迫られることになります。フィリップス曲線が示す短期的なトレードオフは、政策立案者はどちらかを選ばざるを得ないのです。
これは、政府が経済を刺激して雇用を増やす(失業率を下げる)と物価が上がる(インフレが進む)という、一方を立てれば他方が立たないからです。
残念ですが、このジレンマは、政策決定が常に「より良い選択」であり、「最善の選択」ではないことを示しています。
失業率とインフレは長期的にはインフレだけが進む
しかし、1970年代のオイルショックをきっかけに、「より良い選択」にも陰りが見えることになります。
それまで失業率を改善するためにはインフレが起こるのはやむうえないこと、と考えられてきましたが、オイルショックをきっかけに「高失業率」と「高インフレ」が同時に現れたことから、2つがトレードオフになっているのは短期的な時だけではないか、と主張するものが現れます。
それが後のノーベル経済学賞受賞者となる、ミルトン・フリードマンです。
彼は、短期的には「失業率」と「インフレ」はトレードオフになってはいるものの、長期的に見ると間違っているとする「自然失業率仮説」を主張します。
フリードマンによると、金融緩和(お金をジャブジャブにすること)をして景気を刺激し、失業率を下げようとすると、一時的に失業者が減ります。しかし、その代償として物価が少し上がります(インフレ)。
これが短期的なトレードオフです。「失業を減らす」という良い効果の裏で、「インフレ」という望ましくない副反応が出るけれど、効果があるから使う意味があります。
もし、政府が「失業率を下げたい!」と、金融緩和を何度も繰り返すとします。最初は失業率が下がりますが、やがて人々は物価が上がり続けていることに気づきます。給料が上がっても、それ以上に物価が上がれば生活は楽になりません。
そうなってくると、企業も労働者も「どうせ物価は上がる」と織り込み始め、賃上げ要求が強まるなどして、結局、失業率は元の「自然失業率」という水準に戻ってしまいます。
しかし、何度も金融緩和を繰り返した副作用として、インフレだけがどんどん加速していくことになります。
つまり、「失業率を下げたい」という目的は達成できないのに、望ましくない「高インフレ」という副作用だけが残る状態になります。これが長期的にトレードオフが存在しないという状態です。
なぜこれが政策にとって重要なのか?
このフリードマンの「長期的にトレードオフがない」という発見は、政府が経済政策を行う上で、「やってはいけないこと」や「効果がないこと」の限界を教えてくれた点で非常に重要です。
もし長期的にインフレと失業のトレードオフがなければ、政府が安易に金融緩和や財政出動を繰り返して失業率を無理に下げると、インフレを加速させるだけで、肝心の失業率は改善しないという無駄な努力になります。これは経済を不安定にするだけです。
フリードマンは「長期的に失業率を下げるには、経済構造そのものに手を入れるしかない」ということを示唆しました。
例えば、労働者のスキルアップ支援、労働市場の流動性を高める改革、起業しやすい環境づくりなど、自然失業率そのものを引き下げるような政策こそが、本当の意味で失業問題の解決につながる、という認識に変わったのです。
この考え方は、1970年代に多くの国が高インフレと高失業率が同時に進行する「スタグフレーション」に苦しんだ経験とも結びつき、現代の経済政策の基礎となっています。
つまり、短期的には「ちょうどいい」ように見えたものも、経済は常に変動しているので、長期的な影響も考えておかなければいけないという複雑な現実な現実を表わしています。
つまり、「完璧な解決策」は存在しないので、常に状況を見直しながらバランスを取り続ける必要があるのです。
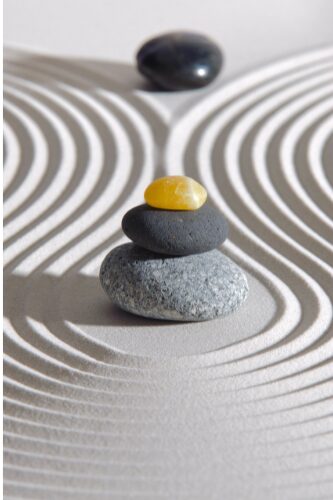
経済だけじゃない!私たちの日常に潜む「トレードオフ」
経済学の専門用語のように聞こえる「トレードオフ」ですが、実は私たちの日常生活の中に溢れており、私たちは無意識のうちに日々これを受け入れ、選択しています。
トレードオフとは、前にも出てきましたが「一方を得るためには他方を犠牲にしなければならない関係」であり、二つ以上の欲求や目標を同時に満たすことが困難な状況を指します。
日常の「トレードオフ」例
私たちの身の回りには、さまざまなトレードオフがあります。
あなたにも心当たりがあるのではないでしょうか?
| 得られるもの(メリット) | 犠牲にするもの(デメリット) |
| 時間の節約(外食、デリバリー) | 食費の増加、健康管理の難しさ |
| キャリアの発展、高収入 | 家族との時間、プライベートな時間 |
| 一時的な楽しみ(高カロリー食) | 健康・体重管理、長期的な体調 |
| 高品質な商品・サービス | 高コスト、予算の圧迫 |
| 福祉政策の充実 | 増税、国民の負担増 |
| 環境保護の推進 | 経済成長の鈍化、産業への規制 |
これらの例は、時間と金銭、キャリアと家族、健康と楽しみといった個人の選択から、福祉政策と税金、環境問題と経済成長といった社会的な課題まで、多岐にわたるトレードオフの存在を示しています。
これは、トレードオフが経済学の概念に留まらず、あらゆる場所で「何かを得るには何かを諦める」という選択避けれらないということがはっきりと分かります。
さらに、生物学の世界にもトレードオフは存在します。
例えば、ペンギンは飛ぶ能力を犠牲にする代わりに、泳ぐ能力に特化しています。
また、鹿の大きな角や孔雀の美しい羽は繁殖に有利ですが、その維持には多大なエネルギーが必要となります。ウミガメが一度に多くの卵を産む一方で、その多くが捕食されることや、ヒトを含む大型哺乳動物が少数の子孫を長く育てることなど、生物の寿命と繁殖力もトレードオフの関係にあると言えます。

これらの例は、トレードオフが自然界の進化の過程においても重要な役割を果たしていることを示しています。
日常生活の中にあるトレードオフを意識することは、選択することのヒントを与えてくれるだけでなく、心理的なストレスを軽くしてくれます。初めに挙げた童話のように3つの選択肢の中から選ぶということは、現実にはほとんどありません。
現実には多くの選択肢の中から、良く分からない未来のことを考えて選択します。そんな不安な状態から少しでも早く逃れようと、私たちは決めることをやめてしまったり、選択肢の特定の属性に注目したり、反応したりして、自分にとって最適なものとは違う選択をしてしまうことがあります。
「ちょうどいい」を探すヒント:トレードオフを理解する力
クマさんの家で「ちょうどいい」ものを見つけるのが難しかったように、大変残念な話ですが、経済も日常も完璧な「ちょうどいい」は存在しません。
ちょうどいいものがないなら、私たちは毎日あれやこれやと思い悩むことは無意味だったのでしょうか?
そんなことはありません!
最適なものがない世界でも、この「トレードオフ」の本質を理解することこそが、日々の小さな悩みを軽くし、より良い意思決定をするための強力なヒントになります。

なぜ悩みが軽くなるのか
どうしてトレードオフを理解すると、心が軽くなるのでしょうか?
その理由はまず、トレードオフを理解することで、「全てを手に入れることはできない」という現実を受け入れられるようになります。これにより、完璧な解決策を追い求めるストレスから解放され、「一方を犠牲にしても仕方ない」と割り切ることができるようになります 。
また、どちらも正しく見えるものを選ぶときにも、感情的にならず、何を得て何を犠牲にするのかを合理的に考える助けになります 。
例えば、自炊をして食費を節約するか、外食やデリバリーを利用して時間を節約するかといった選択において、自分の時間の価値をしっかりと理解し、どれだけの時間や労力を節約できるのか、また代わりにいくらのコストがかかるのかを考慮して、最適な選択を行うことができます 。
このように、何を選んで、何を犠牲にするのかはっきりとみえることができれば、自分の価値観にあった選択ができるようになり、意思決定の質を高めることができます。
トレードオフを活かすためのヒント
つまりトレードオフの「最適解」は静的なものではなく、個人の価値観、外部環境、時間の経過によって動的に変化し続けています。私たちの身の回りにあるものは常に変化し続けています。
これを理解することで、私たちは固定観念にとらわれず、柔軟な思考で問題に対処できるようになるのです。
- 自分の価値観を明確にする
何を優先し、何を諦めるのかは、個人の価値観によって大きく異なります。自分にとって何が本当に大切なのかを理解することが、適切なバランスを見つける第一歩です。 - 外部の意見やフィードバックの活用
もちろん私たちは全てのことについて知っているわけではありません。自分一人では見落としがちなトレードオフを発見するためには、他者の視点や専門家の意見を取り入れることが有効です。 - 継続的な見直し
私たちのまわりは常に変化します。
一度下した意思決定やトレードオフのバランスも、定期的に見直し、必要に応じて調整することが重要です。一度見つけた「ちょうどいい」が続くわけではなく、常に状況の変化に対応して調整が必要です。
まとめ:経済も日常も、完璧じゃなくていい
「3びきのくま」の物語が教えてくれるように、完璧な「ちょうどいい」は、立場や状況によって異なります。
経済政策も、私たちの日常の選択も、常に一方を立てれば他方が犠牲になる「トレードオフ」の関係にあります。失業率とインフレ率のバランスを取る経済政策の難しさから、日々の時間の使い方やお金の管理、キャリアとプライベートのバランスといった個人的な選択に至るまで、私たちは常に「何かを得るために何かを諦める」という状況に直面しています。
大切なのは、完璧な解決策を求めるのではなく、トレードオフを受け入れ、自分にとって、あるいは社会にとって「最も望ましいバランス」を見つけ出すことです。それは時に、どちらか一方を諦める「割り切り」の決断を伴います。
経済学の概念も、このように日常の選択と結びつけて考えることで、決して遠い存在ではなく、私たちの生活に深く根ざした知恵であることが分かります。
この「トレードオフ」の視点を持つことで、私たちは日々の小さな悩みや大きな決断に直面した際に、より冷静に、そして前向きに対処できるようになるでしょう。
私たちは完璧じゃないからこそ、そこに工夫や選択の余地が生まれ、それが人生の豊かさにつながるのです。
参考文献
経済学入門 ティモシー・テイラー
3びきのくま - Wikipedia
ゴルディロックス相場 - Wikipedia
失業 - Wikipedia
雇用不安解消のためのシステム改革
インフレーション - Wikipedia
フィリップス曲線 - Wikipedia
ミルトン・フリードマン - Wikipedia
日本における自然失業率仮説の検証 -積極的景気政策への反省材料として-
